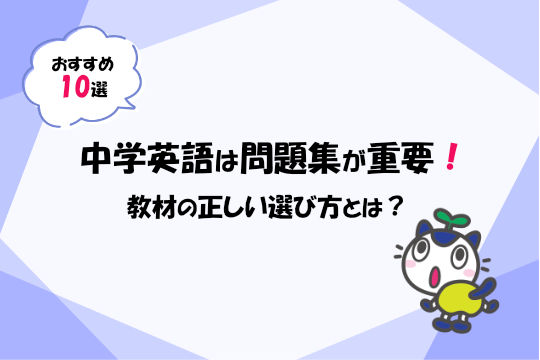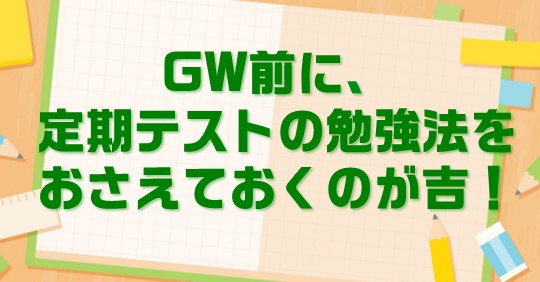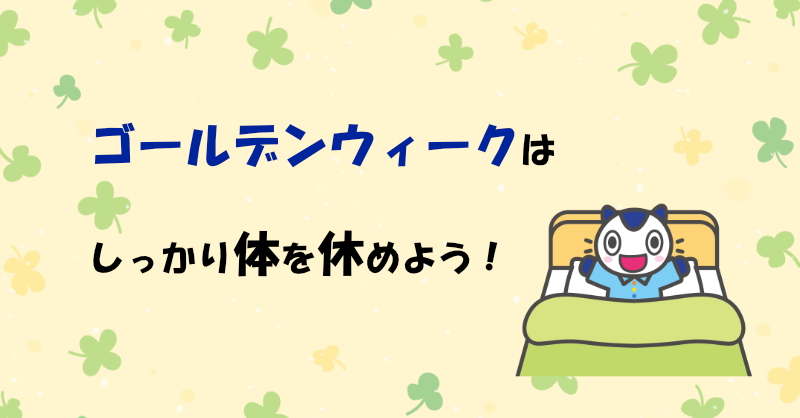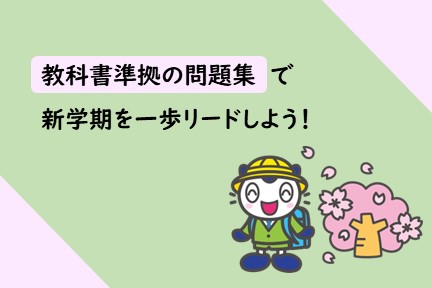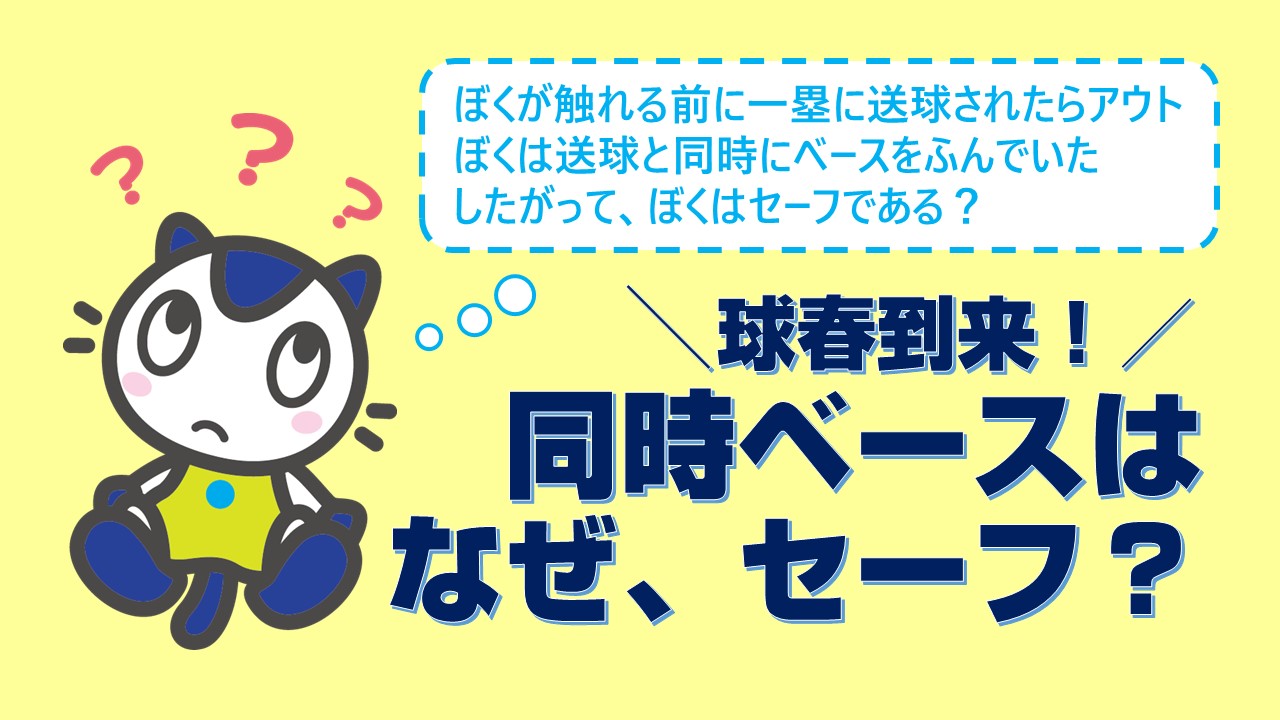なるほど!Bunri‐LOG
対象
【おすすめ10選】中学英語は問題集が重要!教材の正しい選び方とは <2025年度最新版!>
中学生のみなさん、英語の学習に悩んでいませんか? 小学校のときに比べて急に難しくなった英単語や文法に戸惑い、英語に苦手意識を持っている人もいるかもしれません。 英語は知識を積み重ねてゆく教科のため、ひとつわからないままにしておくと、新しく習ったことが理解できなくなってしまうことがあります。 そうならないためには、学校での授業に加えて、家庭でも自分に合った問題集を選んでコツコツ学習することが大切です。 そこで今回は、中学英語の学習にぴったりな問題集を、目的やレベル別に紹介します。 成績アップのための問題集を探している人、これから高校受験や英検®合格を目指す人はぜひ参考にしてください。 <目次> 1.中学英語は問題集選びが重要! 2.中学校の問題集はどう選ぶ? 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 4.レベルに合わせて、実力アップができる おすすめ問題集3選 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 6.英検®対策に! わからないをわかるにかえる英検® シリーズ 7.まとめ <POINT> ・中学英語は家庭学習も大切。まずは教科書の内容をしっかり予習・復習しよう。 ・中学英語の問題集は目的とレベルに合わせて選ぶのがおすすめ。 ・中学英語が理解できていれば高校進学後の英語力も伸びやすい。 1.中学英語は問題集選びが重要! 中学生になるとたくさんの英単語を覚え、しっかり文法を理解したうえで、長文を読んだり、英作文を書いたりする力が求められます。 小学校では歌やゲームを使いながら、英語を話したり聞いたりするコミュニケーション型の授業が中心だったため、中学校での文法重視、読み書き重視の授業に戸惑うケースも少なくありません。 しかし、基礎となる単語や文法をしっかりと押さえたうえで演習を繰り返せば、英語に対する苦手意識を克服できます。 問題集や参考書を使って自分なりの勉強法を見つけましょう。 基礎が詰まった「中学英語」 文部科学省による2021年度の学習指導要領改訂で、中学英語の学習内容は大きく変わりました。 それまで高校英語の範囲だった語彙や文法事項の一部が中学に前倒しされ、3年間で学ぶ内容はぐんと増えています。 また、「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り)」「話すこと(発表)」「書くこと」の4技能5領域の総合的な育成がより強く求められるようになりました。 中学で学習する英語は、高校、大学と英語を学んでゆくうえでの基礎となるものです。 高校、大学と進学するにつれて、より複雑な英語表現や長文読解の理解力が必要になります。 土台となる中学英語がしっかり身についていれば、新しい文法表現や入り組んだ難しい長文に出会ったときでもスムーズに理解ができるため、中学英語の習得は重要です。 問題を解くことは成績アップにつながる 中学英語を習得するには、繰り返し演習問題を解くことが大切です。 教科書を読んだり、授業を聞いただけで、何となく英語がわかったような気になっていても、いざテストを受けてみると、単語のつづりがちがっていたり、文法の間違いをしていたり……ということはありませんか? 英単語や英文法を正しく覚えるには、インプットするだけでは足りません。 いろいろな問題を解いてアウトプットしながら、身につけた知識を整理していくことで、脳に記憶が定着しやすくなります。 インプットとアウトプットを繰り返して知識を定着させるには、問題集を使った学習が効果的です。 では、英語の問題集を選ぶときには、どのような基準で選べばよいのでしょうか。 書店やネットショップでは数多くの英語教材や問題集が販売されているため、どれを選べばよいのか迷ってしまいますよね。 そこで、自分に合った英語教材の選び方を紹介します。 教科書の内容に対応しているものを選ぶ 市販されている問題集には「教科書準拠版」と、そうでないものがあります。 教科書準拠版とは、それぞれの教科書の内容に沿った問題集です。 みなさんは、学校でどの教科書会社の教科書を使っていますか? 「え? 教科書って日本全国同じじゃないの?」と思った人もいるかもしれませんね。 実は、中学校の英語の教科書は現在6つの教科書会社が発行していて、それぞれ内容が異なっています。 ・東京書籍(NEW HORIZON) ・開隆堂(SUNSHINE) ・三省堂(NEW CROWN) ・教育出版(ONE WORLD) ・光村図書(Here We Go!) ・啓林館(BLUE SKY) 学校の授業は教科書に沿って行われるため、家庭での予習・復習には教科書の内容に沿った「教科書準拠版」の問題集がおすすめです。 教科書準拠版の問題集は、それぞれの教科書と単元名や英単語、英熟語などがそろっていて、教科書の参照ページも載っています。 重要ポイントの解説も教科書の内容に沿っているため、授業の内容が理解しやすいのもポイントです。 また、定期テストの問題は教科書の範囲から出題さるため、教科書準拠版で学習すれば成績アップが見込めます。 授業の予習・復習、定期テスト対策には、まずは教科書準拠の問題集で学習を始めるのがよいでしょう。 教科書準拠の問題集を探すなら 2.中学校の問題集はどう選ぶ? 学習目的に合っているか 中学生向けの問題集には、日常学習用、定期テスト対策用、入試対策用などがあり、それぞれの問題集は、学習者の目的を効率よく達成できるように編集されています。 そのため、自分の学習の目的あった問題集を選ぶことが、効率的・効果的に学力を伸ばす近道になるのです。 ・定期テストの対策がしたい ・苦手を克服したい ・受験対策がしたい ・英検®合格を目指したい これらの目的を定め、自分に合ったレベル・学年の教材や問題集を選びましょう。 簡単すぎて手応えのないものはもちろん、難しすぎる教材も身につかないため、レベルの把握は重要です。 また、英語は文法・語彙の知識を基盤としながら、「聞く力」「読む力」「話す力」「話す力」「書く力」を総合的に育成する教科です。 そのため、特定の分野の苦手克服や強化を目的とするのか、それとも包括的に学習したいのかでも選ぶべき問題集は変わってきます。 解説や付属品が充実しているか 解説が充実していることも問題集選びの重要なポイントです。 一人で学習する際には、テキストに注やヒントがたくさんあるものを選ぶとよいでしょう。 また、別冊の解答解説が充実していると、解答のポイントや間違いやすい点がよくわかります。 どんな付属品がついているかも重要です。 英語の場合はとくに、リスニングの音声に対応しているかどうかをチェックしましょう。 デザインやレイアウトが見やすいか 実際に問題集を使う際、どのようなデザインが自分に合っているかを考えることも大切です。 カラフルな紙面がよいのか、1色、2色刷のシンプルなデザインがよいのかは好みによります。 市販の問題集では、図やイラストを用いて視覚的にも頭に入りやすくしていたり、ぱっと見てわかりやすいレイアウトであったりと、さまざまな工夫がされています。 その中から自分が見やすい・使いやすいと感じる教材を選びましょう。 3.授業の予習・復習&定期テスト対策に おすすめ問題集3選 こちらでは、予習・復習・定期テスト対策にぴったりの問題集を紹介します。 学校で習った内容を自分のものにするには自宅での学習は欠かせません。 教科書準拠の英語の問題集ならば授業に沿った学習ができ、テスト対策にも効果的です。 中学教科書ガイド 英語 【2025年度改訂】 教科書の内容をしっかり理解したいならば「中学教科書ガイド 英語」がおすすめです。 教科書全てを網羅した内容で、問題の答えや文法解説が詳しく、一人でも学べる工夫がされています。 毎日の復習にぴったりな問題ページも充実しており、定期テストに出題されやすい英語の文法など要点をわかりやすく学べます。 教科書ガイドが1冊あれば、1年間の教科書レベルの内容が習得できるつくりになっているのも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク 英語 【2025年度改訂】 教科書ワークはオールカラーの整然とした見やすい紙面が特徴の問題集です。 単元ごとにステージ1から3まで自然とレベルアップできる仕組みで、教科書の内容理解が深まります。 また、1冊で英語4技能である「書く(ライティング)」「読む(リーディング)」「聞く(リスニング)」「話す(スピーキング)」全てが学べます。 定期テスト対策として使える「スピードチェック」、音声つきの「英単語カード」、PCやタブレットで取り組める自動採点CBT、手軽に取り組めるWEBアプリ「Newどこでもワーク」といった付属品も豊富です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 英語 【2025年度改訂】 こちらは定期テスト対策にぴったりの問題集です。 特に大切な要点を押さえた解説と、テスト対策に絞った問題がそろっています。 2色刷の紙面のため、重要なポイントを赤シートでかくしながら、効率的に学習できます。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なものがそろっているのもうれしいポイントです。 毎日の学習に「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、定期テスト前にはこちらの問題集も活用する、という使い方をおすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 4.レベルに合わせて、実力アップができる おすすめ問題集3選 こちらでは英語の学力レベルごとにおすすめの問題集を紹介します。 英語は積み上げ型の教科のため、自分の習熟度にあった問題集でなければ、思うような効果が上がらない場合があります。 自分のレベルに合っている問題集を日々の学習に取り入れて、成績向上に役立てましょう。 わからないをわかるにかえる 英語 【2025年度改訂】 「英語を基礎の基礎から勉強したい」という人におすすめの問題集です。 オールカラーの紙面はイラストや図をふんだんに使い、わかりやすさを追求しています。 特に文法の図解は視覚的に理解できるため、英語に苦手意識のある人でも学びやすいでしょう。 演習問題の分量も絞っているので毎日続けやすく、重要単語カードやリスニング音声もそろっています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 英語 教科書の内容はある程度理解できていて、「さらに一歩進みたい」という人におすすめです。 基本問題、標準問題、実戦問題と段階的にステップアップできます。 教科書とはちがう題材で豊富に演習するため、定期テスト対策から高校入試の基礎固めまでの確かな実力が身につくでしょう。 各単元の冒頭にQRコードがあり、スマホで音声が聞けるのも特徴です。 また、発音の練習ができるスピーキングアプリもあり、リスニング・スピーキング対策もしっかりできます。 (※スピーキングアプリは「完全攻略英文法」には付属していません。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 英語 難関高の受験を視野に入れながら、中学英語を完璧に近づける問題集です。 中1から過去の入試で出題されたレベルの問題に触れられます。 定期テストレベルの「徹底理解」から、ややレベルの高い「実力完成」、難関校入試レベルの「難関攻略」と、段階的に国立・私立難関校を目指せる高い学力を育成する構成になっています。 英語が得意な中学生、難関校を目指している中学生にとっても手応えを感じられる1冊でしょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.高校入試に備える おすすめ問題集3選 高校入試の英語は、中学3年間で学習した内容の理解が求められます。 高校入試の約7割が中学1 ~2年生で学ぶ範囲から出題されるため、早めの対策と学習の定着が合格のカギです。 高校入試対策ができる問題集を活用し、苦手をなくしましょう。 わからないをわかるにかえる 高校入試 英語 中学3年間で学んだ英語の知識を、基礎レベルから入試レベルまで一気に引き上げてくれる問題集です。 高校入試対策のはじめの1冊として、苦手な単元をしっかりやり直して入試に挑みたい受験生にぴったりな内容となっています。 とくに巻末の「入試対策」では英作文、長文読解、リスニングについて、出題パターン別に解き方を徹底解説しているため、英語が苦手な人も取り組みやすいでしょう。 入試直前まで使える合格ミニブックなど便利な付録もついています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策 !「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」「10日間完成中学3年間の総仕上げ」 英語 8日間or10日間で仕上げる入試対策用の英語問題集です。 うさぎとヒツジのかわいいキャラクターがコーチとして解説を担当してくれるため、受験対策が楽しくなるような紙面となっています。 「8日間中学1・2年の総まとめ」 入試までまだ時間的余裕はあるけれど、これまで勉強してきた単元に不安がある、短期間に復習をしたいという人に最適です。 8日間で中学1年、2年の復習と定着確認ができます。 使用時期は3年生に進級する直前の春休みや3年生の夏休み頃がおすすめです。 「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 こちらは3年間の総仕上げができる問題集です。 使用時期は3年生の夏休み∼冬休み頃がよいでしょう。 入試のリハーサルができる模擬テストつきです。 どちらも英文法が色分けして解説されていたり、問題を見ながら採点ができる縮刷解答がついていたりと、英語の学習をスムーズに進める工夫がされています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 「中1・2の総復習」「3年間の総仕上げ」 英語 こちらも高校入試対策にぴったりな問題集です。 1カ月ほどで取り組めますが、ボリュームがあるため計画的に進めるのがよいでしょう。 要点とポイントが簡潔にまとめてあり、標準問題からステップバイステップで入試レベルまで力を伸ばせます。 「3年間の総仕上げ」の後半に収録されている「入試対策特集」は問題数が多く、文法・語彙・表現、英作文、読解、リスニングについて分野別に対策ができます。 じっくり取り組めばこれ1冊でも英語の入試対策が可能です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 6.英検®対策に!わからないをわかるにかえる英検® シリーズ 英検®対策には、基本から学べて合格力がつく「わからないをわかるにかえる英検®」シリーズがおすすめです。 教本を兼ねた「問題集」、単語や表現をまとめた「単語帳」があります。 わからないをわかるにかえる英検® 問題集 【2025年度改訂(2級・準2級・3級)】 英検®チャレンジ1冊目におすすめの問題集です。 英検®の試験を解くために必要な文法を丁寧に解説し、英検®初挑戦の人にも手取り足取りわかりやすい紙面になっています。 単元ごとに最重要事項や合格のカギが細かくチェックできるほか、ライティングやリスニングの出題パターンと解答手順が詳しく解説されているのも魅力です。 「練習問題」を解き、「実戦問題」で実力をつけ、「模擬試験」で本番に備えましょう。 また、一人では対策しづらい4級・5級のスピーキングテストや、3級以上の二次面接対策の対策についてもポイントを押さえて解説しているため、万全の対策で試験に臨めます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる英検® 単語帳 単語を覚えるには、「わからないをわかるにかえる英検® 単語帳」がおすすめです。 1回15分! 単語帳で覚えて、テストで解くから忘れません。 QRコードの読み取りで、単語やフレーズの音声を聞くことができます。 付録のスマホアプリ「どこでもワーク」では本冊に対応した単語をいつでも、どこでも学べます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 7.まとめ 中学英語の問題集は目的を決めてレベルに合ったものを選ぶ必要があります。 教科書準拠の教材を使えば、普段の予習・復習として基礎を固めることができますし、入試対策の教材を使えば、効率的に目標とする高校の合格に近づけるでしょう。 英語は中学生の間に基礎をしっかり固めることで、高校受験対策も進学後の学力アップも難しくはありません。 ぜひ文理が発行する英語問題集を学力アップにお役立てください。
これで大丈夫! はじめての定期試験
動画で大筋チェック 定期試験の足音…? 冬のような寒い日と、初夏のような暑い日を行き来しながら4月・ゴールデンウィークが過ぎ、 ようやく新しい環境にも慣れてきたのではないでしょうか。 新しい学年で、新しい行事が多いなか部活や遊び、勉強と忙しくも楽しい日々を送っていると思います! あと2~3週間でやってくるのが、定期試験です。学年内順位が出たり、偏差値化されたり、進学に関わったり…と大事な試験です!緊張しますよね。 逃げず、焦らず、今からしっかりと対策すれば大丈夫です! 今回は、定期試験対策のコツをご紹介します。 過去の記事では、連載も行っていました!こちらもぜひ参考にしてみてくださいね♪ 【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回 タイムマネジメント! 平日は学校や部活など、なにかと時間が取られるものです。試験が近づいてきたからといって、食事や睡眠を削った無理は禁物です! まずは試験までの残りの期間、どのくらい勉強をする時間があるか確認してみましょう。 次に、五教科のゴールを決めて、そのために何をすべきか書き出してみましょう。 決められた時間はしっかりと切り替えて勉強できれば、着実に実力アップできます! ノートやプリントが揃っているか、しっかりチェック! 学校の先生は、こだわって授業を行って、試験を作っています。 まずは、先生方の板書をしっかりノートにとっているか、プリントは揃っているか、しっかりと確認しましょう。 足りない部分は先生やクラスメイトにしっかりと聞くのがベスト。それでも足りない・間に合わない!という場合は、教科書や学習参考書で補うこともできます。 事前準備は必ず完璧にして、試験勉強に挑みましょう。 暗記、練習、見直し 「ノートは極力色を付けずにとって、ノートの内容全てを覚えられるようにしましょう。」 「ノートの重要な単語は薄いピンクやオレンジのペンで書いて、赤シートで隠して覚えるといいですよ!」 …巷には色々な勉強方法に関する情報が溢れています。是非色々な方法を試してみてください。きっと自分に合う方法が見つかるはずです。 ノートやプリント、学校で配布される問題集で暗記・練習を繰り返すことが、基本になります。 そのうえで、理解が不十分だと感じた場合や、もっと演習量をこなしたい場合には、市販の学習参考書を活用してみましょう。 では、ここからは学習参考書の具体的な活用方法をご紹介します! 活用方法① 解説をしっかり読んで、練習! 授業やノートだけでは分からない部分や、苦手意識がある単元は丁寧な解説付きの参考書や、教科書準拠の参考書で説明のページを読み、少しずつ練習してみましょう。 問題を解いた後は、必ず解説を読みましょう!徐々に力が付いてきます。 活用方法② 効率的にいつでもどこでも暗記! 全ての教科を完璧にするほど時間がない…!というそこのあなた! 市販の学習参考書には、付録が付いていることをご存じですか?小さい復習ノートや、単語カードなど付録は勉強の心強い味方です。たくさん活用しましょう! 活用方法③ 試験の予行演習! 授業の内容や、教科書の内容を覚えられるようになってきたら、今度は試験の予行演習をしてみましょう! 教科書ワークや定期テストの攻略本では、試験の練習ができます。時間を測って解いてみて、丸付け、間違い直しをしましょう。 何回か練習をすれば、試験にも慣れるはずです。 さあ、本番に向けて気持ちを整えて、学習を始めましょう。 試験があるからといって無理は禁物。しっかりと食べて、睡眠をとってください!キュリオとの約束ですよ! 定期テスト対策におすすめのシリーズ 中学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら! 今回の執筆者東京営業部 A 水族館巡りが大好き!最近イカやタコはとても頭がいいことを知って、飼育を検討しています。
GW前に、定期テストの勉強法をおさえておくのが吉!
GW、思いっきり楽しみたいですね! 色々予定が入っている人も、のんびり休むぞ!という人も、 いるでしょうか。 せっかくの連休ですから、充実した楽しいものにしたいですね。 しかしちょっと待ってください。 中学生の皆さんは、 このタイミングで定期テスト対策について知っておくのがおすすめです。 その理由は? その理由はずばり、 です。 中学校の中間テストは、だいたい5月中旬~6月中旬に行われます。 GW明け、なかなかスイッチが入らないうちにテスト期間に突入!となったら、 「何から始めればいいのか?」「間に合うのか?」と焦ってしまいますよね。 あんなに楽しかったゴールデンウィークを、「あの時始めておけば…」と後悔する羽目になるかもしれません。 中学1年生なら、初めての定期テストなのでなおさらです。 事前に、定期テスト対策はどのくらいの期間で、何をすればいいかが分かっていれば、 休み明けに対する心づもりをしておくことができますね。 いままで「なるほど!Bunri-LOG」では、定期テスト対策についてもたくさん紹介してきました。 GW前に一度読んでおくといい記事を、いくつかまとめます! 定期テスト対策のオススメ記事 中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介 ▶記事を読む テスト勉強を始める時期や、教科別のポイント、テスト対策に おすすめの問題集についてまとめています。 【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回 ▶記事を読む より具体的に、テスト勉強のやり方の一例を紹介! 全5回+おまけ の連載記事です。 青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法 ▶記事を読む 青色、オレンジ色、緑色… 色が勉強のしやすさに与える影響があるという話を聞いたことはありませんか? 心構えを作ったうえで、GW楽しみましょう! 悔いのないGW、悔いのない定期テストになるよう、応援しています!
ゴールデンウイークはしっかり体を休めよう!
4月もそろそろ後半ですね。 新学期から始まった新生活には慣れましたか? 入学したての学校やクラス替えで緊張したり、部活に入部してハードな練習をしたり、学年が上がって学習内容も難しくなって来て、、、と忙しい毎日を過ごしているのではないでしょうか。 新しい生活は刺激いっぱいで楽しいですが、知らず知らずのうちに疲れやストレスも溜まってくるものです。 5月のゴールデンウイークで少し学校もお休みですから、この機会に新学期の復習に集中・・・も良いですが、ここは一旦机を離れて、ゆっくりお休みするのはいかがでしょう? ということで、ゴールデンウイークに取り入れたい休み方を考えてみましょう。 入浴 身体を休めるには入浴が効果的なようです。 もし普段は部活や習い事に追われてゆっくりお風呂に浸かっていないという人は、せっかくのお休みの日は時間をかけてお風呂に入るのはどうでしょうか? 個人的におススメなのでお風呂の電気を暗くして、温めのお湯に入浴剤を入れてゆっくり浸かることです。 リラックスできて良いですよ~。 昼寝 5月となれば暖かくなってきますからね。 早い時間にお風呂に入って、暖かい日差しをうけながらウトウトと昼寝・・・。 最高ですね。 コーヒーや紅茶などカフェインが入っている飲み物が好きな人もいるかも知れませんが、なるべくカフェインを取らない方が寝ている間に体が休まるようですよ。 なお、学校が休みだからと言って夜遅くまで起きて、朝寝坊するのは考えものです。 生活のリズムが狂ってしまいますから、学校がある日と同じように早寝早起きは基本ですね。 適度な運動 身体を休める、と言うとついつい家にこもりがちですが、適度に運動した方が睡眠の質は良くなるようです。 晴れた日は友達と外で遊んだり、ひとりで家の近くを散歩したり、家族と近所のお店に買い物に行ったり、日中は太陽の光を浴びて気持ち良く過ごしたいですね。 家のお手伝いで体を動かすと家族に感謝されて一挙両得ですよ。 ごはんを食べる 体力回復には十分な栄養補給が一番。 普段忙しくて朝食を摂っていないなど不規則な食生活をしていませんか? 連休の内に規則正しい食生活を意識しましょう。 好きなメニューのレシピを調べて、自分で作ってみるなど、新しいチャレンジをしてみても良いですね! という事で、今年のゴールデンウイークは新学期から頑張った心と体を一旦休めることを意識して過ごしてみてはいかがでしょうか。 充分休養を取って元気が出たら、また文理の問題集を開いて勉強を頑張って行きましょう! ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:30代 今回のひとこと:最近は毎週末ヤリイカを買ってさばき、イカソーメンにして食べています。北海道のヤリイカは美味しいですね~。
みんなで学ぼうSDGs!
?明日は何の日? 4月22日はアースデイ(別名:地球の日、英語:Earth Day)です。 1970年に始まった「アースデイ」は世界175カ国、約5億人が参加する世界最大の地球フェスティバルで 地球の環境保護への支援を示すための毎年恒例のイベントです。 近年の「アースデイ」への関心の高まりは、SDGsに大きな関わりを持ちます。 SDGsにも地球の環境保護のための項目が含まれています。 「SDGs(エスディージーズ=持続可能な開発目標)」は、最近の中学・高校入試において頻出のテーマの一つです。 この記事では、そんなSDGsについてあらためて学んでいきたいと思います。 1.SDGsって何? SDGsは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、17の目標を掲げた国際的な取り組みです。 これらの目標は、世界中で直面している課題を解決し、持続可能な未来を実現するために設けられました。 誰ひとり取り残されることなく、人々が安定してこの地球で暮らし続けることができるように、 世界のさまざまな問題を整理し、解決に向けて具体的な目標を示したのが、このSDGsなのです。 2015年に国連で採択され、国際社会は一致団結して、2030年を目指してこの目標を達成しよう、と合意しました。 2.SDGsの目標とは? SDGsには17の目標があります。以下にそれぞれの目標を紹介します。 1.貧困をなくそう 2.飢餓をゼロに 3.すべての人に健康と福祉を 4.質の高い教育をみんなに 5.ジェンダー平等を実現しよう 6.安全な水とトイレを世界中に 7.エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基盤を作ろう 10.人や国の不平等をなくそう 11.住み続けられるまちづくりを 12.つくる責任、つかう責任 13.気候変動に具体的な対策を 14.海の豊かさを守ろう 15.陸の豊かさを守ろう 16.平和と公正をすべての人に 17.パートナーシップで目標を達成しよう 3.SDGsを実現するためには? SDGsを実現するためには、私たち一人ひとりが、行動を起こすことが大切です。 私たちが簡単にできることとして具体的には、以下のようなことが挙げられます。 1.ライフスタイルを見直し、環境に優しい行動を心掛ける こまめな節電・節水で無駄なエネルギー消費が抑えられます。 また、エコバックやマイボトルを持ち歩くことでプラスチックごみの問題解決に貢献できます。 簡単なことに思えますが、一人ひとりが心掛けることが何よりも大切なのです。 2.SDGsに関する情報を学び、周りの人たちと共有する SDGsについて、学校の「総合的な学習の時間」や「社会」の授業で勉強します。 学校で勉強したことをぜひ、保護者の方々に共有してみましょう!それも立派なSDGs実現に向けた取り組みです。 3.市民活動やボランティア活動など、SDGsに向けた取り組みに参加する 支援団体が募集するボランティア活動に参加することで、実際にSDGsに貢献している実感を持ちやすいです。 保護者の方と一緒に、身近な場所で開催されているボランティア活動に参加してみるのも良いかもしれません。 4.SDGsと入試 前述のとおり、SDGsは、最近の中学・高校入試において頻出のテーマの一つです。 実際の入試ではどのようにSDGsについて問われるのでしょうか? 最も基本的な出題例は、「SDGs(=持続可能な開発目標)」を日本語またはアルファベットで書かせる問題です。 複数の学校において、同様の問題が出題されています。 また、SDGs実現のために実際に行われている取り組み事例などをあげて、 さきほどあげたSDGsの17の目標のうち、どの目標に該当するか選択肢の中から選ばせる問題も頻出です。 難関校では、SDGsの17の目標について自由記述で深く掘り下げる必要のある問題が出題されています。 まとめ SDGsは、持続可能な開発を進めるための国際的な取り組みで、17の目標が掲げられています。 SDGsを実現するためには、私たち一人ひとりの行動が重要です。 SDGsに関心を持ち、積極的に取り組むことで、世界中の人々の生活を良くし、持続可能な未来を実現することができます。 SDGsは、2030年までの達成を目指しています。2030年というと、今の小学6年生は20歳を迎えるころでしょうか。 先ほどSDGs実現のためにできる具体的な行動などを紹介しましたが、学生のみなさんに何よりも真剣に取り組んでほしいのが「学ぶこと」です。 2030年を迎えるころには、今の学生のみなさんは社会だけでなく、世界・地球を支える大人になります。 その時のために、今のうちに、学校の授業や友だちとの遊びなどを通して、たくさんのことを学んでいってください! 【今回の執筆者】 イニシャル:M 年代:20代 ~今日の一言~ とにかく言いたいSDGs!
小1プロブレムを乗り越えるには?
新1年生の保護者のみなさま、お子さまの小学校入学、おめでとうございます。 わが子のこれからの成長が楽しみな半面、学校生活にうまくなじんでくれるか、友だちはできるかなど、気がかりなこともあるかもしれません。 小学校に入学すると、これまでの家庭や保育園、幼稚園での生活とは大きく変わってきます。 慣れないことばかりで、学校生活や勉強につまずく子どもは少なくありません。 本日は、そんな小1プロブレムについてのお話です。 小1プロブレムとは? 小1プロブレムとは小学校に入学したばかりの子どもが、学校生活になじめず、行動面・精神面・学習面などで問題にぶつかることです。 たとえば、 行動面では、 ・集団行動がとれない ・授業中席についていられない ・先生が話しているときに勝手に話し出す 精神面では、 ・集中力が続かない ・ストレスで体調不良に陥る、休みがちになる 学習面では、 ・読み書きなどの学習に遅れが生じる ・学習意欲が低下する などの問題にぶつかることがあります。 小1プロブレムの要因は? では、なぜ子どもたちが小1プロブレムに陥るかというと、それはそれまでとは大きく異なる環境に置かれるからです。 たとえば、幼稚園や保育園では比較的自由な教育が行われますが、小学校では決められた時間、席について授業を受けなければならず、とまどうことがあります。 また、この年齢の子どもはまだ発達の初期段階にあるため、集中力が短く、読み書きや計算などの学習に対しても未熟な場合があります。 また、家庭環境が学習に与える影響も大きいです。 家庭学習の習慣が身についていないと、学校の授業についてゆくことが難しくなります。 小1プロブレムの解消に向けて 小1プロブレムにぶつかったら、焦らずお子さまと向き合うようにしましょう。 まずは、今日学校であったこと、勉強したこと、楽しかったこと、嫌だったことなど話を聞いてあげてください。 そして、お子さまが自信を持てるように、肯定的な言葉をかけるようにしましょう。 また、家庭での学習習慣を身につけさせることも大切です。 その際、お子さまが興味を持った教材を用いることで、学習意欲を高めることができます。 また、学習の合間には適度な休憩をとり、集中力を切らさないよう、徐々に訓練していきましょう。 家庭と学校の連携も重要です。 学校とのコミュニケーションをとり合い協力して、お子さまにあったサポートを行いましょう。 まとめ お子さまが学校になじめないと、保護者のみなさまも焦燥感を抱くかもしれません。 けれども、これはお子さまが成長する過程で起こりうることです。 じっくりお子さまと向き合い、環境を整えてゆくことで、解決の糸口が見えてくることがあります。 見守りながら、サポートしていきましょう。
理科と社会の1・2年生 始めました!
2023年3月に、文理から「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク」が発刊されました。 コンセプトなどはこちらからお願いします。 今日は理科と社会の1・2年生ってどんな内容なの? という謎にお答えします。 ★カッチカチに回答すると 小学1・2年の理科と社会は、 3年生以降の内容の先取りとなっております。 メールでお問い合わせいただいた場合は、このような回答になります。しかし、ここはブログなので、編集者の気持ちを前面に出してお答えしましょう。 理科編集担当から 主に3・4年生の学習内容を中心に構成していますが、テーマによっては5・6年生の内容にも触れています。 “理科”は一度で学習したらおしまい、ということはなく、学年が上がると共に内容を深堀りしていく教科です。 たとえば4年生では、人の体のしくみとして骨や筋肉について学習しますが、6年生ではさらに呼吸のしくみや食べものの消化・吸収などを学習します。 ワークの中では、小学校のどの学年で学習するかも示しました。 理科への興味・関心をもってもらえるよう、植物・動物、天体、電気、力、大地の変化など、さまざまなテーマを扱っています。 1・2年生にも“理科”がわかりやすいように、身近な題材・テーマをピックアップしました。 “教科学習”が始まる前の準備として、文字をなぞったり、シールを使って答えたりして、楽しみながら取り組むことができるように工夫しました。 イラストや写真をたくさん使っているので、すべてのテーマの学習が終わると、1冊の図鑑のように読み直すこともできます。 社会編集担当から 地図や、地域の様子、社会のしくみを学習する3年生・4年生の内容が中心になっています。 でも、それだけだと「ザ★社会!」という感じがしない(?)ので、都道府県や世界の国々のようすの入門的な内容も入っています。 社会といえば、書いて覚える暗記教科! というイメージがあるかもしれませんが、1・2年生の成長や発達をふまえて、楽しみながら学習ができるように工夫をました。 たとえば…… シールをはって答えたり、 めいろを解いたり、 さまざまな作業をしながら、思考力を伸ばし、社会の見方・考え方を身につけることができます。 また、人に教えたくなる(?)もの知りクイズも掲載。 解くと得意になる! 誌面見本でお気づきかもしれませんが、小学校低学年でも読み進められるように、すべての漢字にふりがなを付けています!理科も社会も、小学校1・2年生が授業で学ぶ前に学習することで「私できる! 得意だよ」になれる教材になっております。ぜひご購入をご検討ください! 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
【2025年度最新】教科書準拠の問題集で新学期を一歩リードしよう!
新学期、始まりました! 新しい教室、新しい学年でバタバタな日々だと思いますが、この時期は何かとわくわくしますよね! 初回の授業を終えた方も多いのではないでしょうか? 新学年の教科書を開いて難しそう・・・と不安に思っている方や、今年こそは成績あげるぞ!と意気込んでいる方も 文理の「教科書準拠の問題集」で勉強を始めてみませんか? 教科書準拠の問題集とは? 「教科書準拠」と言われてもピンとこない方もいるのではないでしょうか? 「教科書準拠」とは、それぞれの教科書の内容に沿って作られているという意味です。 教科書準拠の問題集のメリットには次のようなメリットがあります。 ・学校で使う教科書の内容に沿った内容の教材 ・学校の授業の進度に沿って学習ができる ・予習や復習、定期テストに向けた勉強に最適 まさに教科書が配られた今! 使用開始するのにぴったりな教材です! タイプ別「教科書準拠」の問題集のおすすめ! ひとえに「教科書準拠」の問題集といっても様々あります。 ここでは、皆さんがどのように勉強したいタイプかに分け、おすすめを紹介します! ◎教科書の内容理解を徹底理解したいキミに! →→→「教科書ガイド」がおすすめ!(小・中・高) 教科書ガイドは教科書に掲載されている問題の解答や、解説が載っていて、授業内で分からなかった部分もしっかりサポートしてくれます! まずは授業の内容を完璧に理解したい方におすすめです! 小学教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 高校教科書ガイド ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ◎問題を解きながら予習・復習を徹底しつつ、テスト対策もしたいキミに! →→→「教科書ワーク」がおすすめ!(小・中) 「教科書」ワークはスモールステップで進める構成で、学校の授業に合わせて、予習・復習さらにはまとめの問題でテスト対策まで対応できます! また、「小学教科書ワーク」「中学教科書ワーク」ともにふろくが充実しているので、授業のプラスαの内容も学習できます! 小学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ワーク ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ◎まずは学習習慣を身につけたい小学生のキミに! →→→「教科書ドリル」がおすすめ!(小) まずは毎日の学習習慣を身につけたい方には短時間で取り組める「教科書ドリル」がおすすめ! 毎日の学習習慣が身についてきたら、予習やテスト対策が1冊でできる「小学教科書ワーク」と組み合わせるのもおすすめです! 小学教科書ドリル ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ◎定期テストの対策をメインに学習したい中学生のキミに! →→→「定期テストの攻略本」がおすすめ!(中) テストに出る内容に焦点を絞ってあるので効率的に学習することができます! 日々の学習を「教科書ガイド」や「教科書ワーク」で取り組みながら、 テスト前に「定期テストの攻略本」を使用するとより得点アップが期待できます! 定期テストの攻略本 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 文理の「教科書準拠」の問題集は様々ありますが、ご自身の用途で使い分けてみてくださいね! 教科書準の問題集を探すなら 教科書準拠の問題集を使ったおすすめの勉強法! では「教科書準拠」の問題集を使ってどのように勉強すれば良いのか? おすすめの勉強法についてご紹介します! 1.目標を設定する 勉強を始める上で目標を設定することは非常に大切です。 特に新学期は心機一転新しい目標にチャレンジできる絶好の機会です! 目標を設定することで、やる気を持続させることもできます。 目標は、例えば初回の定期テストまでと短期的なものから、 1年後目指す姿と長期的なものまで、幅広く立てることができますが、 長期的な目標を立てて途中で挫折しないよう、まずは短期の目標を設定することをおすすめします。 2.計画を立てる 目標を立てたら今度はその目標を達成するための計画をたてましょう! 計画は1日2時間勉強するといった抽象的なものではなく、 「数学の予習を中心に問題集の5ページ~30ページを1週間で学習する」 など、具体的に何をするかといったことまで決めるようにしましょう。 「教科書準拠」の問題集を使用すれば、 教科書の単元と見比べながら学習する範囲を決めることができるので、 授業の進捗具合に応じて学習する内容を組み立てることができます。 3.文理の教科書準拠の問題集で予習・復習! 予習・復習は、日々の授業をしっかりと理解するために非常に重要な勉強方法です。 授業前に予習をし、授業で学んだ内容をしっかりと復習することで、理解度を深めることができます。 教科書準拠の問題集は授業の進度に合わせて使用できるため、 授業の予習・復習にぴったりな問題集です! 特に教科書ワークはスモールステップで進める構成になっているので、 予習でまとめページや基本的な問題の学習を行い、 授業で学習の理解度を確認、 さらに復習で応用問題に取り組めば、確実に学習が定着します。 4.学習記録をつける 日々の学習記録をつけましょう! 学習時間を記録しておくと、自分の学習状況が可視化できることはもちろん、モチベーションにも繋がります。 また、次の目標を立てる際にも以前の学習時間を参考にすることができ、効率的に学習計画をたてることができます。 「教科書準拠」の問題集の学習記録は「まなサポ」がおすすめです! 「まなサポ」は毎日の学習時間を記録、確認することができるシンプルな無料アプリです。 ▶学びサポート 5.適度に休息! 新学期から飛ばしすぎると途中で息切れしてしまします。 適度にお休みの日を作り、無理なく継続できるように気をつけましょう。 特に勉強が手一杯になって睡眠時間が・・・なんてことにならないよう、 スモールステップでコツコツ実践していきましょう! 新学期頑張るキミを応援!文理のキャンペーンについて 文理ではただいま春のキャンペーンを開催中です! 今回ご紹介した「小学教科書ワーク」ではキャンペーンを実施中です。 ぜひこの機会に応募をお待ちしています! ▼2025年度 小学教科書ワーク4科目セット キャンペーン
ご入学・ご進学おめでとうございます!~新学期の舞台裏を大調査~
祝 入学・進学! 早咲きの桜は新緑に代わり、すっかり春らしい季節になりましたね。 新学期を迎えたみなさん、ご入学・ご進学おめでとうございます! これから新しいクラスで運動や勉強をがんばろう!と意気込んでいるのではないでしょうか? なにか目標を立てて、一生懸命取り組んでみましょう。 2023年度が、たくさん成長できる一年になりますように! 春はみんなが忙しい季節… 保護者の方々、学校の先生などなど、みなさんの頑張りをサポートする方がたくさんいます。なので、そんな方々も新学期は大忙し。 みなさんと新しい学級で気持ちよく学校生活をスタートするために、先生はどんな準備をしているのでしょうか? 今回は、学校の先生にインタビューしてみました! 学校の先生にインタビュー! 答えてくれた方: 公立小学校で先生をしているAさん Q.体育館で、先生が挨拶をしてくれます。大勢の前で挨拶をして緊張しないのですか? A.緊張します!伝えたいことを忘れないように、メモを書いて何度も読んで暗記しています。 Q.教室が飾りつけは、担任の先生が用意しているのですか? A.みなさんの入学・進学をお祝いして、先生総出で教室の飾りつけをしています。 それ以外にも、みなさんの机やロッカーの場所を決めて名前シールを貼ったり、学級文庫を整理整頓したりしてスムーズに学校生活が始められるよう頑張っています。 Q.児童・生徒の顔や名前はどうやって覚えていますか? A.担任するクラスが決まった時から、まずは名前を一生懸命覚えています!名前シールをたくさん作るので、自然と頭に入ることも多いです。 新学期になって顔を合わせるようになったらすぐに顔と名前が一致するようになります。 答えていただき、ありがとうございました! …新学期の舞台裏が少しだけ分かりましたね! これ以外にも先生は、保護者の方とスムーズにやりとりができるように懇談会の準備をしたり、年間計画をたてたり、学年・学級だよりを用意したりと、 先生同士で協力しながら色々な準備をしています。 先生やクラスのみんなと一緒に、学校生活を全力で楽しみましょう! 保護者の方々も、お道具箱の準備や給食セット・教科書の用意など、色々な準備があります。 学校生活以外にも、家庭学習や習い事など、春はたくさんのことを始める時期ですね! 保護者の方にもインタビューしてみましょう。 実はこんな準備をしていた…といった発見ができるかもしれませんよ!
世界の国々こんにちは ~セネガル~
4月4日は何の日かと調べてみたら、「獅子の日」だったり「ヨーヨーの日」だったり、「あんぱんの日」(明治天皇が水戸藩の下屋敷を訪れた際、あんぱんが献上されたとされる)だったりしたのですが、ひとつ、目が留まったのが、「セネガルの独立記念日」。 これが異彩を放ってるように見えました。 「セネガル」といえば、何を思い浮かべます? ん、「セネガル」? セネガルって、アフリカですよね。 セネガル、聞いたことはありますが、ぼんやりとしています。 どこにあるのか、どこから独立したのか、何を食べているのか、全く知らないので、ちょっと知りたくなりました。 そういえば、セネガルといえば、私が真っ先に思い出したのは、サッカーでした。 思い起こすと2018年のロシアワールドカップ日本代表がグループリーグで対戦していました! キーパーの川島選手がパンチングしたボールが相手選手(マネという有名な選手)に当たり、先制された試合です。 のちに、途中交代の本田圭佑選手が同点弾を決め、結果は2対2に。思い出された方もいらっしゃいますかね。 日本がセネガルに一番近づいた日ではないでしょうか。 「セネガル」はどんな国? セネガルはアフリカ大陸の最西端にあり、面積は日本の約半分。公用語はフランス語のイスラム国家。 ということは、と思ったら、やはりかつてはフランスの植民地の時代があり、第二次世界大戦が終結後、1960年の4月4日にマリ連邦としてフランスから独立、その後、単独国家としてセネガル共和国となりました。 セネガルでは人気スポーツはやはりサッカーだそうです。 2002年の日韓ワールドカップではベスト8、前述の2018年のロシア大会、 そして昨年2022年のカタール大会の3階の出場をしております。 ロシア大会の日本戦で点を決めたマネ選手は、セネガルでは英雄で、イングランドやドイツリーグで活躍しています。 また、首都は「ダカール」。 「ダカール」と聞くと、「パリ・ダカールラリー」をすぐ思い出してしまいます。 サハラ砂漠の中を縦断するので、世界一過酷と言われていたカーレースです。(第1回は1978年) 以前は、フランスのパリからスタートして、セネガルのダカールがゴールだったので、「パリ・ダカールラリー」でしたが、スタート地点が変わったりの変遷を経て、今は形を変えての大会になっているようです。 「セネガル」の料理は? 世界の国々をみていくと、食いしん坊な私はどうしても、何を食べているのかが気になります。 なんとセネガルの主食はお米だそうです! アフリカなので、お米とは思いませんでした。 国民料理としては、「チェブジェン」という、魚と野菜の炊き込みご飯。かなりポピュラーだそうで、 たいていのお店にはおいてあるような料理で、日本人好みの味付けらしいです。 あと「マフェ」というピーナッツソースを使った羊肉のシチュー。 見た目はカレーライスのようで、日本人にも違和感のない料理に見えますし、美味しそうです! セネガルに行ってみたい?! アフリカ大陸の西端部に位置するので平均気温は高く、雨季と乾季があるようで、なかなか日本の気候とは異なりそうです。 ただ、ワールドカップで日本と対戦したことがあったり、日本人好みの味付け?!といわれる料理だったり、と 日本とはちょっとつながりがあるセネガル。 世界の国々、いつか訪れてみたいものです。 ~今回の執筆者~イニシャル:N所属:営業部門年齢:50代今回のひとこと:飛行機、久しく乗ってないです
【2023エイプリルフール跡地】ファッションブランド「Bunri」登場!
Bunriは、その日の気持ちや、やる気に合わせたファッションを提案。 勉強を頑張る女の子を応援するブランドです。 Smile Always slowly but surely one step ahead full of curiosity このページは、エイプリルフール用に作成されています。 文理からアパレル商品を販売する予定は 今のところございません。 今回、イラストレーターのたなか様に、文理の学習参考書をモチーフとしたファッションイラストを描いていただきました。 以下、元となった学習参考書と、たなか様よりいただいたコメントを紹介します! わからないをわかるにかえる ーーどんな学習参考書? 「わからないをわかるにかえる」は、やさしくわかりやすい説明で、基礎から積み上げられる学習参考書です。 ニガテ克服にオススメ。高校入試編や、英検対策シリーズもあります。 たなか様よりコメント 少しやんちゃで、元気っ子なイメージのデザインにしました。 全体的にスポーティな印象なので、リボンパーカーでかわいらしさをプラスしています。 中学教科書ワーク ーーどんな学習参考書? 「中学教科書ワーク」は、教科書に沿って作られた「教科書準拠」の問題集です。 毎日の予習・復習~定期テスト対策をサポートします。 たなか様よりコメント 参考書のカラフルな特徴を意識して、さわやかだけどポップな印象にしました。 セーラー襟で学生感も出しつつ、全体的にシンプルにまとめています。参考書の特徴である六角形をポイントで入れてみました。 完全攻略 ーーどんな学習参考書? 「完全攻略」は、教科書レベルでは少し物足りないときにおすすめです。 入試を見据えた日々の学習に活用できます。高校入試対策ができる「1・2年の総復習」「3年間の総仕上げ」シリーズも。 たなか様よりコメント ちょっぴり背伸びをした、お姉さんっぽいイメージのコーデです。 袖が特徴的なジャケットは、ショート丈でトレンド感があります。ベストを合わせてこなれ感を演出しました。 ハイクラス徹底問題集 ーーどんな学習参考書? 「ハイクラス徹底問題集」は、過去問を通して実戦的な力を身につけられる学習参考書です。 日々の授業はばっちりで、さらに力を伸ばしたいときに。 たなか様よりコメント 上級者向けの参考書なので、大人っぽく上品なイメージでデザインしました。 チェック柄のロングワンピースをメインに、ゴールドのベルトで引き締め効果を出しています。 登場した商品の詳細はこちらから! ▼表紙をタップしてシリーズサイトへ Special Thanks! イラストレーターたなか 様 Twitter Instagram skeb
おかしなドリル豆知識
この春、文理からとってもかわいい新刊が出たことをご存知でしょうか!こちらの、「おかしなドリル」です。 今日は、文理のTwitter・Instagramで投稿中の「おかしなドリル」豆知識から、いくつかご紹介します! 画像をタップするとツイートに飛ぶので、気になったら見てみてくださいね☆ 裏表紙まで、お菓子パッケージを意識! 一番の特長は、お菓子のパッケージそっくりなその見た目。 そっくりなのは、オモテだけじゃないんです! 裏表紙を見てみると… お菓子の裏面で、見たことのあるような表示が! 原材料は?保存方法は?なんと書いてあるでしょうか。 シールはクリアタイプ!台紙に貼ることで絵が完成! 8点すべて、シールとシールを貼る達成表が付録になっています。 シールは透明になっていて、達成表に貼っていくことで、自分だけの絵が完成! おかしのキャラクターたちといっしょに、どんな絵を作ろうか…… そんなところも楽しめます! アポロの中には、ラッキースターが…?! お菓子のアポロを買うと、たまに星形のアポロ「ラッキースター」が入っています。 なんと、おかしなドリルのアポロ、「小学1年 けいさん」も、紙面のどこかに ラッキースターが隠されているそうです! 私はまだ見つけられていません…… みなさんもぜひ探してみてください! 楽しくおいしい?勉強タイムをぜひ! 算数が苦手な子も、楽しく勉強できるドリルを作りたい!という思いから作られた「おかしなドリル」 算数と向き合う時間をきっと素敵なものにしてくれるはずです。 おかしなドリル豆知識は、この後も文理のTwitter・Instagramで随時更新しますのでお楽しみに! ▼Instagramでは、制作秘話をマンガで紹介しています! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら SNSキャンペーン開催中! 抽選で、「明治のおかし詰め合わせ」が当たるキャンペーンを開催中です! 応募締め切りは4/16! TwitterからでもInstagramからでも応募できますので、ぜひご参加ください! ▼以下バナーより、詳細をチェック! ~今回の執筆者~イニシャル:I所属:営業部門年代:20代今回のひとこと:顔がかいてあるチョコベビーを食べるのが好きでした
高校生活とアルバイト
新高1のみなさん、4月から晴れて高校生ですね! 皆さんはどんな高校生活を送りたいですか? 高校は中学より規模が大きく、部活や委員会など活動の幅も広がって様々な仲間と協力できるのは楽しいですね。 かくゆう私も高校生活は部活に打ち込んで・・・、という事は全然なく、いわゆる帰宅部でございました(笑)。 中学では部活に所属することが必須だったので、なんとなく運動部に所属してはいましたが、高校は任意だったので特定の部活には入部せず。 しかし帰宅部って、まあ暇なんですね。。。 学校が終わって家でテレビを見て怠惰に過ごす毎日・・・。 そんな中、母親から「あなた家に帰ってきてダラダラしているだけならアルバイトでもしたら?」と言われ、その手があったか!と思って始めたのは近所のスーパーでのアルバイトでした。 労働基準法56条によると満15歳に達した日以後の3月31日が終了するまで働くことができません。 ということは、4月1日以降は働くことが出来るわけですね。 ※校則によってアルバイトを禁止している学校や、許可を得ればOKの学校等、様々あるようですので皆さんの通う高校の規則は必ず確認しましょう。 私が通っていたとある神奈川県の県立高校では当時アルバイト禁止では無かったので、高校1年生の夏から早速アルバイトを始めることしました。 食品スーパーのお仕事 さて、そんな私が初めてアルバイトをしたのは高校と自宅の丁度中間地点にある地元チェーンの食品スーパー。 学校帰りに通うのが便利だったから、と単純な理由でした。 そこでの担当は「品出し」。 どんな仕事か一言でいうと、お店が仕入れた商品を売場に出すこと、です。 スーパーって毎日、仕入先から様々な商品が送られて来ます。 お店に届いただけですと、まだ売場の裏、いわゆるバックヤードに置いてあるだけです。 お客様に買って頂くためには、その商品が置かれている売場の棚に置かないと、誰も買ってくれません。 ですからその入荷品を仕分けし、売場に並べる必要があります。 なんだ、そんなの簡単でしょ。と思うかも知れません。 しかし、これ意外と難しいのです。 まず、商品を売場に陳列すると言っても、売場の棚には1商品あたりにおける量に限りがあります。 ですから、現在売場の棚にはどれくらいの商品が並んでいて、どのくらいの商品を持っていけば丁度良い数になるのかを考えて持って行かないと行けません。 また商品は入荷したけれど、元々バックヤードに置いてある在庫がある場合はそちらから先に使わないといけないので、入荷商品とバックヤードの在庫の数の両方を頭にいれておかないといけません。 さらに、食品を陳列する際は「後から補充する商品は今ある商品の一番後ろに陳列する」というルールがあります。 ご存じの通り食品には賞味期限や消費期限があり、陳列されている商品は手前から売れて行きますので、これをやらないと賞味/消費期限が短い商品が残ってしまいます。 あと、お客さんがある商品を手前から取ると、その商品のスペースが空いてしまうと売場の見栄えが悪くなります。 売れた商品がある棚は奥の商品を手前に動かしてこのスペース埋める「前出し」という作業が発生します。 これを商品補充作業と同時に行っていくわけですね。 と、まあ一口に「品出し」といっても色々な事を考えながら作業するわけです。 お客様からのお問合せ また、意外と多い業務はお客様からの問い合わせ対応です。 スーパーって色々な商品ありますから、どの売場にあるのか迷ったお客様から問い合わせを受けるのです。 しかもお客さんが迷いやすいマニアックな商品になればなるほど聞かれますから、品出し担当は普段あまり商品を補充しないような細かい売場まで把握している必要があります。 あくまで私の個人的な経験ですが、例えば「高野豆腐」は良く聞かれましたね。 豆腐売場にあると思いきや、乾物売場にあるからですね。 あと「餃子の皮」も結構聞かれます。 現材料的には小麦粉ですが、冷蔵が必要なので小麦粉売場にはありませんし、またチルドの餃子が売っている練り物売場を探す方も多いですが、やはり無いのですね。 ではどこにあるかと言うと、、、正解は精肉売り場です。 これは餃子の皮を買う方の多くは一緒に「挽肉」も買うからなのです。 スーパーの陳列って深いですねえ。(あくまで私が働いていたスーパーの例です。) アルバイトは実戦的スキルが付く 他にも売場の様々な場所に散った買い物かごを回収して所定の場所に戻したり、閉店後にブラインドやシャッターを下ろしたり、お客様が汚してしまった棚や床を掃除したり・・・とまあ仕事は多岐に渡ります。 これらの業務を限られた時間内にこなすには、どうすれば効率良く捌けるのか、という点を常に考えながら身体を動かしますし、教えてくれる社員がいたとしてもほとんどの時間は自分で考えながら仕事をしますので問題解決のスキルが付きます。 また毎日お客様からのお問合せを受けますので、初対面の人と対話することにもかなり慣れることが出来ました。 これはなかなか学校生活で身に着けるのは難しいのではないでしょうか。 やはり楽しみなお給料 そしてアルバイトの一番の良いところ、それは何と言ってもお給料です。 私がアルバイトしていた20数年前でスーパーの時給は680円くらいだったと思いますが、1日5時間程度を週3、4日くらい働いて、月4~5万円くらいのお給料を貰っていたと思います。 アルバイトを始める前は月3000円くらいのお小遣いをもらっていましたので、アルバイトを始めてからは母親に「ボクは自分で稼いでいるので、もうお小遣いとか要りません!」と言ったときは気持ちよかったですねえ。 まあバイク買ったり楽器買ったりして毎月全部使い切っていましたが・・・。 まとめ もちろん、アルバイト先からお給料をもらって働くわけですから、失敗したり仕事が終わらない場合は社員の人に怒られたり厳しく指導されたり、病気などよほどの事がなければ決められた出勤日には出勤しないと行けませんので遊びに行くのを我慢したり、辛いことも多かったです。 しかし仕事を通じて学校では学べない経験が出来ますので、もし興味がある方は高校生になってからアルバイトを始めるのも考えてみてはいかがでしょうか?もちろん高校生は学校の勉強が最優先ですから、学業が疎かにならないように気を付けてくださいね! 今回も長くなりましたが、受験生の皆さんがよりよい高校生活を送れるよう願っております! ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:30代 今回のひとこと:今でもスーパーに買い物に行くとアルバイト時代の習慣で「前出し」をしそうになってしまいます。
ちぇこ Czech チェコ?
Dobrý den ! (ドブリーデン) こんにちは! WBC(ワールドベースボールクラシック)、盛り上がっていますねえ~! (執筆時はまだ、大会途中です。)予選ラウンドは順調に確実に勝ちを積み重ね、イタリアにも勝って、決勝ラウンド進出しました! (私は前回、ワールドカップの開催している最中に、このBunri-LOGブログを書いたので、「ドイツ☆スペイン☆コスタリカ」と題して、コスタリカについて、ちょっとだけ紹介させていただきました。) 今回のWBC、予選ラウンドで戦った国は、中国、韓国、オーストラリア、チェコ。中国、韓国、オーストラリアは、そこそこイメージつきますよね。 中国は、言わずと知れた中華料理。万里の長城など。 韓国は、トッポギやサムギョプサル。韓流ドラマは好きな人、多いでしょう。 オーストラリアは、コアラ、カンガルー、オージービーフ。 でも、「チェコ」って? 「チェコ」といえば、って何を思い浮かべます? 今回のWBCの予選最終戦で、チェコと戦って、チェコを意識する出来事がいつくかありました。 佐々木朗希投手の剛速球がチェコの選手のひざに当たってしまったエピソードは、皆さんもご記憶に新しいのではないでしょうか。 一塁の山川選手が当たったチェコの選手に歩み寄り、謝罪する場面があり、球場内から拍手が送られてました。その2日後には、佐々木朗希投手がチェコの選手たちが泊っているホテルを訪れ、両手いっぱいのお菓子を渡した、というエピソードも!佐々木朗希選手、すばらしい! それをうけて、チェコの監督は日本の文化、観衆に驚き、「なんとジェントルなんだ」と感動してくれたらしいです。チェコの監督、すばらしい!! そんな出来事があって、チェコという国をもう少し知りたくなりました。 「チェコ」はどんな国? チェコは東ヨーロッパにある、山脈に囲まれた内陸国です。 チェコって聞くと、チェコスロバキア?って思い浮かぶのは、年代の差がありそうですが、激しく変化してきた歴史が激動を物語っています。 第二次世界大戦が終わった後は社会主義体制の国となり、チェコスロバキア共和国として復活した時代もあれば、自由化民主化路線が布かれるなど、紆余曲折を経て、社会主義の崩壊、そして、スロバキアと分離して、現在のチェコ共和国となっています。OECD(経済協力開発機構)やNATO(北大西洋条約機構)、EU(欧州連合)にも加盟しており、今回のWBSのメンバーが、社会人野球の選手のように多くが仕事を持っての選手だった、という興味深いエピソードもありました。選手たちの職業は、学校の先生だったり、消防士、営業マン、電力会社勤務や大学生など、だったようです。 「チェコ」の有名な食べ物って? チェコと言えば、「ビール」です。国民1人あたりのビール消費量は、なんとチェコが世界一なんですって。(知りませんでした) 主食は「クネドリーキ」というゆでパンです。小麦粉やじゃがいもを練って作ります。 日本人にとってのお米でしょうか。 内陸に位置するチェコは、伝統的に肉料理が中心。豚肉がよく食べられ、牛肉や鶏肉も食べる。 お魚は種類は少ないですが、「鯉(コイ)」を食べるようです。特にクリスマスは「鯉」だそうです。フライにしたり、スープにしたり。ビール煮なんかもあるそうです。 「チェコ」に行ってみたい♪ 日本の北海道よりも北に位置していて、歴史も文化も異なる「チェコ」。今回のWBCで対戦して、心温まるエピソードから「チェコ」をちぇこっと知りたくなりました。 日本代表が決戦のアメリカの地に降り立った際、大谷翔平選手、空港で「チェコ」の国旗が付いた帽子を被っていましたね!粋な計らいに、チェコのキャプテンも喜びのコメントを発表してました。そんな、日本とつながりが深くなった「チェコ」首都プラハには、世界遺産にもなっているお城やステンドグラスなど、世界の中でも屈指の美しい街が広がります。 世界の国々、いつか訪れるのを夢みながら・・・♪ 世界の国々といえば・・・ 文理の定番「小学教科書ワーク」の新学期限定4科目セットの付録は、今年は「世界のあいさつと国旗カード」になっています。そして、あの「地球の歩き方」とコラボしているので、国旗カードの裏には世界のあいさつとともに「ものしりまめちしき」も載っています!よかったら、書店さんに行って、見てみてください。 ※冒頭の「Dobrý den!(ドブリーデン)」はチェコ語で「こんにちは!」です(^^♪ ~今回の執筆者~イニシャル:N所属:営業部門年齢:50代今回のひとこと:世界はひとつ(^^♪
球春到来! 同時ベースはなぜ、セーフ?
3月に入って野球界は一気に盛り上がりをみせております。 しかし子供の野球チームでボランティア審判をしているおじさんたちは、 シーズンオフの真冬に審判講習会に駆り出され3月を待つ間もなくシーズンインしており、 寒風吹きすさぶ原っぱにて、走っては「アウト!」走っては「セーフ」と、 基礎動作をひたすら繰り返すという、遠くから見たらなんとも滑稽だろうなぁと思いつつ、 寒さも相まって体を温めるには格好の運動なのでもあるのですが、 そんな中講師の方から突然こんなことを聞かれたのです。 「同時ベースはなぜ、セーフですか?」と。 同時ベースというのは、例えば打者が打って一塁に走ります。 打者が一塁ベースに到達する前に、打ったボールが一塁に到達したらアウト。 ボールより先に打者が到達したらセーフ。じゃあそれが同時なら?というのが論点です。 ある程度野球を知っている方なら「そりゃあセーフでしょ」を誰もが思うのですが、 ではどうして?と聞かれると「・・・」の方が多いと思います。 ルールブックに書いているからというのでは、本当の回答になっておりません。 野球は「公認野球規則」なる、日本における野球の公式ルールを定めた文書で それを編纂した書籍があり、 いわば野球の法律書なるもので、9つの大項目に分かれて構成されております。 その中に「5.00試合の進行」という項目の中から、 「5.09 アウト」内にある「(a)打者アウト」は、 「(10)打者が第3ストライクの宣告を受けた後、 またはフェアボールを打った後、一塁に触れる前に、その身体または一塁に触球された場合」 という表記があります。 つまり送球・触球と打者の一塁到達が同じだった場合は、 打者が一塁に到達している=「触れているという解釈」によって、 アウトではない=セーフという論理が成り立つわけです。 どうでしょう?そう考えると野球のルールも結構興味深くないですか? ただ、保健体育のテストでこうした設問は、ほぼ問われないでしょう(笑) 弁護士の六法全書然り、野球の審判員も公認野球規則を覚えることは必須でありますが、 ボランティア審判だから、試合前のミーティングでは何卒ご容赦をと言いつつも、 なんとか際どいプレーが起きないよう試合中はドキドキしてしまう、 今年もそんなまた、球春を迎える時期になってしまいました。 ~今回の執筆者~イニシャル:O所属:営業部門年齢:40代今回のひとこと:ジャッジは自信をもって!
ホワイトデーの贈り物
本日3月14日はホワイトデー。 バレンタインデーにプレゼントをもらった人が、お返しを贈る日ですね。 バレンタインの定番といえばチョコレートですが、ホワイトデーには何を贈りますか? バレンタインデーほどザ・定番というものはありませんが、お花やハンカチなどのちょっとした小物はよく選ばれるプレゼントです。 そして、やっぱり人気なのはおかしですね。 ホワイトチョコレート、クッキー、マシュマロ、キャラメル、マカロンなど、かわいくておいしいおかしは喜ばれます。 かわいくておいしいおかしといえば…。 こちらは、おかしではなく、おかしをモチーフにした、小学1・2年生向けの算数ドリルです。 その名も「おかしなドリル」! meijiさんとのコラボレーションで生まれた、この春刊行の新シリーズです。 アポロやマーブルチョコレートなどおなじみのおかしのパッケージのモチーフがドリルのデザインになっています。 ドリルの中身もおかしのネタがいっぱい。 計算問題もこんな風に出題されると、楽しく解けそうですよね。 ご自身のお子さまへのプレゼントに、あるいは小学1・2年生のお子さまのいる保護者の方へにホワイトデーのお返しにそえて、「おかしなドリル」もいっしょにプレゼント、というのはいかがでしょう? ちょっと変わりだねで、喜ばれることまちがいなしです! 「おかしなドリル」のくわしい紹介はこちらをご覧ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら