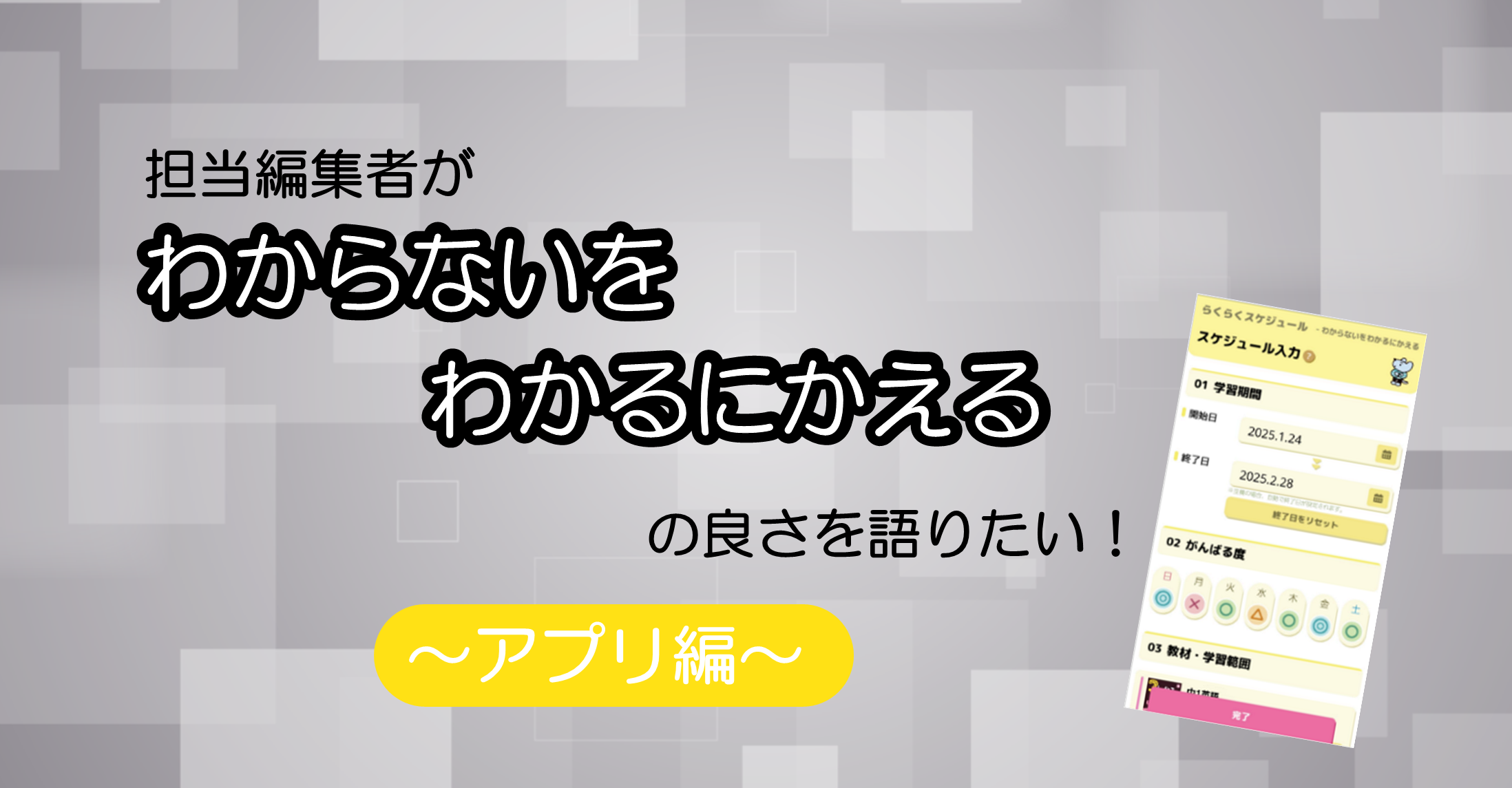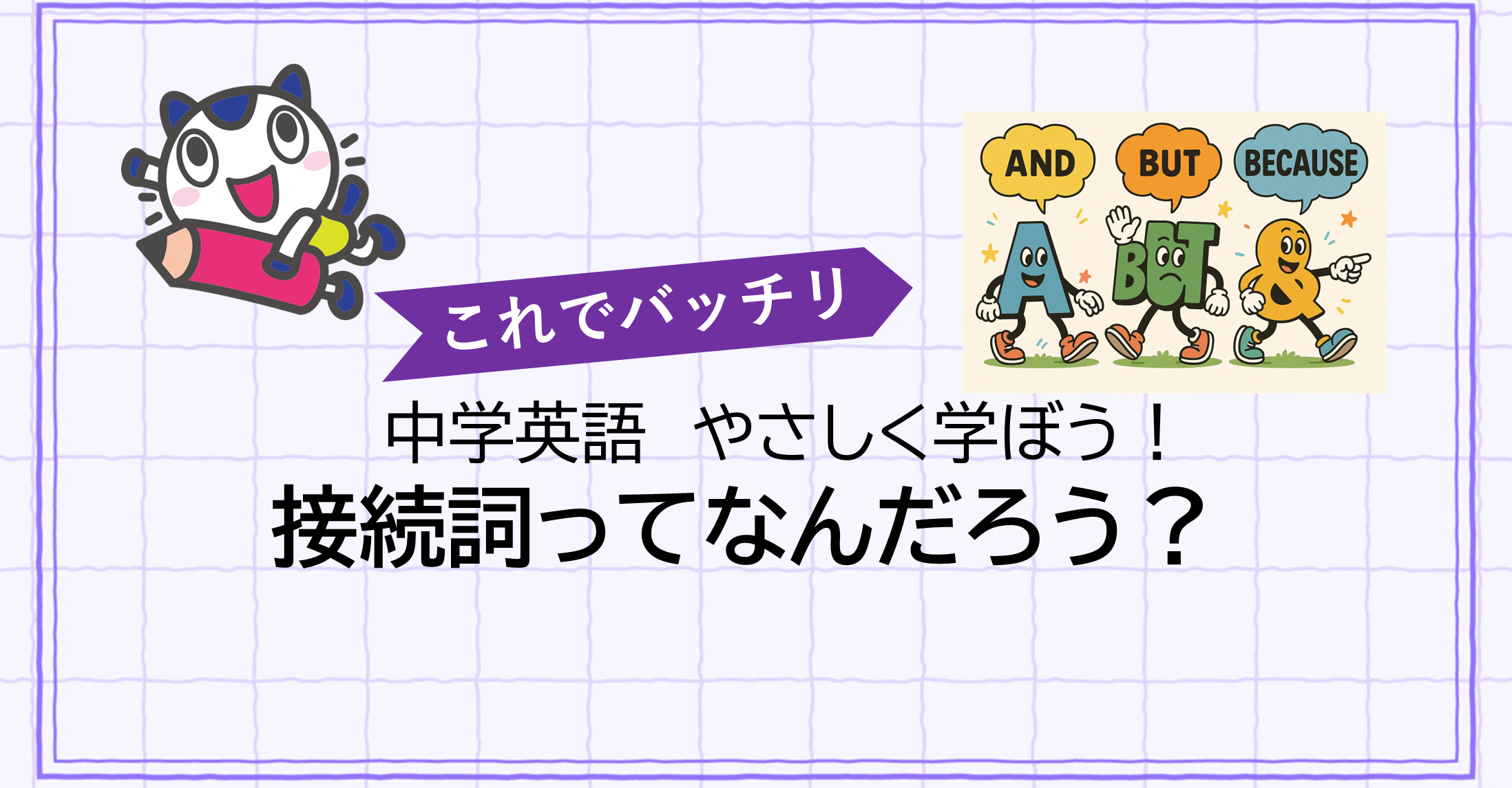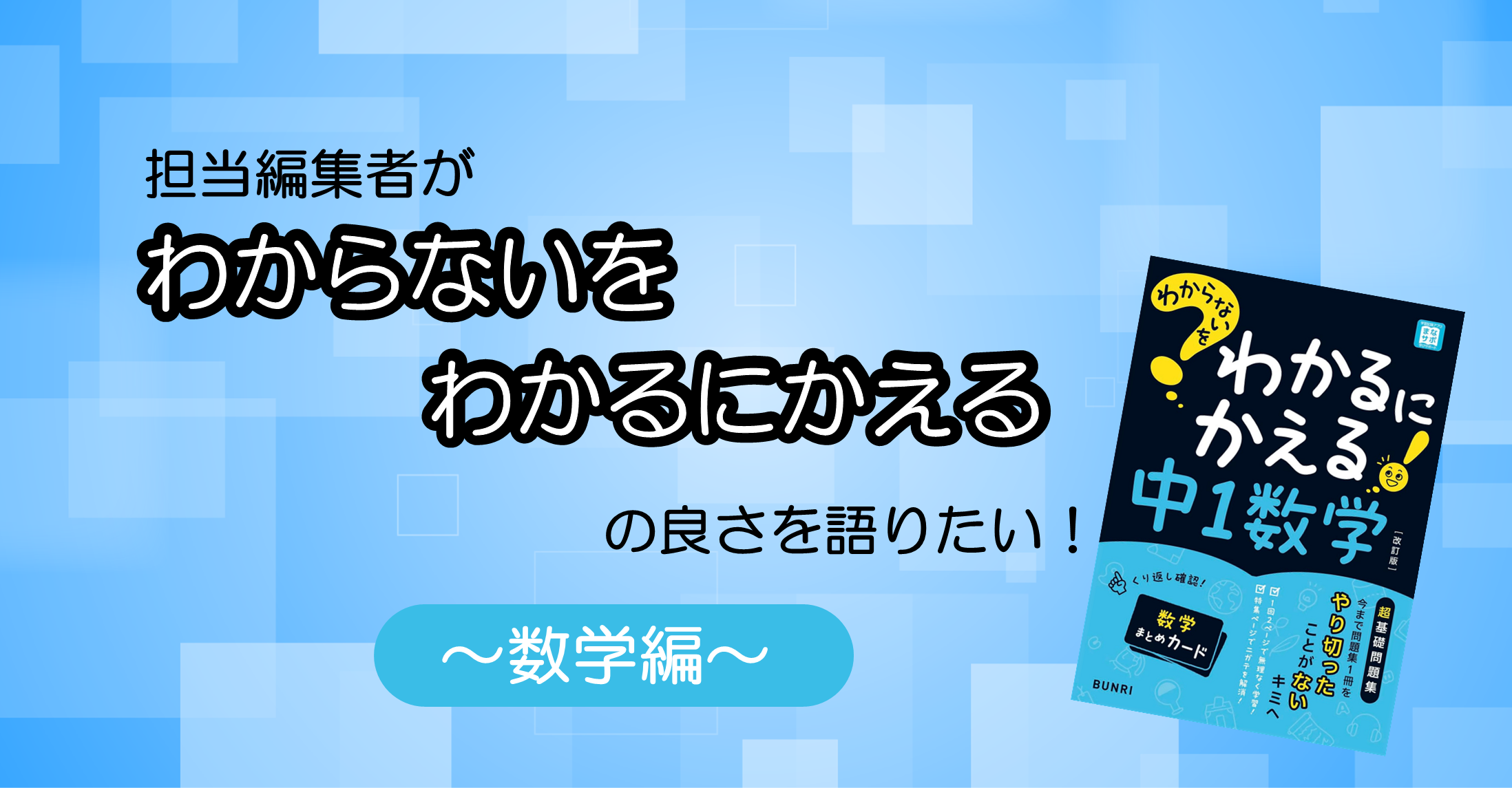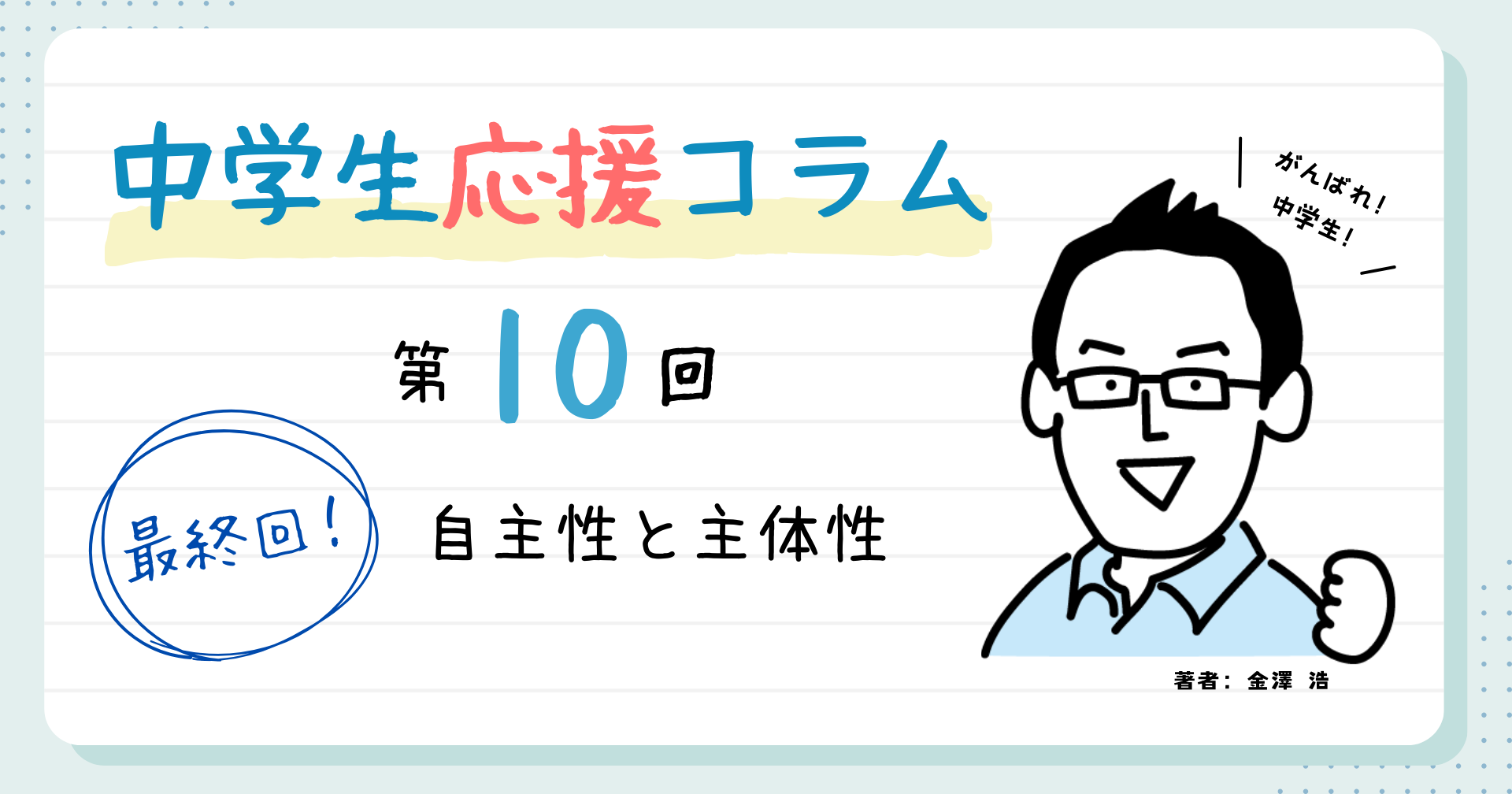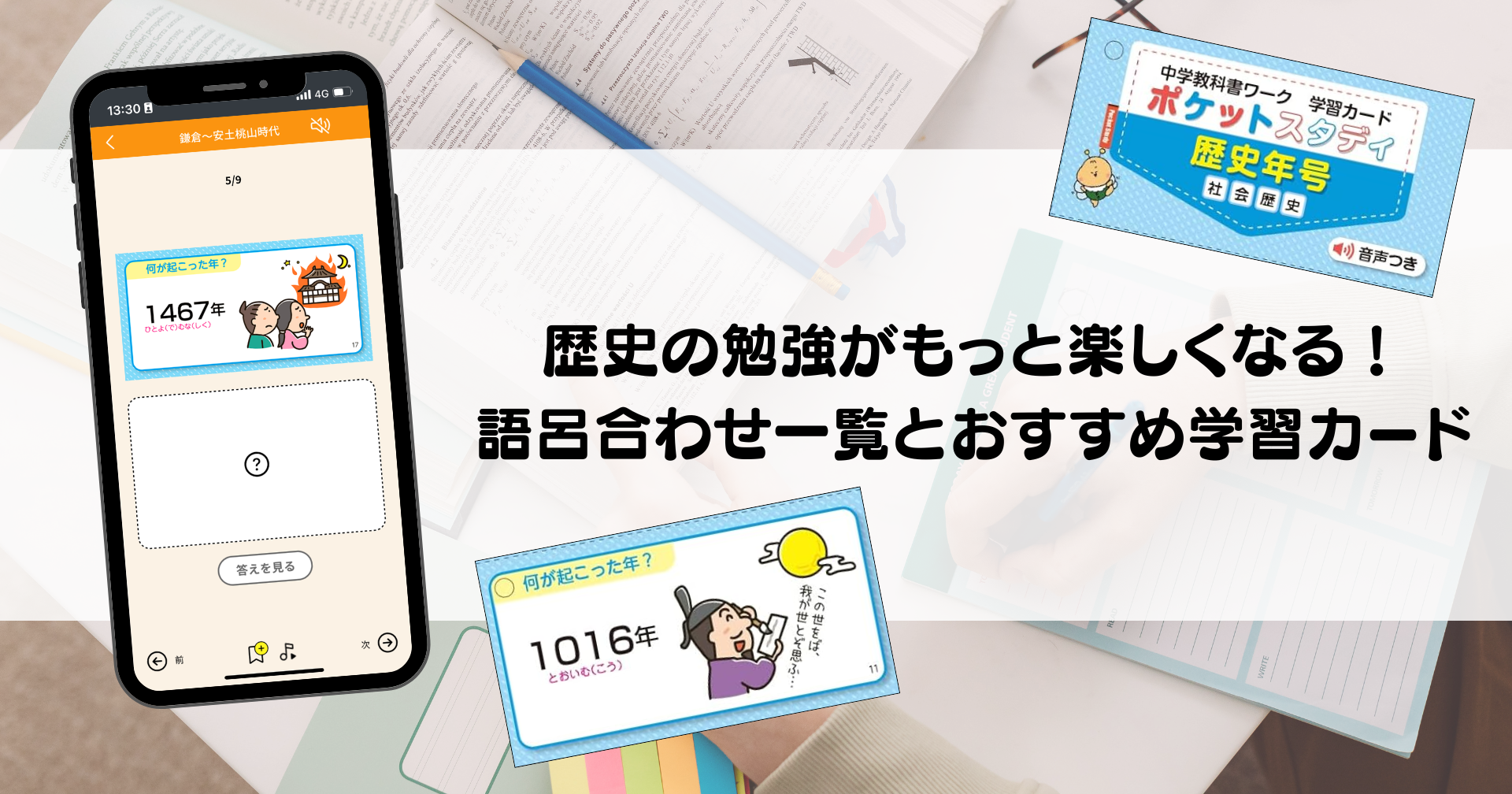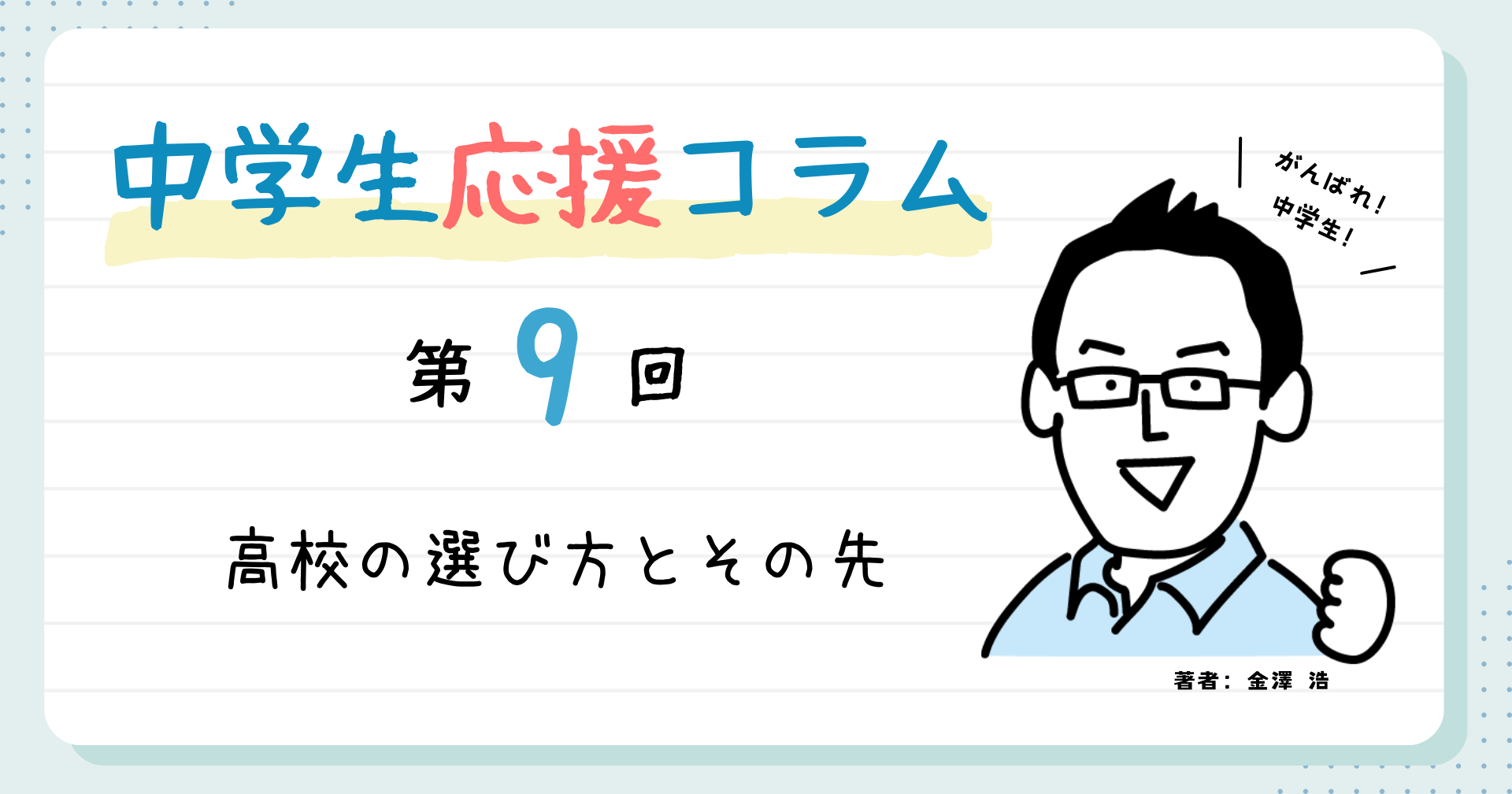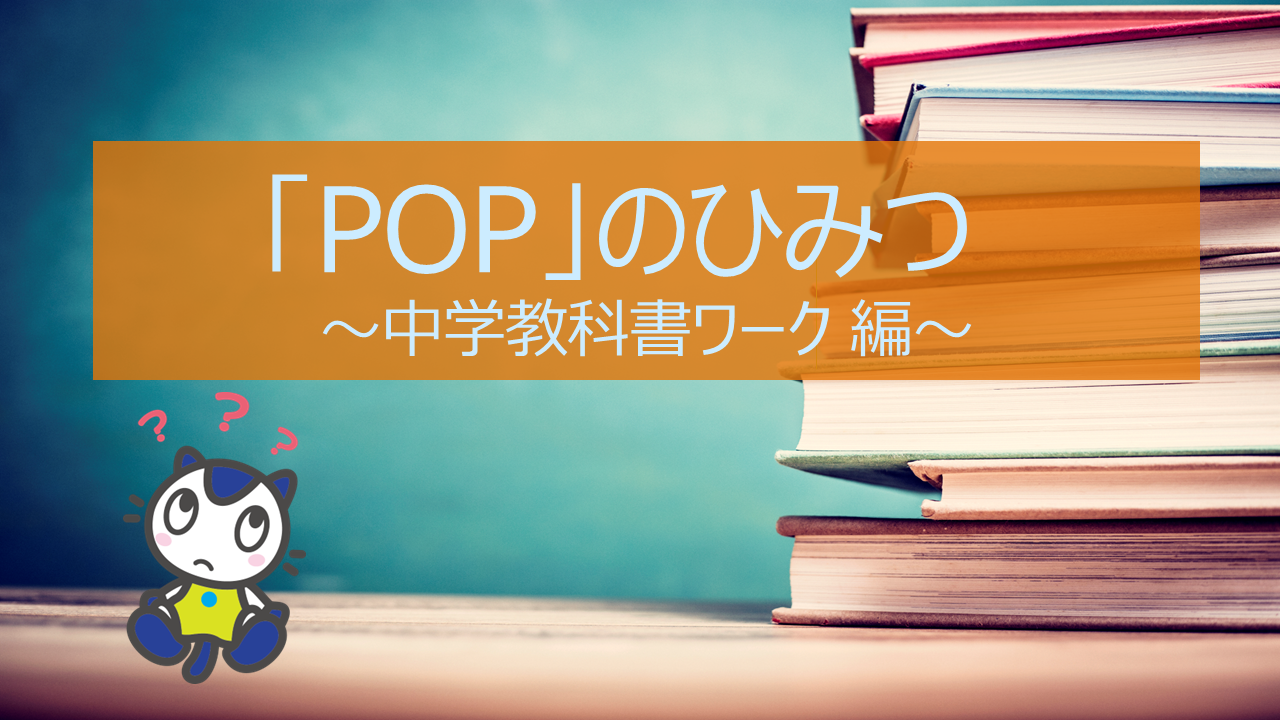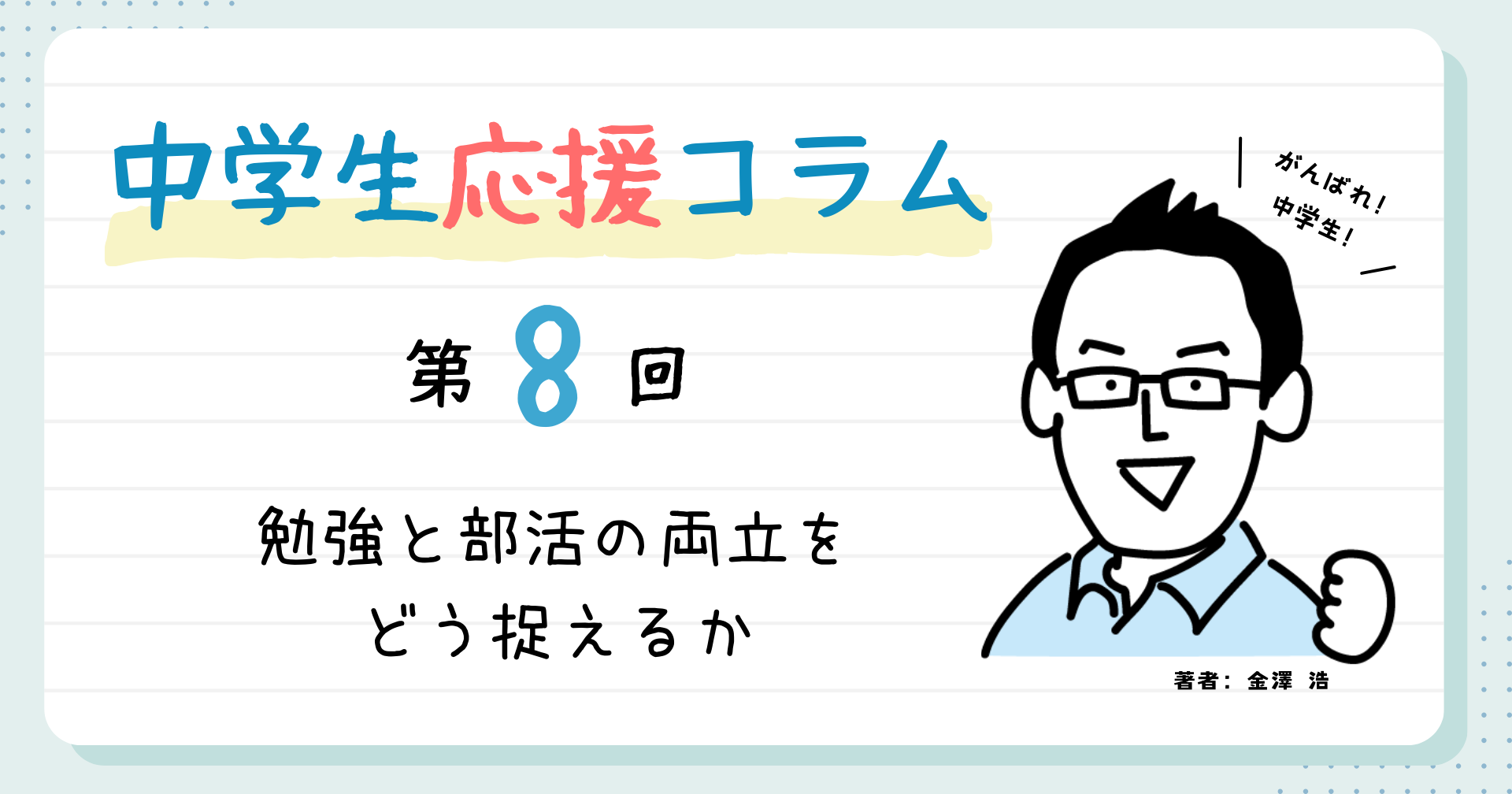なるほど!Bunri‐LOG
対象
スキマ時間を有効活用!中学教科書ワーク特典アプリ「New どこでもワーク」で始める新しい学びのスタイル
もくじ はじめに シーン1. 外出先や電車の中でもサッと学習! シーン2. 自宅学習で苦手克服! 間違えた問題もすぐに解き直し! シーン3. ちょっとした休憩時間に、ゲーム感覚で知識をゲット! 教科書ワークと「Newどこでもワーク」で、学習効果をさらにアップ! はじめに 今回は、2025年4月に改訂された中学教科書ワークにあるアプリ「New どこでもワーク」について紹介します。 このアプリは、「どこでもワーク」という名前の通り、場所を選ばずに学習できるのが大きな魅力です! 「実際、どんな風に使えるの?」と疑問に思う方もいますので、皆さんが「Newどこでもワーク」をより具体的にイメージできるように、様々なシーンでの活用方法をご紹介します。 シーン1. 外出先や電車の中でもサッと学習! 友達や家族で外出したときや、出かけたときの電車の中などで、ちょっとした空き時間ができることはありませんか? 「Newどこでもワーク」の学習カードモードを使えば、そんなスキマ時間を有効活用できます。 例えば、英語の単語や歴史の重要用語などを、カードをめくるように手軽にチェック! イヤホンを使ってリスニングの練習もできますよ。 重い参考書を持ち歩く必要もなく、スマホ1つでサッと学習できます! シーン2. 自宅学習で苦手克服! 間違えた問題もすぐに解き直し! 自宅での学習では、じっくりと問題に取り組みたいですよね。 「Newどこでもワーク」の問題演習モードは、じっくり学習したい人におすすめです。 練習モードとテストモードがあるので、練習で十分に理解してから、テストにチャレンジしてみましょう。 もし間違えてしまっても大丈夫! 「Newどこでもワーク」は、間違えた問題だけを解きなおすことができます。 単元の内容を理解できるまで、何度も繰り返し学習できます。 さらに、「ふせん」機能を使えば、あとで解き直したい問題や、特に覚えておきたい問題に印をつけられます。 ふせんをつけた問題だけを解くこともできるので、正解したけれど不安、苦手に思う問題は、「ふせん」機能で定着させましょう! このように、自分だけのオリジナル問題集のように活用できるので、苦手な単元を集中的に練習することもでき、「ここがちょっと…」という部分を克服するのに役立ちます。 シーン3. ちょっとした休憩時間にやる気アップ! 勉強の合間の休憩時間には、ポイントシステムを利用してみましょう。 「Newどこでもワーク」では、問題を解いたり、アプリにログインしたりするたびに「ポイント」がもらえます。 このポイントは、アプリ内の「アイテムショップ」で使うことができます。 「アイテムショップ」では、ポイントを使って様々なアイテムを手に入れることができ、そのアイテムを使って、アプリ内の「キュリオの部屋」を自分好みにカスタマイズできます。 自分だけの素敵な部屋ができたら、SNSで友達に共有するのも面白いかもしれませんね! 勉強のごほうびに、楽しみながらポイントをためて、お気に入りの部屋を作り上げてみてください。 中学教科書ワーク「Newどこでもワーク」で、学習効果をさらにアップ! 「Newどこでもワーク」は、中学教科書ワークと合わせて使うことで、さらに学習効果を高めることができます。 中学教科書ワークで基礎をしっかり学んだら、「Newどこでもワーク」で理解度を確認したり、苦手な部分を補強したり… 2つを上手に組み合わせることで、効率よく、そして楽しく学習しましょう! ※「Newどこでもワーク」は中学教科書ワークの特典となります。アプリをご利用になる際は、中学教科書ワークをお買い求めください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
「2025 中1 2冊教科セット 限定版キャンペーン 」を開始しました
「 完全攻略 中1 英語・数学2教科セット」または「わからないをわかるにかえる 中1 英語・数学2教科セット」をご購入いただいた方の中から、 抽選で100名様に「図書カードネットギフト」1000円分をプレゼントいたします。 対象商品 「 完全攻略 中1 英語・数学2教科セット」または「わからないをわかるにかえる 中1 英語・数学2教科セット」 ※対象商品は応募券がついている2教科セットのみです。応募券のない単品2冊の購入では応募できません。 応募方法 応募はがき 対象商品についている応募券を切り取り、はがきに貼付してご応募ください。 また、はがきには下記の必要事項をご記入ください。 応募券 ①おなまえ ②メールアドレス ③電話番号 ➃質問1の答え ⑤質問2の答え 質問1 最近の「英語」と「数学」のテストでは何点満点中何点でしたか。 質問2 この本を選んだ「きっかけ」と「決め手」を、それぞれ下の選択肢から選んでください。 1.なんとなく 2.店頭で見かけて 3.SNSやネットで見て 4.先輩や友人に薦められて 5.表紙を見て 6.POPを見て 7.キャンペーンをやっているから 8.2冊セットだから 9.このシリーズを使っているから 10.文理の他のシリーズを使っているから 11.その他(自由記述) 応募先 〒141-8426 東京都品川区西五反田二丁目11番8号 株式会社文理 「2教科セット限定版キャンペーン」係 宛 応募締切 2025年12月31日(水)当日消印有効 抽選・発表 厳正な抽選の上、プレゼント品の発送をもって、当選者の発表にかえさせていただきます。 プレゼント品は、ご応募時にご記入いただいたメールアドレスへお届けいたします。 ※お一人様何口でもご応募できますがはがき1通につき1口の応募とさせていただきます。 当選者へのプレゼント品のお届けは2026年2月下旬を予定しております。 お問い合わせ 下記フォームからお問い合わせください。 お問い合わせ 応募規約 2025 中1 2教科セット限定版 キャンペーン 応募規約 以下の規約を最後までお読みください。 応募をもって、本キャンペーンの規約のすべてにご同意いただいたものとみなします。 未成年の方については、保護者の同意を得たものとみなします。 キャンペーン概要 「 完全攻略 中1 英語・数学2教科セット」または「わからないをわかるにかえる 中1 英語・数学2教科セット」をご購入いただいた方の中から、抽選で100名様に「図書カードネットギフト」1000円分をプレゼントいたします。 対象商品 「 完全攻略 中1 英語・数学2教科セット」または「わからないをわかるにかえる 中1 英語・数学2教科セット」 応募資格 対象商品をご購入いただいた、日本国内在住の方 応募方法 対象商品についている応募券を切り取り、はがきに貼付してご応募ください。 また、はがきには下記の必要事項をご記入ください。 応募券 ①おなまえ ②メールアドレス ③電話番号 ④最近の「英語」と「数学」のテストでは何点満点中何点でしたか。 ⑤この本を選んだ「きっかけ」と「決め手」を、それぞれ下の選択肢から選んでください。 1.なんとなく 2.店頭で見かけて 3.SNSやネットで見て 4.先輩や友人に薦められて 5.表紙を見て 6.POPを見て 7.キャンペーンをやっているから 8.2冊セットだから 9.このシリーズを使っているから 10.文理の他のシリーズを使っているから 11.その他(自由記述) 応募先 〒141-8426 東京都品川区西五反田二丁目11番8号 株式会社文理 「2教科セット限定版キャンペーン」係 宛 応募締切 2025年12月31日(水) 当日消印有効 抽選・発表 厳正な抽選の上、プレゼント品の発送をもって、当選者の発表にかえさせていただきます。 プレゼント品は、ご応募時にご記入いただいたメールアドレスへお届けいたします。 ※お一人様何口でもご応募できますがはがき1通につき1口の応募とさせていただきます。 当選者へのプレゼント品のお届けは2026年2月下旬を予定しております。 注意事項 • 本キャンペーンは株式会社文理が実施しております。 • 本キャンペーンの参加によりユーザー間に生じたトラブルや、ユーザーに生じた一切の損害(直接・間接を問いません。なりすましアカウントによる被害も含みます)等について、当社はいかなる責任も負いません。 • 本規約に対する違反行為が発覚した場合は予告なしに応募を無効とさせていただきます。 • 応募の際にかかるはがき・切手代は応募者のご負担とさせていただきます。 • 応募はがきにご記入いただいたメールアドレスの削除または変更等の理由により、プレゼント品のお届けができない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。 • プレゼント品の販売・交換・換金等には応じかねます。 • 当選権利の換金・他人への譲渡はできません。 • プレゼント品お受取後の交換・返却等には応じかねます。 • プレゼント品到着後の紛失・破損等につきましては対応いたしかねます。 • 図書カードネットギフトには有効期限がございます。ご注意ください。 • 本キャンペーンは予告なく変更・中止・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。これらの変更・中止・終了により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。 個人情報について ご記入いただく個人情報は当社が責任をもって管理し、 プレゼント品の発送、当社の商品・サービスのご案内、アンケート実施、企画開発などの目的で使用いたします。 お預かりした個人情報を使い、当キャンペーンプレゼント品発送を業者へ委託する場合がございます。 当社の個人情報保護の詳細につきましては、 プライバシーポリシーをご覧ください。 お問い合わせ 下記フォームからお問い合わせください。 お問い合わせフォーム 完全攻略 わからないをわかるにかえる
編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~スケジュール作成アプリ編~
もくじ はじめに アプリのこだわりポイント 『わからないをわかるにかえるシリーズ』のご案内 はじめに この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも同じでしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回はスケジュール作成アプリ編です。 アプリのこだわりポイント 1.「学習スケジュールってどうやって立てるの?」という悩みをらくらく解決! 「もうすぐテストだし、勉強しなきゃ…、とは思うけれど、テスト当日までにテスト範囲を終わらせるにはどうしたらいいの?」と悩むキミ! 学習スケジュールを立てるなら、『わからないをわかるにかえる』に対応した「らくらくスケジュール」におまかせ! 学習スケジュールをかんたんに立てることができます。 使う場面はキミ次第。 定期テスト前のテスト勉強をするとき 長期休みを使って復習をするとき 学校の授業とは別に、『わからないをわかるにかえる』1冊を終えることを目標としてじっくり勉強を進めるとき いろいろな場面で、「勉強しなきゃ」と思ったら、まずは「らくらくスケジュール」で学習スケジュールを立ててみましょう。 2.入力するのは3つの項目だけ! 学習スケジュールを立てるために入力するのは、 学習期間 がんばる度(1日の勉強時間数) 教材(学習範囲) の3つだけ。 入力して「完了」を押せば、自動的に学習スケジュールが完成! ここで、スケジュールの立て方のコツをひとつ紹介。 それは、 短期間でたくさんの範囲をやろうとしないこと。 たくさんの範囲を選ぶと1日にやることが多くなってしまいます。 無理なく学習できる範囲を選びましょう。 3.いつでもスケジュール再調整が可能! 計画を立てたものの、予定どおりに進んでいないな、と思ったら、スケジュールの再調整をしましょう。 終わっていない課題を最初に決めた終了日までに何とかして終えるスケジュールに作り直してもよし、 期間や勉強する内容を変えて作り変えてもよし。 キミの希望に合わせて、学習スケジュールを立て直すことができます。 アプリの使い方は、YouTubeの文理公式チャンネルからも確認できます。 チャンネルはこちら ↓ なお、アプリを使うときは、保護者の方にも「使っていいかな?」と一言たずねてくださいね。 安心して使うために、おうちの人といっしょにアプリの使い方を確認するのもおすすめです! 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができるとうれしいです。 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
算数と数学の違いってなに? 中学校の数学でつまずかないために
小学校では「算数」だったのに、中学校に入ると「数学」に教科名が変わりますよね。「名前が変わったけど、内容も変わるの?」と不思議に思ったことはありませんか?この記事では、「算数」と「数学」のちがいや、それぞれの考え方について、わかりやすく説明します! もくじ 算数と数学の区別 算数ってどんな教科? 数学ってどんな教科? 算数と数学のちがいを問題で比べてみよう 算数が得意だったのに数学でつまずくのはなぜ? 算数・数学のおすすめの問題集 まとめ 算数と数学の区別 日本では 算数も数学も、数や図形について学ぶ教科です。日本の学校では、小学校で学ぶのが「算数」、中学校から学ぶのが「数学」と決められています。 海外では では、海外ではどうでしょう?たとえばイギリスでは、小学校からずっと「mathematics(マスマティクス、略してmaths)」を学びます。日本のように「算数」と「数学」に分けていません。ちなみに英語には「arithmetic(アリスマティック)」という言葉もありますが、これは計算に関する分野のことを指します。 算数ってどんな教科? 算数で学ぶこと 小学校の算数では、たし算・ひき算・かけ算・わり算などの基本的な「計算」や、小数、分数などの「数」、三角形や四角形、円などの「図形」について学びます。 また、「変化と関係」や「データの活用」なども学びます。 目的は「生活で使える力」を身につけること 算数の目的は、ふだんの生活で役立つ力をつけることです。具体的には、次のような力です。 ・計算の意味を理解して、正しく使えるようになる力 ・図形の形や大きさを理解する力 ・表やグラフで情報を整理して表現する力 ・問題を順序立てて考えて解決する力 もう少し、具体的な例を見てみましょう。 ・買い物でおつりを計算するには? → たし算、ひき算、かけ算、わり算を使う ・15分間で水そうに入る水の量を求めるには? → 1分間に入る水の量を求め、15分後の量を計算する ・目的地まで何分かかるか調べるには? → 「速さ・時間・道のり」の関係を使って計算する このように、算数で学ぶのは日常生活で使える知識です。 具体的な数値を求めるのが算数と考えることもできます。 数学ってどんな教科? 数学で学ぶこと 中学校に入ると、「数と式」「図形」「関数」「データの活用」などを学びます。 これらは、「算数」の内容の続きですが、より頭の中で考える場面(抽象的な場面)が多くなります。 例えば、次のようなものが登場します。 ・実物では見えない「マイナスの数(−)」が登場。 ・図形に「証明」が登場。証明とは、あることが正しいと論理的に説明することです。 数学の目的は「筋道を立てて考える力」を育てること 数学では、物事を順序立てて考える力(論理的思考力)を育てます。具体的には、次のような力です。 ・抽象的に考える力 ・いくつかの情報から、法則やルールを見つける力 ・決まった手順で、間違えずに考えを進める力 ・証明や式の意味を理解し、考え方を伝える力 算数との大きな違いは、「なぜそうなるのか?」を筋道立てて説明することが求められる点です。 算数と数学の違いを問題で比べてみよう ここからは、「算数」と「数学」の類似問題を見比べてみましょう。 例)変化と関係 算数 ▲『小学教科書ワーク 算数 6年 東京書籍版』p.111 ☆算数では、2つの数の関係を実際に数え上げて調べます。 数学 ▲『中学教科書ワーク 数学 中1 東京書籍版』p.104 ☆数学では、2つの数量の関係を文字を使った式で抽象的に表します。 ここで問題! 長さの等しい棒で、下のように四角形をつなげた形をつくります。四角形の個数が x 個のとき、棒の本数を、文字x を使った式で表してみましょう。 答え: 1+3x(本) 例)おうぎ形の面積 算数 ▲『小学教科書ワーク 算数 6年 東京書籍版』p.66 ☆算数では、円周率を3.14として計算し、答えを具体的な数値で求めます。 数学 ▲『中学教科書ワーク 数学 中1 東京書籍版』p.104 ☆数学では、円周率を πとして計算します。 ここで問題! この図形の面積を、円周率 をπとして求めましょう。 答え: π×42×90/360=4π(cm2) 算数が得意だったのに数学でつまずくのはなぜ? 原因①:算数の基礎がしっかりしていない 中学の数学が難しいと感じる人は、実は「算数」の基礎が十分に身についていないことがあります。 算数・数学は、積み上げの教科。前の内容がわからないと、新しい内容が理解できません。 中学に入る前に、小学校の内容で「わからないところ」や「忘れているところ」がないか、もう一度振り返ってみましょう。 また、計算力を高めるには問題演習が大事になります。問題集やドリルを使って、苦手な単元を復習しましょう。 原因②:答えがあっていることだけを重視している 算数ドリルなどの答えあわせで、答えがあっていれば〇にしていませんでしたか? 数学のテストでは、途中のプロセスも重要で、途中式が間違っていると減点される場合もあります。 数学では答だけでなく、そこに至る過程もしっかり理解していないと、つまずいてしまうことがあります。 原因③:「考え方のプロセス」が苦手 数学では、「どうやってその答えになったか」という考え方の過程(プロセス)がとても大切です。 考え方のプロセスを身につけるには、まず例題をしっかり読んで、考え方の流れを理解しましょう。 そのあと、似たような問題を解くことで、「考え方のプロセス」が自然と身につきますよ。 算数・数学のおすすめの問題集 この記事の例題で取り上げたシリーズを紹介します。 「小学教科書ワーク 算数」 教科書に合わせた準拠版の問題集で、学年別の発行です。 全ての教科書に対応した「数と計算」「文章題・図形」も学年別に発行しています。 小数や分数、割合、図形など、苦手な単元がある方はこちらをご利用ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「中学教科書ワーク 数学」 教科書に合わせた準拠版の問題集で、学年別の発行です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科書準拠の問題集を探すなら! まとめ 小学校の「算数」は、生活に使える力を育てる教科、 中学校の「数学」は、それをもっと深く、論理的に考える教科です。 「数学が難しいな」と感じたら、算数に戻ってみるのもおすすめです。 また、答えだけでなく「どう考えたか」を大切にしながら学ぶと、きっと数学も得意になりますよ!
編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~社会編~
この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は社会(地理・歴史・公民)編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 社会』とは? 社会のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 社会』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 社会』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 社会は、「地理」「歴史」「公民」の3冊を発行しています。 社会のこだわりポイント 1. かわいいイラスト・図・写真で「見てわかる」! 社会といえば覚えることがたくさん。 独特の用語や、人名、複雑な社会のしくみ… 文字を読むだけではいつまでもわからない。 そこで『わからないをわかるにかえる社会』では、楽しいイラストや図、写真を使って、おさえておくポイントを楽しく説明しています。 言葉だけでは覚えられなくても、イラストとセットで確認することで、より覚えやすくなります。 ゆるくてかわいいイラストを見ると、息抜きにもなっちゃうかも! まとめページの最後には、ときどき編集者渾身のダジャレも。 笑っている間にいつの間にか大切なことを覚えられちゃいます。 ん? そんなにおもしろくない…?? まあ、それはほら、その……。やさしくしてください。 2. (ほぼ)全文ふりがなつき! 「漢字で答えなさい」という問題が多い社会。 ・習ったはずの漢字でも読み方が難しくて、きちんと覚えられていない、覚えたはずなのに書けない! ・読み方を間違って覚えてしまった! あるあるです。 教科書も読めない漢字があってよくわからない…。 『わからないをわかるにかえる社会』は、重要な語句もそうでない語句もとにかくほぼすべての漢字にふりがなを振り、漢字が苦手でもとりくみやすい工夫をしています。 漢字と一緒に読み方も覚えれば、定期テストでの得点UPまちがいなし! 3. たのしい特集ページつき! まじめに勉強ばかりだと疲れてしまいませんか? 勉強にだって息抜きの時間は必要です。 『わからないわかるにかえる社会』では、各章のまとめのページの最後に楽しい特集ページを設けています。 内容は「みんなのおなやみ相談室」と「楽しく復習 クイズ&パズル!」の二本立て。 「みんなのおなやみ相談室」は社会を勉強するときに、だれもが感じるあんななやみやそんななやみを、社会科担当がずばっと解決! 勉強の合間にぜひ読んでみてくださいね。 このおなやみの答えは…紙面を見てのお楽しみ! 「クイズ&パズル」では、単調になりがちな復習が楽しくなるように、クイズやパズル形式で出題。 考えるだけで各章の復習がさらっとできるしくみになっています。 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。
編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~理科編~
この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は理科編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 理科』とは? 理科のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 理科』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 理科』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 数学は、「中学理科1~3年」の3冊を発行しています。 理科のこだわりポイント 1…図とイラストで「見てわかる」! 文字ばかりの問題集だと理解がしにくい…。 理科は特にそんな声をよく聞きます。 『わからないをわかるにかえる理科』では、そんな声を解消するためにたくさんの図版とイラストを使って、学習のポイントが一目でわかるように工夫しました! 特に実験・観察の問題は図を見ながら解くことが多いため、図とイラストでイメージを膨らませながら勉強すると、理解も深まります。 授業中やテスト本番で「あ、この図は『かえる』で見たな」と思い出してもらえるように、テストにもよく出る図を厳選して紙面に載せました。 2…ふりがな付きのていねいな解説で「読んでわかる」! 解説文や重要語句には、ふりがなを付けました。 書けるけど読めない、読めるけど書けない、を解消するひと工夫です。 「●●を何というか」という用語問題は、学校の定期テストでもよく出題されます。 そのため、重要語句は絶対に覚えてほしいもの。 漢字と一緒に読み方も覚えて、定期テストでの得点に繋げていきましょう♪ また、ただ語句を覚えるだけでなく、内容を正しく理解してもらうためにも、解説はやさしく・丁寧なものとなるよう、工夫しました。 3…いろいろなタイプの練習問題で「解いてわかる」! 左ページの解説を読み終わったら、すぐに右ページの練習問題に取り組めます。 物理・化学・生物・地学の分野ごとのポイントをおさえた練習問題を解くことで、学習内容の理解度を確認できる構成としました。 また章末の特集ページでは、用語問題、実験・観察問題、記述問題、作図問題、計算問題など、定期テストでも頻出な問題を集めているので、いろいろな形式の問題を解き進めることで、苦手を克服させることができます。 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。
中学英語 やさしく学ぼう 接続詞
目次 はじめに 接続詞ってなに? これだけは覚えよう! 重要な接続詞の使い方 接続詞の使い方のコツ 接続詞のまとめクイズ 接続詞を勉強しよう! おすすめ問題集 まとめ 接続詞で英語がもっと楽しくなる! はじめに 英語で「わかりやすい文」を書くには、接続詞(せつぞくし)はとても大切!接続詞を使えば、文をつなげて、自分の考えをスムーズに伝えることができます。 たとえば、 I like soccer. I play it every day. → I like soccer and I play it every day. (私はサッカーが好きで、毎日やっています。) It was raining. We went out. → It was raining, but we went out. (雨が降っていたけど、私たちは出かけました。) このように、接続詞を入れるだけで、英文がぐっと自然に! 接続詞を味方につけて、伝える力をアップさせましょう。 接続詞ってなに? 接続詞の役割を知ろう 接続詞とは、「文と文」や「言葉と言葉」をつなぐつなぎことばのこと。 英語では会話でも文章でも、この“つなぎ役”が大活躍します。例を見てみましょう。 I have a dog and a cat. (私は犬と猫を飼っています。) I like tennis, but I don’t play it well. (テニスは好きだけど、上手じゃない。) こんなふうに、接続詞を使うと気持ちや理由がスムーズに伝わります。 もし、英語が「単語や文を並べただけになっている…」という人は、まずは基本の接続詞を覚えましょう! ぐんとレベルアップできますよ。 これだけは覚えよう! 重要な接続詞の使い方 ①「並列」を表す接続詞:and、then 使い方 ・and は「~と~」「そして」、似ている内容をつなげるときに使う。 ・then は「それから」「そのあとで」、順番や順序を表す。 I like apples and oranges. ※単語と単語をつなげる (私はりんごとオレンジが好きです。) He plays soccer and studies English. ※文と文をつなげる (彼はサッカーをし、そして英語を勉強します。) I did my homework, then I watched TV. (私は宿題をして、それからテレビを見ました。) ②「反対のこと」を表す接続詞:but、however、though 使い方 ・but は「しかし」、前の内容と反対のことを言う。 ・however は「しかしながら」、少しかたい表現。また、文の最初に来ることが多い。 ・though は「~だけれども」、文の最後に来ることもある。 I like soccer, but I can’t play well. (私はサッカーが好きですが、上手にできません。) I wanted to go skiing. However, it was too cold outside. (私はスキーに行きたかったです。しかしながら、外は寒すぎました。) She is kind, I don’t like her though. (彼女は親切です、でも私は彼女が好きではありません。) ③「理由」を表す接続詞:because、since、as 使い方 ・どれも「~なので」「~だから」。 ・because は理由を強調するときに使う。 ・since 、asは主に相手がすでにその理由を知っているときに使うことが多い。ややかたい表現。 I was absent from school because I was sick. (私は病気だったので、学校を欠席しました。) Since it was raining, we watched TV at home. (雨が降っていたので、私たちは家でテレビを見ました。) As he was busy, he didn’t come. (彼は忙しかったので、来ませんでした。) ④「結果」を表す接続詞:so、therefore 使い方 ・理由を表す接続詞(becauseなど)と逆の方向で使うのがポイント。 ・soは「だから~」、thereforeは「それゆえ」。 ・soのほうがややカジュアルな表現、thereforeのほうがややかたい表現。 I was hungry, so I ate a sandwich. (私はお腹がすいていました、だからサンドイッチを食べました。) He didn’t study hard, therefore he failed the test. (彼はあまり勉強しませんでした、その結果テストに落ちました。) ⑤「仮定」を表す接続詞:if、unless 使い方 ・if は「もし~なら」、条件を表す。 ・unless は「~でない限り」「もし~でなければ」、ifとは逆の条件を表す。 If it rains, we will stay home.= We will stay home if it rains. (もし雨が降ったら、私たちは家にいます。) Unless you hurry, you’ll miss the bus. = You’ll miss the bus unless you hurry. (急がなければ、バスに乗り遅れますよ。) ⑥「時間」「順序」を表す接続詞:when、while、before、after 使い方 ・when は「~するとき」。 ・while は「~している間」。 ・before は「~する前に」、after は「~する後に」。 ・before と after は、前置詞としても使う(例:before lunch)。 I was sleeping when the phone rang. = When the phone rang, I was sleeping. (電話が鳴ったとき、私は寝ていました。) He was singing while he was cooking. = While he was cooking, he was singing. (彼は料理をしている間、歌っていました。) I finished my homework before my mother came home. (母が帰ってくる前に私は宿題を終えました。) We went out after the rain stopped. (雨がやんだあとに、私たちは出かけました。) ⑦「選択」を表す接続詞:or 使い方 ・orは「AかB」「~、それとも…」、2つの選択を表すときに使う。 Do you want tea or coffee? (あなたは紅茶かコーヒーがほしいですか?) ⑧「~ということ」を表す接続詞:that 使い方 ・「~ということ」「~というのは」、思っていることや知っていることを伝えるときに使う。 ・省略することもできる。 I know that she is a good teacher. = I know she is a good teacher. (私は彼女がよい先生だということを知っています。) 接続詞の使い方のコツ ① 同じ接続詞ばかり使わない! andやbutなど同じ接続詞だけを使って文を続けると、文がダラダラとした印象に…。 いろいろな接続詞を使い分けて、読みやすく、伝わりやすくしましょう。 悪い例I like cats and I like dogs and I like birds.(猫が好きで、犬が好きで、鳥も好きです。) 改善例I like cats and dogs, but I like birds the most.(猫と犬が好きだけど、一番好きなのは鳥です。) ② 自分の意見を書くときに接続詞を使おう! 自分の気持ちや考えを書いたり話したりするとき、接続詞が活躍します!上手に使って、作文やスピーチで自分の意見をわかりやすく伝えましょう。 例 I like English because it’s fun.But I didn’t do well on the test last week.So I’m going to study hard for the next one. (英語は楽しいので私は英語が好きです。でも、先週のテストはよくできませんでした。だから、次のテストに向けて一生けんめいに勉強します。) 接続詞のまとめクイズ 上記で取り上げた接続詞のクイズにチャレンジ! 次の英文の( )に入るもっとも適切な接続詞を、下の3つの中から1つ選びましょう。 【問題】 ① I like soccer ( ) I play it every day. but / and / because ② It was raining, ( ) we played games. so / and / before ③ I was tired, ( ) I went to bed early. though / because / so ④ He likes Math, ( ) I like English. but / or / when ⑤ You can have tea ( ) coffee. if / or / that ⑥ I went to the park ( ) it was sunny. before / because / unless【答と訳】 ① 答:and 訳:私はサッカーが好きで、毎日それをします。 ② 答:so 訳:雨が降っていたので、私たちはゲームをしました。 ③ 答:so 訳:私は疲れていたので、早く寝ました。④ 答:but 訳:彼は数学が好きですが、私は英語が好きです。⑤ 答:or 訳:紅茶かコーヒー、どちらかを選べます。⑥ 答:because 訳:晴れていたたので、私は公園に行きました。 接続詞を勉強しよう! おすすめ問題集 『中学教科書ワーク』 ・教科書会社別、学年別に作成。 ・学校で使っている教科書の内容を理解するのにとっても役立つ。 ・教科書に対応した暗記ブック、スキマ時間の学習に役立つ英単語カードなどの特典も充実! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 『わからないをわかるにかえる』 ・学年別(1年、2年、3年)に発刊。 ・「英語はちょっと苦手…」という方も、安心して学べる構成。 ・左の文法の説明を読む(理解)→右の問題を解く(確認)、 で文法の重要ポイントを着実におさえることができる。 ・文法の説明は、イラストや図解がいっぱい。楽しく学習できる! ・英単語カード(音声付き)、らくらくスケジュール(WEBアプリ)の特典付き。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「難しい問題にチャレンジしたい」というあなたには、次の2つがおすすめ。 『完全攻略』 ・「定期テスト対策」に加え、「高校入試対策」もこのシリーズでバッチリ。 ・発音アプリと連動した小冊子に加え、充実した特典がたくさん! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 『ハイクラス徹底問題集』 ・「定期テスト対策」に加え、高校入試の「難関校対策」にも対応。 ・詳しい解答解説で難問もしっかり理解できる! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 接続詞で英語がもっと楽しくなる! 接続詞は「英語で伝える力」をぐんと高めてくれる、とても大切なことばです。 最初は、andやbutなど、よく出てくる接続詞の使い方を覚えましょう。 それから、少しずつほかの接続詞もチャレンジしてみましょう。 接続詞を使いこなせるようになると、“前後の流れ”がスムーズに伝わるようになります。 今日からさっそく、英語を書くとき・話すときに「つなぎことば」の接続詞を意識してみましょう!
編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~英語編~
この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! この問題集が他とどうちがうのか、4つのポイントで解説していきます。 今回は英語編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 英語』とは? 『わからないをわかるにかえる 英語』担当編集者のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 英語』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 英語』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 英語は、「中1英語」「中2英語」「中3英語」の3冊を発行しています。 『わからないをわかるにかえる 英語』担集者のこだわりポイント 見てわかる! 「見てわかる」誌面をテーマに、英文解説のポイントと、対応する練習問題を同じ色で紐づけしました。 解答のポイントが見てわかります! 問題集の説明を読んでも、いざ問題を解くときに、説明のどの部分をヒントに解いたらいいのかわからない、と困った経験がある方はいませんか? 本書では、複雑な文法説明をなるべくシンプルにし、解答のポイントが見てわかるようになっているので、問題が解きやすいです! 色つきの問題ばかりでは、ヒントが多くて簡単すぎる、という方も、ご安心を! 色をヒントにする問題と色なしで自力で考える問題、両方にチャレンジできるように作りました。 見て楽しい! 英語の問題集の例文って面白くない、と思ったことはありませんか? 「わからないをわかるにかえる英語」では、例文の場面を、ユーモラスなイラストで表現しました。 マンガを読んでいるような楽しい気持ちで、英語を勉強してくださいね。 聞いてわかる! なんと、今回のリニューアルから、本編の全ページに英語音声を搭載しました! これまで読者アンケートで、英語の読み方がわからないから、例文や問題の英文を読むことができない、とのお声をいただいていました。 そこで、通常単元の例文、練習問題・まとめのテストの解答の英文、特集ページの例文に英語の音声を搭載しました! リニューアル前から引き続き、リスニング問題にも、もちろん音声がついています。 英語の読み方を理解するためだけでなく、スピーキングやリスニングの練習にも役立ちます! 音声を簡単に聞けるように、見開きごとにQRコードを掲載しています。 スマホでQRコードを読み込むと、そのページの音声を聞ける音声配信サイトに、直接飛ぶことができます。 PCでも音声を聞くことができるので、ご購入いただいた方は誌面の説明をご参照ください。 ※「QRコード」は、デンソーウェーブの登録商標です。 特集ページでつまずきやすい英文法も見てわかる! 「英文法をわかるにかえる!」と題して、つまずきやすい英文法をピックアップし、詳しく解説しています。 混同しやすい文法項目も、イラストや図解を通して、わかりやすく整理できます。 キャラクターたちと会話している感覚で、文法を学んでいただけるとうれしいです! 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【英検®対策】シリーズ 「わからないをわかるにかえる」シリーズのコンセプトを踏襲した、カラーの誌面でやさしく学べる英検対策本です。 5級~2級の「問題集」と「単語帳」を発行しています。 ※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 ※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。
編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~数学編~
この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は数学編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 数学』とは? 数学のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 数学』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 数学』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 数学は、「中学数学1~3年」の3冊を発行しています。 数学のこだわりポイント 1.式の意味がわかる!丁寧な注釈 各単元にある例題の解説では、その式で何をしているか、どのような考え方を使っているかを注釈で示しています。 注釈を読みながら穴埋めをすることで、重要な考え方や解き方を理解することができます。 担当は学生時代、数学の解説を読んで「途中式だけ書かれているけど、なんでこの式になるのかわからない…」と思うことがありました。 『わからないをわかるにかえる』では、そんなお悩みを解決するため、できる限り丁寧な注釈を入れるようにしています。 2.例題と練習問題が対応! 各単元は2ページ構成で、1ページ目が例題、2ページ目が練習問題となっています。 例題と練習問題は対応しているので、もし練習問題でつまずいても、前のページの例題で解き方を確認することができます。 ここで工夫したのは、例題と練習問題をできる限りスモールステップでつなげること。 練習問題で一気にレベルを上げることはせずに、例題の解法を理解していれば解ける問題を掲載しています。 例題で解き方を理解し、練習問題で似た問題を実際に解いてみることで、無理なく着実に力をつけることができます! 3.豊富な図やイラストで視覚的にわかる! 最後のこだわりは、重要事項が「読んでわかる」だけでなく、「見てわかる」ような図やイラストをたくさん掲載したことです。 親しみやすいキャラクターのイラストで、考え方や公式、間違えやすいポイントなどを紹介しています。 テスト中、問題が解けずに困っているときに、ふと『わからないをわかるにかえる』で見たイラストが思い浮かんできた…。 そんなふうに役立てるよう、かわいいけれどユニークで印象に残るようなイラストを目指しました! 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。
編集担当が『わからないをわかるにかえる』の良さを語りたい! ~国語編~
この春リニューアルした『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズ。 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミでも、やり切ることができる問題集になるよう、5教科の各担当者は全力で編集しました! 「そうはいっても、問題集なんてどれも一緒でしょ?」と思ったそこのキミ! この問題集が他とどうちがうのか、3つのポイントで解説していきます。 今回は国語編です。 もくじ 『わからないをわかるにかえる 国語』とは? 『わからないをわかるにかえる 国語』担当編集者のこだわりポイント 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 『わからないをわかるにかえる 国語』とは? 今まで問題集1冊をやり切ったことがないキミへ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ほぼすべてが見開きのレイアウトで、図やイラストを使ってわかりやすく解説しているので、今まで問題集1冊をやり切ったことがない人でも、無理なく取り組むことができます。 中学教科書の改訂年である、この2025年春に改訂しました。 『わからないをわかるにかえる 国語』ラインナップ 『わからないをわかるにかえる』(学年別・領域別)シリーズは、数学・理科・英語は学年別、国語・社会は領域別のラインナップになっています。 国語は、「中学国語1~3年」「文章読解1~3年」「古文・漢文1~3年」の3冊を発行しています。 『わからないをわかるにかえる 国語』担当編集者のこだわりポイント できる限りのふりがなを入れました 今回のリニューアルに「重要語句にはすべてふりがなつき」があります。ただ、5教科のなかでも特に文字量が多い国語……どこまでふりがなをつけるべきか悩みましたが、「読むことが苦手な子がつまずかないよう、できるだけ入れる!」として、一部の漢字問題や見出し以外のほとんどにふりがなをつけることにしました。 とはいえ、読みづらくなってしまってはいけませんよね。担当は、紙面のデザイナーさんと何度もやり取りをしました。 場所によってはふりがなを小さめの級数(文字の大きさのこと)にしてみるなどこだわりぬいた結果、読みやすさとわかりやすさが両立できたのではないかなー!と思っています。 小学生の中学先取り学習にも最適です! (注…ふりがなの細かい方針については各教科で異なります) 丁寧すぎるぐらい丁寧な説明にしました 超基礎系問題集の特色として「丁寧な説明」がありますが、『わからないをわかるにかえる国語』はちょっと度を超すぐらい、じっくり丁寧に説明しています。 たとえば、つまずきが多い「熟語の構成」。順を追って考え方を説明しているので、とってもわかりやすい!インパクトの強いイラストも載せてあり、共に覚えておくことでテストの時に役立ちます。(①) 苦手な人が多い国語の文法も、図やイラストで丁寧に解説するのはもちろんのこと(②)、文法用語もできるだけかみくだいて説明するようにしました(③)。 また、どうしても難しい言葉で説明しなくてはいけないときは、言葉の説明を小さく入れています。(④) 解説マンガを入れました 従来版でも豆知識やクイズを掲載していた特集ページ。 そのままでも十分国語の学習には役立つのですが、マンガ好きの担当は、国語が苦手な人にも読んでもらえるよう、解説マンガをできるだけたくさん入れ込みました! 勉強の合間に、肩の力を抜いて読んでもらいたいと思っています。 そうすれば、いつの間にか国語が好きになっているかも……? 『わからないをわかるにかえる』シリーズのご案内 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】シリーズ ニガテなところがどんどんわかる!超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集!小学生の先取り学習や、高校生・大人の学び直しにもおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら わからないをわかるにかえる【高校入試】シリーズ ニガテをなくして合格へ!受験勉強も超基礎からやさしく学べる、中学生のための問題集です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わかる」ための工夫が満載な『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 たくさんの人の「わからないをわかるにかえる」お手伝いができると嬉しいです。
中学生応援コラム 第10回「自主性と主体性」
皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 今回がいよいよ最終回となります。私が今一番伝えたい、「自主性」と「主体性」という言葉についてお伝えしたいと思います。 2つのちがい 例えば部屋の掃除をする、ということについて。 親から子に「毎週1回はきちんと掃除しなさい」と伝えて、子がその通りに言いつけを守って掃除をする。素晴らしいことですよね。 一方で、特に親から子に何も言ってないのに、子が自分の部屋を定期的に掃除している。これも素晴らしいことだと思います。 この二つの違いはわかるでしょうか。 自主性というのは、他人から言われたことや決められたことに率先して取り組むということです。 先ほどの掃除の例でいうと前者(A)の、言いつけを守って掃除をするパターンです。 主体性というのは、やるかどうかも含めて自分が決めて自分で行動するということです。 先ほどの例では後者(B)の、何も言わずに掃除するパターンです。 これらはどちらがいい、どちらが悪い、というものではありません。 「どちらも必要」なものであり、あまりに偏ると良くない影響が出てきてしまいます。 何も指示がなかったらどうしていいかわからない、というのは主体性が欠ける例ですし、他の人の忠告を聞かずに好き勝手やってしまうのは自主性が欠ける例です。 このコラムをお読みの皆様の家庭では、どのような声掛けが多いでしょうか? そもそも、現在保護者のお父様・お母様の家庭ではどのような声掛けをされていた記憶がありますか? 自主性の時代から主体性の時代へ 一般的な話として、日本という国は歴史的にも文化的にも、「自主性」をとことん磨いてきたのだと思います。 敗戦の後、挙国一致で戦勝国に追いつけ追い越せでやってきた復興の過去。 世間体の価値づけや、年配・先輩を敬い従うような教えの浸透した文化。 親の言いつけを守ること、先生のいうことを聞くこと、目上の人のアドバイスに耳を傾けること。 いずれも自主性をど真ん中に置いた考え方です。 外国の人が日本の学校現場に来ると、その静かさや整然と座っている様子に感銘を受けるのですが、これは日本人の自主性が優れている証拠であり、日本の教育の特徴でもあると思います。 ところが、急激な技術発展と環境変化、それに伴うグローバル化、そして日本の超少子高齢社会という要素も相まって、今までのような「自主性」を軸に据えた形ではもう前に進めなくなっているのです。 目上の人の言う通りやっていればうまくいく、そんな時代は終わりを告げました。 いい大学に行けば、大企業に入れば、「いい生活」ができる、という一昔前の常識はもうなくなっています。 離職率の高まり、外国人労働者の増加、今まであった職業の消滅と新しい職業の誕生。 全てが自主性から主体性へのシフトが必要であることを表しています。 主体性を育む なんとも難しい話になってしまいましたが、保護者の皆様に考えていただきたいのは、家庭の子育ての中にいかに「主体性を育む」ような働きかけを入れられるか、ということです。 例えば掃除の話で例に取ると、「毎週一回掃除をしなさい」という声掛けから一工夫してみませんか、ということです。 よく勘違いされるのですが、「しなさい」という言い方を変えてみませんか、というと「何も言ってはいけない」と捉える方が多くいらっしゃいます。 なかなか掃除をしない子を見ても、声をかけてはいけないと思い込んでしまうようなのですが、そうではありません。 黙っていては子どもになんの刺激もないわけですから、自主性も主体性も育まれません。何かアプローチをするのはとても大切なことです。 例えば掃除でいうならば、こんな流れでアプローチしてみてください。 (1) 「あら、部屋が汚いように思うけど、どう?」とか、「最近掃除してないみたいだけど、あんまり必要性は感じない?」と本人の認識を確認する。 (2) 「お母さんは〜〜が大切だと思うから、あなたに定期的に掃除してほしいと思ってるけど、それはどう思う?」と指示・命令・押し付けではなく、自分の考えとその根拠を伝えて相手の解釈を確認する。 (3) (2)で子どもが理解を示したら、「どれくらいだったら掃除できそう?」と頻度や程度を確認する。理解を示さなかったら、「どういう目的で掃除しないの?」と掃除しないことで得られるメリットを聞いてみて、自分が理解できるかどうかを考えてみる。 文字で書くと簡単なのですが、これは意外と難しい話です。なぜなら、今まで積み上げてきた関係性があるからです。 今までがっつり指示しまくっていた親がいきなりこのアプローチで来たら、子どもは本当のことをなかなか言わないでしょう。 親のことを面倒な存在だと捉えてしまっているようなら尚更です。 でも何もしないならそれは変化していきません。ちょっとずつ意識しながら、子どもへの声かけの仕方を変えていきませんか。 変えることで明日の、来週の、来月の、そして未来の子どもの成長が変わっていくならば、ちょっとの変化はとても価値のあることではないでしょうか。 おわりに 子どもは一人ひとり個性があり、誰一人同じ人はいません。 ご自身の子どもを一人の人間としてよく観察し、尊重しながら一緒に考え成長していく。 そんな関係性の親子になれたらきっと将来にわたっていい関係でいられると、心から信じています。 これから受験や未来に向かっていく中学生のみなさん、それを支える保護者の皆様を応援しております! ここまでお読みいただきありがとうございました! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む
歴史の勉強がもっと楽しくなる!語呂合わせ一覧とおすすめ学習カード
歴史の勉強がもっと楽しくなる!語呂合わせ一覧とおすすめ学習カード はじめに 歴史の学習は、年号や出来事、人物名など覚えることが多く、苦手意識を持つ人も少なくありません。 特に「年号の暗記」は、テストの穴埋め問題や並べ替えで正答率を上げるためには避けては通れないポイントです。 ですが、無理に数字を丸暗記しようとしてもなかなか覚えられず、勉強が嫌になってしまうこともあります。 そこで今回は、歴史の勉強をもっと楽しく、そして効率的にする方法として、「語呂合わせ」を活用した暗記法をご紹介します。 あわせて、「中学教科書ワーク 歴史」特典の、 語呂合わせと相性抜群の学習カード「ポケットスタディ 歴史年号」や、「Newどこでもワーク」といった おすすめの学習ツールについても詳しく解説します。 歴史の年号暗記はなぜ重要? 歴史の年号を覚えることには、単なる「知識の詰め込み」以上の意味があります。 年号を正しく記憶しておくことで、出来事が「いつ起きたのか」という時間的な位置づけが明確になり、 歴史の流れを理解しやすくなるのです。 たとえば、鎌倉時代に起きた元寇と、室町時代の南北朝の争いについて、 どちらが先かが分からないまま学習を進めていても、日本の歴史の構造を正確に把握することはできません。 年号を覚えることは、「なぜその出来事が起きたのか」という因果関係を考える土台にもなるのです。 語呂合わせとは 語呂合わせの基本的な考え方 語呂合わせとは、数字を音や言葉に置き換え、覚えやすくする方法です。 たとえば「710年」は平城京が建立された年です。 唐(現在の中国)の都市長安をモデルとしており、律令制を確立したことも押さえるべきポイントになります。 「なんと(710)長安そっくりだ」といった具合に、数字に意味を持たせて押さえるべきポイントを取り入れることで記憶に残しやすくします。 語呂合わせの多くは、ダジャレやイメージしやすいフレーズで構成されており、視覚的・聴覚的に記憶を助けてくれるのが特徴です。 語呂合わせのメリット 語呂合わせの最大のメリットは、「覚えにくい数字」が「面白くて印象的な言葉」に変わることで、記憶に残りやすくなる点です。 たとえば「794年=なくよ(794) うぐいす平安京」という語呂は、多くの人が学生時代に一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。 このように、語呂合わせは記憶の手がかりとなるだけでなく、学習に対する心理的なハードルも下げてくれます。 クイズ形式のおすすめの学習ツールの紹介 「ポケットスタディ 歴史年号」の特徴 「ポケットスタディ 歴史年号」は、コンパクトなカード形式の学習ツールで、 片面に「年号」と「語呂合わせ」、「イラスト」、もう片面に「出来事」が書かれており、クイズ感覚で学ぶことができます。 語呂合わせと組み合わせて使えば、「1467年 ひとよ(14)でむな(67)しく応仁の乱」といった形で、数字と出来事を一緒に覚えられます。 このカードは通学時間や休憩時間、寝る前の数分など、すきま時間に手軽に取り組めるのが魅力です。 カードの順番をシャッフルして使うことで、記憶の定着も一層深まります。 「Newどこでもワーク」の活用法 「Newどこでもワーク」は、5教科の3年間の学習内容をどこでも手軽に勉強できるWEBアプリです。 問題演習と学習カードの機能がありますが、社会の学習カードは「ポケットスタディ」の内容が音声でも学べます。 視覚と聴覚の両方を使って学習することで、記憶の定着率がアップします。 朝起きたら1つの時代分の年号を音声で聞き、夜寝る前にその内容をカードで復習する…といった学習方法がより効果的です。 耳で聞いたフレーズが頭の中で再生され、語呂合わせがより印象に残りやすくなります。 ▶Newどこでもワークの詳細はこちら 時代別・主要な歴史年号の語呂合わせ ここでは、「中学教科書ワーク 歴史 ポケットスタディ」に掲載されている年号をもとに、 各時代の代表的な語呂合わせをご紹介します。 飛鳥時代 593年 聖徳太子が政務に参加「明日からも 大使は仏教をいつくしみ」 奈良時代 710年 都が平城京に移る「平城京 なんと長安そっくりだ」 平安時代 794年 都が平安京に移る「なくよ うぐいす平安京」 鎌倉時代 1185年 源頼朝が守護・地頭をおく「人々はご恩に報いる 奉公を」 室町時代 1392年 足利義満が南北朝を統一「いざ国を まとめて御所を 室町に」 江戸時代 1635年 参勤交代が制度化される「大名は 一路参勤交代へ」 語呂合わせを活用した効果的な暗記法 繰り返し音読する 語呂合わせは、声に出して読むことでより記憶に残ります。 何度も繰り返し音読することで、耳と口を使って脳に定着させることができるのです。 自分で語呂を作成する 市販の語呂合わせも便利ですが、自分でオリジナルの語呂を考えることで、より強い印象が残ります。 自分なりの言葉遊びを加えたり、好きなキャラクターや出来事に関連づけたりすると楽しくなります。 関連する出来事と結びつける 単に年号と語呂だけを覚えるのではなく、その前後の出来事や背景とあわせて覚えることで、歴史のつながりを深く理解できます。 たとえば、「794年 平安京遷都」とあわせて、「貴族文化の発展」「国風文化」なども関連づけて覚えるとよいでしょう。 クイズ形式で覚える 「ポケットスタディ」や「Newどこでもワーク」を使ってクイズ形式にすることで、楽しく学びながら知識を定着させられます。 友達や家族と問題を出し合うのもおすすめです。 まとめ 歴史の年号を覚えるのは決して簡単なことではありませんが、 語呂合わせを活用すれば、暗記の負担を軽減しながら効率的に学ぶことができます。 そしてその語呂合わせをさらに活かすためには、 「中学教科書ワーク」の特典、「歴史年号 ポケットスタディ」や「Newどこでもワーク」などの学習ツールを併用するのが効果的です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ぜひ、自分に合った学習スタイルを見つけて楽しく学びながら歴史に強くなりましょう!
中学生応援コラム 第9回「高校の選び方とその先」
皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 今回は高校の選び方の秘訣をお伝えしていきます。 内申点と偏差値が大きな要素になることは間違いないのですが、それだけで選ばないようにしてほしい!と強く思っています。 高校に行くかどうか 私が高校選びを生徒と一緒に考えるとき、まず最初に問うのは「高校、行くの?」ということです。 小中学校は義務教育ですが、高校については選択する権利があります。 別に決まりきったレールの上にあるわけではなく、様々な道がある中で高校に行くことを選ぶこともできますが、行かないことを選ぶこともできるわけですから、その意思決定を出発点にしてほしいのです。 目的について考える また、高校に行くなら何を目的にするのか、ということも合わせて考えてもらいたいと思います。 人によって高校に行く理由は様々ですが、一番多いのは「将来のため」という回答です。 もしこれを言葉にしたら、ぜひ「将来のためってどういうこと?」ともう一段・二段具体的にする質問を投げかけてみましょう。 多くの生徒は、この質問には明確な答えが出てこないと思いますが、それでいいのです。 自分にとって良い将来とはどういうことなのか?を考えるきっかけを作ることが大切です。 答えられないということは考えてないってことだ、そんなことではダメだ、と言わないように気をつけてくださいね! また、このタイミングで「高校を卒業したらどんなふうになりたいの?」という質問も投げかけてみてください。 これもこの時点で答えがはっきり出なくてもいいのですが、大学や社会でどんなことをやりたいか、どういうことに興味があるか、考えるきっかけを作ることはとても大切なことです。 高校選びとその先の進路は切っても切れない関係ですから、合わせて考えてみてほしいところです。 目的とマッチする高校を探す これらの質問を通して高校に行く理由がある程度クリアになると、高校の3年間でどんなことをすると良いか、アクションが明確になります。 部活に熱中するのか、大学受験に向けてしっかり勉強に取り組むのか、経験を広げるためアルバイトやボランティア、留学などに取り組むのか・・・。 もちろんこれらの組み合わせになるケースもあるでしょう。 それだけ3年間というのは貴重で、とても重要な期間です。 どんな3年間にしたいのか、高校に行く目的をもとに掘り下げてみてください。 そして、自分の考えがある程度まとまってから、高校探しに入ります。 高校には「教育目標」や「校風」というものがあり、自分が3年間でやりたいことに向いているかどうかをそれらと照らし合わせて考えていってください。 留学などに取り組みたいのに、とにかく勉強で忙しいような学校だとミスマッチになりますし、自分の意思で自由に決めたいのにとても厳しく指導する学校を選ぶのも合いませんよね。 高校選びはマッチングですから、自分がどうしたいかをしっかり考えて、その気持ちと合うような高校を選んでいくことをおすすめします。 高校を探す際には、まず条件をいくつかリストアップしてみましょう。 距離はどれくらいまで大丈夫か、寮生活も選択肢に入るか。部活はやりたいか。進路実現の状況はどうか。 学習以外の高校としての取り組みは。行事の力の入れ具合は。施設や設備の綺麗さは・・・ などなど、要素は数多くありますから、そのうち何を重視するのかをまずはたくさん出してみてください。 その条件をある程度満たす高校、となると自然と数は絞れてくるはずです。 そして重要なのは、「生徒自身がその高校に足を運んで見てみること」です。 3年間通うのは親ではなく生徒自身ですから、どれだけ中学校の方で忙しいとしても、必ず自分の目で見る機会を作ってください。 できれば通う手段(公共交通機関)で行ってみることをおすすめします。 そこに通うとなったらどうなのか、最大限イメージをしながら、その立地・校舎・教員・生徒を確かめていってください。 イメージをもって勉強にのぞもう ここまでしっかりやれば、「この高校なら通いたい!」というところが見つかっていくと思います。 そうなればあとは合格するためにしっかり努力をしていくのみです。 特に高校のことを考えていなかったときと比べると、力の入り具合も変わってくるはずですし、勉強の効率もグッと上がっていきます。 ぜひ生徒自身がそのような状態になるよう、しっかり対話を重ねていっていただきたいと思います。 次回はいよいよ最終回です! 自主性と主体性、この言葉を比べながら、どんな大人に育っていってもらいたいかというところを考えていきたいと思います。 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む
「POP」のひみつ ~中学教科書ワーク編~
進学・進級おめでとうございます。 新しい学校、新しい学年はいかがでしょうか。 新しいことには期待も膨らみますが、不安も出てきますね。 あせらず、ゆっくり臨んでいきましょう。 今回は、書店さんに並んでいる問題集のそばについている「POP」をちょっとご紹介したいと思います。 2025年度 中学校の教科書が新しくなりました! 2025年に中学教科書が改訂になり、それにともない、私たち文理の「中学教科書ワーク」も改訂になりました。 ですので、書店さんには新しい「中学教科書ワーク」が並んでいます。 表紙は教科によって矢印の色が違う、矢印が右方向へ進んでいる⁈ものです。 たとえば、英語は紫、数学はブルー、国語は赤色です。 ぜひ、書店さんに行って、お手にとって中身を見てみてください。 実際に中身を見て、表紙や紙の感じ、何冊か買った想定での持った感じや表紙の感じを感じてみてください。 「感じ」ばかりですが、1年間、勉強するモノですから、自分で見ててみると違うと思います。 やる気も出ます! POPって何? ここからは、書店さんに行ってからの話なのですが、「中学教科書ワーク」が変わると、それに伴って、POPも変わります。 POP(ポップ)って、なんとなくご存じだと思いますが、お店で商品の場所を知らせたりの注意喚起するための宣伝物のことです。 (POP=「Point of Purchase(ポイント・オブ・パーチェス)」の略) 書店さんに行ったら、学習参考書だけでなく、コミックや雑誌、文庫本やライトノベル、文具などさまざまなものがありますね。 それぞれ各ジャンルのコーナーには、それぞれのPOPがあります。 コミックでのコーナーには、各キャラクターのイラストが描かれたPOPがたくさん売り場をにぎやかにしていますし、 アイドルの写真集や作家さんの単行本の売り場では、サインが書かれて貼られていたりします。 「中学教科書ワーク」のPOP 文理の「中学教科書ワーク」も、教科書改訂にともない、改訂して、POPも新しくしました! 表紙からイメージしています。 表紙のモチーフの矢印で、ここに「教科書ワーク」があるよ、と示しています。 また、下の部分には、「中学教科書ワーク」特典の「CBTテスト」についてや、「スマホアプリ」について、紹介しています! サポートアイテムがたっぷりついているので、スキマ時間を利用して、効率よく、タイパよく、勉強できると思います。 中学生は、部活などで忙しいですからね。 このPOPを目指して書店さんで探してみてください。 POPのひみつ(新学期バージョン) このPOPは、英語と数学の色、紫と青の矢印を載せて、2教科2種類を置ける2面用のPOPとなっております。 ただ、書店さんによっては、売り場のスペースに限りがあって、表紙を見せておく、平台陳列ができないこともあるのです。 そんな時に便利なように、1面だけの陳列でできるように、分割できるようにしました~! → また、「中学教科書ワーク」はおかげさまで、新学期の4月や定期テストが始まる5月、6月はよく売れます。 そのため、4月あたりはたくさん書店さんに積んで販売してもらっています。 せっかく作ったこのPOPがつかえないともったいないので、さらに分割できるようにしてあります! → 後ろから見る 後ろから差す感じに! POPのひみつ(定期テスト間近バージョン) 新学期の季節が終わり、5月、6月になってくると定期テストがあります。(学校によって異なりますが) 新学期が始まったときは、英語や数学の教科書ワークを皆さん、買っていかれます。 ただ、定期テストは理科社会もあります。 日常は英語数学が中心に勉強していますが、定期テスト間近には、理科社会も欲しくなります。 その時のために、POPも変身できるようにしました~! どうなってるかというと・・・ ① → ②→ ③ 英語と数学の裏に、理科、社会の、グリーンとオレンジが出現します! 定期テストの時期になって、理科社会をお手元にない方は、書店さんでこのバージョンのPOPを探してみてください。 (※書店さんは、ぜひこのようにクリンと裏返ししてお使いいただけるとうれしいです) おっ! 棚差しと棚下POP?! 新学期時には、書店さんでは平台陳列といって、表紙を出して積んでくれてますが、なかなかすべてを陳列できません。 平台に並んでいるものの以外は、棚に入っています。 その時に、見出しとして使ってもらっているのが「棚差しPOP」と「棚下POP」です。 棚差し 棚下 まとめ 「中学教科書ワーク」のPOPのひみつを、ちょっとご紹介させていただきました。 これらのPOPで、ここに「教科書ワークがある!」「目立ってわかりやすかった~」とか、探している方のお役に立てたらうれしいです。 ちょっと、POPを作っているものからのご紹介でした。 文理の「中学教科書ワーク」は、いわゆる教科書準拠版という、教科書に準拠している=教科書の配列にあっている、単語や用語が教科書と一緒、の問題集です。 まず、学校の授業をしっかり理解して、そこから考えていこう、という方には合います。 高校入試にはつきものの「内申書」で高内申をとるには、学校の定期テストでしっかり点数をとっていくことが重要です。 よろしければ、ぜひ書店さんでお手に取って、見てみてください! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 【今回の執筆者】 イニシャル:KN⊿ 年代:50代 ~今回の一言~ お客様にお役立ちのPOP作りを♪
中学生応援コラム 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」
皆さん、こんにちは! このコラムでは、中学生が学校の勉強をスムーズに進め、良い高校入試を迎えるサポートをするために、学校の勉強や入試に向けて取り組むべきポイントをお伝えしていきたいと思います! 今までの更新コラム 第1回「高校入試のとらえ方(1) 種別と学科」第2回「高校入試の捉え方(2) 受験形態」第3回「内申ってなんだろう 高い内申をとるために必要なこと」第4回「内申点と将来の選択肢への影響」第5回「定期テストってなんだろう 高得点を取るために必要なこと」 第6回「定期テスト成功の秘訣!普段から意識したいこと」 第7回「模擬試験はできるだけ早くから受けよう!」 第8回「勉強と部活の両立をどう捉えるか」 第9回「高校の選び方とその先」 第10回「自主性と主体性」 さて、今回は多くの中学生にとって永遠の悩みとも言える「部活動と勉強の両立」というテーマに切り込んでいきたいと思います! カギは「見える化」と「優先順位」、この二つを覚えておいてくださいね。 両立とはどんな状態? まず皆さんに考えていただきたいのは、部活動と勉強が両立できていない状態、というのはどういう状態か?ということです。 おそらくは、「部活動で疲れてしまって勉強する時間が取れない」とか「勉強のプレッシャーで部活に集中できない」とか、どちらか片方または両方のクオリティが下がってしまっている状態なのではないでしょうか。 では次に考えたいのは、その状態はどうなったら解消できるのか?ということです。 (余談ですが、ここで「何がいけないのか?」という考え方をしてしまうと、何かを取り除かないといけなくなり、両立には繋がりにくくなります) 私の今までの実体験だと、「勉強する時間がもう少し取れれば」とか、「成績が上がれば」とか、やはり部活動より勉強の方が優先なのでは、という考え方が多く出てくると思います。 そこで最初のキーワード「見える化」が大切です。 時間の使い方の「見える化」 普段の一日の過ごし方を、一回ノートやエクセルなどに書き出してみて、自分の時間の使い方を見える化してみましょう。 そうすると、多くの場合「この時間、何やってるっけ?」という謎の時間が出現します。 ぼーっとしている、何となく過ごしている、という時間が実は結構あるんです。 そういう時間を工夫して勉強に使えば、1日あたり1時間くらい勉強することができて、かなりの違いが出てくるのです。 工夫の仕方も様々です。 例えば食事の後リビングでのんびりしてしまうなら、食事が終わったら家族で協力してひとまず勉強机に向かうようにするとか、眠くなってしまうならお風呂に入る時間を調整してサッパリしてから時間を使うようにするとか、部活から帰ってきたら30分だけ宿題に取り組んでからご飯を食べるとか・・・ 家庭の生活サイクルに合わせて、みんなで一緒に考えられるといいかもしれません。 一方で、見える化したけどあんまり使える時間がないなあ・・・という人もいるかもしれません。 そういう人は、おそらく空いている時間で何か別のこと(ゲームとか読書とかテレビとか)をやっているのだと思います。 そこで出てくるのがもう一つのキーワード、「優先順位」です。 「優先順位」をつける やりたいこと・やるべきことをざっと書き出してみてください。箇条書きで大丈夫です。 書き出したら、それらを「重要度」「緊急度」の二つの軸で、以下の四つに分類してみてください。 (1)重要ですぐ(早め)にやるべきこと (2)重要だけどすぐではなくていいこと (3)重要ではないけどすぐやるべきこと (4)重要ではなくすぐでなくてもいいこと おそらく、ゲームや読書やテレビ、というのは(2)か(4)になるのではないでしょうか。 一方で勉強(特にテスト前)は(1)(2)あたりになるでしょう。 (4)に入ることはやらなくても問題ありませんから思い切って全てやらないことにして、(1)(3)を片付け、そして(2)に集中していく、という形で整理をしてみましょう。 これが優先順位をつける、という作業です。 この順位づけは、部活動と勉強の話以外にも応用できます。 例えばテスト前に9科目の勉強の順番を決めたいとなった場合は、成績を上げる必要がある科目かキープでいいのか、苦手な科目なのか得意なのかによって重要度や緊急度が変わります。 それをはっきり決めてから取り組む順番を決めると、非常に効率の良い勉強ができるようになりますよ。 将来にも役立つ こんな時間の使い方や優先順位の決め方ができるようになれば、大人になっても役立つこと間違いなし! 社会に出て活躍するためのアプローチの一つとして、部活動と勉強の両立という課題に向き合ってみてはいかがでしょうか? さて、いよいよこのコラムも終盤戦になってきました。次回は「高校の選び方」というテーマで、自分の進路をどうやって決めていくべきかお伝えしていきます! 筆者:金澤 浩(かなざわ ひろし) 大手学習塾で20年以上指導し、様々な生徒を合格に導く。現在は共育コンサルタントとして講演会や個別での進路選択や学習の支援に取り組む
受験生を優しく支える!プレッシャーをかけない応援メッセージ集
はじめに 受験期のプレッシャーと応援の重要性 受験は大きなイベントであり、多くの中学生が様々なプレッシャーを感じています。 保護者や教師からの期待、友人との競争、そして自身の目標に対するプレッシャー。 これらが重なり、心身に大きな影響を及ぼすことがあります。 試験前の緊張や不安が学習効率を下げ、結果的に成績が下がってしまう、なんてことも少なくありません。 だからこそ、受験生に対する応援、声かけは非常に重要です。 適切な言葉や行動が、受験生のメンタルを支え、勉強に取り組む助けになります。 今回は、受験生を優しく支えるための具体的な応援メッセージやコミュニケーションの方法について紹介していきます! プレッシャーにならない応援メッセージのポイント 受験生を励ますときは、出来る限りプレッシャーを与えないことが重要です。 努力を認める 「最近、本当に一生懸命勉強してるね。あなたの努力はちゃんと見てるから、自信を持ってね。」というように、受験生の努力を認めることは非常に重要です。 どれだけ勉強をしても結果が伴わない時期、思うようにいかない瞬間が受験では訪れます。 「頑張っているのに結果がでない」という思いは、受験生本人が一番感じているのです。 そのため、本人が取りこぼしてしまいがちな過程に目を向けることも大切です。 周りから努力が評価されることで、自信を持ち、より前向きに取り組むことができるのです。 安心感を与える 「どんな結果であれ、あなたの頑張りを誇りに思うよ。」と伝えることで、安心感が与えられます。 受験期はプレッシャーに押しつぶされそうになったり、自身のすべてがダメだと感じてしまったりと、普段よりメンタルが落ち込みやすいです。 安心感を与えることで、少しでも受験生がプレッシャーから解放され、リラックスして勉強に集中できる環境を作りましょう。 具体的な言葉の例 ここでは、具体的な受験生への応援メッセージをいくつか紹介します。 ●「あなたが頑張っている姿を見ると、誇らしいよ。」 ●「勉強したことは、必ず役に立つよ。」 ●「試験は大事だけど、あなた自身が大切だから無理しすぎないようにね。」 ●「頑張った分だけ結果はついてくるから、焦らずにやっていこうね。」 などがあげられます。 避けるべき応援メッセージ 受験生にプレッシャーを与えてしまう可能性のある言葉や表現にも注意が必要です。 過度な期待を示す言葉 「絶対に合格してね。」や「親戚一同が期待してるから、頑張ってね。」などの過度な期待は、 受験生にとって大きなプレッシャーになります。 こうした言葉は、受験生が自分に対して過剰な期待を抱く原因となり、逆に不安を増すことがあります。 受験生は「合格しなければならない」という思いに駆られ、緊張や不安が増すことがあります。 「君ならできるから、安心して挑んでね。」といった言い方に変えると、プレッシャーを軽減できます。 比較する表現 「○○さんはもっと頑張っているよ。」というような他人との比較は、受験生の自信を損なう可能性があります。 兄弟での比較も避けた方がよいでしょう。 「あの子はもう合格圏内にいるらしいよ。」という言葉や「みんなが頑張っている中で、あなたはどうなの?」といった表現も、 受験生に焦りを感じさせることがあり、プレッシャーに繋がりかねません。 個々の努力や成長を尊重し、比較ではなく本人の進歩を評価することが重要です。 保護者の方(自分)にとっては応援メッセージになることであっても、受験生本人にとってはプレッシャーになる言葉もあります。 結果などにも関心を寄せてほしいのか、結果には触れないでほしいのか、保護者の方の意見・体験を聞きたいのか、そうではないのかなどは、 本人に寄るところが大変大きいです。 受験生に響く良い言葉がけが出来るように、しっかりと本人の性質に合わせて声がけをするようにしてくださいね! 受験生とのコミュニケーションの取り方 日常生活で受験生と接する際の適切なコミュニケーション方法や、リラックスできる環境作りの工夫を紹介します。 日常生活での気遣い 1.食事の配慮受験生にとって、栄養バランスの取れた食事は非常に重要です。 勉強に集中できるように、健康的な食事を用意することが大切です。 例えば、脳に良いとされる魚やナッツ、野菜を使った料理。 また、受験生の好みや食べやすいメニューを考慮することで、食事の時間を楽しみに感じてもらえます。 簡単に食べられるおにぎりやサンドイッチを作っておくとよいですね。 2.家事の負担を減らす受験生が勉強に集中できるよう、家事の負担などを軽減することも重要です。 家族全員で協力して役割分担をすることで、受験生の負担を軽減することができます。 これらの気遣いを通じて、受験生が安心して勉強に集中できる環境を作ることができます。 日常生活の中での小さな配慮が、受験生にとって大きな支えとなるでしょう。 リラックスできる環境作り 1.自由な時間を確保する勉強だけでなく、趣味や友人との時間も大切です。 受験生がリフレッシュできるよう、友達と遊ぶ時間を設けたり、趣味に没頭する時間を持たせることも重要です。 心のバランスを保ちながら、勉強に取り組むことが大切です。 2.リラックスできる時間を提供する勉強の合間に、リラックスできる時間を設けることも大切です。 例えば、夕食後に一緒に映画を観たり、ボードゲームを楽しんだりすることで、受験生がリフレッシュできる時間を提供します。 このような時間が、受験生のストレスを軽減し、心の余裕を持たせる助けになります。 3.勉強環境を整える 静かで集中できるスペースを作ることで、受験生が安心して勉強に取り組めるようになります。 ただ、音があるほうがいいのか、ないほうがいいのかは本人の好みがかなり分かれます。 受験生の好みに合わせて調整することを心がけてください。 受験生を支えるおすすめの学習教材 コーチと入試対策! 8日間完成 中学1・2年の総まとめ 「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」 コーチといっしょに、8日間で中学1・2年の内容を総まとめ! すべての受験生が入試対策を前向きにスタートできる、とっておきの1冊です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策! 10日間完成中学3年間の総仕上げ 「10日間完成 3年間の総仕上げ」コーチといっしょに、10日間で中学3年間の内容を総復習! 入試に出る重要な内容をていねいに復習できる、とっておきの1冊です。 短期間で3年間の復習ができ、入試に向けて自分の得意や苦手分野をおさえることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 豪華特典:応援日めくりの紹介 「コーチと入試対策!」の特典として、「応援日めくり」があります。 机に飾って眺めるだけでその日の確認テストができ、コーチの応援メッセージも付いています! 応援メッセージでモチベーションを高めて、頑張ってください! 受験生の努力をしっかりサポートするアイテムとなっています。 まとめ 受験は、保護者や周りの人の力添え、努力があるとより万全の体制で挑めるものです。 努力を認め、安心感を与えることが、受験生のメンタルを支える鍵となります。 みなさまが良き春を迎えられるよう、心よりお祈りしております!!