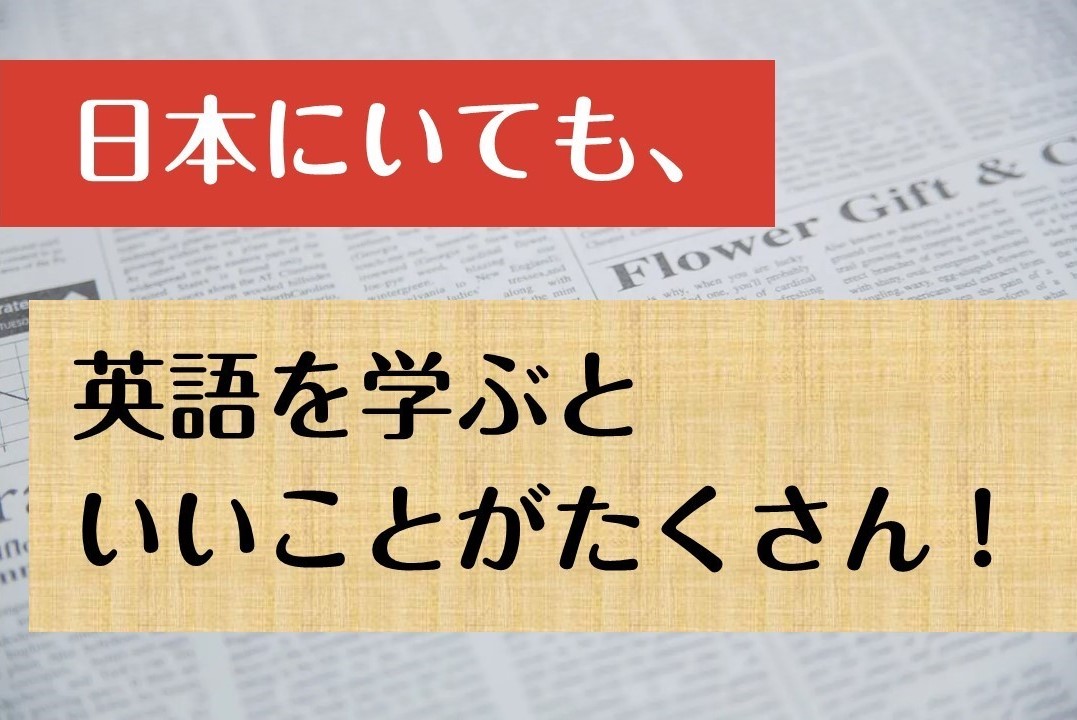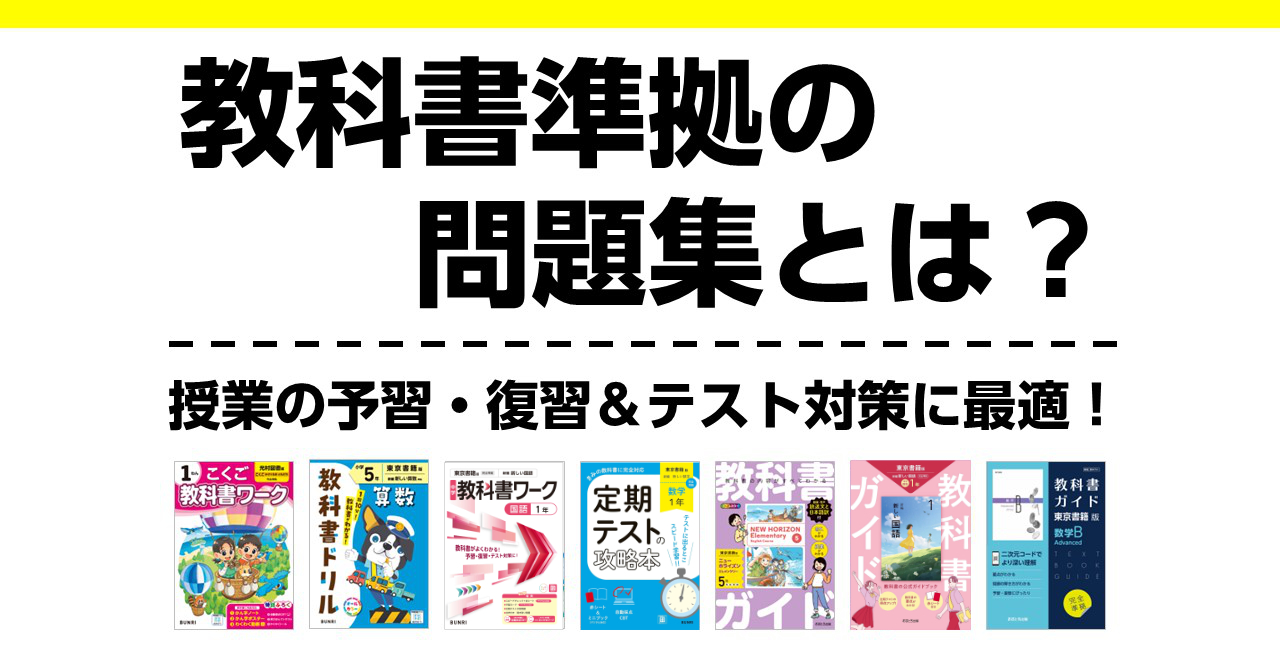中学英語 やさしく学ぼう 接続詞
はじめに
英語で「わかりやすい文」を書くには、接続詞(せつぞくし)はとても大切!
接続詞を使えば、文をつなげて、自分の考えをスムーズに伝えることができます。
たとえば、
I like soccer. I play it every day.
→ I like soccer and I play it every day.
(私はサッカーが好きで、毎日やっています。)
It was raining. We went out.
→ It was raining, but we went out.
(雨が降っていたけど、私たちは出かけました。)
このように、接続詞を入れるだけで、英文がぐっと自然に!
接続詞を味方につけて、伝える力をアップさせましょう。
接続詞ってなに?
接続詞の役割を知ろう
接続詞とは、「文と文」や「言葉と言葉」をつなぐつなぎことばのこと。
英語では会話でも文章でも、この“つなぎ役”が大活躍します。
例を見てみましょう。
I have a dog and a cat.
(私は犬と猫を飼っています。)
I like tennis, but I don’t play it well.
(テニスは好きだけど、上手じゃない。)
こんなふうに、接続詞を使うと気持ちや理由がスムーズに伝わります。
もし、英語が「単語や文を並べただけになっている…」という人は、まずは基本の接続詞を覚えましょう!
ぐんとレベルアップできますよ。
これだけは覚えよう! 重要な接続詞の使い方
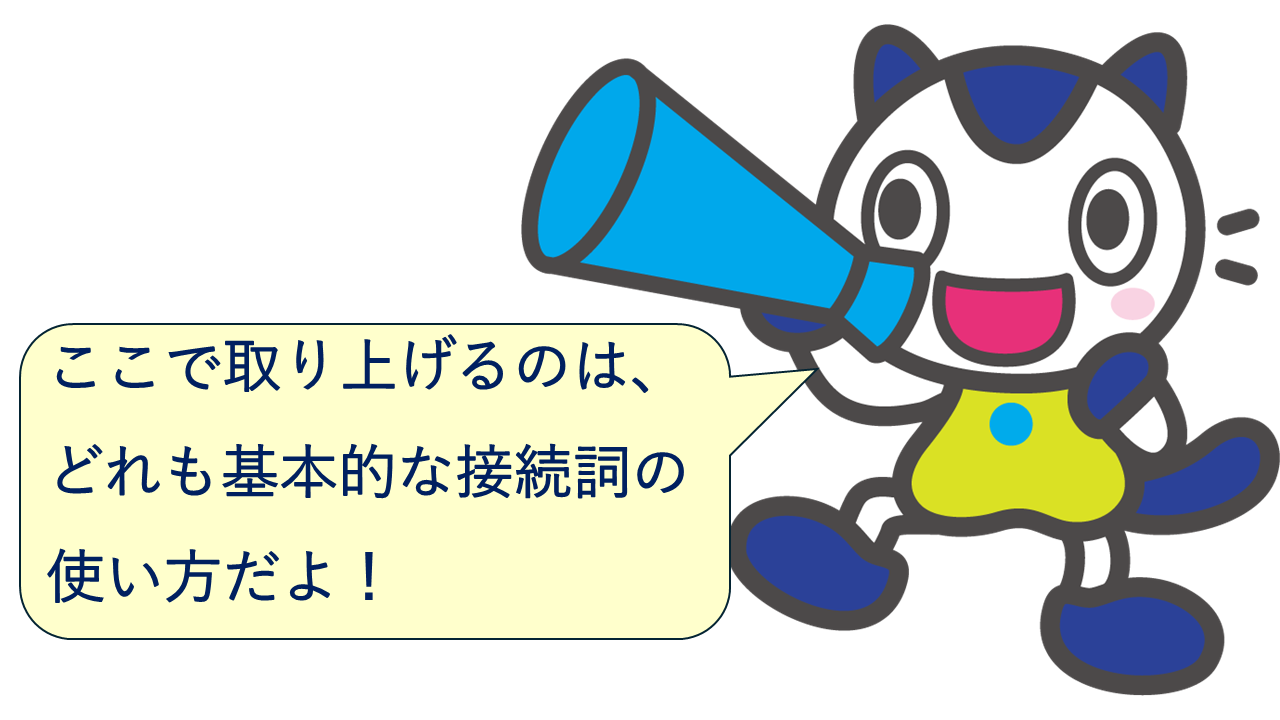
①「並列」を表す接続詞:and、then
使い方
・and は「~と~」「そして」、似ている内容をつなげるときに使う。
・then は「それから」「そのあとで」、順番や順序を表す。
I like apples and oranges. ※単語と単語をつなげる
(私はりんごとオレンジが好きです。)
He plays soccer and studies English. ※文と文をつなげる
(彼はサッカーをし、そして英語を勉強します。)
I did my homework, then I watched TV.
(私は宿題をして、それからテレビを見ました。)
②「反対のこと」を表す接続詞:but、however、though
使い方
・but は「しかし」、前の内容と反対のことを言う。
・however は「しかしながら」、少しかたい表現。また、文の最初に来ることが多い。
・though は「~だけれども」、文の最後に来ることもある。
I like soccer, but I can’t play well.
(私はサッカーが好きですが、上手にできません。)
I wanted to go skiing. However, it was too cold outside.
(私はスキーに行きたかったです。しかしながら、外は寒すぎました。)
She is kind, I don’t like her though.
(彼女は親切です、でも私は彼女が好きではありません。)
③「理由」を表す接続詞:because、since、as
使い方
・どれも「~なので」「~だから」。
・because は理由を強調するときに使う。
・since 、asは主に相手がすでにその理由を知っているときに使うことが多い。ややかたい表現。
I was absent from school because I was sick.
(私は病気だったので、学校を欠席しました。)
Since it was raining, we watched TV at home.
(雨が降っていたので、私たちは家でテレビを見ました。)
As he was busy, he didn’t come.
(彼は忙しかったので、来ませんでした。)
④「結果」を表す接続詞:so、therefore
使い方
・理由を表す接続詞(becauseなど)と逆の方向で使うのがポイント。
・soは「だから~」、thereforeは「それゆえ」。
・soのほうがややカジュアルな表現、thereforeのほうがややかたい表現。
I was hungry, so I ate a sandwich.
(私はお腹がすいていました、だからサンドイッチを食べました。)
He didn’t study hard, therefore he failed the test.
(彼はあまり勉強しませんでした、その結果テストに落ちました。)
⑤「仮定」を表す接続詞:if、unless
使い方
・if は「もし~なら」、条件を表す。
・unless は「~でない限り」「もし~でなければ」、ifとは逆の条件を表す。
If it rains, we will stay home.= We will stay home if it rains.
(もし雨が降ったら、私たちは家にいます。)
Unless you hurry, you’ll miss the bus. = You’ll miss the bus unless you hurry.
(急がなければ、バスに乗り遅れますよ。)
⑥「時間」「順序」を表す接続詞:when、while、before、after
使い方
・when は「~するとき」。
・while は「~している間」。
・before は「~する前に」、after は「~する後に」。
・before と after は、前置詞としても使う(例:before lunch)。
I was sleeping when the phone rang. = When the phone rang, I was sleeping.
(電話が鳴ったとき、私は寝ていました。)
He was singing while he was cooking. = While he was cooking, he was singing.
(彼は料理をしている間、歌っていました。)
I finished my homework before my mother came home.
(母が帰ってくる前に私は宿題を終えました。)
We went out after the rain stopped.
(雨がやんだあとに、私たちは出かけました。)
⑦「選択」を表す接続詞:or
使い方
・orは「AかB」「~、それとも…」、2つの選択を表すときに使う。
Do you want tea or coffee?
(あなたは紅茶かコーヒーがほしいですか?)
⑧「~ということ」を表す接続詞:that
使い方
・「~ということ」「~というのは」、思っていることや知っていることを伝えるときに使う。
・省略することもできる。
I know that she is a good teacher. = I know she is a good teacher.
(私は彼女がよい先生だということを知っています。)
接続詞の使い方のコツ
① 同じ接続詞ばかり使わない!
andやbutなど同じ接続詞だけを使って文を続けると、文がダラダラとした印象に…。
いろいろな接続詞を使い分けて、読みやすく、伝わりやすくしましょう。
悪い例
I like cats and I like dogs and I like birds.
(猫が好きで、犬が好きで、鳥も好きです。)
改善例
I like cats and dogs, but I like birds the most.
(猫と犬が好きだけど、一番好きなのは鳥です。)
② 自分の意見を書くときに接続詞を使おう!
自分の気持ちや考えを書いたり話したりするとき、接続詞が活躍します!
上手に使って、作文やスピーチで自分の意見をわかりやすく伝えましょう。
例
I like English because it’s fun.
But I didn’t do well on the test last week.
So I’m going to study hard for the next one.
(英語は楽しいので私は英語が好きです。
でも、先週のテストはよくできませんでした。
だから、次のテストに向けて一生けんめいに勉強します。)
接続詞のまとめクイズ
上記で取り上げた接続詞のクイズにチャレンジ!

次の英文の( )に入るもっとも適切な接続詞を、下の3つの中から1つ選びましょう。
【問題】
① I like soccer ( ) I play it every day.
but / and / because
② It was raining, ( ) we played games.
so / and / before
③ I was tired, ( ) I went to bed early.
though / because / so
④ He likes Math, ( ) I like English.
but / or / when
⑤ You can have tea ( ) coffee.
if / or / that
⑥ I went to the park ( ) it was sunny.
before / because / unless
【答と訳】
接続詞を勉強しよう! おすすめ問題集
『中学教科書ワーク』
・教科書会社別、学年別に作成。
・学校で使っている教科書の内容を理解するのにとっても役立つ。
・教科書に対応した暗記ブック、スキマ時間の学習に役立つ英単語カードなどの特典も充実!
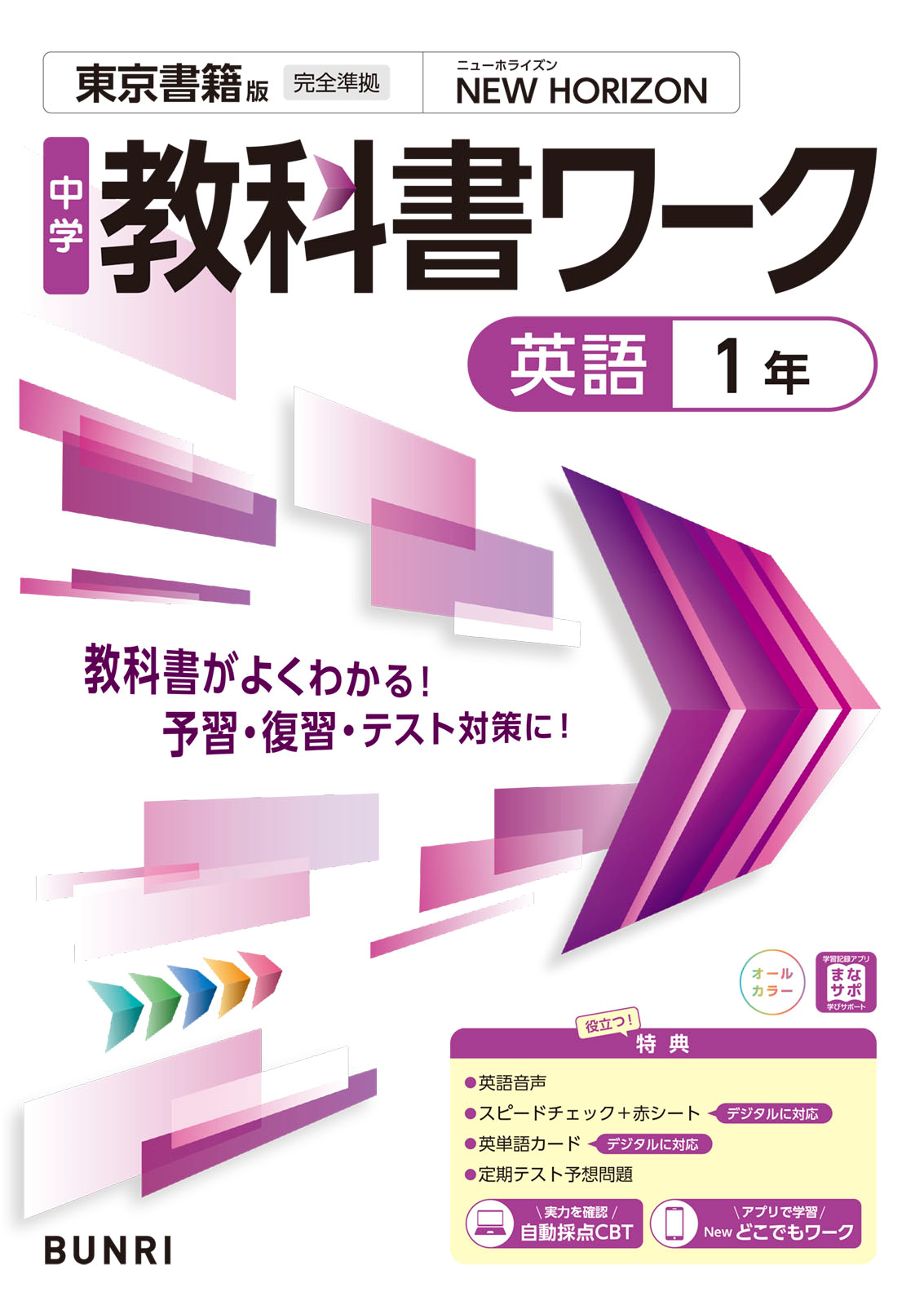
『わからないをわかるにかえる』
・学年別(1年、2年、3年)に発刊。
・「英語はちょっと苦手…」という方も、安心して学べる構成。
・左の文法の説明を読む(理解)→右の問題を解く(確認)、
で文法の重要ポイントを着実におさえることができる。
・文法の説明は、イラストや図解がいっぱい。楽しく学習できる!
・英単語カード(音声付き)、らくらくスケジュール(WEBアプリ)の特典付き。
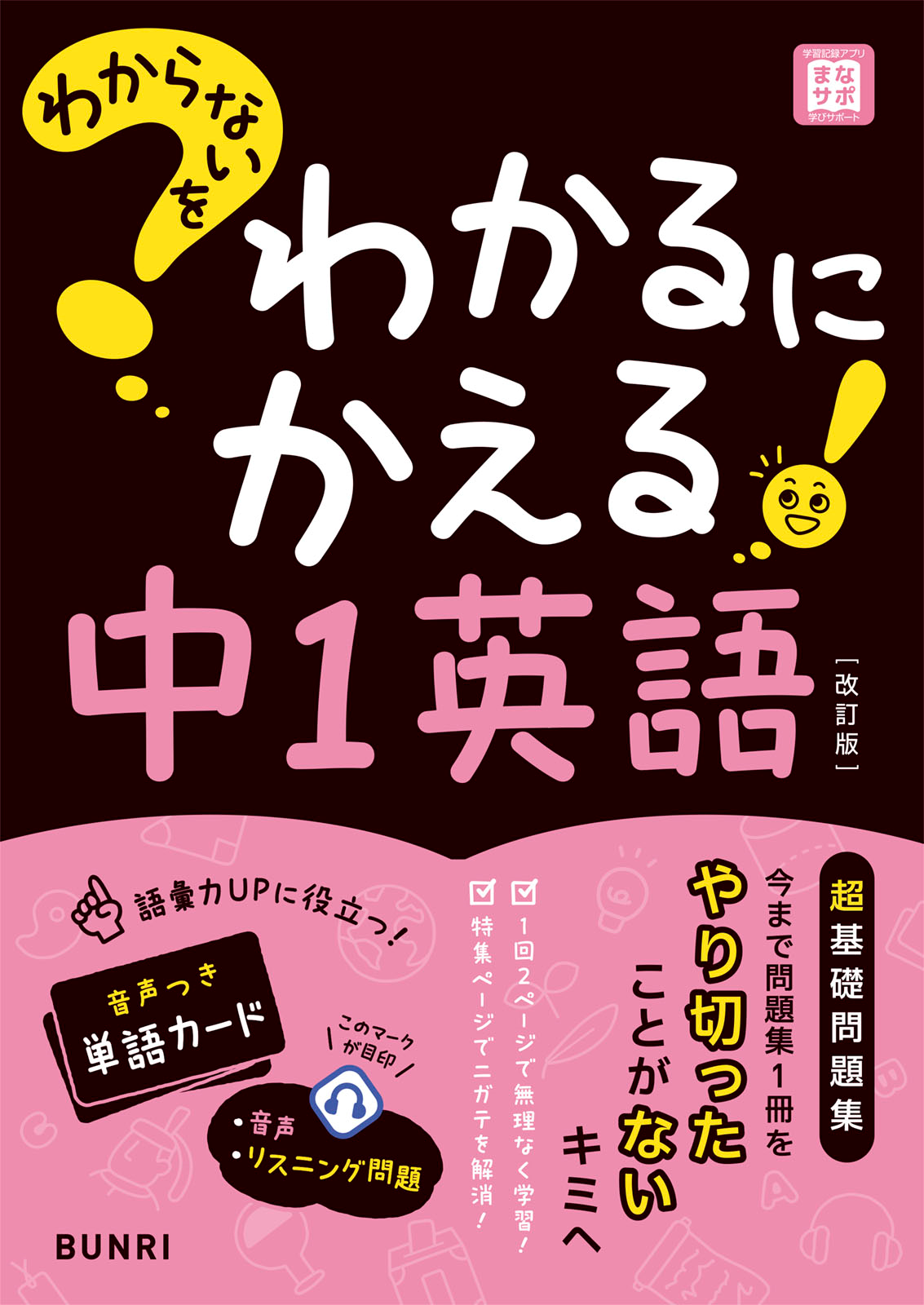
「難しい問題にチャレンジしたい」というあなたには、次の2つがおすすめ。
『完全攻略』
・「定期テスト対策」に加え、「高校入試対策」もこのシリーズでバッチリ。
・発音アプリと連動した小冊子に加え、充実した特典がたくさん!
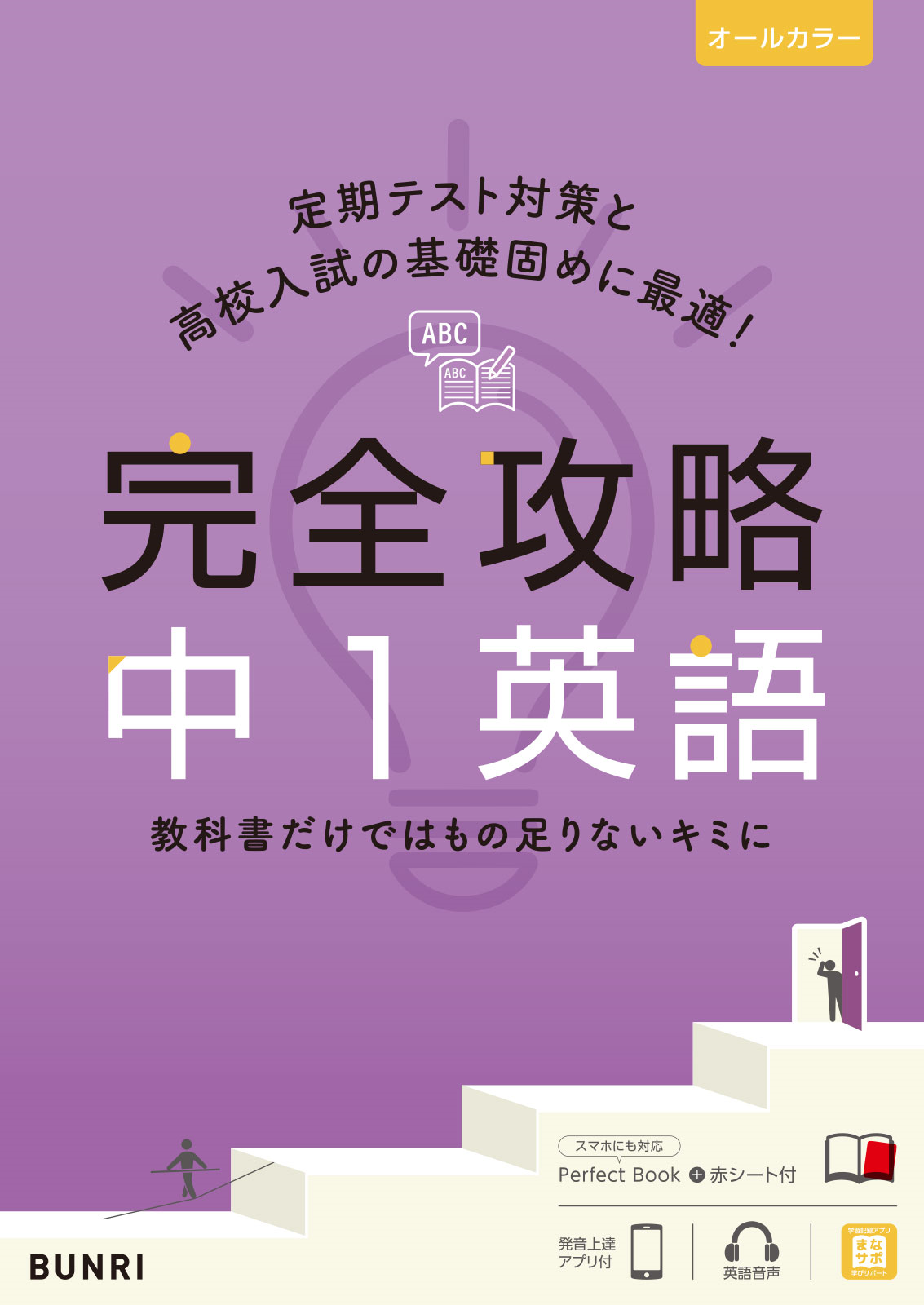
『ハイクラス徹底問題集』
・「定期テスト対策」に加え、高校入試の「難関校対策」にも対応。
・詳しい解答解説で難問もしっかり理解できる!
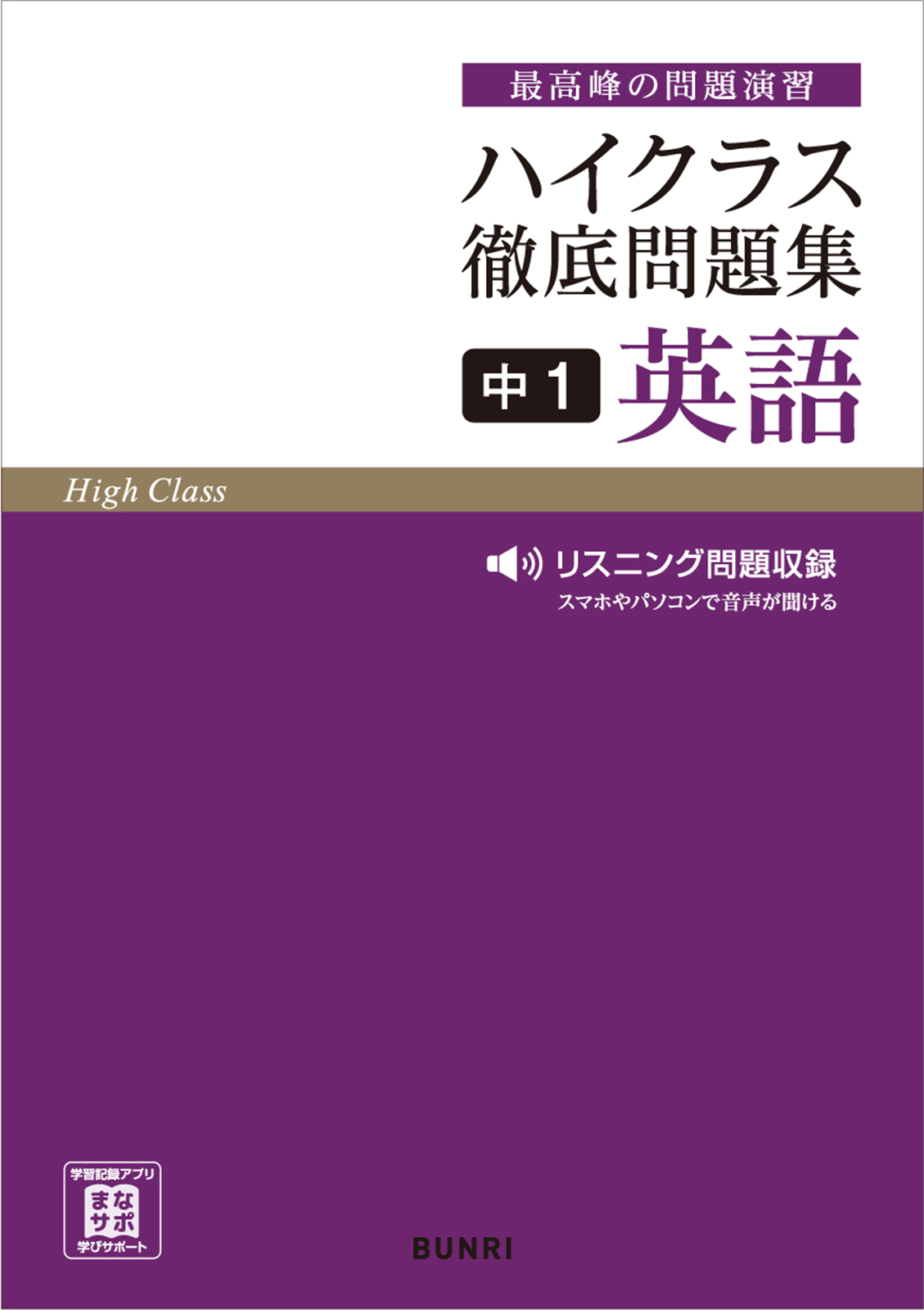
まとめ 接続詞で英語がもっと楽しくなる!
接続詞は「英語で伝える力」をぐんと高めてくれる、とても大切なことばです。
最初は、andやbutなど、よく出てくる接続詞の使い方を覚えましょう。
それから、少しずつほかの接続詞もチャレンジしてみましょう。
接続詞を使いこなせるようになると、“前後の流れ”がスムーズに伝わるようになります。
今日からさっそく、英語を書くとき・話すときに「つなぎことば」の接続詞を意識してみましょう!