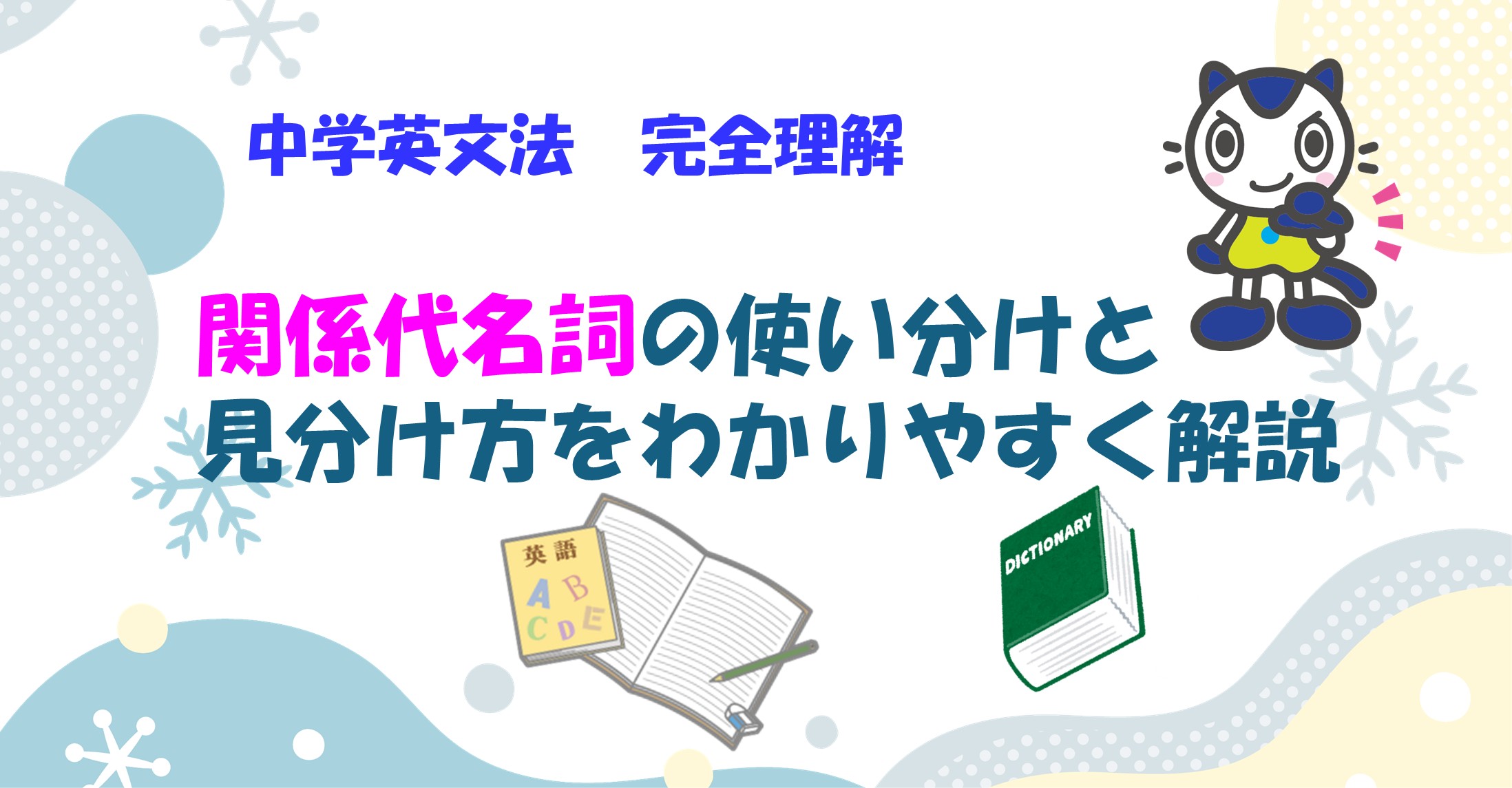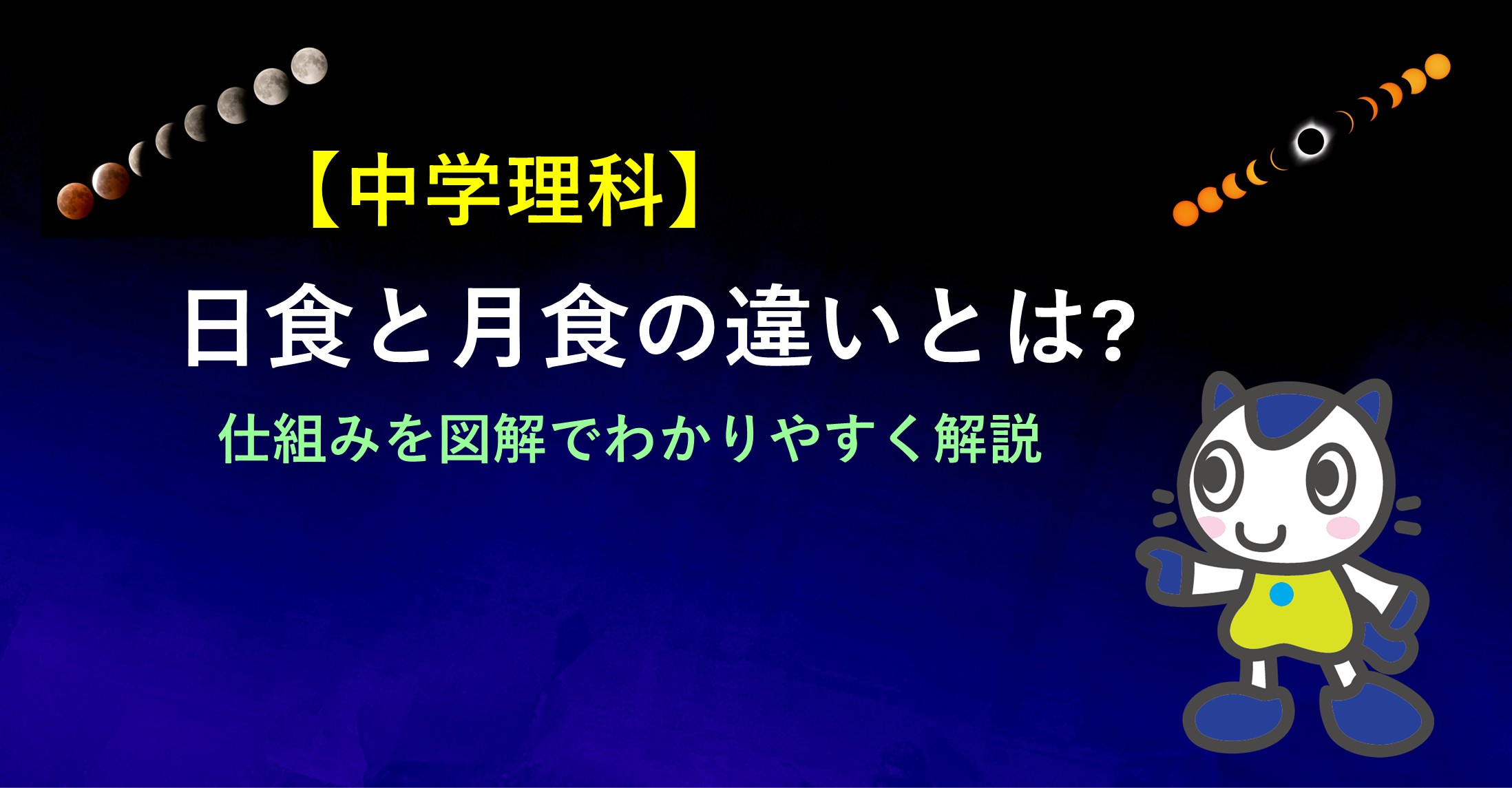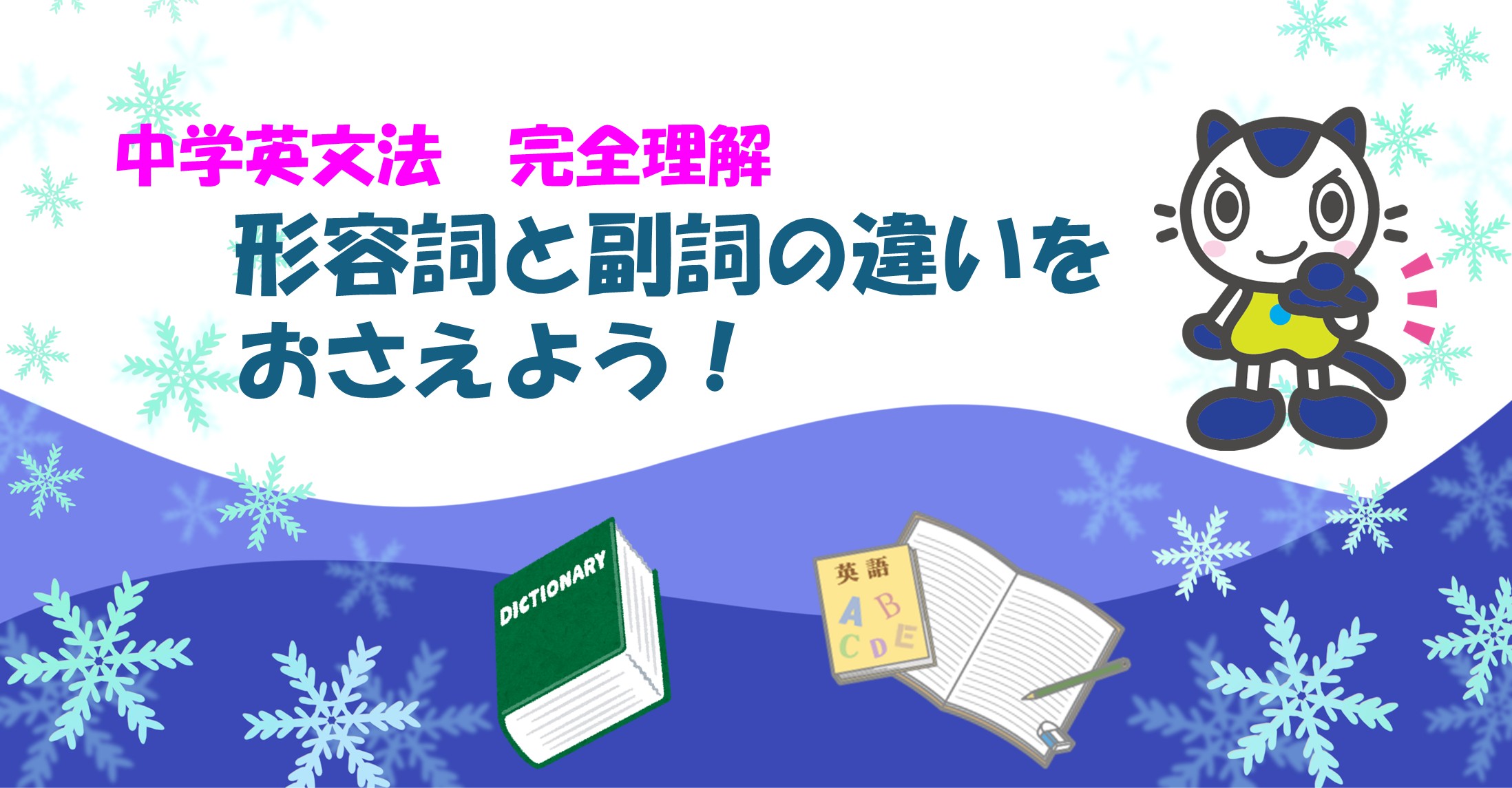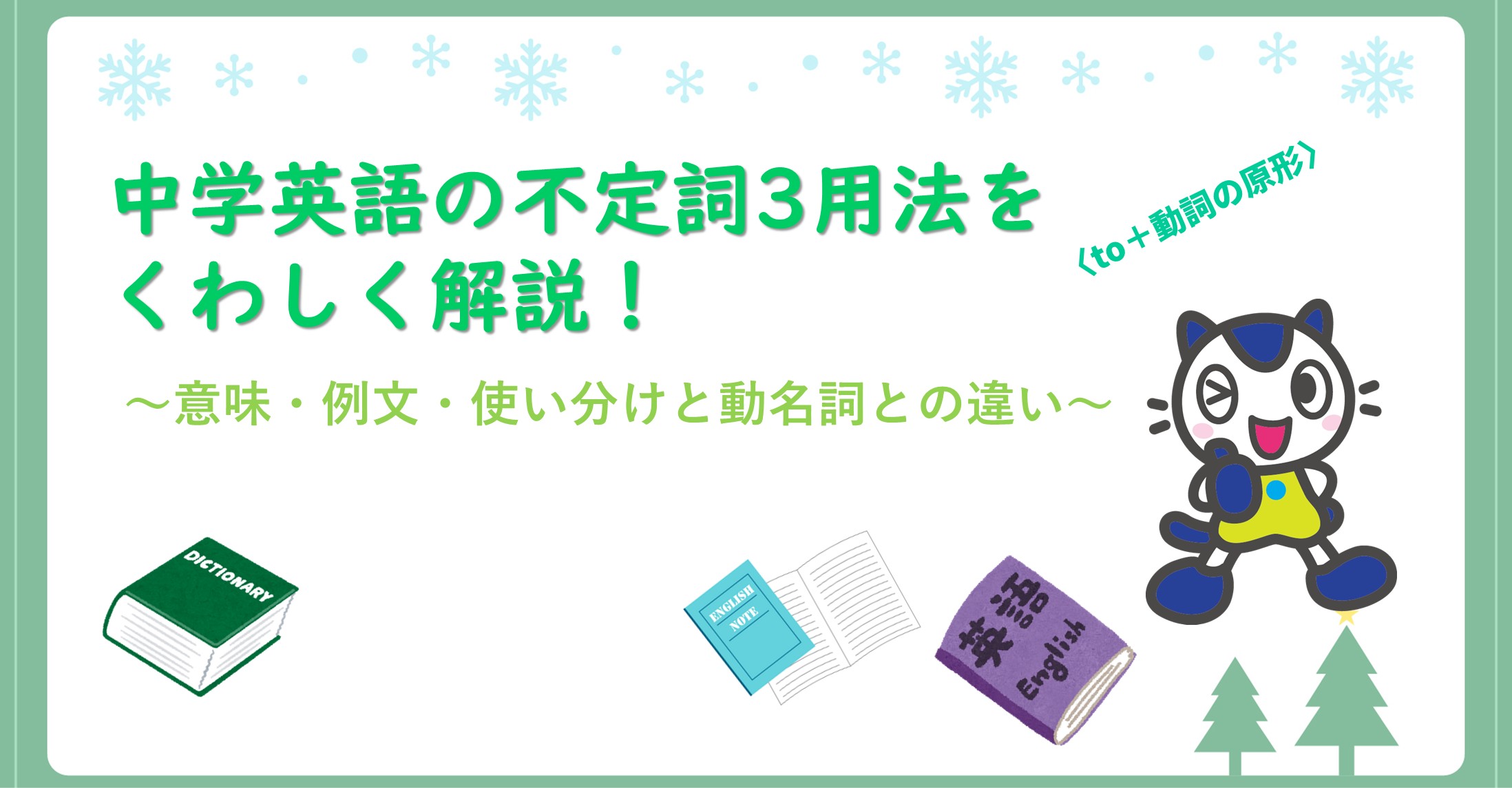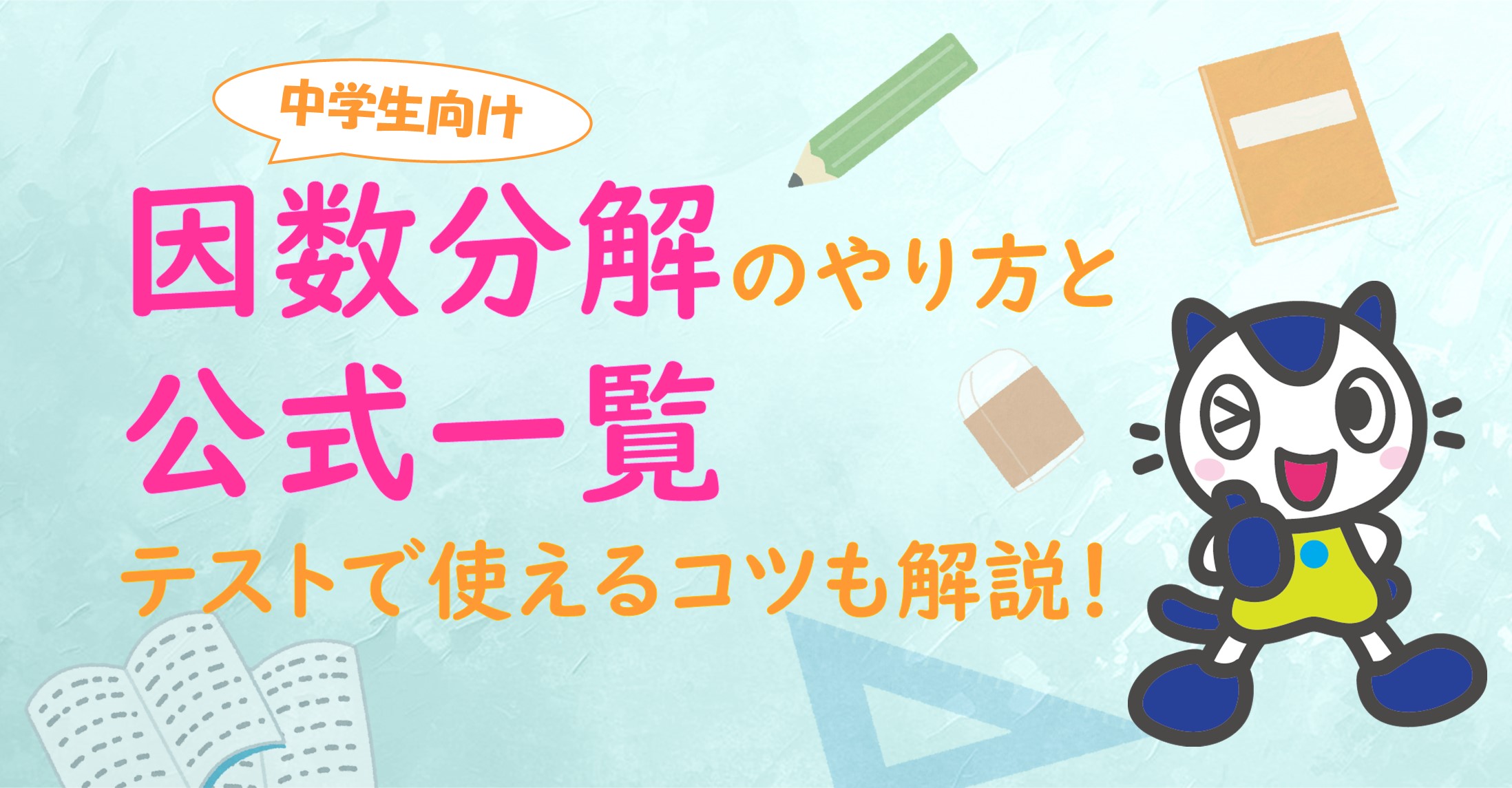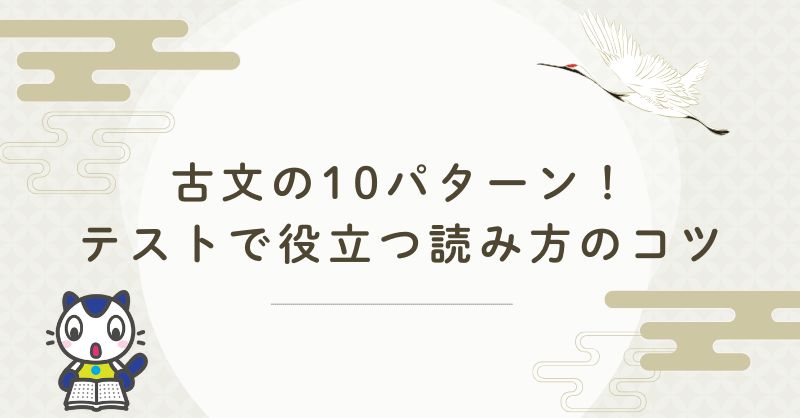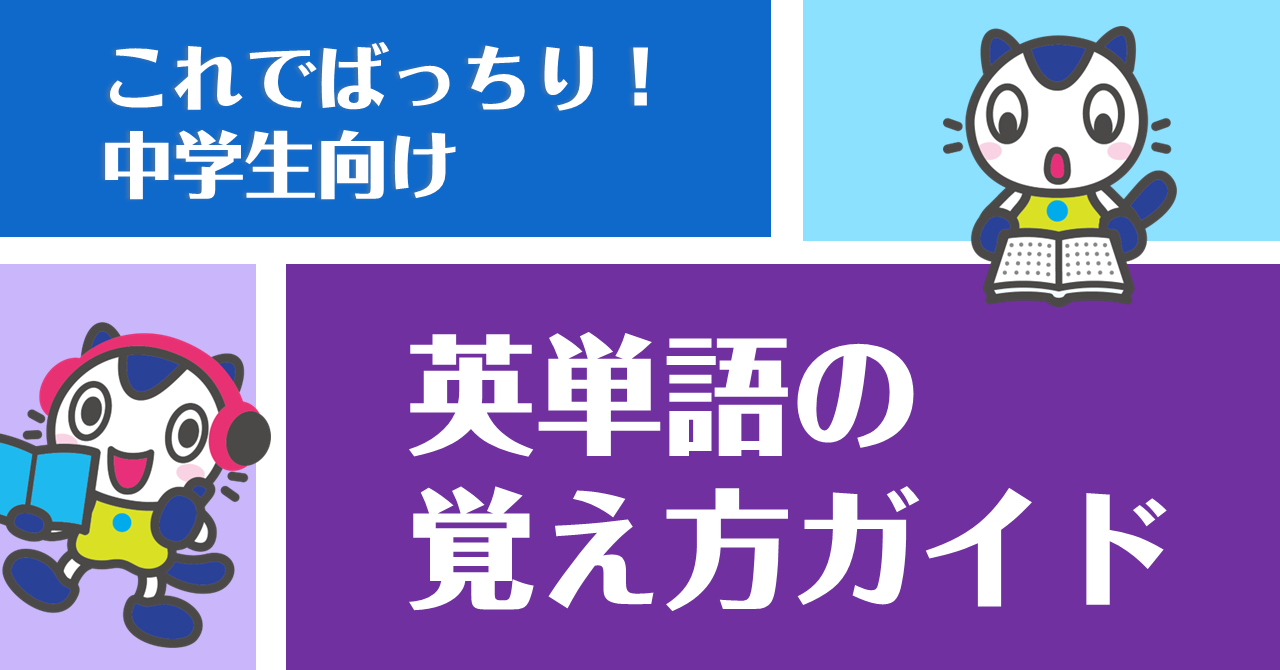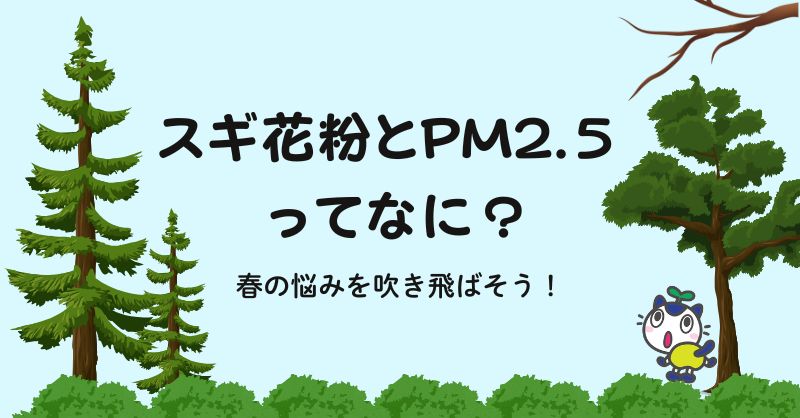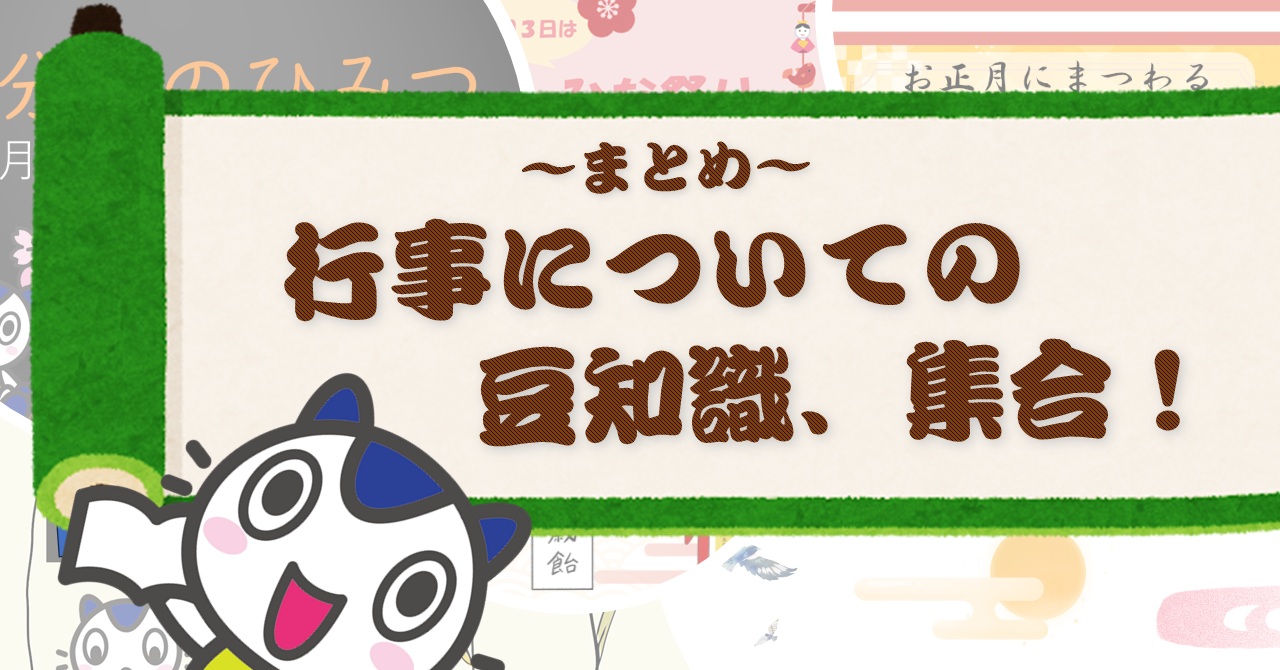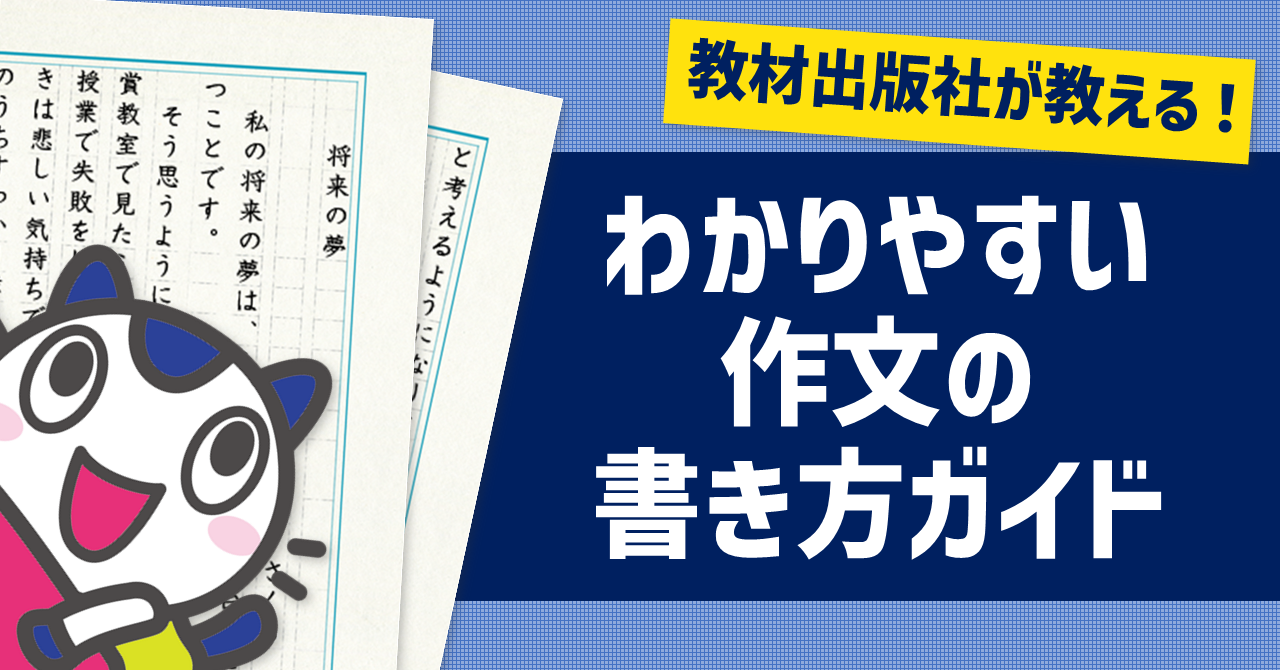なるほど!Bunri‐LOG
対象
【中学英文法 完全理解】関係代名詞の使い分けと見分け方をわかりやすく解説
もくじ はじめに 関係代名詞の正体は「説明を追加する接着剤」 関係代名詞の選び方(who / which / that) 関係代名詞の「主格」「目的格」とは? その見分け方 テストでねらわれる「ひっかけポイント」 【実践】理解度チェックテスト! まとめ 中学英文法を学習するのに最適の文理のおすすめ教材 はじめに 「関係代名詞が出てきてから、英語が難しくなってきた…」 「関係代名詞が入っている英文の意味が分からない」 などと感じる方が多いかもしれません。 しかし、関係代名詞のルール、 「後ろから説明を加える」 という仕組みさえつかめば、スッキリとわかるようになります。 この記事では、中学英文法の難所の1つ「関係代名詞」の攻略法をわかりやすく説明します。 関係代名詞の正体は「説明を追加する接着剤」 関係代名詞とは、「2つの文を1つにつなぎ、さらに名詞を詳しく説明する接着剤」のことです。 たとえば、次の2つの文を合体させてみましょう。 I have a friend.(私には友達がいます) He lives in Tokyo.(彼は東京に住んでいます) この2つの文を関係代名詞を使って1つの文にすると下記のようになります。 このwhoが関係代名詞です。 Heの代わりをしながら、前のa friend(説明される語句[名詞]=先行詞)」を詳しく説明する役割をもっています。 ここで、「関係代名詞を使うと文が長くなって難しそう…」と感じる人もいるかもしれません。 でも、新しい文が増えたわけではありません。 I have a friend. → I have a friend who lives in Tokyo. このように、もともとの文「I have a friend」に、 「who lives in Tokyo(東京に住んでいる)」 という説明を後ろからくっついただけです。 関係代名詞は、「前の名詞を後ろから説明するためのパーツ」だと考えましょう。 また、関係代名詞を含む部分は、前の名詞を説明する「ひとかたまり」としてとらえましょう。 ★文理の問題集で「関係代名詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 関係代名詞の選び方(who / which / that) 中学で学習する関係代名詞は、who、which、thatの3つです。 どの関係代名詞を使うかは、先行詞が 「人」か「もの(人以外と考えてください)」か で決まります。 ※先行詞が「人」の場合、関係代名詞(目的格)としてwhomを使うことがあります。 しかし、中学教科書ではほとんど扱われていないため本ブログ記事でも省略しております。 以下、who・which・thatの関係代名詞を使った例文を見てみましょう。 ●who 先行詞が「人」のとき ●which 先行詞が「もの」のとき that:「もの」「人」どちらにも使える まとめると下記のようになります。 ※先行詞が「人」の場合、主格の関係代名詞はwhoを使うのが一般的ですが、まれにthatが使われることもあります。 1.thatは万能な関係代名詞 先行詞が「人」でも「もの(人以外)」でも、①「主格」でも②「目的格」でも全部に使うことができます。 「迷ったらthat!」と覚えておきましょう。 ※ただし、問題で「that以外を使って」などのただし書きがある場合があるので注意が必要です。 2.関係代名詞が省略できるのは②「目的格」のときだけ 関係代名詞のあとに〈主語+動詞〉が続くときは、関係代名詞を省略できます。 〈説明される語句+主語+動詞〉の形になります。 関係代名詞の「主格」「目的格」とは? その見分け方 関係代名詞の「後ろから説明をくっつける」という特徴は理解できましたか? 次は、関係代名詞には「主格」と「目的格」の見分け方についておさえましょう。 ポイントは、ずばり 関係代名詞のあとに主語があるかどうか です。 ①主格(関係代名詞の直後に「動詞」) I know a boy who speaks Chinese.(私は中国語を話す男の子を知っています) 関係代名詞who の直後に plays(動詞)→ 主格! ②目的格(関係代名詞の直後に「主語+動詞」) This is the book that I read yesterday.(これは私が昨日読んだ本です) that の直後に〈 I(主語)+ read(動詞)〉がある → 目的格! ★補足 目的格の関係代名詞は会話や文章では省略されることが多いです。 This is the book I read yesterday. → bookのあとの関係代名詞(whichまたはthat)が省略されています。 テストでねらわれる「ひっかけ」ポイント ①三人称単数現在形(三単現)の s を忘れないで! 関係代名詞が主格(後ろが動詞)のとき、その直後の動詞の形は先行詞に合わせます。 a girl は三人称単数で現在の文なので s が必要! Iにひきずられてlikeとしないように注意! ②関係代名詞のあとに、主語や 目的語を書かない! 関係代名詞は、それに続くの文の中で「主語」や「目的語」の役割もしています。 そのため、次のように代名詞をもう一度書くのは間違いです。 who がすでに he の代わりをしているので、he は不要です。 主格の関係代名詞の直後は動詞、主語は不要、つまり〈関係代名詞+動詞〉と覚えておきましょう。 thatがすでにhimの代わりをしているので、himは不要です。 目的格の関係代名詞に続く動詞の後に目的語は不要、つまり〈関係代名詞+主語+動詞~〉と覚えておきましょう。 ③thatが好まれる場合がある 基本的に、関係代名詞のwhichとthatは入れ替えが可能です。 しかし、先行詞に特定の修飾語(first・lastや最上級など)がついているときは、that が好んで使われることがよくあります。 先行詞に下記の修飾語が含まれているときは、関係代名詞はthatを使いましょう。 all、every、-thing(anything、nothingなど)、the only、the very、 最上級、序数(first、secondなど)など 【実践】理解度チェックテスト! これまでこの記事で説明したことが理解できているかチェックしてみましょう。 問題 ( )に入る適切なものをアまたはイから選んでください。 Q1. I have a friend ( ) lives in Canada. ア who イ which Q2. This is the bus ( ) goes to the station. ア who イ which Q3. The girl ( ) you met yesterday is my sister. ア that イ which Q4. The dictionary ( ) I bought is very useful. ア who イ which Q5. Look at the cat ( ) is sleeping on the sofa. ア who イ which Q6. She is a teacher who ( ) English very well. ア speak イ speaks Q7. This is the best book ( ) I have ever read. ア which イ that 【解答と解説】 Q1. ア who 先行詞が「人」なのでwho。直後が動詞(lives)なので、この関係代名詞は主格。 Q2. イ which 先行詞が「もの」なので which。直後が動詞(goes)なので、この関係代名詞は主格。 Q3. イ that 先行詞が「人」なのでthat。直後にyou metと〈主語+動詞〉が続いているので、この関係代名詞は目的格。 省略することもできます。 Q4. イ which 先行詞が「もの」なのでwhich。直後にI boughtと〈主語+動詞〉が続いているので、この関係代名詞は目的格。 省略することもできます。 Q5. イ which 先行詞が「もの(動物)」は which を使います(基本、「人」以外はwhichまたはthat)。 直後に動詞(be動詞のis)がきているので、この関係代名詞は主格です。 Q6. イ speaks ここでのwhoは直後に動詞がきているので主格の関係代名詞。 先行詞「人」(a teacher)が三人称で現在の文なので、それに合わせて動詞に s をつけます。 Q7. イ that 先行詞にthe best があることに着目。最上級が先行詞に含まれるときはthat を選びます。 ここでのthatは目的格なので省略することも可能です。 まとめ 関係代名詞をマスターするポイントは3つ! 1.関係代名詞(who、which、that)の使い分け 先行詞が「人」か「もの」で判断する 「人」・・・whoまたはthat 「もの(人以外)」・・・whichまたはthat ※先行詞に特定の修飾語(all、every、-thing、最上級など)が含まれる場合はthatが好まれる 2.関係代名詞が「主格」か「目的格」かの見分け方 直後が動詞・・・「主格」、省略できない 直後が〈主語+動詞〉・・・「目的格」、省略できる 3.「主格」の関係代名詞の注意点 関係代名詞の直後の動詞の形は先行詞に合わせる 先行詞が三人称単数で現在の文の場合は、sまたはesをつけるのを忘れないこと 上記の3つを理解すれば、中学英語の関係代名詞はバッチリです! 中学英文法を学習するのに最適のおすすめ文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用までを豊富な問題量に取り組むことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されています。 ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
【中学理科】日食と月食の違いとは? 仕組みを図解でわかりやすく解説
もくじ 日食について考えてみよう 月食について考えてみよう 終わりに 天体分野に強くなる! 文理のおすすめの問題集 日食について考えてみよう 日食とは? 日食とは、太陽が月にかくされる現象です。 地球から見て、太陽の前に月がくると、月によって太陽の一部、または全体がかくされてしまいます。 観ているテレビの前に家族のだれかが立ってじゃまをするとテレビが見えなくなってしまいますね! これと似たようなもので、月がじゃまをして太陽が見えなくなってしまうのです。 日食はいつ起こるの? 日食が起こるとき、地球から見た太陽の前に月がくるので、太陽、地球、月の位置関係は次の図のようになります。 つまり、月を間にはさんで、太陽、月、地球が一直線上に並ぶことになります。 これを、地球の北極側のはるか上から見るとどうなるでしょうか。 このとき、月は太陽の光の当たらない半面を地球に向けています。地球から月を見ることはできません。 つまり、新月です。日食が起こるのは、新月のときなのです。 日食にはどのような種類があるの? 太陽の欠け方などによって、次の3つに分けられます。 部分日食…太陽の一部分のみがかくされる日食 皆既日食…太陽全体がかくされる日食 金環日食…太陽のいちばん外側の部分だけがかくされず、リング状に光る日食 この3つのちがいはどうして起こるのでしょうか? ■部分日食と皆既日食 次の図のように、太陽、月、地球が一直線上に並んだとき、月の影が2種類できます。 本影…太陽からの光が完全にさえぎられてできる影 半影…太陽からの光の一部分のみがさえぎられてできる影 ❶図のQ地点、R地点のように、半影に入った地点では、太陽は一部のみがかくされ、その部分が欠けて見えます。 これが部分日食です。 ❷図のP地点のように、本影に入った地点では、太陽全体がかくれて見えません。 これが皆既日食です。 ❸図のP地点のように本影に入っても、皆既日食とはならない場合があります。 どのようなときでしょうか? 皆既日食のように、月が太陽全体をすっぽりとかくすためには、地球から見た月の見かけの大きさが、太陽より大きくなければなりません。 ところが…! 月の見かけの大きさが太陽より小さければ、太陽全体をかくすことはできません。 このとき、地球から見て太陽と月の中心が重なると、月にかくされなかった部分がリング状に光っています。 これが金環日食です。 まとめると、 月の見かけの大きさが太陽より大きいとき→皆既日食 月の見かけの大きさが太陽より小さいとき→金環日食 となります。 なぜ、月の見かけの大きさが変わるの? 同じものでも、遠くにあるほど小さく見えますね。 月も同じです。月が地球から遠くにあるほど小さく見えます。 「えっ!地球から月までの距離はいつも同じではないの?」と思うかもしれません。 しかし、地球から月までの距離は変わるのです。なぜでしょうか? 月は地球のまわりを公転しています。 もし、月の公転軌道(公転するときに動く道すじ)が、地球を中心とした円であれば、地球から月までの距離はいつも同じです。 したがって、月の見かけの大きさはいつも同じです。 しかし、月の公転軌道は円ではありません。だ円です。 図で、月がAの位置にあるときは、Bの位置にあるときよりも地球から遠く、したがって小さく見えます。 このように、月の見かけの大きさは変化し、その結果、皆既日食であったり金環日食であったりします。 なお、月が地球に最も近いBの位置にあるときに満月になると、月は大きく見えます。 この月をスーパームーンといいます。 「月の見かけの大きさが変わるのはわかったけれど、見かけの大きさが、月と太陽で同じくらいなのはなぜかな?」 と思いませんか。 月の見かけの大きさはやや変わります。しかし、小さな変化はするものの、太陽の見かけの大きさとほぼ同じです。 その理由は…! 太陽の直径は月の直径のおよそ400倍です。一方で、地球から太陽までの距離も地球から月までの距離のおよそ400倍だからです。 何という偶然でしょうか! だれかがそのようにしたわけではありません。 月は地球の衛星です。太陽系には衛星をもっている惑星がいくつもあります。 しかし、それぞれの惑星から見た衛星の見かけの大きさが太陽と同じであるものは、月のほかには存在しません。 日食が観察できる地点はどこかな? 本影に入った地点では皆既日食(または金環日食)が、半影に入った地点では部分日食となることは説明しましたね。 地球は自転しています。この自転によって、本影、半影に入る場所は移動していきます。 これらの影を通る場所でのみ日食が観察されます。それ以外の場所では観察できません。日食が起こったとしても、見られる場所は限られています。 皆既日食(または金環日食)が見られる地点では、まず半影に入って太陽が欠け始め、皆既日食(または金環日食)となり、続いて、欠けている部分がだんだん小さくなっていきます。 日食の進み方(皆既日食の場合)は? 地球の自転によって、太陽は東から西へ1時間に15°動きます(日周運動)。 もし、月が地球のまわりを公転していなかったら、月は太陽と同じく東から西へ1時間に15°動くはずです。 しかし、月は地球の自転と同じ向きに公転しています。 1公転に約27日かかりますが、計算をやさしくするため、これを30日とすると、 1日あたり12°、1時間あたり0.5°公転します。 したがって、月の日周運動は1時間で、15°-0.5°=14.5°となります。 太陽は1時間に15°、月は1時間に14.5°、つまり、日周運動では、太陽の方が月より動きが速いことになります。 太陽は、月を東から西に向かって追いかけていき、月に追いついたときに欠け始めます(日食が始まる)。 そのため、太陽は日周運動の進行方向の西側から欠け始めます。 皆既日食の写真でもわかるように、皆既日食のときには、太陽のまわりに白くかがやく光が肉眼でも見えます。 これは、太陽を取り巻く高温のガスの層で、コロナといいます。 日食はなぜたまにしか起こらないの? 日食はたまにしか起こらないため、起こるときにはニュースになります。 しかし、すでに説明したように、日食は新月のときに起こります。新月は1か月ごとに訪れます。 もし、新月のたびに日食が起こるとすれば、1か月に1回は日食が見られるため、ニュースにはならないでしょう。 なぜ、日食はたまにしか起こらないのでしょうか。 地球は太陽のまわりを公転しています。月は地球のまわりを公転しています。 地球の公転面と月の公転面が同じ平面上にあれば、新月のたびに日食が起こることになります。 しかし、この2つの公転面は、ごくわずか(およそ5°)にずれているのです。 このため、太陽、月、地球が一直線上に並ぶことは、たまにしか起こらず、したがって、日食は珍しい現象として話題になるのです。 次に日食が起こるのは? 今年(2026年)には、2月17日に金環日食、8月13日に皆既日食が起こります。 しかし、残念ながらどちらも日本では観察できません。 2月17日は南極、8月13日は北極付近などでしか観測することはできません。 日食が日本で見られるのは2030年6月1日まで待たなければなりません。このときは、北海道で金環日食が見られます。 (もちろん天気がよければ、ですが…) 日食を観察しよう ■絶対にやってはいけないこと 太陽の光は大変強く、目を傷めるため、次のことは絶対にしてはいけません! ■安全な観察のしかた ピンホールの利用 厚紙などに小さな穴をあけたものを用意し、穴に太陽の光を通すと、影の中に、欠けた太陽の形をした光が見られます。 日食専用のグラス、遮光板の利用 日本で日食が観察できる日が近づいてくると、安価な専用グラスや遮光板などが販売されることが多く、これらを利用してもよいでしょう。 ただし、中には目の保護の効果が少ない質のよくないものが販売されている場合もあるので注意しましょう! また、太陽を長時間見ることはやめましょう。 その他 専門家が遮光・減光フィルターなどを用いて特殊な加工を施した双眼鏡や望遠鏡、眼鏡などであれば、それを利用してもかまいません。 ただし、その場合でも、長時間にわたって太陽を見続けることは避けましょう。 月食について考えてみよう 月食とは? 月食とは、月が地球の影に入ってしまい、その一部、または全部が見えなくなる現象です。 電球などの光源を背にして立つと、その前に自分の影ができますね。 この影の中に物(光を出さない物)を入れると、入れる前と比べて暗くなり、見にくくなります。 これと似たような現象が月食です。 月食はいつ起こるの? 月食が起こるとき、地球から見て、太陽とは反対側に月がくるので、太陽、地球、月の位置関係は次の図のようになります。 つまり、地球を間にはさんで、太陽、地球、月が一直線上に並ぶことになります。 これを、地球の北極側のはるか上から見るとどうなるでしょうか。 このとき、月は太陽の光の当たる半面を地球に向けています。地球から月を見ると、太陽の光の当たっている面全体を見ることができます。 つまり、満月です。月食が起こるのは、満月のときなのです。 月食にはどのような種類がある? 月食には、皆既月食、部分月食、半影月食があります。次の図で考えてみましょう。 上の図のように、月の影には、太陽の光が地球によって完全にさえぎられる本影と、太陽の光が一部さえぎられる半影があります。 月全体が本影に入ると皆既月食、月の一部のみが本影に入るのが部分月食、月が半影にしか入らないのが半影月食です。 ■皆既月食と部分月食 月全体が本影に入る現象が皆既月食、月の一部が本影に入る現象が部分月食です。 月は、公転によってまず半影に入ります。 (半影の部分は影がたいへんうすいため、肉眼で見ただけではわからないことが多いです!) やがて本影に入り始め、全体が本影に入ると皆既月食、一部のみしか本影に入らないと部分月食となります。 皆既月食でも、月が真っ暗で全く見えなくなることはほとんどなく、暗い赤色に見えます。 なぜでしょうか? 太陽の光のうち、赤色の光が大気に入るときに屈折したり、大気中のちりなどの粒子にあたって散乱したりすることで、本影に入ってくるからです。 やがて、月は本影から抜け、半影に入り、やがては半影からも出ていきます。 月が半影の部分しか通過しない場合は、半影月食となります。半影の部分は影は大変うすいので、言われないと気づかない場合もあります。 図で地球と月の位置関係を見ると、「月が地球の影を横切った後は満月ではなくなるように思うけれど!」と疑問に思いませんか? ここで注意しなければならないのは、月が本影を横切るのに、地球を中心に何度くらい動く(公転する)のかです。 地球の直径は月の直径のおよそ4倍、月が横切る本影の直径は月の直径のおよそ3倍です。 また、地球から月までの距離は、地球の直径のおよそ30倍あります。 これらをもとに計算すると、月はわずか1.5°くらい公転すれば本影を通過できることになります。 月食のしくみを表した図では、実際の距離や直径をそのまま同じ割合で縮小して表すことができません。 そのため、わかりやすく説明するために、これらの割合を大幅に変えて表してあります。 月の満ち欠けを説明する図を考えると、月が横切ったあとは満月ではなくなってしまう位置にくるように思います。 しかし、実際は満月の位置からわずか1.5°くらいしか公転していません。したがって、月は満月のままです。 月食の進み方は? 日食の進み方のところで、日周運動の速さは、月より太陽の方が速いことを説明しました。 つまり、太陽による地球の影の動く速さも、月の動く速さより速くなります。 また、月は地球の影に追いつかれたときに欠け始めます。地球の影は東から月に迫ってきます。 したがって、月は日周運動の進行の向きとは逆の東側から欠けていきます。 日食が観察できる地点はどこかな? 日食は、起こったときでも見られる場所が限られているのに対し、月食は、そのとき月が見えていればどこでも観察できます。 月食の頻度は? 月食は満月のときに起こりますが、満月のたびに起こるわけではありません。 これは、日食の場合と同様で、地球の公転面と月の公転面がやや傾いているからです。 ただ、日食は月食よりも頻繁に起こっています。しかし、日食を観察できる地域は限られています。 一方、月食はそのとき月が見える場所ならばどこでも観察できます。そのため、月食の方が多く起こっているように思われがちです。 次に月食が起こるのは? 今年(2026年)の3月3日に皆既日食、2028年7月7日には部分日食が起こります。 いずれも日本で観察できます。 2028年7月7日の部分日食は、欠けたままの月が地平線の下に沈む月入帯食(げつにゅうたいしょく)とよばれる現象が起こります。 ※欠けた状態の月が地平線からのぼる現象を月出帯食(げっしゅつたいしょく)といいます。 月食を観察しよう 私たちはいつも肉眼で月を見ています。月食も月を見ることに変わりはないので、安心して肉眼で観察しても大丈夫です。 双眼鏡や望遠鏡があれば、より詳しく月面のようすなどを観察できます。 終わりに 天体の分野は、理解しづらく、また誤った解釈をしがちで、苦手意識をもっているみなさんも多いのではないでしょうか。 このブログを書いている本人も、理系人間ですが、天体は苦手でした(いや、いまも苦手です)。 地球から太陽までの距離は地球の直径のおよそ11740倍、太陽の直径は地球のおよそ109倍です。 これらをそのまま縮小して紙面に表すとします。 地球を直径1cmの円でかいたとすると、この円から11740cm(117.4m)離れた位置に直径109cmの円をかいて太陽を表さなければなりません。 さらに、地球からはるかかなたにあるオリオン座などの星をかきたすことなどは不可能です。 そこで、天体の位置関係などを図に表すときは、紙面におさまるように、また、説明しやすくするように、距離や大きさを大幅に変更してかきます。 さらに、空間で起こっていることを平面に表しますから、イメージしにくく、理解に苦しんだり、誤った解釈をしてしまったりしがちです。 最近では、3次元的にとらえられる動画なども出ていますので、理解を深めるための参考にするとよいでしょう。 日食、月食については、次のことをしっかりおさえておきましょう。 ■どんな現象なの? 日食…月が太陽をかくし、太陽が欠けて見える現象(太陽は西側から欠ける) 月食…月が地球の影に入り、月が欠けて見える現象(月は東側から欠ける) ■起こるときの位置関係は? 日食…太陽-月-地球の順に一直線上に並ぶ。(月が間に入る) 月食…太陽-地球-月の順に一直線上に並ぶ。(地球が間に入る) ■起こるときの月の満ち欠けは? 日食…新月 月食…満月 天体分野に強くなる! おすすめの文理の問題集 「わからないをわかるにかえる」 中学で学習する理科を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 実験や観察などをスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、理科が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する理科の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 基礎の反復から応用まで問題をしっかりとこなすことで、中学で学習する理科の内容を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されています。 日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「理科の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な内容も扱っています。また、難関高校の入試問題も収録しています。 ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
中学英文法 完全理解 形容詞と副詞の違いをおさえよう!
もくじ 形容詞と副詞とは? それぞれの役割を理解しよう 形容詞と副詞の違い 3つの見分けるポイント 注意すべき形容詞と副詞 形容詞・副詞の見分け方 実践テクニック これは必ず覚えよう。頻出! 形容詞・副詞の重要単語リスト 形容詞と副詞、よくある質問(FAQ) 練習問題 形容詞と副詞を見分けよう まとめ 「形容詞」「副詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 形容詞と副詞とは? それぞれの役割を理解しよう 英語の文法で、多くの中学生がつまずきやすいのが形容詞と副詞の違いです。 「goodとwellってどう違うの?」 「-lyがついていたら副詞?」 など、疑問がたくさん出てきますよね。 まず大切なのは、 「形容詞も副詞も、ほかの言葉を説明する(修飾する)役割をもっている」 ということです。 ここでいう「修飾」とは、「どんな?」「どのように?」と補足説明することだと考えてください。 ① 形容詞の役割 形容詞は、名詞を説明する言葉です。人・物・ことの「性質」や「状態」を表します。 たとえば、下記のように使います。 このように、形容詞は「名詞の前」に置かれて、あとの名詞がどんなものかを説明します。 「どんな花?」「どんな犬?」と考えると、形容詞が使われていることが分かります。 ② 副詞の役割 副詞は、名詞以外を説明する言葉です。動詞・形容詞・ほかの副詞を説明します。 たとえば、下記のように使います。 「どのように走る?」「どれくらい美しい?」と考えると、副詞が使われていることが分かります。 ★文理の問題集で「不定詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 形容詞と副詞の違い 3つの見分けるポイント 形容詞と副詞を見分けるときは、次の3つのポイントを順番に考えるのがコツです。 ① どの語を修飾しているか(一番大事!) 最も重要なのは、その語が何を説明しているかです。 修飾している語が名詞→ 形容詞 修飾している語が動詞・形容詞・副詞→ 副詞 例文でみてみましょう。 このように、「どの語を説明しているか」を意識すると、正しく判断できます。 ② 語尾で見分ける(-lyがあるかどうか注目) 多くの副詞は、-lyで終わります。たとえば、quickly(急いで)、slowly(ゆっくりと)、carefully(注意深く)などが-lyで終わる副詞です。 ただし、下記のような例外もあるので注意が必要です。これらは形容詞としても副詞としても使われます。 「-lyがない=形容詞」と決めつけないようにしましょう。 ③ 文中の位置で判断する 形容詞と副詞は、置かれる場所にも特徴があります。 形容詞:名詞の前、またはbe動詞のあと 副詞:動詞の前後、形容詞の前、文の最後など 注意すべき形容詞と副詞 ① よく似た意味のgoodと well どちらも似た意味をもっていたます。しかし、goodは形容詞、wellは副詞です。 例 Emi is a good tennis player.(エミは良いテニス選手です) 形容詞 ⇒名詞tennis playerを説明 Emi sings well.(エミは上手に歌います) 副詞 ⇒動詞singsを説明 ② fastとhard とearly これらは、形容詞でも副詞でも同じ形で使います。 の中での役割を見てどちらの品詞か判断しましょう。 例 ●fast 形容詞 Ken is a fast runner(ケンは速い走者です) 副詞 Ken runs fast.(ケンは速く走ります) ⇒名詞(runner)を修飾しているので上の文のfastは形容詞、動詞(runs)を修飾している下の文のfastは副詞です。 ●hard 形容詞 This is a hard problem.(これは難しい問題です) 副詞 Nao studies hard.(ナオは一生懸命勉強します) ⇒名詞(problem)を修飾しているので上の文のhardは形容詞、動詞(studies)を修飾している下の文のhardは副詞です。 ●early 形容詞 I take an early train.(私は早い電車に乗ります) 副詞 I get up early.(私は早く起きます) ⇒名詞(train)を修飾しているので上の文のearlyは形容詞、動詞(get up)を修飾している下の文のearlyは副詞です。 ③hardとhardly 形が似ていてどちらも副詞として使います。しかし、意味が大きく異なります。意味の違いをしっかりとおさえておきましょう。 hard:一生懸命に hardly:ほとんど~ない 例 My brother studies hard.(私の弟は一生懸命に勉強します) My brother hardly studies.(私の弟ほとんど勉強しません) 形容詞・副詞の見分け方 実践テクニック ステップ① まずは、前後の単語をチェック 「この語は、どの語を説明している?」と考えるクセをつけましょう。 名詞を説明しているのなら形容詞、それ以外なら副詞です。 ステップ② be動詞のあとに置けるかをチェック be動詞のあとにきて、主語を説明するのは形容詞です。 She is happy(〇) 形容詞 She is quickly.(×) 副詞 これは必ず覚えよう。頻出! 形容詞・副詞の重要単語リスト ① よく使う形容詞 20選 名詞を説明したり、「~だ」と状態を表したりするときに使う重要な形容詞です。 ② よく使う副詞 20選 動作の様子や、程度・頻度、時、場所などを説明する重要な副詞です。 形容詞と副詞、よくある質問(FAQ) Q:very は形容詞ですか?副詞ですか? A:very は副詞です。形容詞や副詞をさらに強める働きをします。 例 very big(とても大きい)・・・」big(形容詞)を説明 very well(とても上手に)…well(副詞)を説明 Q:-lyがついていたら必ず副詞ですか? A:いいえ。friendly(親しみやすい、友好的な)、lovely(かわいい、すてきな)、lively(活気のある)のように形容詞のものもあります。 例 ① Mr. Mori is friendly.(森先生は親しみやすいです) ② Aki has a lovely bag.(アキはかわいい鞄を持っています) ③ We live in a lively town.(私たちは活気のある町に住んでいます) ⇒be動詞のあとにきて主語を説明していたり(①)、名詞を説明している(②・③)ことから形容詞です。 Q:be動詞のあとは形容詞、副詞、どちらを使いますか。 A:基本的には形容詞を使います。be動詞のあとでは、「主語がどんな状態か」を説明するため、形容詞がきます。 副詞は、動詞の動きや様子を説明する言葉なので、be動詞のあとには使いません。 (〇)Eito is kind.(エイトは親切です) → kind は 主語(Eito)を説明する形容詞。 (×)Eito is kindly. → kindlyは副詞なので使えない Q:同じ単語なのに、形容詞と副詞の両方になるのはなぜですか? A:fast や hard などは、文の中での役割によって形容詞にも副詞にもなります。 形は同じでも、「何を修飾しているか」でどちらの品詞か判断しましょう。 例 a fast car(速い車)…名詞carを修飾→形容詞 run fast(速く走る)…動詞runを修飾→副詞 練習問題 形容詞と副詞を見分けよう この記事の仕上げとして、練習問題にチャレンジしましょう。 次の英文の訳に合うように、( )に入る最も適切な語を下の語群から選びましょう。 そして、形容詞か副詞か答えましょう。※同じ語は1回しか使えません。 問題 語群 【 good / well / fast / happy / carefully / easy / slowly / hard / busy / quiet 】 解答と解説 まとめ 形容詞と副詞の違いは、何を修飾しているかを見れば判断できます。 語尾や置かれている位置も見分けるポイントですが、まずは「どの語を説明しているか」を考えることが大切です。 このポイントを意識して問題に取り組めば、定期テストや入試でも自信をもって解けるようになります。 少しずつ練習しながら、確実に身につけていきましょう。 「形容詞」「副詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用までを豊富な問題量に取り組むことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されています。ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
1月9日は「とんちの日」! 一休さんに学ぶ「視点切り替え術」(新学期の生活にも役立つ!)
もくじ 【とんちクイズ】一休さんからの「めでたい」挑戦状 「とんち」は、世界を広げる魔法の知恵 【とんちクイズの答え】一休さんが伝えたかったこと 新しい目標を胸に、今日を軽やかに過ごそう 【とんちクイズ】一休さんからの「めでたい」挑戦状 1月9日は 語呂合わせで「いっ(1)きゅう(9)」の日にちなんだ「とんちの日」(クイズの日)とされています。 まずは、とんちの名手として知られる一休さんにまつわる、新年にふさわしいこのクイズに挑戦してみてください。 【問題】 お正月、街中が「おめでとう!」と賑わう中、一休さんはなんと「本物の骸骨(がいこつ)」を棒の先に刺して、 「ご用心、ご用心」と叫びながら歩き回りました。 さて、一休さんは一体なぜ、おめでたい日にそんなショッキングなことをしたのでしょうか? A. 街の人を驚かせて、お年玉(お布施)をたくさんもらうため B. 「死んだ先祖も一緒にお正月を祝っている」という供養の気持ちを示すため C. 正月の浮かれ気分に喝を入れ、一日一日の大切さを伝えるため D. 当時流行していた病を追い払うための、厄除けの儀式だったため E. 誰も見たことがない新しい「お正月飾り」を考案したため (正解は記事の後半で!) 「とんち」は、世界を広げる魔法の知恵 「とんち」と聞くと、単なるなぞなぞを思い浮かべるかもしれません。 でもその本質は、「当たり前だと思っている思い込みを、パッと外すこと」にあります。 「パラダイムシフト」で世界を変える 専門的な言葉では、これを「パラダイムシフト」と呼びます。 パラダイムシフトとは、それまで当然だと思われていた考え方や価値観が、ガラリと劇的に変わることを指します。 一休さんは、まさにこの「視点の切り替え」の天才だったのです。 一休さんの鮮やかな「とんち」エピソード 一休さんの有名なエピソードには、行き詰まった状況を打破する「自由な発想」が詰まっています。 【エピソード1:屏風(びょうぶ)の虎退治】 将軍様から、 「屏風に描かれた虎が夜な夜な暴れて困るから、捕まえてくれ」 という無理難題をふっかけられた一休さん。 普通なら「絵なんだから無理ですよ」と諦めるところです。 しかし一休さんはしばらく考えた後、「承知しました!」と答えて縄を構え、力強くこう言いました。 「私が捕まえるので、まずは虎を屏風の中から追い出してください!」 「虎は実体があるものだ」という相手の前提を逆手に取ることで、不可能なはずの状況をひっくり返してしまったのです。 【エピソード2:毒の水あめ】 和尚さんが「これは子供が食べると毒だ」と嘘をついて独り占めしていた水あめを、一休さんはこっそり全部食べてしまいました。 普通なら怒られる絶体絶命のピンチですが、一休さんはわざと和尚さんの大切な茶器を割り、泣きながらこう言いました。 「大切な茶器を割ってしまったので、死んでお詫びしようと毒(水あめ)を飲みました。でもまだ死ねません!」 怒られるという状況を、「お詫びのために命をかける」という全く別の文脈に書き換えてしまった鮮やかな切り返しです。 【とんちクイズの答え】一休さんが伝えたかったこと さて、冒頭の五択クイズ。 正解は…… C. 正月の浮かれ気分に喝を入れ、一日一日の大切さを伝えるため でした。 おめでたいお正月の真っ只中、骸骨を掲げて歩く一休さんに人々は驚き、「縁起でもない!」と怒りました。 しかし、一休さんは涼しい顔でこう歌を詠んだのです。 「正月は 冥土(めいど)の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」 「今」を大切にするためのメッセージ これは、 「お正月が来たということは、めでたいけれど、それは同時に人生のゴール(冥土)に一歩近づいたということでもある。 だから浮かれてばかりいないで、今日という日を大切に用心して生きなさい」 という教えでした。 一見怖い行動の裏には、 「限られた時間を大切にしてほしい」 という一休さんの深い優しさが込められていたのですね。 文理の高校入試教材はこちら! 新しい目標を胸に、今日を軽やかに過ごそう お正月が過ぎ、今日からまた慌ただしい新学期の日常が始まります。 皆さんはもう、今年の目標は立てましたか? 目標を「一日の積み重ね」に落とし込む 大きな目標を達成させるのは、「今日」という一日の積み重ねです。 一休さんの教えのように、時間は無限ではありません。 「いつかやろう」と思っていることを達成するために、 「明日」ではなく、「今日」の予定の中に組み込んでみましょう。 柔軟な心で新しい1年を歩もう 何気なく過ぎていく1日も、私たちにとっては二度と戻らない大切な時間です。 行き詰まったときは、一休さんのように「視点を切り替える」ことを思い出してみてください。 思い込みを少し手放すだけで、きっと毎日はもっと軽やかに、面白くなっていくはずです。 新しい1年、皆さんが柔軟な心で目標に向かい、毎日を大切に歩んでいけるよう応援しています! ◆ 文理のおすすめ高校入試教材 ◆ 「完全攻略高校入試」シリーズ「わからないをわかるにかえる高校入試」シリーズ「コーチと入試対策」シリーズ 執筆者紹介 【今回の執筆者】 スー 【プロフィール】 学生時代サッカー、テニス部に所属していました。 スポーツ全般大好きです! 横浜F・マリノスサポーター 最近ボドゲにはまっていて、ボドゲカフェによく行きます!
サンタクロースはもうやってきた?! 12月6日は「シンタクラース祭」
12月といえば、子どもたちが心待ちにする「サンタクロース」の季節。でも実は、サンタクロースは、クリスマスより前にもう“やってきている”国があるのをご存じでしょうか? 今日のブログでは、オランダの伝統行事「シンタクラース祭」についてご紹介します。 シンタクラースってだれ? シンタクラース(Sinterklaas)は、オランダやベルギーなどで親しまれている聖人の名前です。毎年12月5日の夜(または6日)に、子どもたちへプレゼントを届けてくれる存在として知られています。 白いひげに赤い衣装、長い杖――その姿、どこかで見覚えがありますよね。 そう、シンタクラースこそ、サンタクロースのモデルの一人なのです。 シンタクラースのモデルは「聖ニコラウス」 シンタクラースの元になった人物は、聖ニコラウス(Saint Nicholas)。聖ニコラウスは、4世紀ごろに活躍した、現在のトルコ南部(ミラ)の司教だった人物です。貧しい人や子どもを助けたことで知られています。 特に有名なのが、貧しい3人の娘が住む家の暖炉に、こっそりと金貨を投げ入れて、幸せな結婚をさせたという逸話です。この見返りを求めずに与えるやさしさが、今の「プレゼントを配るサンタクロース」の原点になりました。 12月6日は彼の命日であり、キリスト教では「聖ニコラウスの日」として祝われています。 シンタクラース祭はどんなお祭り? オランダでは、11月中旬になると、シンタクラースが船でやってくる入港イベントが行われます。シンタクラースは、白い祭服に赤いケープをまとい、赤い帽子をかぶっています。 そして、アメリゴという白馬に乗り(トナカイではないのですね)、ズワルト・ピートと呼ばれる従者を連れています。到着の日からシンタクラースは各地を回り、子どもたちにお菓子を配ってまわります。 クライマックスは12月5日の深夜。子どもたちは寝る前に、わら、ニンジンなどが入った靴と、水の入ったコップを暖炉のそばに置いておきます。これは、白馬アメリゴに一休みしてもらうためです。 そして、シンタクラースの歌を歌います。 翌朝、子どもたちが目覚めると、靴の中にはシンタクラースからのプレゼントが入っているのです。 オランダだけでなく、ベルギーやルクセンブルクなどでも、地域によって多少の違いはありますが、「シンタクラース」を祝う文化があります。こうした「シンタクラース」(Sinterklaas)の文化が、現在の「サンタクロース」(Santa Claus)の原型になっています。 ちなみに、オランダやベルギーなどでは、「シンタクラース祭」に加えて「クリスマス」もお祝いするそうです。2回もプレゼントがもらえるなんて、うらやましいですね。 文理LINE公式アカウントでクリスマスキャンペーン実施中! 現在、文理LINE公式アカウントにて、「2025クリスマスキャンペーン」を開催中です。 7問の3択クイズに答えてサンタさんのお手伝いをしてくれた方の中から、抽選で5名様に、500円分の図書カードネットギフトをプレゼント! 応募締切は2025年12月24日 23:59 です。 この機会に、ぜひ「文理LINE公式アカウント」を友だち追加してご応募ください。
中学英語の不定詞3用法を詳しく解説! ~意味・例文・使い分けと動名詞との違い~
もくじ はじめに 不定詞とは? 基本の形と役割を理解しよう 不定詞の3つの用法:具体的な判別法 3つの用法の見分け方:簡単な判別ステップ ★ 発展編 知っておきたい! 不定詞の応用表現 よくある質問:不定詞と動名詞(~ing)の違い まとめ 「不定詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 はじめに 英語の不定詞は、〈to+動詞の原形〉の形で表します。 最初は少し難しく感じるかもしれませんが、不定詞は英語の表現の幅を一気に広げてくれる大切な文法です。 不定詞の基本をしっかり理解しておくと、動名詞やあとで学ぶ不定詞の応用表現もスムーズに入ってきます。 不定詞は、形は同じ(〈to+動詞の原形〉)でも文の中でどんな役割をしているかによって意味が異なります。 主に次の3つの働きがあります。 1 名詞的用法:文の主語・目的語・補語になる(「〜すること」) 2 形容詞的用法:名詞を説明する(「〜するための」「〜すべき」) 3 副詞的用法:動詞や形容詞を説明する(「〜するために」) 一見、複雑そうですが、ポイントは「文中のどこに置かれているか」と「どんな意味で使われているか」の2つ。 この基本をつかめば、3用法の区別はそれほど難しくありません。 この記事では、この3つの用法をていねいに解説します。 さらに、不定詞の応用表現や名詞的用法とよく似た意味で使われる動名詞との使い分けについても、記事の最後でわかりやすく説明します。 読み終わるころには、「不定詞って意外と簡単!」と自信をもてるようになりますよ。 ★文理の問題集で「不定詞」を学習するならこちらがおすすめ。 「わからないをわかるにかえる」 「完全攻略」 「ハイクラス徹底問題集」 不定詞とは? 基本の形と役割を理解しよう 不定詞は、〈to + 動詞の原形〉の形で表します。形を見るだけで「不定詞だ」とわかります。 重要なのは、この〈to + 動詞の原形〉が文の中でどんな役割を果たすかを理解することです。 不定詞の基本3用法 まずは〈to+原形〉でひとかたまりになっていることを認識し、次に「文中の位置」と「意味」でどの用法かを判断するクセをつけましょう。 不定詞の3つの用法:具体的な判別法 1 名詞的用法 不定詞が名詞と同じ働きをし、「~すること」の意味を表します。 動詞の目的語になります。また、文の主語や補語になることもあります。 2 形容詞的用法 不定詞が直前の名詞を説明し、「~するための」「~すべき」を表します。 見分け方のコツは「不定詞の直前に説明を受ける名詞があるか」をチェックすることです。 3 副詞的用法 不定詞が後ろから動詞や形容詞を説明します。 「~するために(目的)」や「~して(感情の原因・理由)」を表します。 見分け方のコツは「不定詞の前に説明を受ける動詞句や形容詞があるか」をチェックすることです。 3つの用法の見分け方:簡単な判別ステップ 〈to + learn〉を例に、文中の位置によって用法が変わる例を見てみましょう。 【判別ステップ】 1 「~すること」と訳してみる もし文が意味をなすなら名詞的用法。 2 直前に名詞があるか確認する 名詞があれば、それを説明している形容詞的用法。 3 「なぜ?」「どうして?」と問いかける 動詞や形容詞の目的・理由を説明していれば、副詞的用法。 ★ 発展編 知っておきたい! 不定詞の応用表現 以下の不定詞を使った表現は定期テストでもよく出題されます。 形と意味をセットで覚えましょう。 よくある質問:不定詞と動名詞(~ing)の違い Q1 不定詞も動名詞も目的語にとれる動詞は? like、love、hate、start、begin、continue などの動詞は目的語に不定詞も動名詞もとることができます。 I like to read books.(私は本を読むことが好きです) = I like reading books. Q2 目的語に不定詞だけを使う動詞は? want、decide、hope、wish などの動詞は不定詞のみを目的語とします。 I want to go home.(私は家に帰りたいです) × I want going home. Q3 目的語に動名詞だけを使う動詞は? enjoy、avoid、finishなどの動詞は動名詞(~ing)のみを目的語にとります。 I enjoy playing soccer.(私はサッカーをすることを楽しみます) × I enjoy to play soccer. Q4:不定詞と動名詞で意味が異なる動詞は? try、remember、forgetなどはどちらを目的語としてとるかで意味が異なるので要注意です。 tryとrememberを例に見てみましょう。 まとめ 不定詞〈to+動詞の原形〉には、名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法の3つの働きがあり、それぞれが文の中で異なる役割を果たしています。 どの用法を使っているのかを見分けるときは、 「文中の位置を見る」 「意味を訳してみる」 「その文で何を説明したいのか考える」 の3ステップがとても役立ちます。 また、不定詞と動名詞の違いもおさえておきましょう。 不定詞は「~すること」「〜するための」「~するために」などの幅広い使い方をします。 一方、動名詞は「~すること」という名詞的な働きが中心です。 この特徴を押さえておけば、その違いも自然と理解しやすくなります。 最初は少し難しく感じるかもしれません。しかし、ポイントをつかむと不定詞は英語表現を一気に広げてくれる便利な文法です。 問題練習をしながら、ぜひ「不定詞を使いこなせる」感覚を身につけていきましょう。 「不定詞」を学習するのにおすすめの文理の教材 「わからないをわかるにかえる」 不定詞など中学で学習する英文法を基礎からじっくり学びたい、どこから手をつけていいかわからないという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 文法をスモールステップで図解やイラストでていねいに解説しています。 そのため、英語が苦手な人でも基礎から練習を着実に積み重ね、理解することができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「完全攻略」 中学で学習する英文法の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズがおすすめです。 このシリーズは豊富な問題量が特徴です。 文法の基礎の反復から応用まで問題をしっかりとこなすことで、文法を完全に理解し、定着させることができます。 定期テスト対策ページに加えて、過去の入試問題を扱ったページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応が可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「ハイクラス徹底問題集」 難易度の高い問題に挑戦し、応用力を圧倒的につけたい人向けの「英語の最高峰の問題集」です。 この教材では、教科書では取り上げていない高度な英文法も扱っています。 難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな問題を解くことで、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 現在の学習レベルに関わらず、英語を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
勉強の合間に食べたいおすすめお菓子 5選
みなさん、長時間の勉強、おつかれさまです! 問題を解いたり、暗記をしたりしていると、だんだん頭がぼーっとしてきますよね。 そんなときに欲しくなるのが、ちょっとした「お菓子」です。 お菓子っておいしいですよね! そこで今回は「勉強の合間にお菓子を食べたくなる」、そんな時におすすめのお菓子とちょっとした食べ方の工夫を紹介します。 実は、勉強の合間に食べるお菓子には、集中力を回復させたり、気分転換になったりする大切な役割があります。 今回は、小学校高学年から中学生におすすめしたい「勉強の合間に食べたいお菓子 5選」をご紹介します! 1 チョコレート まずは定番のチョコレート。 チョコレートに含まれる「ブドウ糖」は、脳の大事なエネルギー源です。 疲れた頭にすばやく栄養が行きわたり、集中力アップが期待できます。 特におすすめなのは、食べすぎを防ぎやすい個包装タイプのチョコレート。 一口サイズなら、勉強の邪魔にならずにパクッと食べられますね。 甘いものが好きな人には、ぴったりのおやつです。 2 ガム 眠気を吹き飛ばしたいときは、ガムがおすすめです。 ガムをかむことで脳が刺激され、集中しやすくなると言われています。 特にミント味やフルーツ味など、すっきりした味のガムは、気分転換にもなります。 プロスポーツ選手も試合中にガムを噛んでいることがありますね。 長時間同じ姿勢で勉強していると、どうしても集中力が切れがちになります。 そんなとき、ガムをかむことでリズムが生まれ、やる気も回復しやすくなりますよ。 3 クッキー・ビスケット ちょっと小腹がすいたときには、クッキーやビスケットがぴったり。 サクサクとした食感で気分転換になり、甘さで疲れもやわらぎます。 牛乳やお茶と一緒に食べると、さらにリラックスできますね。 ただし、食べすぎると眠くなってしまうこともあるので、2~3枚くらいを目安にするのがおすすめです。 4 ナッツ・小魚 甘いお菓子だけでなく、体にもやさしいおやつ、ナッツや小魚も取り入れたいところ。 アーモンドやくるみなどのナッツ類、小魚アーモンドは、カルシウムやミネラルが豊富で、成長期の体にもぴったりです。 よくかんで食べることで、脳への刺激にもなり、眠気対策にも効果的。 甘いお菓子が続いたときの、リフレッシュにもおすすめです。 5 グミ 最近人気なのがグミです。 ほどよい硬さでかみごたえがあり、味のバリエーションも豊富なので、気分に合わせて選べます。 かむことで眠気が覚めやすく、勉強のスイッチを入れなおすのにぴったりです。 最近は特にかみごたえを強くしたグミも売っていますね。 またフルーツ味のグミなら、気分も明るくなって、次の問題にも前向きに取り組めそうです。 個人的にはブドウ味のグミが好きです! みなさんはどうですか。 まとめ いかがでしたでしょうか。 勉強の合間に食べるお菓子は、ただの「お楽しみ」ではなく、集中力を回復させたり、気分転換になったりする大切なサポーターです。 ポイントは、 食べすぎないこと だらだら食べ続けないこと 勉強の区切りで食べること この3つを意識することです。 お気に入りのおやつを上手に取り入れて、毎日の勉強を少しでも楽しく、そして効率よく進めていきましょう! 【今回の執筆者】厚別太郎【プロフィール】北海道在住で、北海道グルメのレポートが趣味です。音楽が好きで、時々札幌周辺のライブハウスに出現します。 最近はオンライン対戦の野球ゲームにもハマっています(*^〇^*)
2025クリスマスキャンペーン実施中!
2025クリスマスキャンペーン もうすぐクリスマス! サンタさんは大忙し。ひとりで、世界中の子どもにプレゼントを届けるのはとっても大変です。そんなサンタさんのお仕事を、文理LINE公式アカウントで出題する7問の3択クイズに答えて手助けしてあげましょう。 最後まで問題を解いてくれた方の中から、抽選で5名様に500円分の図書カードネットギフトをプレゼント! 応募資格 利用規約に同意していただいた日本国内に在住の方ならどなたでも応募可能です。 応募方法 STEP1:文理のLINE公式アカウントを友だち追加 STEP2:クイズに回答 STEP3:すべてのクイズに回答すると進める応募フォームに必要事項を記入し、応募 ※応募は、おひとり様1回までとなります。 ▲メニューから「2025クリスマスキャンペーン」をタップ プレゼント内容 抽選で5名様に、図書カードネットギフト500円分をプレゼント 当選について ・応募期間終了後、抽選によって当選者を決定いたします。 ・当選発表は、2025年12月下旬、景品の発送をもってかえさせていただきます。 ※景品の発送は日本国内に限らせていただきます。 ※LINEのアカウントの削除または変更等の理由により、プレゼントのお届けができない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。 お問い合わせ 本キャンペーンに関するお問い合わせは、こちらのフォームまでお願いいたします。 当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご注意ください。
【中学生向け】因数分解のやり方と公式一覧 テストで使えるコツも解説
もくじ はじめに 因数分解とは? 因数分解の解き方:共通因数でくくる 因数分解の解き方:4つの公式 因数分解の解き方ステップ 練習問題で確認しよう まとめと商品紹介 はじめに 今回のテーマは中学3年生の数学で出てくる「因数分解」です。 「因数分解」という言葉を聞いて、 「難しそう…」 「公式がたくさんあって覚えられない!」 と感じている人もいるかもしれません。 しかし、心配はいりません! 因数分解は、中学数学の大きな柱ですが、正しい手順といくつかのコツさえつかめば、必ず理解できるようになります! この記事では、因数分解が「なぜ大切なのか」という基礎から、テストで使える4つの公式、さらには応用問題の解き方まで、ステップごとにわかりやすく解説します。 この記事を最後まで読んで、因数分解への理解を深め、定期テストや高校入試で自信を持って問題が解けるようになりましょう! 因数分解とは? 因数分解とは、簡単に言うと「多項式をかけ算の形(因数の積の形)になおす操作」のことです。 まずは因数について確認しましょう。 例えば、6という数は、次のようにかけ算の形になおすことができますね。 6=2×3 このとき、2や3を6の因数と呼びます。 因数分解とは、多項式をいくつかの因数の積の形に分解することです。 【例】 2a2+6ab=2a(a+3b) 左側の式 2a2+6ab はたし算(単項式の和)の形ですが、 右側の式 2a(a+3b) は、2 と a と (a + 3b) という因数のかけ算の形になっています。 展開と因数分解の関係 因数分解を理解する上で、展開(てんかい)との関係を知っておくことが大切です。 因数分解は、展開の逆の操作だと考えると、イメージがしやすいでしょう。 展開:かけ算を計算して、たし算・ひき算の形になおすこと (x+2)(x+3) ― 展開 → x2+5x+6 因数分解:たし算・ひき算の形を、かけ算の形になおすこと x2+5x+6 ― 因数分解 → (x+2)(x+3) このように、展開と因数分解は、「たし算・ひき算の形」と「かけ算の形」を行き来する、裏表の関係になっています。 このイメージを持っておくと、公式を理解する際にも役立ちます。 なぜ因数分解を学ぶのか 「わざわざ式をかけ算の形になおすのはなぜ?」 と思うかもしれません。 ここでは、因数分解を学ぶ理由を3つ紹介します。 • 2次方程式を解くため x2+5x+6=0 のような2次方程式の解を求めるときは、左辺を因数分解をして、 (x+2)(x+3)=0 の形になおすことで、 x=−2 または x=−3 という解を求めることができます。 • 計算を簡単にするため 複雑な多項式を因数分解してシンプルな形にすることで、計算ミスを防ぐことにつながります。 特に、「式の値」を求めるときに役立ちます。 【例】 x=98のとき、x2+4x+4 の値を求めましょう。 直接代入して求めることもできますが、 982+4×98+4 を計算するのはたいへんです。 そこで、先に因数分解をして (x+2)2 にしてから代入します。 (98+2)2 = 1002 = 10000 と、計算が簡単になります! • 高校数学の基礎となるため 高校で学ぶより高度な数学(数Ⅱ、数Bなど)でも、因数分解は当たり前の基礎技術として使われます。 今のうちにしっかり身につけておくことが、将来の数学の土台となります。 因数分解は、定期テストでも高校入試でも必ず頻出する重要な分野です。 しっかり理解を深め、数学の基礎力を身につけましょう! 因数分解の解き方:共通因数でくくる ここからは、因数分解の解き方についてです。 因数分解をするとき、まず最初に考えるべきなのが、「共通因数でくくる」という方法です。 共通因数でくくるとは? 共通因数とは、多項式のすべての項に共通してかけられている数や文字のことです。 多項式を、共通因数と残りの部分の積の形になおす操作を、「共通因数でくくる」「共通因数でくくり出す」と言います。 これは、展開のときの分配法則の逆の操作です。 【例】 2x+6 を因数分解しましょう。 1.共通因数を見つける それぞれの項 ( 2x と 6 ) の中に共通して含まれている因数を探します。 2x=2×x 6=2×3 両方の項に共通しているのは、2 です。 つまり、共通因数は 2 です。 2.共通因数でくくる 共通因数 2 を式の前に出し、かっこでくくります。 2x+6=2(x+3) 符号と文字の扱いに注意する 多項式の最初の項がマイナスのときは、マイナスも共通因数の一部としてくくり出すことが多いです。 特に、共通因数に文字も含まれる場合は注意が必要です。 【例】 −3ab+12bを因数分解しましょう。 この式は、共通因数として数(係数)と文字の両方に着目します。 1.共通因数を見つける 数(係数)の部分 : −3 と +12 の共通因数は −3 文字の部分 : ab と b の共通因数は b です。 したがって、共通因数は −3b です。 2.共通因数でくくる −3ab+12b=−3b(a−4) 【注意】 マイナスでくくると、かっこの中の項の符号がすべて逆になることに注意しましょう。 ○ −3ab+12b=−3b(a−4) × −3ab+12b=−3b(a+4) 因数分解の解き方:4つの公式 共通因数でくくれない場合、次に因数分解の4つの公式を使います。 これらは、展開の公式を逆にしたものです。 展開の公式をしっかり覚えていると、スムーズに理解できます。 公式① x²+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b) これは「たして (a+b)、かけて ab」になる a と b の組み合わせを見つける公式です。 【式の形】 x の項の係数が a+b(和)、定数項が ab(積)になっているのが特徴です。 【解き方のコツ】 1.まず、定数項 ab に注目し、積になる a と b のペアを考えます。 2.そのペアの中で、和が x の項の係数 (a+b) になるものを見つけます。 3.見つけた a と b を (x+a)(x+b) の形に当てはめます。 【例】 x2+7x+12 を因数分解しましょう。 1.積が 12 になるペアを探します。 (1, 12)、(2, 6)、(3, 4) … 2.その中で、和が 7 になるペアはを見つけます。 (3, 4) 3.x2+7x+12=(x+3)(x+4) 公式② x²+2ax+a²=(x+a)² 公式③ x²-2ax+a²=(x-a)² これらは、「和の平方」「差の平方」と呼ばれる公式です。 公式①で、 a=b の特殊なパターンと考えると理解しやすいでしょう。 【式の形】 xの項の係数が 2a ( a の2倍)、定数項が a2 ( a の2乗) になっているのが特徴です。 (※公式③は符号がマイナスです。) 【解き方のコツ】 1.定数項が、ある数 a の2乗になっていることを確認します。 2. x の項の係数が、1で確認したaの2倍になっているかを確認します。 3.符号に注意して (x±a)2 の形になおします。 【例】 x2−10x+25 を因数分解しましょう。 1.定数項 25 は 52 、または (−5)2 です。 2.xの項の係数 −10 は、−5 の 2 倍なので、公式③で a=5 のときだとわかります。 3.x2−10x+25=(x−5)2 公式④ x²−a²=(x+a)(x-a) (2乗)ー(2乗) の形をした因数分解の公式です。 公式①で、 b=ーa の特殊なパターンと考えると理解しやすいでしょう。 【式の形】 x の項の係数が 0 になっていて、項が2つしかないのが大きな特徴です。 【解き方のコツ】 1.式が (2乗)ー(2乗) の形になっているかを確認します。 2.(x+a)(x−a) の形に当てはめます。 【例】 x2−49 を因数分解しましょう。 1. 49 は 72 なので、x2− 72 の形です。 2.x2−49=(x+7)(x-7) 展開公式との関係 公式①から④は、すべて展開公式を逆にしたものです。 因数分解ができたら、展開し直して元の式に戻るか確認する習慣をつけましょう。 これにより、ミスが減り、公式の理解もさらに深まります。 x2+7x+12 ― 因数分解 → (x+3)(x+4) (x+3)(x+4) ― 展開 → x2+7x+12 因数分解の解き方ステップ これまでに学んだ「共通因数でくくる」方法と「4つの公式」を使えば、多項式の因数分解ができるようになります。 しかし、問題を見たときにどの方法を使えばいいか迷ってしまうことがありますよね。 ここでは、因数分解のときに迷わず正解にたどり着くためのステップを解説します。 1.共通因数を探す 因数分解を始めるとき、公式が使えるかどうかを確認する前に、必ず共通因数があるかを確認しましょう。 共通因数を見つけてくくり出すことで、その後に使う公式を見つけやすくなります。 【チェックポイント】 すべての項に共通する因数(数や文字)はないか? 【注意点】 共通因数をくくり出すのを忘れると、完全に因数分解された形にたどり着けなくなります。 2.使える公式があるか判断する 共通因数をくくりだしたあと、残った多項式を見て、どの公式が使えるかを判断します。 次のように順序だてて考えましょう。 【項が2つ】 → 公式④ x²−a²=(x+a)(x-a) が使えるか確認する 【項が3つ】 → 【定数項が a² の形になっている】 → 公式② x²+2ax+a²=(x+a)² 公式③ x²-2ax+a²=(x-a)² が使えるか確認する → 【定数項が a² の形になっていない】 → 公式① x²+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b) が使えるか確認する 工夫して分解する応用パターン 共通因数やくくり出し、公式を組み合わせることで解ける応用問題のパターンをいくつかご紹介します。 「これ以上分解できない」状態まで分解しきるのが因数分解のゴールです。 1.複雑な式は展開してから分解する 元の式が複雑なかっこのかけ算の形になっている場合、まずは展開して同類項をまとめることで、公式が使える形になることがあります。 【例】 (x+3)(x−1)−12 ← 展開の公式を使って展開します =x²+2x−3−12 ← 同類項をまとめます =x²+2x−15 ← たして +2、かけて -15 になる数(5,-3)を探して、公式①を使います =(x+5)(x−3) 2.多項式を共通因数としてくくり出す 共通因数が数や文字ではなく、多項式になる場合もあります。 多項式全体を1つのかたまりと考えて、共通因数をくくり出します。 一見共通因数がないように見えても、一部を因数分解すると共通因数が見つかることがあります。 【例】 5(a−2)+a²−2a ← 5(a−2) と a²−2a に分けて考え、後ろの式で a をくくり出します =5(a−2)+a(a−2) ← 多項式 (a−2) が共通因数になっているので、くくり出します =(a−2)(5+a) 3.共通因数をくくり出してから公式を使う 共通因数でくくり出したあと、さらに因数分解できる場合があります。 因数分解できるかどうか、必ず最後までチェックしましょう。 【例】 3x³y−12xy³ ← 共通因数 3xy でくくり出します =3xy(x²−4y²) ← x²−4y² で、公式④を使って因数分解します =3xy(x+2y)(x-2y) 4.x² の項の係数が1でない式 x² の項の係数が常に1とは限りません。 そんな式でも、公式②または③が使える場合があります。 何かの2乗になっているか考えるのがポイントです。 【例】 9x²−6xy+y² ← 公式が使える形に変形します =(3x)²−2×3x×y+y² ← 公式③を使います =(3x−y)² 練習問題で確認しよう これまでの知識が定着しているか、以下の問題で確認してみましょう。 因数分解は、「共通因数」→「公式」の順番で考えることが大切です! 【問題】 次の式を因数分解しましょう。 1.4x²−16x 2.a²+8a+15 3.25x²−16y² 4.3x²−30x+75 5.(x+3)²−5(x+3) 【ヒント】 解き方に迷ったら、以下のヒントを参考にしてください。 1.まずは、数と文字の共通因数を見つけて、くくり出しましょう。 2.公式①のパターンです。たして +8、かけて +15 になる2つの数を探しましょう。 3.(2乗)ー(2乗) の形です。公式④を使いましょう。 4.最初に共通因数の3をくくり出し、かっこの中の式で公式③を使います。 5. (x+3) を共通因数としてくくり出しましょう。 【解答と解説】 1. 4x²−16x ← 共通因数 4x でくくり出します =4x(x−4) 2. a²+8a+15 ← たして 8 、かけて 15 になる組 (3,5) を見つけます =(a+3)(a+5) 3. 25x²−16y² ←(2乗)ー(2乗) の形にします =(5x)²ー(4y)² ← 公式④を使います =(5x+4y)(5x-4y) 4. 3x²−30x+75 ←共通因数 3 をくくり出します =3(x²−10x + 25) ← かっこの中で、公式③を使って因数分解します =3(x−5)² 5. (x+3)²−5(x+3) ←共通因数 (x+3) をくくり出します =(x+3){(x+3) - 5} ← かっこの中を整理します =(x+3)(x - 2) まとめと商品紹介 いかがでしたか。因数分解の基本を理解したら、あとは定着させるために練習あるのみです。 因数分解の知識を確かな力に変えるために、あなたのレベルに合った文理の教材で次のステップに進みましょう! おすすめの商品 因数分解の基本と応用を理解したら、あとは練習あるのみです。 文理では、お客様ひとりひとりのレベルや目的に合わせた教材をご用意しています。 ここでは、あなたの学習を次のステップに進めるための、おすすめの商品を3シリーズご紹介します。 わからないをわかるにかえる ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 因数分解を基礎からじっくり学びたい、これまでどこから手をつけていいかわからなかったという人に最適なシリーズです。 この教材は、「わからない」を「わかる」にかえることを徹底的に追求しています。 定義や公式といった基礎的な内容を、簡単な例題で丁寧に解説しているため、因数分解が苦手な人でも、着実に基礎から練習を積み重ねることができます。 簡単なステップで自信をつけながら学習を進めたい方に、特におすすめします。 完全攻略 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 因数分解の知識を深め、確かな実力をつけたいなら「完全攻略」シリーズが役立ちます。 このシリーズは豊富な演習量が特徴で、基礎の反復から応用までしっかりと問題演習をこなすことで、因数分解を完全に理解し、定着させることができます。 また、定期テスト対策ページや、過去の入試問題を扱った実戦問題ページも収録されているため、日々の学習から受験対策まで幅広い学習に対応可能です。 学校の授業の進度に合わせて使いたい方にも最適です。 ハイクラス徹底問題集 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 難易度の高い問題に挑戦し、数学の応用力を圧倒的につけたい人向けの最高峰の問題演習集です。 この問題集では、因数分解の複雑な応用問題や、複数の知識を組み合わせる思考力を要する問題を豊富に扱っています。 難関高校の入試問題も収録されているため、ハイレベルな演習を通じて、ライバルに差をつけたいと考えている学習者を徹底的にサポートします。 現在の学習レベルに関わらず、数学を極めたいという意欲のある方は、ぜひ手に取ってみてください。
古文の10パターン!テストで役立つ読み方のコツ
教科書で出てくる古文。 「なんだか昔の言葉で読みにくい……。」と思ったこと、ありませんか? でも実は、古文には“決まったパターン”があるのです。 今回は、教科書や入試によく登場する古文の10パターンを、例文と現代語訳つきで解説します。読み進めながら「これ、他の作品でもあった!」という発見がきっとあるはずです。 もくじ パターン1:クスッと笑えるオチのある話(徒然草) パターン2:たとえ話の言いたいことは(伊曽保物語) パターン3:おどろくべき正体(徒然草) パターン4:思いがけない奇跡(今昔物語) パターン5:芸は身を助ける(宇治拾遺物語) パターン6:機転を利かす(沙石集) パターン7:ものの見方が個性的(枕草子) パターン8:生き方の知恵を語る(徒然草) パターン9:過去に学ぶ(花月草紙) パターン10:歌にこめられた思い(伊勢物語) 平安時代の恋愛観と結婚の流れ 古文のパターンを引用元の作品から推測しよう! 古文のパターン早見表 おわりに:「でも、どうやって覚えたらいいの?」 パターン1:クスッと笑えるオチのある話(徒然草) 獅子と狛犬 『徒然草』より (神社に参った上人は、社の前の獅子と狛犬がたがいに後ろ向きに立っているのを見て、「大変すばらしい、深いわけがあるのだろう」と涙ぐんだ。上人はその理由を知りたがり、年配で詳しそうな神官を呼び、尋ねた。) 古文 「この御社の獅子の立てられやう、さだめて習ひあることに侍らん。ちと承らばや」と言はれければ、 「そのことに候ふ。さがなき童べどもの仕りける、奇怪に候ふことなり」とて、 さし寄りて、据ゑなほして去にければ、上人の感涙いたづらになりにけり。 現代語訳 「このお社の獅子の立てられ方は、きっといわれがあることでございましょう。少々お聞きしたいものです」とおっしゃったところ、 「その事でございます。いたずら好きな子供たちがいたしましたことで、けしからぬことでございます」と言って、 (獅子と狛犬に)近寄って、(元のように)置き直して行ってしまったので、上人の感動の涙はむだになってしまった。 読解ポイント 偉い立場の人が勘違いして失敗する展開は古文によくあります。「誰が」「どうした」を正しく読み取ることが、話の面白さをつかむカギです。 この場合は上人という宗教上で偉い立場の人が勘違いしたという点がくすっと笑えるポイントですね。 パターン2:たとえ話の言いたいことは(伊曽保物語) 例)鼠の会議『伊曽保物語』より (鼠たちが会議をした。猫につかまらないためには、猫の首に鈴を付ければよいという意見にみんな賛成した。) 古文 「然らば、このうちよりだれ出てか、猫の首に鈴を付け給はんや」といふに、 上臈鼠より下鼠に至るまで、「我付けん」といふ者なし。 是によつて、そのたびの議定事終わらで退散しぬ。 其ごとく、人のけなげだてをいふも、只畳の上の広言なり。 現代語訳 「そうしたら、この中からだれが出て行って、猫の首に鈴をお付けになるか」と言ったところ、 身分の高い鼠から身分の低い鼠に至るまで、「私が付けよう」と言う者はいない。 これによって、そのときの協議の決着はつかず解散した。 このように、人が勇気のあるようなことを言うのも、ただ安全な畳の上に座って大きなことを言うようなものである。 読解ポイント 古文のたとえ話は、ことわざや教訓とつながることが多いです。 会話文や主語に注意してエピソードの内容をしっかり読み取ったうえで、そのエピソードを通して筆者が言おうとしていることをとらえましょう! この話では「口で言うのは簡単だが、実行は難しい」という教えを示しています。 パターン3:おどろくべき正体(徒然草) 二人の武士『徒然草』より (なんとかの押領使というものは、大根がすべての病気にきくと信じて、毎日食べていた。ある時、館が敵に襲われたが、二人の武士が突然現れ、追い払ってくれた。) 古文 いと不思議に覚えて、「日ごろここにものし給ふとも見ぬ人々の、かく戦ひし給ふはいかなる人ぞ」と問ひければ、 「年ごろ頼みて、朝な朝な召しつる土大根らにさぶらふ」といひて失せにけり。 深く信をいたしぬれば、かかる徳もありけるにこそ。 現代語訳 (押領使は)とても不思議に思われて、「日ごろこの館に仕えていらっしゃるとも思われない人たちが、このような戦いをなさるとは(あなたがたは)どういう人ですか」とたずねると、 (二人の武士は)「(あなたが)長年頼みにして、毎朝召しあがった大根たちでございます」と言って消えてしまった。 深く信じていたので、このような恩恵もあったのである。 読解ポイント 人間だと思っていた人物が実は別の存在だった、という展開は古文の定番です。 また、このような話では主人公が恩恵をうけるという話も多く、いいことをしたからいいことが返ってくるというパターンは覚えておきましょう! 「鶴の恩返し」などの昔話も同じパターンです。 パターン4:思いがけない奇跡(今昔物語) 真夜中の泣き声『今昔物語』より (夜の見回りをしていた人は、草むらから泣き声が聞こえた。草むらへ向かうと、怪しげな男がいたので、つかまえた。なんと盗人がその寺の弥勒菩薩の銅像を盗んでこわそうとしていたのだ。見回りをしていた人が盗人を捕らえて、役所につき出し、牢屋に閉じ込めた。) 古文 天皇にこの由を奏して、仏をば取りて、本のごとく寺に安置し奉りつ。 これを思ふに、菩薩は血肉を具し給はず。豈に痛み給ふところあらむや。 しかるに、ただこれ凡夫のために示し給ふところなり。 「盗人に重き罪を犯さしめじ」と思ひ給ふためになり。 現代語訳 天皇にこのことを申し上げて、仏を取り返して、もとのように寺に安置し申し上げた。 このことを思うと、菩薩は肉体をもっていらっしゃらない。どうしてお痛みになるところがあろうか(、いや、ないはずだ)。 だとしたら、ただこれ(=菩薩が泣き叫んだこと)は、凡夫にお示しくださったのだ。 「盗人に重い罪を犯させないようにしよう」とお思いになったため(に泣き叫んだの)だ。 読解ポイント 仏教の教えを広めるために書かれたお話を「仏教説話」といいます。 極楽や地獄の話、ありえない奇跡の話など不思議な話も多くあります。 信仰や徳が奇跡を呼ぶという展開がよくあります。 今回は菩薩の不思議な力についての話でしたね。 パターン5:芸は身を助ける(宇治拾遺物語) 内裏の立て札『宇治拾遺物語』より (内裏に「無悪善」と書かれた札がたてられていた。嵯峨天皇に命じられて、小野篁がしぶしぶ札の言葉を読むと、読めてしまったので、札を立てた犯人だと疑われてしまった。) 古文 「さればこそ、申し候はじとは申して候ひつれ」と申すに、 御門、「さて何も書きたらん物は読みてんや」と仰せられければ、 「何にても読み候ひなん」と申しければ、片仮名の子文字を十二書かせ給ひて、 「読め」と仰せられければ、「ねこの子のこねこ、ししの子のこじし」と読みたりければ、 御門ほほゑませ給ひて、事なくてやみにけり。 現代語訳 (篁が)「だから、申し上げますまいと申しましたのに」と申し上げると、 御門(=嵯峨天皇)は、「では何でも書いたような物は読めるのだろうか」とおっしゃったので、 (篁は)「何でも読みましょう」と申し上げたところ、(御門は)片仮名の「子」という字を十二個書かせなさって、 「読め」とおっしゃったので、(篁は)「ねこの子のこねこ、ししの子のこじし」と読んだので、 御門はほほえまれて、何事もなく済んだのだった。 ※片仮名:当時は「子」という文字を片仮名の「ネ」として使用していた。 読解ポイント 特技や教養がピンチを救う場面です。 昔は和歌や漢詩などの文化的教養が、人生を左右するほど重要でした。 今回は小野篁の漢文の知識が役に立ったお話ですね。 パターン6:機転を利かす(沙石集) 毒の飴? 『沙石集』より (児は「食べたら死ぬ」と言われて、坊主がどうしても食べさせてくれない飴をなんとしても食べたかった。 そのため、坊主がいない間にこっそり食べて、そののちに坊主の大事にしていた水瓶を割った。坊主が帰ってくると、泣いたふりをして、語りだした。) 古文 「大事の御水瓶を、あやまちに打ち割りて候ふ時に、いかなる御勘当かあらむずらむと、口惜しく覚えて、命生きてもよしなしと思ひて、 人の食へば死ぬと仰せられ候ふ物を、一杯食へども死なず、 二、三杯まで食べて候へどもおほかた死なず。 果ては小袖につけ、髪につけて侍れども、いまだ死に候はず」とぞ言ひける。 飴は食はれて、水瓶は割られぬ。慳貪の坊主得るところなし。 児の知恵ゆゆしくこそ。 現代語訳 (小児は)「大事にされていた御水瓶を、まちがって割りましたときに、どのようなおしかりがあるだろうかと(思うと)、残念に思って、生きていてもしようがないと思って、 人が食べると(必ず)死ぬとおっしゃいました物を、一杯食べたけれど死なない、二、三杯まで食べましたけれど全く死なない。 最終的には小袖につけ、髪につけましたが、まだ死にません」と言った。 (坊主にとっては)飴は食われて、水瓶は割られた。 けちな坊主には(損ばかりで)得るところがない。 児の知恵はすばらしいものだった。 読解ポイント 飴を食べるために機転を利かせて、結果的に状況を有利にする展開です。 一休さんのとんち話も、このパターンに近いです。 実際には、児は「食べたら死ぬ」と言われていたものを食べてから坊主の秘蔵の水瓶をわざと割っていますが、 機転を利かせて、水瓶を割ってしまったから「食べたら死ぬものを食べた」としているのですね。 パターン7:ものの見方が個性的(枕草子) 五月の山里散策 『枕草子』より (筆者は山里を散策することについて語っている。) 古文 左右にある垣にあるものの枝などの、車の屋形などにさし入るを、 急ぎてとらへて折らむとするほどに、 ふと過ぎてはづれたるこそいとくちをしけれ。 よもぎの、車に押しひしがれたりけるが、輪の回りたるに、近ううちかかりたるもをかし。 現代語訳 左右にある垣根にある何かの枝などが、牛車の人が乗る部分などに入ってくるのを、 急いでつかんで折ろうとするうちに、 すっと通り過ぎてはずれてしまうのは、とても残念だ。 よもぎの、牛車(の車輪)に押しつぶされたのが、車輪が回るときに(くっついて持ち上がってきて)、近くに引っかかっているのもおもしろい。 読解ポイント 日常の何気ない情景を面白く感じる感性が表れています。 枝が手に入らず「残念」と思う感情や、つぶされたよもぎが引っかかることを「おもしろい」と感じる感性です。 このような文章では「作者が何を面白いと感じたのか」を読み取ることが大切です。 パターン8:生き方の知恵を語る(徒然草) 形からでも 『徒然草』より (筆者は物に触れることが行動を呼び起こすと説いている。信仰心がなくても、仏の前に座り、数珠を手に取り、経文を手に取ると、自然とよい行いができる。乱れた心のままでも、座禅用の椅子に座れば、重いかげず禅定の境地に入るだろう。) 古文 事理もとより二つならず。外相もし背かざれば、内証必ず熟す。 しひて不信を言ふべからず。 仰ぎてこれを尊むべし。 現代語訳 (仏教において)現象と真理はもともと二つのものではない。外部に現れた姿がもし(仏教の教えに)背かなければ、内心の悟りも必ず成熟する。 (形だけだからと)一概に不信心だと言ってはいけない。 敬ってこれを尊いものと(して大事に)するべきである。 読解ポイント 古文には現代でも通用するような「生き方の知恵」が書かれているものがあります。 今回は概念的な文章で少し難しいかもしれませんが、「形から入ることの大切さ」を説いた内容ですね。 行動の形を整えることで、心や考え方も変わるという教えです。 ほかにも『徒然草』に掲載されている「高名の木登り」というものでは、「失敗は簡単なところで必ず起こるものだ」という知恵が書かれています。 パターン9:過去に学ぶ(花月草紙) 用心する男 『花月草紙』より (遠くの火事にも用心していた男は、周りの人々に日々笑われていた。ある日、はるか遠くの火事が男たちの住むあたりまで広がり、人々はすべてを失い、困って果てていた。) 古文 かのをのこ、したりがほにて、「かしてまゐらせん」とて、 かの縄を引きたぐれば、はさみよ、くしよなどいふもの引きあげつ。 また袋のうちより、うつはものなど出だしつつ、 「つねづね人にわらはれずば、いかでかかるときはほまれしつべき」と言ひしを、「げにも」と言ひし人ありしとぞ。 現代語訳 その男が、得意げな顔で、「貸してあげましょう」と言って、 あの縄を引き寄せると、はさみや、くしなどといったものを引きあげた。 また袋の中から、食器などを出しながら、 「ふだんから人に笑われなければ、どうしてこのようなときに名誉に思えるだろう」と言ったのを、「(なるほど)その通りだ」と言った人がいたということだ。 読解ポイント 日頃の備えや過去の経験から学ぶ重要性を説いていますね。 今回引用した『花月草紙』は「随筆」と呼ばれるジャンルです。 「随筆」は筆者の体験や考え、見聞きした出来事などが書かれています。 パターン10:歌にこめられた思い(伊勢物語) 筒井筒『伊勢物語』より (結婚から数年後、女の親が亡くなり貧しくなると、男はほかに妻をもうけた。女が気にしていない様子なのを見て、女の浮気を疑った男は、新しい妻のもとへ行くふりをして植え込みに隠れて女の様子をうかがった。) 古文 この女、いとよう化粧じて、うちながめて、 風吹けば沖つしら浪たつた山 夜半にや君がひとりこゆらむ と詠みけるを聞きて、かぎりなくかなしと思ひて、河内へも行かずなりにけり。 現代語訳 この女は、とても念入りに化粧をして、物思いにふけって、 風が吹くと沖の白波がたつ、その「たつ」の名をもつものさびしい龍田山を、 夜中にあなたはひとりでこえているのでしょう。 と詠んだのを聞いて、(男は)この上なくいとおしいと思って、河内(の国にいる新しい妻のところ)へも行かなくなってしまった。 ※河内:現大阪府 龍田川:奈良県にある、大和(現奈良県)と河内(現大阪府)の間にある要路で険しい山のこと。 つまり河内にいるほかの女に会いに行こうと彼は今、龍田川を越えているのだろうか、と物思いにふけっているということですね。 読解ポイント 和歌は短い中に深い感情を込めます。恋や別れ、自然を題材にした歌は、入試頻出です。 平安時代の恋愛観と結婚の流れ ここで平安時代の貴族の恋愛について少しふれましょう。 平安時代の貴族の恋愛・結婚は今の恋愛とは全く異なります。 古文作品を読むうえでは必須の知識ですので、しっかりと押さえておきましょう。 恋愛から結婚までの流れ ①男性が女性の噂話を聞く 顔を見たことがなくとも、美しい女性、教養のある女性の噂を聞きます。 ②男性が和歌を書いた手紙(文)を送り、女性に思いを伝える この和歌の出来や、筆跡がどのような男性か判断する大きな材料となりました。 ③女性が手紙を読み、いいなと思ったら返事をする 「返歌」と呼ばれるものですね。 ④手紙のやり取りを続け、男性が女性の家に来る ⑤三日連続で男性が家に来たら結婚成立 和歌のやり取りは、物語・日記文学に数多く描かれます。 一夫多妻制だった平安時代 現代の日本では一夫一妻制が一般的ですが、当時の貴族社会では一夫多妻制が普通でした。 色々な場所に妻がいるのが普通なのです。 このため、古文の恋愛物語では、男性が別の女性のもとへ通ったり、女性がそれを切なく思ったりする場面がよく出てきます。 古文のパターンを引用元の作品から推測しよう! 多くの場合、教科書や試験問題には引用元が明記されています。 そこから「この作品なら、こんなパターンの話かな」と想像しながら読むと、内容の理解がぐっとスムーズになります。 たとえば―― パターン1:クスッと笑えるオチのある話 → 『徒然草』のような随筆や、『古今著聞集』『宇治拾遺物語』といった説話集に多く見られます。 パターン4:思いがけない奇跡(仏教説話) → 『今昔物語集』はもちろん、『発心集』や『沙石集』など、仏教説話を多く収めた作品に頻出です。 パターン9:過去に学ぶ → 平安時代の『枕草子』、鎌倉時代の『方丈記』、同じく鎌倉時代の『徒然草』は「日本三大随筆」と呼ばれ、このパターンがよく見られます。 江戸時代の松平定信『花月草紙』や本居宣長『玉勝間』などの随筆でも同様です。 もちろん、作品の傾向はあくまで目安です。 必ずしも同じ作品が同じパターンになるとは限りません。 ですが、引用元を手がかりにパターンを予想することは、古文読解の大きな助けになります。 古文のパターン早見表 おわりに:「でも、どうやって覚えたらいいの?」 古文は今回紹介したパターンを知っておくと、ぐっと読みやすくなり、 練習すれば、より、スラスラと読めるようになります。 わからないをわかるにかえる 中学 国語 古文・漢文 1~3年 本テキストでは、今回の10パターンをより丁寧に、練習問題付きで解説しています。 それぞれの特徴をおさえながら取り組むことで、 テストや入試に出てくる初めて目にする古文が、どのパターンかを考えて対応できる力が身につきます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 【今回の執筆者】 イニシャル:MS 年代:20代 ~ひとこと~ 大学でも古文を勉強していましたが、とっても面白く、奥深い世界でした。
色々な国の言葉で「こんにちは」と言いたいんだ!
色々な国の言葉で「~~」と言いたいシリーズです! 前回の記事では「ありがとう」という感謝のフレーズを色々な国の言葉でご紹介しました。 今回は、世界の様々な国の「こんにちは」という挨拶のフレーズをご紹介したいと思います。 海外に行った時に、その土地の言葉で挨拶ができたらとっても素敵ではないでしょうか! ※紹介しているのは、基本的な表現です。その他の言い方もあります。 色々な国の「こんにちは」 英語:「Hello」 (ハロー) アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど、英語圏で広く使われている挨拶です。 ただ、日常会話で「こんにちは」と挨拶したい場合、「Hello」よりも「Hi」(ハイ)を使う方が一般的です。 初対面やお店で店員さんと話す場合などには「Hello」を使い、親しみを込めた挨拶をしたい場合は「Hi」を使いましょう。 フランス語:「Bonjour」 (ボンジュール) フランス、ベルギーなどのフランス語圏での「こんにちは」です。 「Bonjour」は、「おはよう」と「こんにちは」を兼ねるので、1日の中で大部分の時間で使うことができます。 夜は「こんばんは」の意味である、Bonsoir(ボンソワール)を使います。ぜひセットで覚えておきましょう。 ドイツ語:「Guten Tag」(グーテン ターク) 「good」を意味する「Guten」と「day」を意味する「Tag」の組み合わせです。 朝と夜は組み合わせを変えて 「Guten Morgen」(グーテン モルゲン)=おはよう 「Guten Abend」(グーテン アーベント)=こんばんは となります。 スペイン語:「Hola」(オラ) スペイン、アルゼンチン、チリなどのスペイン語圏で使われる、基本的な挨拶です。 時間を問わず、1日中いつでも、どんな場面でも使える万能なフレーズです。 イタリア語:「Ciao」 (チャオ) 「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」「さようなら」など、すべての挨拶の意味があるイタリア語での一般的な表現です。 ただし、カジュアルな表現なので敬語を使って挨拶をしたいような相手には使わない方が無難です。 朝から夕方なら「buongiorno」(ブオンジョールノ)、夕方から夜にかけてなら「buonasera」(ブオナセーラ)を使いましょう。 ウクライナ語:「Добрий день」 (ドーブリ デーニ) 様々な場面で使えるフォーマルな「こんにちは」です。 カジュアルな場面だと「Привіт」(プリビットゥ)という挨拶を使います。 ポルトガル語:「Olá」(オラ) ポルトガル、ブラジルなどのポルトガル語圏での挨拶です。 フレンドリーすぎない、少しフォーマルといったイメージです。 スペイン語の「Hola」と似ていますが、ポルトガル語の「Olá」は、「lá」の部分にアクセントを置きます。 ギリシャ語:「 Γειά σας」(ヤーサス) 「こんにちは」という挨拶のギリシャ語です。 フォーマルな挨拶には「 Γειά σας」(ヤー サス)、親しい間柄なら「Γειά σου」(ヤー ス)を使います。 ちなみに、「」かぎかっこのようにみえる Γ は ギリシャ文字で γ (ガンマ)の大文字です。 ロシア語:「Здравствуйте」(Zdravstvujtye)(ズドラーストヴィチェ) 「Здравствуйте」(ズドラーストヴィチェ) はどんなシチュエーションでも使える普遍的なロシア語の挨拶で、「お元気で」のような意味です。 日本語の「こんにちは」のように時間帯で変化する挨拶は 「Доброе утро」(Dobroye utro) (ドーブラエ ウートラ) = おはよう 「Добрый день」(Dobroye dyen)(ドーブライ ヂェン) = こんにちは 「Добрый вечер」(dobriy vyecher)(ドーブライ ヴェーチェル) = こんばんは が使えます。 中国語:「你好」(nǐ hǎo)(ニーハオ) 中国全土で使われる挨拶の表現です。 挨拶として丁寧にしたい場合には「您好」(nín hǎo)(ニンハオ)を使います。 日本語の「こんにちは」のように時間帯で変化する挨拶は 「早上好 (zǎoshang hǎo) (ザオ シャン ハウ)=おはようございます 「下午好」(xiàwǔ hǎo) (シィア ウー ハァォ)=こんにちは 「晚上好」 (wǎnshàng hǎo) (ウァン シァン ハァォ)=こんばんは が使えます。 韓国語:「안녕하세요」 (アンニョンハセヨ) 時間を問わず1日中いつでも、どんな場面でも使える韓国語の基本的な挨拶です。 さらに丁寧に言いたい場合は、「안녕하십니까」(アンニョンハシムニカ)もあります。 タイ語:「สวัสดี」(サワディー) 「สวัสดี」(サワディー)は、フォーマルでもカジュアルでもほとんどすべての場面で使えるタイ語の万能な挨拶です。 この言葉は「こんにちは」だけでなく「さようなら」にも使えます。 挨拶する際には、男性は「ครับ」(クラップ)、女性は「ค่ะ」(カー)を文末につけて、礼儀正しさを示します。 ヒンディー語:「नमस्ते」(Namaste)(ナマステ) インドで使われる、ヒンディー語の「こんにちは、よろしく」のような意味の一般的な表現です。 時間を問わず1日中いつでも、どんな場面でも使えます。 インドネシア語:「Selamat siang」(セゥラマット スィアン) 「こんにちは」という意味のインドネシア語での一般的なフレーズで、大体11時~16時くらいの間の挨拶として使われます。 そのほかの時間帯だと、 「Selamat pagi」(セゥラマット パギ)=午前中のおはよう 「Selamat sore」(セゥラマット ソーレ) =16時~18時くらいのこんにちは 「Selamat malam」(セゥラマット マラム) =18時以降のこんばんは などがあります。 スワヒリ語:「Habari」 (ハバリ) 東アフリカで広く使われている、スワヒリ語の挨拶です。 様々な場面で使える「元気ですか?」といった意味です。 「Habari?」(ハバリ)=「元気?」 「Nzuri sana!」(ンズーリ サーナ)=「とても元気です!」のような一般的なフレーズです。 アラビア語:「مرحباً」(Marhaban)(マルハバン) アラブ全域で通じる挨拶で、時間を問わず「やあ、こんにちは」といった意味のカジュアルな言葉です。 より丁寧かつ正式な挨拶とされていて時間を問わず様々な場面で使われる挨拶が 「السلا َم عل َيك ُم」(Assalamu alaikum )(アッサラーム・アライクム)です。 日本語では「こんにちは」と意訳されますが、直訳すると「あなたに平安がありますように」という意味です。 さいごに 世界はまだまだ広いので、少しの言語しかご紹介できませんでしたが、 ほかに気になる国の言葉があれば、ぜひ調べてみてください! 【今回の執筆者】 イニシャル:MU 年代:20代 ~今日の一言~ 最近見たドラマの影響でフランス国歌を覚えました
これでバッチリ!中学生向け英単語の覚え方ガイド
はじめに みなさん、英単語を覚えるのは得意ですか? 私は苦手です。 しかし、英単語を覚えていないと単語テストで点が取れないのはもちろん、 長文読解やリスニングでは、なんとなく流れはわかるけど何のことかわからない…となってしまったり、 ライティングでは、書きたいことも書き方もわかるけど単語がわからなくて書けない…となってしまったりします。 苦手でも、英単語の学習を日ごろからコツコツ行っておくことは重要です。 今日は、英単語の学習をどのようにしていけばいいのか、コツコツ行うコツをご紹介します。 もくじ 英単語を覚える重要性 忘却曲線を活用した効果的な暗記法 効果的な英単語の覚え方 毎日の学習習慣の作り方 英単語を覚えるのにおすすめの問題集&単語帳 まとめ 英単語を覚える重要性 すでに冒頭でも述べた通り、英単語を覚えることは英語学習全体においてとても大切になります。 たとえば、リーディングやリスニングでは、英文法はしっかりわかっていて内容がつかめても、単語の意味を取り違えるだけで意味が全く変わってしまう場合があります。 スピーキングやライティングでは、自分が話しやすいこと、書きやすいことにもっていくために語彙力が役立ちます。 今の中学生が覚えるべき英単語は1600語~1800語ほど。さらに小学生で習う英単語も含めると、2500語ほどあります。 授業にしっかりついていくためにも、授業外の学習で英単語をしっかり覚えておきたいところです。 忘却曲線を活用した効果的な暗記法 忘却曲線とは? みなさんは、「エビングハウスの忘却曲線」というのをご存じでしょうか? ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱したもので、 人間の記憶が時間経過とともにどのくらい忘れてしまうか、を示しています。 覚えたことは、時間がたつとどんどん忘れられていくことがわかりますね。 エビングハウスは同時に、早い時間に復習すればするほど、再学習にかかる時間を節約でき、記憶の定着率も高くなる。 つまりこまめな復習が効果的であることも示しています。 最適な復習タイミングとは? 英単語も、1回にたくさん覚えるよりも、何度も繰り返して定着させる方が身につきやすいです。 たとえば、「今週はここからここまで!」と決めた範囲を1週間毎日繰り返し見る、というやり方はどうでしょうか。 1週間分の語数は10単語でも20単語でも無理のない範囲で決めてみましょう。 とにかく、一度覚えたら終わりではなく、繰り返しが大切です。 効果的な英単語の覚え方 視覚と聴覚を活用する 英単語を覚えるときには、「目で見る、耳で聞く、口で発音する」のように、五感を活用してみましょう。 読むだけよりも、頭に残りやすくなるはずです。 書いた方が覚えるという人は、書き取りも効果的です。 覚えやすいだけでなく、リスニングやスピーキングで活かすためには発音も重要なので、 英単語帳を選ぶ際には、音声も聞けるものを探してみてください。 例文と一緒に覚える 単語単体ではどうにも覚えられない場合、例文ごと覚える方法もあります。 たとえば、 glad(喜ぶ)なら、「I'm glad to hear that.(それを聞いてうれしいです。)」 guitar(ギター)なら、「I can play the guitar.(私はギターが弾けます。)」 などです。 使う場面も一緒に覚えられるため、思い出しやすくなります。声に出してみるとなおよいです。 複数の単語を同時に覚えられることや、例文の単語を入れ替えることでほかの場面でも活用できることも魅力です。 自分だけの単語帳を作成する 学校で配られる単語帳や市販の単語帳を使う方法もありますが、 自作の単語帳を使うやり方もあります。 ノートに英単語を書き、となりに和訳を書くだけで完成です。 オレンジペンを使えば、赤シートを使えるようにもできます。 メリットとしては、各順番や位置を考えながら手で書くことで、記憶が定着しやすくなります。 また、覚えられない単語に絞る、軽いノートに書くなどすることで、持ち運びやすくすることができます。 「自分で作ることで定着する」という意味では、自分で単語を決めて登録できる英単語アプリなども活用できますね。 毎日の学習習慣の作り方 スキマ時間の活用 部活や習い事などで毎日帰りが遅い、といった場合、 そんな人は、スキマ時間を探してみましょう。 たとえば、電車通学をしていれば、通学の電車の中があります。 朝学校についてからの時間、 また、たとえば送り迎えを待つちょっとした待ち時間などもあるかもしれません。 5~10分程度の時間があれば、英単語の学習は十分可能です。 ふと見つけたスキマ時間を活用できるよう、スマートフォンに単語アプリを入れておく・小さな英単語カードを持ち歩く、など準備しておきましょう。 継続するための工夫 毎日学習を続けるために、どんなことができるでしょうか。 まず大事なのは、「ハードルを低く設定すること」です。 いきなり、「毎日1時間やる!!」と決めるのではなく、「1日15分だけでもOK!」など、ちょっとの目標を毎日こなすことを目指します。 また、意志の強さだけで頑張るのも難易度が高いです。 具体的に、 「取り組めた日はカレンダーにチェックをつける」 「1週間続けられたらのご褒美を用意する」 など、目に見える成果・報酬を設定するのがおすすめです。 英単語を覚えるのにおすすめの問題集&単語帳 効率よく英単語を覚えられる問題集 まずご紹介するのは、『中学教科書ワーク』です。 この問題集の特長は、「教科書に対応して作られていること」で、 教科書で習う順で英単語を学ぶことができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 特典として以下ががついており、スキマ時間の学習に活用できる点もおすすめです。 ・教科書に対応した暗記ブック「スピードチェック」 ・英単語カード「ポケットスタディ」 ・英単語学習もできるWEBアプリ「Newどこでもワーク」 テストブックで二段階の確認ができる英単語帳 「わからないをわかるにかえる 英検®単語帳」は、英検対策用ではありますが、 日常学習の英単語帳としても使えます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 最大の特長は、「テストブックがついていること」です。 別冊のテストブックは、赤シートを使いながら、問題形式で単語を確認できます。 単語帳で覚えたと思ったら、テストブックで問題として聞かれたときに答えられるかを確認するという、二段階での学習ができます。 また、開きやすい本の作りになっていて、ストレスなく使いやすいです。 まとめ 英単語を覚えるには、次の2つが効果的です。 1)自分にとって使いやすいツールを用意すること 2)毎日の習慣として継続すること 1)2)それぞれ自分に合ったものを探してみるとよいでしょう。 とはいえ、何事も始めてみることが大切。 まずは「教科書1ページ分の英単語を1日1回ずつ読む」からでもかまいません。 さっそく今日から英単語の学習を始めてみませんか?
スギ花粉とPM2.5 ってなに?春の悩みを吹き飛ばそう!
はじめに さて、スギ花粉の季節がやってきました。そしてPM2.5の季節もそろそろやってきますね。 今回は、国民病ともいわれる花粉症と、近年環境問題として取り上げられることの多いPM2.5について詳しく解説していきます。 スギ花粉とは? スギ花粉はスギの木から放出される花粉のことです。 これがスギ花粉症を引き起こす原因です。 現在、日本に植えられているスギの多くは、戦後の国土緑化のためなどに植えられたものだといわれています。 その面積、なんと441万ha!※ 森林面積(天然林・人口林ほか)が2,502万ha、人口林は1,009万haなので、人口林の約43%がスギで埋め尽くされているわけですね。 もちろん、天然林の中にもスギは生えているので、日本の森林の中には大変多くのスギが生息しているといえます。 ※令和4年3月31日時点。出典:林野庁ウェブサイト https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html (2025年2月27日利用) スギ花粉はどうして流行しているの? とはいえ、花粉はスギのような木だけでなく、花などの多くの植物にも存在しています。 それではなぜ、スギ花粉症が国民病といわれるまでに流行しているのでしょうか。 それは「スギの花粉がとても小さいから」が挙げられます。 植物の花粉の運ばれ方について、みなさん知っていますか? 虫媒花、鳥媒花、風媒花などがありますね。 今回取り上げているスギは風媒花です。 風に花粉を運んでもらい、子孫を増やすのです。 風に運んでもらう必要があるので、軽く、小さくないといけないのですね。 ヒノキ、ブタクサなどの花粉症もよく耳にしますが、これらもすべて風媒花です。 風に乗って遠くまで飛ぶ上に、先ほどご紹介した通り大変多く生息しているため、大気中に大量に舞います。 そのため、スギ花粉症は国民病と呼ばれるまで流行しているのだと考えられます。 スギ花粉症とその症状 スギ花粉の飛散が始まると「スギ花粉症」を発症する可能性があります。 主な症状には、以下のようなものがあります。 くしゃみ: 繰り返しのくしゃみは典型的なアレルギー反応といわれています。 鼻水・鼻詰まり: 花粉が鼻腔に入ることで炎症を引き起こし、鼻水がでたり、鼻詰まりが生じたりします。 目のかゆみや充血: 目がかゆくなったり、充血したりする症状もあります。 咳や喉の痛み: 喉に花粉が入ることで、咳や痛みが出ることもあります。 スギ花粉は2月中頃から5月あたりまでがピークだといわれていますが、花粉の飛散量が多い日は特に悪化することがあります。 さて、春に猛威を振るうスギ花粉。 同時期にスギ花粉と同じくらい大量に大気中に舞い、近年環境問題として取り上げられるものがあります。 それがPM2.5です。 PM2.5とは? PM2.5(微細粒子状物質)とは、直径が2.5マイクロメートル以下の粒子を指します。 マイクロメートル(㎛)がどのくらいかというと、2.5ミリメートル(㎜)の1000分の1。 スギ花粉の大きさの約10分の1です。 とても小さいと説明したスギ花粉 約30マイクロメートルより何倍も小さいのです。 これらの粒子は、工場からの煙、車の排気ガス、さらには自然現象(火山の噴火、大気中の塵など)によって発生します。 成分は炭素、硝酸塩などで、黄砂とは成分がまったく異なります。(※ただし、黄砂の大きさが2.5マイクロメートル以下の場合は、黄砂もPM2.5 とみなされます。) PM2.5はどこから、どうやってきているの? PM2.5 がどこから、どうやってきているのか理解するためには、まず日本の天気の移り変わりから考える必要があります。 日本では天気がおおむね西から東へ変わることが多いです。 これは偏西風の影響で、低気圧や高気圧が西から東に移動しているからです。 この偏西風の影響で中国などの大陸からPM2.5 が飛んできているのです。 なぜ春にPM2.5 が多いの? それはジェット気流の影響です。 偏西風の中でも一番強い風、ジェット気流は冬の間は南の方に下がっています。 しかし、春になると日本上空近辺に上がってくるのです。 とても強い風に流されて、小さなPM2.5 はたくさん飛んでくるということですね。 PM2.5の影響ってなに? PM2.5はその小ささから、肺深部に容易に侵入し、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があると考えられています。 呼吸器内に付着して体外に出にくいのです。 スギ花粉とPM2.5への対策 それでは、スギ花粉とPM2.5 にどのように対策したらよいか見てみましょう。 外出時の対策 マスクの着用: 花粉やPM2.5から鼻や口を守るために外出時はマスクを着用しましょう。 花粉症の方からしたら当たり前かもしれませんね。 特に花粉対策用マスクやPM2.5対応のフィルターが付いたものをおすすめします。 ゴーグルの使用: 目の保護のため、特に花粉の多い日はゴーグルを使用することをおすすめします。 医療用の保護ゴーグルなどで、少しでも花粉やPM2.5の侵入をなくしましょう。 目薬をする:目に入った粒子を洗い流すため、目薬もおすすめです。 髪をまとめる:髪の長い方、髪に付着している花粉、PM2.5 の量は侮れません。 髪をまとめ、外と触れる面積を少しでも減らすことをおすすめします。 洋服に気を遣う:ウール素材は花粉が付きやすいといわれています。 また、静電気が発生しにくい素材を選択することも花粉やPM2.5 を避けるうえでは有効です。 室内での対策 加湿器をつける:乾燥していると花粉、PM2.5 が舞いやすいのです。 一般的に雨の日は花粉の飛散量が少なくなるといわれています。 カビなどがはえるほどに加湿する必要はもちろんありませんが、加湿器を使い、出来る限り花粉が舞わないようにしましょう。 空気清浄機の使用: 室内の花粉やPM2.5を 除去するために、空気清浄機を導入しましょう。 花粉もPM2.5 もドアから一番入ってくるので、玄関に置くことをおすすめします。 花粉症ってなにかな?PM2.5ってなにかな? 大人の教科書ワーク 今回PM2.5の記事部分は「大人の教科書ワーク」理科の「PM2.5 って何?」というページを参考にしています。 「大人の教科書ワーク」は、今回使用した「理科」以外にも「社会」「実技」「数学」とあります。 どこにサーキュレーターを置けばエアコンの効果が高まるの? クレカや電子マネー、使い過ぎを防ぐには? 数学の「点P」は、どうして図形を動き回るの? 日常で発生するふとした疑問に対して、楽しく学びませんか? 「大人の」とありますが、お子さんにもおすすめ! 気になった方は、是非チェックしてみてください! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ スギ花粉とPM2.5は、共に健康に悪影響を及ぼす要因の一つですが、適切な対策を講じることで、影響を軽減することが可能です。 少しでも対策をして、春を乗り切りましょう! 【今回の執筆者】 イニシャル:M 年代:20代 ~今日の一言~ 3歳のころから花粉症です。 年齢を重ねて症状緩和はしましたが、いまだにこの時期はティッシュが手放せません。とても憎く、とても辛いです。
【まとめ】行事についての豆知識、集合!
いつも「なるほど!Bunri-LOG」をお読みいただき、ありがとうございます! このブログでは、 ・勉強に関するコツ ・文理の商品に関する紹介 ・その他、雑学やお役立ち情報 を紹介しています。 今日はそんな中から、「行事に関する豆知識」を扱った記事をピックアップ! 一挙紹介! 1月の行事 お正月にまつわるエトセトラ 「おとそ」って知っていますか? 答えは記事で!おせち料理やお年玉、お正月の定番アイテムについて、その意味をご紹介! 2月の行事 「節分」のひみつ ~節分って2月3日じゃないの?~ 2025年の節分は、2025年2月2日になります。節分って2月3日じゃないの?!と思った方はぜひ読んでみてください。 3月の行事 3月3日はひな祭り!ひな祭りのまめちしき ひな祭り、ひな人形を出すだけ、というご家庭も多いのではないでしょうか。 ひな人形のかざりにもある、四角い三色のおもち、ひし餅。 この色にも意味があります。 愛知の郷土菓子「おこしもの」のレシピもご紹介! 7月の行事 【こどもたちといっしょに】七夕のふしぎ どうして「たなばた」と読むの?笹にかざる色々な飾りの意味は?雨が降ると織姫と彦星は会えないの?考え始めると不思議な七夕について、紹介します。 8月の行事 「お盆」の ひみつ 学校に通っている間は夏休みまっさかりで、時期を意識することが少ないかもしれません。会社では、お盆休みがあることも多いですね。きゅうりの馬となすの牛、迎え火・送り火…知っているようで知らない「お盆」について、学んでみませんか。 11月の行事 七五三 当日の完全ガイド!持ち物や神社でのご祈祷の流れなど解説いたします! みなさんご自身の七五三のことを覚えていますか?私は千歳飴を食べきれなかったことだけ覚えています。七五三の由来から、具体的にどういう手順で行われるのか?どういう準備が必要か?まで解説! いかがでしたか? 今回ご紹介した以外にも、季節のイベントごとに関する記事は色々あります。 ほかにもバラエティー豊かな記事がありますので、 お時間があれば、ぜひ、過去の記事もさかのぼって読んでみてください。
素数とは?中学数学で押さえておきたいポイント
もくじ 素数って何?基本を知ろう 素数は中学数学でどのように使うの? 素数を見分ける方法 素数に関するよくある質問 素数の面白い応用例 「わからないをわかるにかえる数学」 「大人の教科書ワーク 数学」 まとめ 素数って何?基本を知ろう 素数の定義をわかりやすく 素数とは、「1とその数自身の積でしか表せない自然数のこと」です。 言い換えると、「1とその数以外に約数ををもたない(約数が2つの)自然数」が素数となります。 2、3、5、7、・・・ などが素数ですが、例えば7は、1と7でしかわり切れませんから、素数です。 4や6は、1とその数自身でもわり切れますし、それぞれ2と3でもわり切れますので、素数ではありません。 素数を中学数学で学ぶ理由 素数は、数学の基礎となり、中学数学・高校数学を学ぶうえで必要不可欠な知識となります。 中学では、素数は「素因数分解」や「平方根」で使います。 自然数を素数の積だけで表す素因数分解では、言うまでもなく素数が重要な役割をもっています。 また、小学校5年生で習う「最大公約数・最小公倍数」でも、実は素数が鍵となっています。 数学の基礎となる素数はしっかりと理解を深めておく必要があります。 素数は中学数学でどのように使うの? 素因数分解で使う例 自然数を素数の積だけで表すことを素因数分解といいます。 素因数分解の基本手順はしたのようになります。 したがって、84を素因数分解すると、2×2×3×7となります。(実際の問題に答える際には、2²×3×7としましょう。) 最大公約数・最小公倍数の計算での役割 先ほど、最大公約数・最小公倍数で素因数分解が使えると書きましたが、どのように使うのでしょうか。 たとえば、90と162の最大公約数と最小公倍数を考えます。 90と162をそれぞれ素因数分解すると、こうなります。 これを、下のように縦にそろえて書きます。 90と162の最大公約数は、したのように考えて、18だということがわかります。 90と162の最小公倍数は、したのように考えて、810だということがわかります。 このように、最大公約数や最小公倍数を求める際には、素因数分解が役立ちます。 素数を見分ける方法 小さな数でわり算してみる 素数かどうかを見分けるために、小さな数でわり算をしてみるという方法があります。 【手順】 1. まず2でわってみる 偶数はすべて2でわり切れるので、2以外の偶数は素数ではありません。 例:4、6、8…は2でわり切れるので素数ではない。 2. 次に3でわる 3でわり切れる場合、その数も素数ではありません。 例:9、12、15…は3でわり切れるので素数ではない。 3. 5でわる 最後の数字が0か5で終わる数は、5でわり切れるため、素数ではありません。 例:10、15、20…は5でわり切れるので素数ではない。 4. 7、11、13、19…と暗記している素数でわる エラトステネスの篩(ふるい)を使う方法 こちらの方法は、中学数学では習わないのですが、 「エラトステネスのふるい」という名の通り、ふるいにかけるように、多くの数のなかから素数を見つけのに便利です。 この方法を使って、1~40までの範囲の素数を見つけてみましょう。 【手順】 1. 1を消す 2. 最も小さい素数を残したまま、その素数の倍数をすべて消す。 この場合は、2を残して、2以外の2の倍数をすべてふるい落とします。 3. 残っている中で最も小さい素数を残したまま、その素数の倍数をすべて消す この場合は、3を残して、3以外の3の倍数をすべてふるい落とします。 4. 手順3を最後まで繰り返す。 4はすべてふるい落とされているので、5を残して、5以外の5の倍数をすべてふるい落とします。 最後まで繰り返すと、下図のようになります。 中学のテストでよく出る素数判定問題 中学のテストでは、ある数が素数かどうかを見分ける問いがよく出題されます。 例えば、 問題:101は素数か答えなさい 解答:101の約数は「1」と「101」の2つなので、101は素数である。 などです。 上記で紹介した方法などを用いて、素数かどうかを見分けます。 中学では覚えておくべき素数 中学の問題では、少なくとも【2,3,5,7,11,13,17,19】あたりまでの素数を暗記しておくとよいでしょう。 暗記をしておくことで、素数を見分ける問題が楽に解けるようになります。 もちろん、素数はずっと続いていきますので、興味があれば暗記してみても面白いかもしれないですね。 素数に関するよくある質問 ・1は素数じゃないの? 素数の定義をみてみると、「1とその数以外に約数ををもたない(約数が2つの)自然数」となっています。 たとえば、2の約数は1と2の2つ、7の約数は1と7の2つ。 1は、約数が1自身の1つだけしかないので、素数ではないということになります。 ・なぜ2は素数なのか? なんとなく、2は偶数だから素数ではない気がしてしまいますが、2は素数です。 2は、「1」と「2」自身の2つの約数をもつ自然数なので、2は素数となります。 うっかりミスで、2が素数ではないと勘違いしないようにしましょう。 ・素数は無限にあるの? 素数は無限に存在します。 素数が無数に存在することの証明は、色々な方法でされています。 有名なのは、背理法によるユークリッドの証明です。こちらは紀元前に発見されたものです。 そのほかにも、フェルマー数を用いたゴールドバッハの証明や、2006年に発表されたサイダックの証明などがあります。 ・素数は何年生で学ぶ? 素数は、中学1年生で学びます。 現行の学習指導要領では、素数を1年において扱うことにより、 素因数分解を自然数、素数、倍数、約数、公倍数、公約数などと関連づけ、 整数の性質を探るひとつの道具として利用することができるとしています。 参考:文部科学省「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説」2017年 ▼文部科学省ホームページ 中学校学習指導要領解説:文部科学省 ・100までの素数リストは? 1~100までに、素数は 「 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97」があり、全部で25個あります。 下図の白い背景のマスが、素数です。 素数の面白い応用例 素数は、とても不思議な数字です。 身近でも、素数の面白い応用例や、素数に絡んだ不思議なことがたくさんあります。 インターネットの暗号に使われる素数 インターネット上の情報を守るのに「暗号化」という技術が使われていますが、この暗号化において素数が重要な役割を担っています。 とある文書があったとき、素数×素数のかけ算で文書に暗号をかけます。 第三者には、かけ算の結果が公開されています。 暗号を元の文書に戻すためには別の鍵が必要です。 この鍵を得るためには、自然数=素数×素数と、逆の計算をしなければいけません。 地道に計算するので、素数の桁が大きいほど大変です。 簡単な例で考えると、19×23のかけ算はひっ算を使えばすぐできるけど、437=19×23を逆の計算をするのは大変ですよね。 この作業は、コンピューターでも膨大な時間がかかるため、インターネットのセキュリティでは素数が重要な役割を担っているということです。 自然界の不思議:セミと素数の関係 素数ゼミとよばれるセミを聞いたことがあるでしょうか。 素数ゼミとは、生き残り戦略のために、13年、もしくは17年の間、地中にいるセミのことです。 それでは、なぜ素数である13年、もしくは17年の間、地中にいることが生き残り戦略となるのでしょうか。 その秘密は、最小公倍数にあります。 例えば、13年ゼミ周期で土の中から出てくる素数ゼミに、3年周期で発生する天敵がいたとします。 天敵が3年周期で発生していても、同じ年に13年周期ゼミが地上に出るのは、上の表のように39年経ったときのみです。 39は、13と3の最小公倍数です。13が素数であるため、3を約数に持たないことから、この最小公倍数が大きくなっています。 仮にセミの地上にいる期間が1年短い12年だとすると、地上に出れば毎回3年周期で発生している天敵がいるということになってしまいます。 セミの発生周期が素数であることは、その数自身しか約数がない自然数である素数を地上にでる周期にすることで、 天敵とできるだけ出会わないようにする、セミの生き残り戦略と考えることができます。 「わからないをわかるにかえる数学」 ここでPR! 今回解説した「素数」は中学1年生で学びます。 そんな中学生向けの中学生向けの超基礎シリーズが、こちらの『わからないをわかるにかえる』。 平易な言葉でイラスト豊富に解説し、問題量も多すぎないので学び直しにも活用できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「わからないをわかるにかえる高校入試数学」 人気の超基礎シリーズ「わからないをわかるにかえる」の高校入試対策版です。 中学3年間の内容を基礎からおさらいできます。 やさしい言葉遣いやイラストで、とっつきやすいのが特徴で、苦手な分野が多く、易しめから入りたい人はチェックしてみてください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「大人の教科書ワーク 数学」 日常の悩みや疑問を、小中学校の教科書で解決! それがこちらの『大人の教科書ワーク』です。 実は、今回の記事のなかで紹介した「インターネットの暗号に使われる素数」や「セミと素数の関係」について、 この『大人の教科書ワーク数学』ではさらに詳しく書かれています! この本では、このような数学にまつわる面白いトピックをたくさんとりあげています。 「大人の学び直し」がテーマの本ですが、小中学校の教科書で習う算数・数学の内容を用いながら、 日常のあらゆる疑問に答える形式になっているので、いままさに数学を学んでいる中学生が数学を学ぶ楽しさを知るのにもぴったりです! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ いかかでしたか。 今回の記事では、素数の定義から中学数学で押さえておきたいポイント、素数を応用した例までご紹介しました。 素数は数学の基礎であると同時に、どこか不思議な数字ですよね。 素数を通じて数学の魅力に触れ、ぜひ今の学びを深めてみてください!
教材出版社が教える!わかりやすい作文の書き方ガイド
書く機会は多いけど、なかなか慣れないもの… それが、作文です。 作文用紙の基本的なルールや、読みやすい作文にするためのテクニックを確認してみましょう。 もくじ 作文を書く前に知っておきたい基本ルール 作文のテーマ設定とアイデアの出し方 作文の構成を考える 実際に作文を書いてみよう 上手な作文をかくコツ 入試でも問われる作文力 まとめ 作文を書く前に知っておきたい基本ルール 原稿用紙を使うときには、次のような決まりがあります。 原稿用紙の使い方:タイトル・名前・段落のルール タイトルは1行目に、上から2~3マス空けて、書きましょう。 学年・組・名前は、二行目の下の方に書きます。組と名前の間・名前の下は、1マス空けます。 本文の書きだし・段落の初めは、1マス空けます。 句読点やかぎかっこの正しい使い方 句点・読点について句点や読点は、1マス使って書きます。 間違えやすいポイントとして、行の最初に持ってくることはできません。行の最後に来てしまった場合は、行末のマスに文字と一緒に入れることができます。 かぎかっこについて会話文は改行して、「」を使って書きます。「と」は、それぞれ1マス使います。会話文の終わりの句点と」は、1マスで書きます。これも、行の頭にきてしまう場合は、前の行の最後のマスに入れます。 文体の統一:です・ます調とだ・である調 作文を書くときには、2パターンの文体が考えられます。 です・ます調例) 私はこの夏休み、家族と水族館に行きました。水族館では、イワシの大群や、イルカのショーを見ました。お土産に買ったイルカのぬいぐるみは、私の大切な宝物です。 だ・である調例)私はこの夏休み、家族と水族館に行った。水族館では、イワシの大群や、イルカのショーを見た。お土産に買ったイルカのぬいぐるみは、私の大切な宝物だ。 この2つは、1つの作文の中で混在させず、どちらかにそろえて書きます。そうすることで、読みやすい文章にすることができます。 作文のテーマ設定とアイデアの出し方 興味を持てるテーマを選ぼう 作文で重要なのは、書きやすいテーマにすることです。 書きやすいテーマとは、たとえば ・自分が普段から親しみ、よく知っているもの ・感情が大きく動いた経験がある出来事 などです。 どちらにせよ、文字をたくさん書くのは結構忍耐が要りますので、 なるべく自分が興味を持っていて、書きたいと思えることがあるテーマを選ぶのがよいです。 書き出してアイデアを広げる テーマは決めたものの、何から手を付ければ… そんなときには、こんな手法を試してみましょう。 テーマが「学校行事」だとします。 ステップ1 紙とペンを用意します。ステップ2 「学校行事」と聞いて思いつくものを、どんどん書いていきます。ステップ3 書きだした項目から線を引っぱり、思い出したエピソードや感情を書きだしていきます。ステップ4 書き出した内容のうち、作文にできそうなものを選びます。 ポイントは、「考える前に書く」です。「こんなこと書いていいのかな?」と心配せず、自由に思いつくままに書き出しましょう。 出したアイデアを整理する よく覚えているもの、たくさん書けそうなものを選んだら、書きだした事柄同士のつながりや、新たに思い出したことを整理して、大まかにどんなことを言いたいか、を考えます。 修学旅行 ・班行動では、計画を立てるときにもめた。 →きちんと計画を立てたいのに、意見がまとまらず怒ってしまった。・計画通りいかなかった →当日は、道が混んでいて計画通りいかず、行ける場所が減ってしまった。 せっかく計画を立てたのに、とても焦った気持ちになった。・でも楽しかった →ガイドさんが提案してくれた小さい神社に行き、アイスも食べた。 →ガイドさんの説明が面白くて、友達とのおしゃべりも楽しかった。 →アイスは修学旅行で食べた中で一番おいしかった。 →計画通りいかなかったことは全然気にならなくなった。 ・予定通りいかなくても、臨機応変に切り替えて、楽しい時間を過ごすことが できると学んだ。 作文の構成を考える わかりやすい作文を書くには、いくつかの型を意識するとよいです。 基本構成①:序論・本論・結論型 全体を3つのまとまりに分けて書きます。 序論 文章の書き出しの部分。これから書こうとする話題や問題を示す。 本論 文章の中心となる部分。具体例や、それに基づいた自分の意見を述べる。 結論 自分がもっとも言いたいことを示す部分。本論をまとめて、最終的な自分の主張を書く。 基本構成②:起承転結型 全体を4つのまとまりに分けて書きます。 起 文章の書き出しの部分。これから書こうとする話題や問題を示す。 承 文章の中心となる部分。具体例や、それに基づいた自分の意見を述べる。 転 承の部分を受けて考察を進める。承の部分と対立する意見を示したり、ほかの可能性を示したりしてもよい。 結 じぶん自分がもっとも言いたいことを示す部分。承・転の部分をまとめて、最終的な自分の主張を書く。 実際に作文を書いてみよう 下書きからスタート いきなり「私は…」と書き始めると、途中でうまく繋げられなくなったり、決めた構成が崩れて読みにくくなってしまう可能性が高いです。 まず全体の下書きをしてみましょう。 序論、本論、結論、または、起承転結で分けてそれぞれの項目に書く内容をざっくり書いてみます。 起:修学旅行で一番の思い出は、班行動。 承:班行動は計画段階でもめて不安だったうえ、当日計画通りいかずに焦った。 転:ところが、臨機応変な対応で、楽しい時間を過ごすことができた。 結:予定通りいかなくても、臨機応変に切り替えて、楽しい時間を過ごすことができると学んだ。 文法や表現を気にせず書く 大まかな流れがわかったら、それぞれのパートを肉付けするつもりで書きだします。 まずは完ぺきを目指さず、どんどん書いてみましょう。 書きながら、新しい情報を思い出すこともあります。 そういった情報も自由に付け加えていってみてください。 推敲する 一度書き切ってみた後で、全体を読み直します。 このとき、作文用紙のルールが守れているか、文末表現や接続詞がおかしくなっていないか、 また、下書きで決めた大まかな流れと、「この作文で何を言いたいか」がぶれていないか、を確認します。 少し面倒ですが、この作業を行うことで読みやすさが格段に変わるでしょう。 上手な作文をかくコツ 読者を引き込む面白い導入の作り方 書き出しをちょっと工夫するだけで、先を読みたくなる作文にすることができます。 いくつかテクニックがあるので、一部ご紹介します。 質問形式で始める あなたは最近、心に残る出来事がありましたか? こう聞かれたら、どうでしょうか。 どんな話が始まるのだろう、という気持ちになりますね。 読む人に自分に当てはめて考えてもらうことで、より身近な話題として読んでもらえる効果もあります。 驚きの事実やデータを提示する 日本人が1年間で使う紙の量は、一人あたり約210kgだと言われています。 はじめに、えっ!と思うような驚きの事実を提示するやり方です。 知らなかった!と思える内容であったり、予想を裏切るインパクトのある数字であったりすると、効果が高いです。 自分の体験やエピソードを語る 初めて作文コンクールに挑戦したとき、緊張で手が震えていたことを今でも覚えています。 実体験に基づく言葉は、それだけで説得力があります。 上記の例では、「緊張していた」ではなく、「緊張で手が震えていた」とすることで、よりリアルな場面が想像できるようになっています。 名言やことわざを引用する 「失敗は成功のもと」という言葉がありますが、実はこの言葉が私の作文を書く際の大きな助けになっています。 インパクトのある内容で始められないケースでも、名言やことわざの引用をすることで、印象的な導入となります。 名言を引用する場合、著作権がある場合があるため、注意しましょう。 意外性のある内容で引き込む 作文は嫌いだと思っていました。でも、ある日突然、楽しいと思うようになったのです。 読む人が、「え!どうして??」と思うような内容から始めることで、先を読みたくなるようにします。 「○○と思っていた。でも[しかし/だが/ところが]、○○だった」のように、逆説の接続詞でつないでみましょう。 読みやすい文章を作る語彙の選び方 次の文章を読んで、どのように感じますか? 合唱コンクールに向けて、ぼくたちはすごく練習をしました。すごく早い時間から朝練をし、授業が終わった後も遅くまで練習をしました。結果は、2位でした。すごく悔しかったけど、優勝したクラスの合唱はすごくきれいだったので、すごいと思いました。来年の合唱コンクールでは、今年よりもすごい合唱をするぞ!と思いました。今からすごく楽しみです。 これを、このように変えてみます。 合唱コンクールに向けて、ぼくたちはすごく一生懸命練習したと思います。朝は早い時間から、授業が終わった後も遅くまで、練習を重ねました。結果は、2位でした。すごく悔しかったけど、優勝したクラスの合唱はとてもきれいで、彼らもたくさん練習をしたんだな、と思いました。来年の合唱コンクールでは、今年よりも素晴らしい合唱をするぞ!と心に決めています。今からすごく楽しみです。 少し読みやすくなった気がしませんか? 1つ目の文章では「すごく」という表現がたくさん出てきます。 「とても」「練習を重ねた」「素晴らしい」など別の表現に置きかえると、少し読みやすくなります。 「すごく」の中身がより具体的になるので、共感も得やすいです。 「すごいと思った」という部分も、どうすごいと思ったのか?と書き替えてみました。 また、同じ文章の終わり方(この場合は、「ました」)が続くと、それも読みにくさの一因になります。文末表現も少しバリエーションが出るように考えてみるとそれだけで作文のレベルが上がります。 むずかしく感じるかもしれませんが、 1)辞書を引いて、同じ意味で違う表現がないか探してみる 2)より具体的に気持ちを説明できないか考えてみる をまず意識するといいかもしれません。 入試でも問われる作文力 さて、作文といえば文集や読書感想文など、学校の課題として出ることが多いですが… 高校入試でも、短い課題作文や条件作文、資料を読み取ってまとめる作文などが出題されることがあります。 「完全攻略 高校入試3年間の総仕上げ 国語」では、 入試で出される作文について要点をまとめ、例題を出題している単元があります。 ▼ 入試の作文は普段の作文よりも文字数や時間が少ない中でまとめる必要があり、別途対策しておくことが重要です!今日学んだことを基本にしつつ、色々な問題に触れてみてください。 「完全攻略 高校入試3年間の総仕上げ 国語」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 作文を書くのは、難しいものです。 なぜ書かないといけないのか?と思うことも多いかもしれません。 作文を書くことで、どんな力が身につくのでしょうか。 作文では、「どうすれば読みやすくなるか」「どうすれば読みたくなるか」を考えて書くことが必要になります。 また、枚数や字数に制限があれば、その文字の中でうまく情報を伝える工夫もしなければなりません。 そういう作業を通して、自分の考えや気持ちを整理して他者に伝える力がつきます。 このような力は「書く」ときだけでなく「話す」ときにも役立ちます。 いつか大人になったとき、仕事で、社会生活で、必ず役に立つ時が来るはずです。