夏は受験の天王山!「天王山」って何? 夏のギモン5選
暑い日々が続きますね!
夏は受験の天王山!!!
とよく言われます。
受験生の皆さんは、勉強はかどっているでしょうか?
ところで…
「天王山」って、何か知っていますか?
今日は、夏にまつわる、ちょっとしたギモンを5つ取り上げます!
夏は受験の天王山!「天王山」って何?
「天王山」は、「てんのうざん」と読みます。
どういう意味でしょうか?
天王山とはとても高い山のことで、登るのが大変だけど重要という意味……
ということではありません。
天王山は京都にある山のことで、本能寺の変のあと、明智光秀と羽柴秀吉が戦った場所です。
明智光秀は織田信長の家臣でしたが、信長を裏切ります。
信長は京都の本能寺で命を落とすことになりました。これが本能寺の変です。
同じく信長の家臣であった羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)が、敵討ちのため京都へ進軍。
光秀は京都で迎え撃ちます。
2人の戦いは秀吉の勝利で終わり、その後秀吉が天下統一を果たすわけですが…
その中で、「秀吉が先に天王山を占拠したこと」が、勝敗の大きな分かれ目となったといわれています。
このことから、「勝敗の分かれ目」「ここ一番の大勝負」といったときに、「天王山」という言葉を使うようになりました。
つまり、夏休みを制する者が受験を制する、夏休みが結果に大きく影響する重要な時期、ということですね。
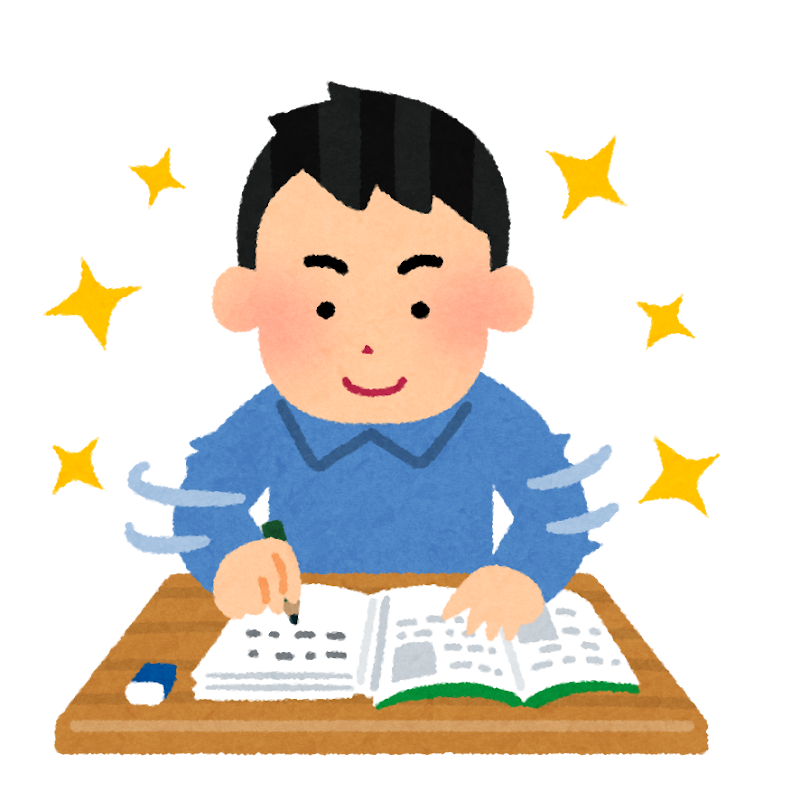
暑い日に、道路がゆらゆらして見えるのはなぜ?
「暑い暑い」と言いながら、家に帰っているとき…
道路の上のあたりが、ゆらゆらして見えることはありませんか?
これは、「シュリーレン現象」と呼ばれる現象です。
強い日差しでアスファルトが温まると、地面に近い空気が温められて、膨張します。
膨張すると、空気の密度が低くなり、密度の高い空気がある方に上昇していきます。
密度が異なると、光の屈折率…曲がり方、が変わってきます。
密度の異なる空気が混ざり合うことで光の屈折が様々な方向に起こり、それがゆらぎとして目に見えているのです。
この空気のゆらぎは、「陽炎(かげろう)」とも呼ばれます。かっこいいですね。
なお、シュリーレン現象は空気中だけで起こるものではなく、水に食塩や砂糖などを溶かすときにも見ることができます。

どうして花火大会は夏に多いの?
花火大会はとても楽しいけど、蒸し暑いし人も多くて大変…
どうして夏にやることが多いのでしょうか。
諸説ありますが、一説としては、
「もともとは、江戸時代に行われていた慰霊祭が起源だから」というものがあります。
江戸時代、飢饉や疫病の流行で多数死者が出たことを受け、隅田川の川開きの日に慰霊のための水神祭が開かれました。
そこで打ち上げ花火が上げられたことをきっかけに、隅田川の川開きの際に打ち上げ花火を上げることが恒例行事となり、全国に広まった、という説です。
「花火と言えば夏」と漠然と思っていましたが、こんな始まりがあったんですね。
教科書に載っている「江戸時代」は、現代とつながっているんだな、と実感できます。

かき氷っていつからあるの?
みなさんは今年、かき氷食べましたか?
私はまだです。
最近はふわっふわでクリームたっぷり、ケーキのようなかき氷なんかもありますが、
かき氷っていつごろから食べられているのでしょうか。
原型となるものは、少なくとも平安時代には食べられていたことが分かっています。
教科書にも載っている、清少納言の『枕草子』の中には…
削り氷に甘葛(あまずら)入れて、あたらしき鋺(かなまり)に入れたる
という文があります。
天葛はシロップのようなものです。
つまり、「削った氷にシロップをかけて、あたらしい金属のお椀に入れたもの」ということになります。
完全に“かき氷”ですね。
当時は冷凍庫もありませんから、氷は貴重なものでした。
限られた人だけが食べられる、高級スイーツだったんですね。
今では、だれでも気軽にかき氷を食べられるようになりました。
「清少納言も食べたんだな」と思うと、これまた味わい深くなりそうです。

夏休みにドリルがおすすめなのはなぜ?
さて、最後のギモンです。
「夏休みに自分でドリルを用意して取り組む」
これって必要なのでしょうか?
結論から言うと、おすすめ!です。
その理由は2つあります。
1)休み中の学習習慣を維持するため
2)授業が進まない間に、苦手を克服するため
1)休み中の学習習慣を維持するため
休み明け、突然毎日授業がある生活に戻るのは大変なもの。
「毎日少しでも机に向かう習慣」は、なるべくつけておいた方が安心です。
(短くてもOK)
手軽なドリル、楽しく取り組めるドリルを買って、ちょこっとずつ取り組むのはいかがでしょうか。
たとえば…
教科書ドリル

おかしなドリル

2)授業が進まない間に、苦手を克服するため
毎日授業で新しい知識を覚える中で、復習を並行して行うのは意外と大変…
長い休みは、絶好のチャンスです!
分野に特化したドリルや、ざっと全体をさらって苦手を見つけられるドリルを使って、
休み中に苦手をつぶし、2学期に向けた土台を作りましょう。
たとえば…
できるがふえるドリル
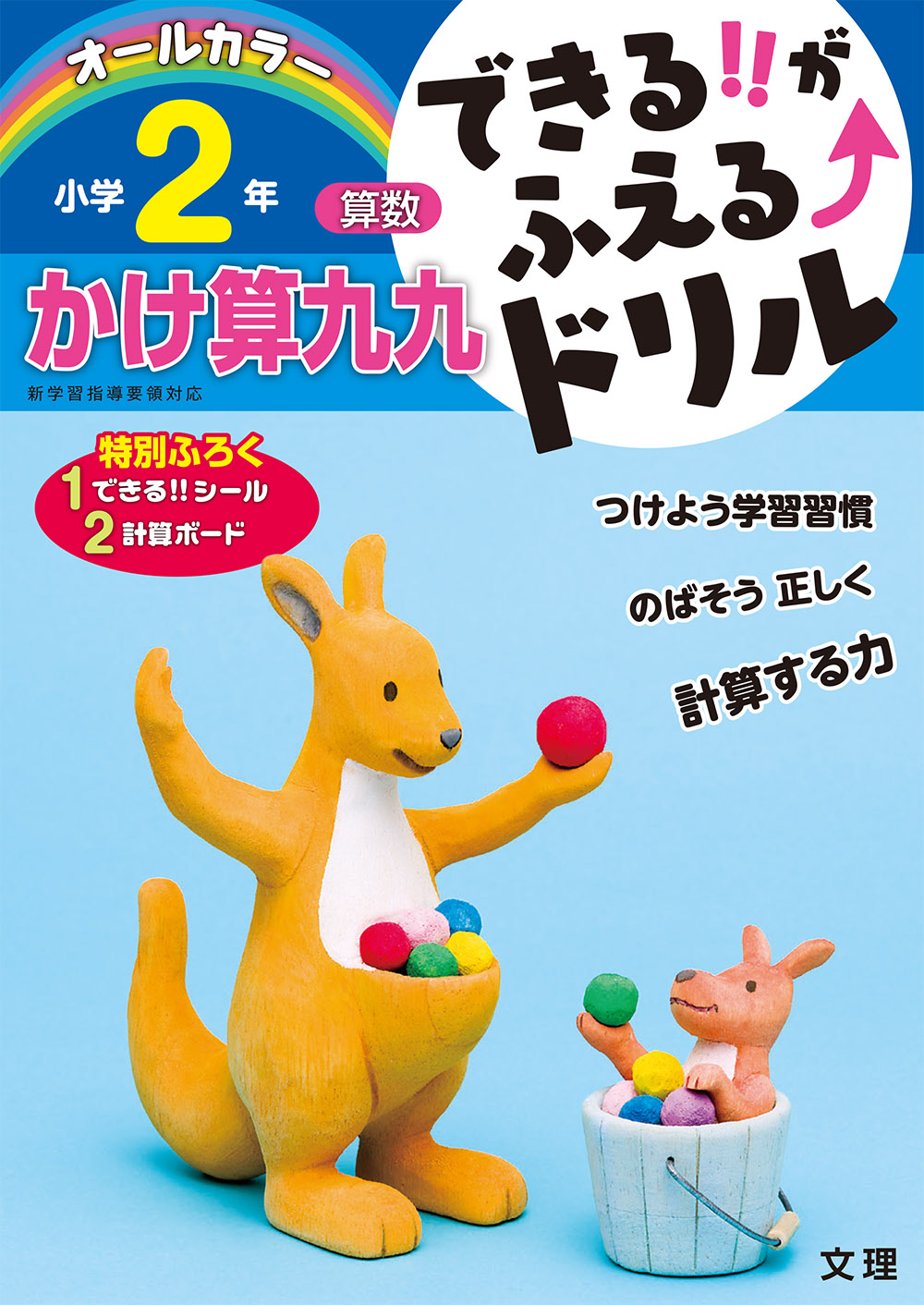
全科まとめて

おわりに
夏のちょっとした疑問について、取り上げてみました。
知ると、「なるほど!」となることばかりで、楽しいですね。
普段の生活の中で、ふと思ったことがあれば、ぜひ調べてみてください。
自由研究の糸口なんかも、見つかるかもしれません。
◆◇今回の執筆者◆◇
イニシャル:M.I.
所属:営業部門
年齢:20代
今回のひとこと:
かき氷食べたいです。




