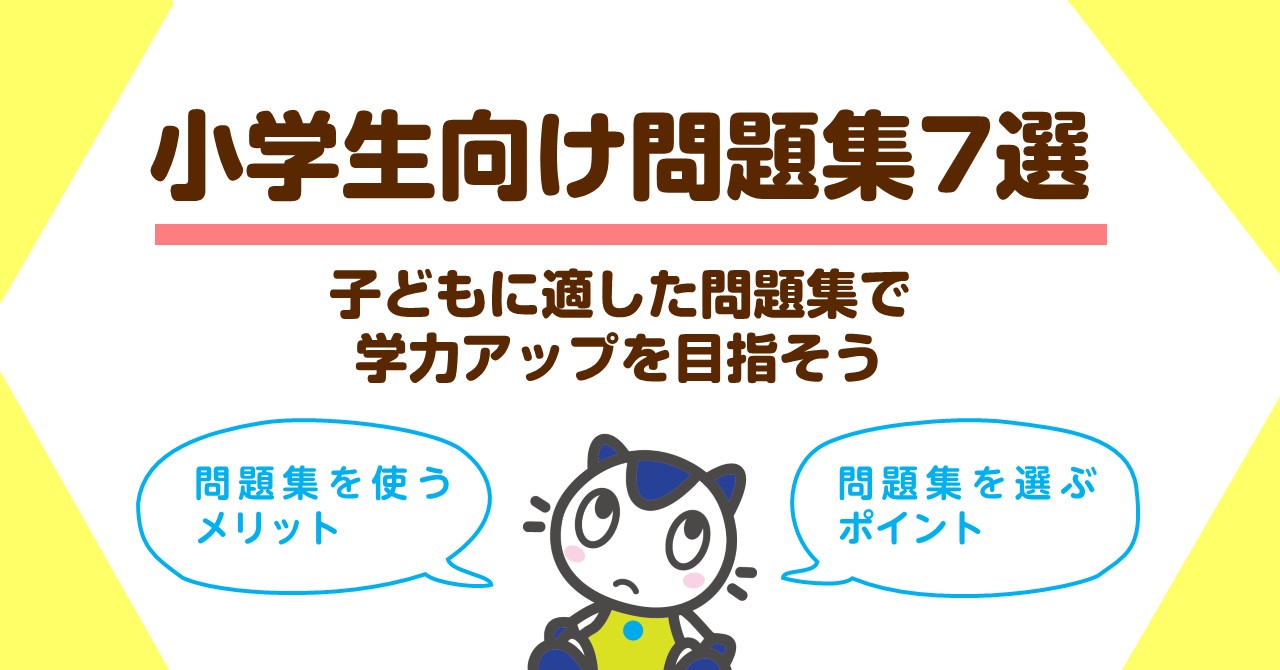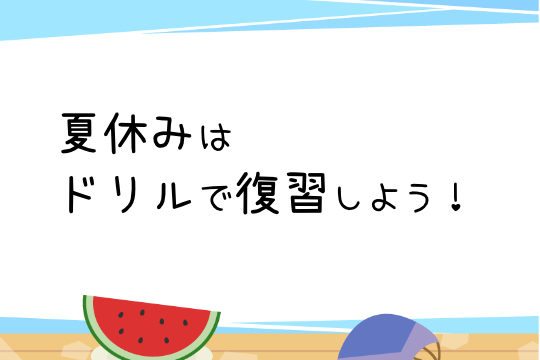なるほど!Bunri‐LOG
対象
「ワーク」と「ドリル」のちがいって? ちがいを知って使い分けよう
はじめに 「ワーク」と「ドリル」って、問題集の種類?、どちらも「勉強に使うもの」ですが、実は少し性格がちがいます。 それぞれの特徴や目的を理解することで、自分に合った勉強法を見つけることができます。 この記事では、特に小学生向けに、「ドリル」と「ワーク」のちがいを説明してみたいと思います。 また、保護者の方にも家庭学習に役立つ情報をお届けしますので、一緒に読んで、子どもたちの学びをサポートしていきましょう。 「ドリル」とは? ドリルの目的と特徴 ドリルはくりかえし練習でできるようになるのが目的です。具体的には、漢字ドリルや計算ドリルなどが代表的な例ですね。 ドリルは、例題や解説が最小限で作りはシンプル。同じ問題や似た問題を何度も解くことで、知識や技能をしっかりと定着させることを目指しています。 「毎日少しずつやると力がつく」という点が、ドリルの魅力です。 たとえば、毎日10分間だけでも漢字の書き取りを続けることで、自然と漢字が身についていきます。 これにより、学ぶ楽しさを感じながら、少しずつ成長していくことができるのです。 また、サイズが小さくて、天とじ(本の上部でとじられている)、価格的に安価なものが多いかもしれません。 どんなときにおすすめ? ドリルは、くりかえして知識を定着させたい人や、まちがえやすいところをなおしたいときにピッタリです。 特に、基礎をしっかり固めたい小学生にとって、ドリルを使った学習は非常に効果的です。 反復することで自信がつき、次のステップに進む準備が整います。 「ワーク」とは? ワークの目的と特徴 ワークには、例題や解説もあったり、基礎的な問題から応用問題まで幅広く含まれていますので、「いろいろな問題に挑戦して、考える力をのばす」のが目的といえるでしょう。 特に難易度が少し高めの問題に挑戦することができるのも特徴です。 「ちょっとむずかしいけど、おもしろい!」と感じられる内容が多く、考える楽しさや達成感を味わうことができます。 ワークを通じて、問題解決能力や論理的思考力を養うことができるため、将来的にも役立つ力を身につけることができるかもしれません。 どんなときにおすすめ? ワークは、例題や解説を見たり、問題を解きながら理解を深めたいときや、考えるのが好きな人にピッタリです。特に、いろんな問題に挑戦したい子どもには最適です。 ワークを使うことで、子どもたちは自分の考えを整理し、より深い理解を得ることができるでしょう。 「ドリル」と「ワーク」を比べてみよう ・ちがいをチェック! どっちをやればいい?使い分けのコツ 教科やレベルにあわせて使い分けることが大切です。 たとえば、基礎を固めるためにはドリルを利用し、その後にワークで応用力を養うという方法が効果的です。 「どっちを買えばいい?」という保護者の方のお悩みもあると思います。 上記の特徴をふまえ、ドリル、ワークそれぞれの特徴を生かし、お子さんがどちらが合うかを見極め、優先して使い分けるのはいかがでしょう。 ドリル中心で学ぶ 漢字の書き取りや計算など、くりかえし学ぶことで基礎を定着させる 1回10分など、毎日コツコツ取り組むことで、学習習慣をつける 苦手の発見と克服に役立つ 紙面例)小学教科書ドリル 国語 ワーク中心で学ぶ 授業の予習や復習に活用でき、理解を深める テスト勉強にも適しており、実践的な力を養う 基礎から応用まで、幅広い力をつけたいときに最適 紙面例)小学教科書ワーク 国語 ドリル+ワークの両方で学ぶ 両方を組み合わせることで、より効果的に学習を進めることができます。基礎を固めた後に応用問題に挑戦することで、バランスよく、学びの幅が広がります。 【保護者向け】家庭学習でワークとドリルをどう使い分ければいい? ドリルとワークは「役割」がちがう ここまでみてくると、やはり、ワークとドリルの役割はちがうようです。 ドリルは反復練習を通じて「基礎固め」を行い、ワークは基礎から応用までの多様な問題を通じて「考える力」を育てるためのものです。 どちらか一方だけでは不十分であり、セットで使うことが効果的です。 子どもの性格によっても選び方を変えよう コツコツ型→ドリル向き 好奇心旺盛→ワーク向き 苦手克服にはまずドリル、得意強化にはワーク 保護者のかたはご自分のお子さんの性格は把握されていると思いますので、その子のタイプによって、選んでみてもいいかもしれません。 じっくりコツコツやる子なので、ドリルで繰り返し学習させてみようかな、とか、ある程度、基礎はできているから、ワークでいろんな問題をやらせてみようかな、とか、「うちの子にはこっちが合いそう」という子どもの性格や学習スタイルに応じた選び方もいいいです。それによって、より効果的な学習が促進されます。 教科書に沿ったワーク&ドリル【2025年最新版】 ・小学教科書ワーク 教科書に完全対応した教科書準拠版ワークです。 (くわしくは、下の「▶シリーズページはこちら」へ) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・小学教科書ドリル 1回10分のオールカラーのB5判ドリルです。算数・国語は教科書準拠版。B5判の小さめサイズです。 (くわしくは、下の「▶シリーズページはこちら」へ) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 教科別!おすすめのワーク・ドリル教材【2025年最新版】 国語編:漢字 上記、教科書ワークと教科書ドリルシリーズにも、「漢字」があります。 算数編:計算・文章題・図形 算数の基礎を固めるための「計算」や、「文章題」も、教科書ドリル、教科書ワークシリーズの中にあります。「図形」問題の教材もおすすめです。 英語・理科・社会(中・高学年向け) 中高学年向けの英語は教科書ワークがあり、理科、社会には教科書ドリル、教科書ワークがあります。 教科書ワークは、全131点もの種類があります。 教科書ドリルは、全77点! 国語、算数、社会、理科、数と計算、文章題・図形などなど・・・ 一部、抜粋してご紹介しましたが、 教科書ワーク、教科書ドリルともに、くわしくは、上記のそれぞれの「▶シリーズページはこちら」のアイコンをクリックしてみて、 ぜひ検討してみてください。 (その他のシリーズもあります!こちらを参照してください) また、書店さんで手に取ってみると、よりちがいがわかりやすいかもしれません。 書店さんにも足を運んで実物を見てみてください! まとめ ドリルとワーク、それぞれ目的やちがいがありました。その種類によって、自分に合ったやり方を見つけて、楽しく勉強することはできそうです。 ただ、ドリルだけやればカンペキ、ワークをやっておけばすべてOKというわけではありません。 それぞれの問題集の特徴を把握し、お子さんがワークでいろんな問題を解いたけど、ドリルで苦手分野をくり返しやってみたい、となるよう、 保護者の方がそれぞれの問題集の特徴を教えてあげるといいかもしれません。 学ぶことは楽しい経験であり、子どもたちが「どっちもやってみたい!」と思えるよう。子どもたちの成長を見守りながら、効果的な学習をサポートしていきましょう。
土用の丑の日とは?おいしいものを食べて夏バテ対策!
いよいよ夏休み! 例年以上に暑く感じる夏!夏休みが始まったご家庭も多いかと思います。 いかがお過ごしでしょうか? 最近、スーパーに行くと「土用の丑の日」という広告を見たり、たくさんうなぎが並んでいるのを目にしたりしますね。 「土用の丑の日」、あまり聞きなれない言葉です。どのような意味なのでしょうか? 土用の丑の日とは? 「土用」とは、季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間を指します。 丁度現在は立夏の直前の約18日間の「土用の期間」となります。 「丑の日」とは、十二支「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥(ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い)」のうち 「丑(うし)」の日を指します。 十二支は一年の始まりに意識しますね。 今年は「辰(たつ)」の年ですが、実は十二支は年を表すだけでなく、月や日を表すことも多く現在でも運勢占いなどに使われているのです! 2024年の土用の丑の日は1月26日、4月19日、5月1日、7月24日、8月5日、10月28日であり、 現在は立夏の直前の7月24日、8月5日に夏ならではのうなぎなどのおいしい食材がたくさん並んでいるのです! 季節の変わり目ということで、昔から体の疲れやすい時期だったのかもしれません。 全力で夏を楽しむために、あえて栄養のあるものをたくさん食べてゆっくりする時間をつくってみましょう♪ なにを食べるの? 「丑(うし)の日」ということで、うなぎ以外でも“う”で始まる食べ物を食べると良いという風習があります。ダジャレですね。 うどん、ウリ(きゅうりなど)、牛、馬…など、 暑いなかでも食べやすいものや栄養をつけられる「う」からはじまる食材はうなぎ以外にもたくさん! スーパーへ行って探してみましょう。 特に、梅干しがおすすめです。酸っぱい梅干しは、栄養もたくさんで元気がでます! 特にお手製の梅干しを作る方は、5月~6月に梅を買って、梅酢に漬け込み土用の丑の日前後のかんかん照りが3日以上続く日に梅を干し、梅干しが完成します。 夏に梅干しを食べるのが待ち遠しいです! 元気が出てきたら遊びも勉強も全力で! たくさん時間があるのは、夏休みならでは。栄養を摂って、遊びや夏休みの宿題、自主学習をがんばりましょう♪ 夏休みにおすすめの学習参考書をご紹介します。 ①全科まとめて この一冊で、全教科をしっかり復習。 夏休みも毎日積み重ねが大切な学習を続ける習慣を忘れないようにしましょう! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ②わからないをわかるにかえる英検5級 9月には第二回試験の申し込みが締め切られ、10月に試験が実施されます。 時間がある夏休み。英語も目標を決めて学習をはじめてみませんか? ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ③教科書ワーク お通いの学校で使っている教科書に沿って学習できます! 得意教科もニガテ教科も、復習はもちろん予習も進めて、万全の状態で新学期のスタートを切りましょう! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
ドリル選びのすすめ【2024年春版】
ようやくあたたかくなってきました。 春休みになり、そろそろドリルを探さないと…という方も多いのではないでしょうか。 2022年にもドリル選びの記事を書きましたが、 あれから新しいシリーズも刊行されました。 そこで、今回は2024年版ドリル選びのすすめをお届けします! 2022年版はこちら▼ さて、前回と同じ導入にはなりますが、 みなさんは書店に所狭しと並ぶドリルを見て いったい何がちがうのだろうか? そう思うことはございませんか? 今日は、文理で作っているドリルについて、そのちがいをご紹介していきます! 他社のドリルを見る際にも、参考になれば幸いです。 ※「ドリル」について 本記事では、図のような綴じ方のドリルについて扱います。 ドリル選びのすすめ ドリルを選ぶときは、まず目的を意識! 毎日短時間さっと取り組む習慣をつけたい! →小さいサイズのA5判ドリルがおすすめ! カラーかそうでないかなど、お子さまの好みに合わせて決めましょう! 文理のドリルなら ▶教科書ドリル 苦手分野の克服を、負担軽めにやりたい! →B5サイズくらいのドリルがおすすめ。 多くの場合冒頭に特長がまとめてあるので、そこを見比べてみてください! キャラクターものも結構あったりします。 お子さまが興味を持てそうなものを、一緒に選ぶといいかもしれません。 文理のドリルなら ▶できるがふえるドリル ▶おかしなドリル 手軽に前の学年の総復習がしたい! →「全科」と名のついたドリルがおすすめ! 全教科が1冊にまとまっています。 問題の量や色づかいなどを見比べて選んでみてください。 普通のドリルよりも単元の分け方がざっくりしているため、進行中の授業に合わせて使うと 習っていない内容が混ざってしまうことも。 復習に特におすすめです。 文理のドリルなら ▶全科まとめて ハイレベルな問題を解きたい! →まずタイトルに「ハイ」や「トップ」が入っているものを探しましょう! ただし、少し力試し…で挑むと難しすぎるものもあるので、 実際に紙面を見る、レビューを見る、などで確認してみてください! 文理のドリルなら ▶ハイレベル算数ドリル 教科書ドリルは1回10分! 学習習慣づけに 教科書ドリルはこの春に改訂し、表紙が新しくなりました! ★小学校の教科書改訂 2024年度は、指導要領の改訂はありませんが、 教科書の改訂がありました。そのため教科書準拠シリーズは 改訂版が発売となります。ご注意ください。 2024年度の小学教科書準拠シリーズ改訂につきまして 教科書ドリルは、A5サイズの小さいドリル。 1回あたり10分程度で終わる分量になっており、 毎日さっとドリルに取り組む習慣をつけたい、というときにおすすめです! ※小さい紙面で、書く欄は少し小さめ。 国語と算数は、教科書準拠版をご用意! より学校の授業の進度に合わせた学習がしやすくなっています。 「教科書ワーク」との併用もおすすめです! 例)ワークで勉強したことを、教科書ドリルでさらに反復。 例)算数の「教科書ワーク」と、算数分野別の「教科書ドリル」を併用。 気になるお値段は、各605円(税込)! ラインナップはシリーズページをご確認ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 楽しい工夫たくさん! 弱点克服にB5サイズドリル 教科書ドリルが「1回10分、問題をこなして定着させる」のに対して、 「少し勉強が苦手で、楽しく取り組める工夫が欲しい」ときにおすすめです。 できるがふえるドリル 2023年には理科も登場! オールカラーで見やすい分野別ドリルです。 ▲楽しく取り組める工夫が随所に。 取り組む時間は、自分で書きこみます。 時間を意識して取り組むことで、集中力もUP! はぎとれるのもうれしいポイントですね! お値段は、各704~880円(税込)。 ラインナップはシリーズページをご確認ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら おかしなドリル 2023年春に新登場! 株式会社 明治とコラボした、おかしがたくさんのドリルです。 紙面にもお菓子がたくさん登場。 勉強だけではなく、お菓子に関するコラムやレシピが書いてあるお楽しみページもあり、 算数が苦手な子でも楽しく始められます。 シールが貼れるのもいいですね! お値段は1,045円(税込)。 ラインナップはシリーズページをご確認ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 全教科を薄く広く、は全科まとめて ※「全科まとめて」は2025年度に改訂しました。下記は旧版についての情報です。改訂版についてはこちら。 「全科まとめて」の裏表紙ですべて説明されているので、見てみましょう。 ということで、 〇何冊も買わなくていい 〇短期間で終えられる 〇カラフルで分かりやすい 〇1枚ずつ切り取って使える 〇英語は聞く練習もできる それが「全科まとめて」です! 目次を見てみると、1冊の中に全教科の学習内容がつまっているのがわかります。 切りはなして、1回分取り組んだら…… 裏面には単元の復習や調べてみたことなどを自由に書けます! 問題は片面だけなので、問題量がほしい!と思って購入されると物足りなく感じるかもしれません。 逆に「1回の分量が多いと最後までやりきれない」という場合は、さくさく達成感が得られるのでおすすめです! 全科ドリルは他社からも何種類か出ていて、「問題の量」「色づかい」「イラスト」「解説の量」などに それぞれ個性があります! ぜひ比較して、目的に合ったものを選んでみてください! さらっと全体をおさらいしたいというときは、5教科それぞれでドリルを買うよりお得かもしれません。 ※「全科まとめて」は2025年春に改訂しました。 改訂版の詳細はこちらの記事をご覧ください。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 算数が得意で、もっとやりたいキミに… 最後はかなり個性的! ハイレベル算数ドリルは、算数でイチバンをめざす小学生におすすめです! 表紙は大変かわいらしいですが…… タイトルに偽りなく、かなりのハイレベル問題になっています。 学校の勉強では物足りず、もっと力をのばしたいときにはとてもよいです! 逆に、苦手の克服や復習用にはあまり向いていないのでご注意ください。 紙面はオールカラーで、ハイレベルな教材の中では、とっつきやすいデザインです。 難点は、問題をたくさん入れた結果、計算スペースが少ないところです…… 計算用の紙などを別で用意していただくと、さらに取り組みやすいです! 地味にすごいのが「学力診断テスト!」 最後に収録されている「そうしあげテスト」に取り組んで、 大設問ごとの得点を文理HPに入力すると…… 学習診断の結果を見ることができます! 大設問ごとに、正解数に応じたアドバイスを得ることができます。 (今回は全問正解と入力しましたが、それでも声かけしてくれます) お値段は各1,298円(税込)です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら おわりに ドリルを選ぶときは、まず目的を意識! 毎日短時間さっと取り組む習慣をつけたい! →小さいサイズのA5判ドリルがおすすめ! 苦手分野の克服を、負担軽めにやりたい! →B5サイズくらいのドリルがおすすめ。 手軽に前の学年の総復習がしたい! →「全科」と名のついたドリルがおすすめ! ハイレベルな問題を解きたい! →まずタイトルに「ハイ」や「トップ」が入っているものを探しましょう! あとは実際の紙面を確認して、実際の字の大きさやイラストの量などが お子様に合うかどうかを確認してみてください!
バレンタインは「おかしなドリル」で楽しもう♪
今日はバレンタインの日ですね! 大切なお友だちやご家族と、チョコレートを作って食べましたか?とびきりおいしいチョコレートを買った方もいるかもしれませんね。 1年のなかでもとっても楽しみな日のうちの1日、バレンタイン。 「おかしなドリル」でもっとバレンタインを楽しみましょう! 「おかしなドリル」とは? 文理と明治がコラボした小学生低学年向けの算数ドリルです! 「普通のドリルでは子どもの集中力が続かない」 「ニガテな算数に進んで取り組むきっかけがほしい」 そんな声にお応えして、多くの人に愛される「おかし」に着目したドリルが誕生しました! おかしにこだわりました! 表紙・裏表紙はおかしのパッケージにそっくり! 算数の問題にも、たくさんおかしが登場します。 切り取り式なので、学童に自習学習用として持って行ったり、家庭学習の習慣付けに使ったりするのにもおすすめです。 お楽しみ要素もたくさん! ドリルの間にある「チョコっとまめちしき」や「チョコっとひとやすみ」では、食育関連のテーマやおかしのアレンジレシピなど、幅広いコンテンツを掲載。 楽しく知識の幅を広げることができます。 モチベーションを高める付録つき単元ごとにシールを貼っていく達成表や、学習テーマに沿った算数ボードの付録付き!工作ができるペーパークラフトも付いています。 付録を活用しながら1冊全部、やる気を持った状態で進めることができるので、お子さまの自信になります! レシピでおかしを作ってみよう 今日はバレンタイン♪ということで、「おかしなドリル おかしなドリル 2年 たし算・ひき算」に掲載されているレシピを作ってみましょう! とろけるキャラメルファッジ 材料 明治エッセルスーバーカップ(バニラ)⋯4〜5個 <キャラメルソース> 砂糖…80g 生クリーム…100ml 水…25 ml <デコレーション> アボロ…適量 ミントの葉…適量 〇道具〇 電子レンジ、手鍋、ボウル、ヘラ <作り方> ①手鍋に砂糖と水を入れて、中火にかけます。 ②5〜6分煮詰めてあめ色になったら弱火にして、 ③電子レンジで温めた(500Wで20秒程度)生クリームを, 少しずつ加えて混ぜながらキャラメルソースに仕上げます。 ④②の粗熱が取れたらボウルに氷水を入れ、手鍋の底を当ててぽってりしたかたさになるまでへラで混ぜます。 ⑤トッピングを加えて完成! チャレンジしてみましょう! おかしなドリルは、工作やお菓子作りなど、ドリル1冊1冊に親子で楽しめるコンテンツがつまっています! 親子でドリルを進めながら、親子で一緒にチャレンジしてみてください♪ ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
理科と社会の1・2年生 始めました!
2023年3月に、文理から「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク」が発刊されました。 コンセプトなどはこちらからお願いします。 今日は理科と社会の1・2年生ってどんな内容なの? という謎にお答えします。 ★カッチカチに回答すると 小学1・2年の理科と社会は、 3年生以降の内容の先取りとなっております。 メールでお問い合わせいただいた場合は、このような回答になります。しかし、ここはブログなので、編集者の気持ちを前面に出してお答えしましょう。 理科編集担当から 主に3・4年生の学習内容を中心に構成していますが、テーマによっては5・6年生の内容にも触れています。 “理科”は一度で学習したらおしまい、ということはなく、学年が上がると共に内容を深堀りしていく教科です。 たとえば4年生では、人の体のしくみとして骨や筋肉について学習しますが、6年生ではさらに呼吸のしくみや食べものの消化・吸収などを学習します。 ワークの中では、小学校のどの学年で学習するかも示しました。 理科への興味・関心をもってもらえるよう、植物・動物、天体、電気、力、大地の変化など、さまざまなテーマを扱っています。 1・2年生にも“理科”がわかりやすいように、身近な題材・テーマをピックアップしました。 “教科学習”が始まる前の準備として、文字をなぞったり、シールを使って答えたりして、楽しみながら取り組むことができるように工夫しました。 イラストや写真をたくさん使っているので、すべてのテーマの学習が終わると、1冊の図鑑のように読み直すこともできます。 社会編集担当から 地図や、地域の様子、社会のしくみを学習する3年生・4年生の内容が中心になっています。 でも、それだけだと「ザ★社会!」という感じがしない(?)ので、都道府県や世界の国々のようすの入門的な内容も入っています。 社会といえば、書いて覚える暗記教科! というイメージがあるかもしれませんが、1・2年生の成長や発達をふまえて、楽しみながら学習ができるように工夫をました。 たとえば…… シールをはって答えたり、 めいろを解いたり、 さまざまな作業をしながら、思考力を伸ばし、社会の見方・考え方を身につけることができます。 また、人に教えたくなる(?)もの知りクイズも掲載。 解くと得意になる! 誌面見本でお気づきかもしれませんが、小学校低学年でも読み進められるように、すべての漢字にふりがなを付けています!理科も社会も、小学校1・2年生が授業で学ぶ前に学習することで「私できる! 得意だよ」になれる教材になっております。ぜひご購入をご検討ください! 「トクとトクイになる! 小学ハイレベルワーク」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
おかしなドリル豆知識
この春、文理からとってもかわいい新刊が出たことをご存知でしょうか!こちらの、「おかしなドリル」です。 今日は、文理のTwitter・Instagramで投稿中の「おかしなドリル」豆知識から、いくつかご紹介します! 画像をタップするとツイートに飛ぶので、気になったら見てみてくださいね☆ 裏表紙まで、お菓子パッケージを意識! 一番の特長は、お菓子のパッケージそっくりなその見た目。 そっくりなのは、オモテだけじゃないんです! 裏表紙を見てみると… お菓子の裏面で、見たことのあるような表示が! 原材料は?保存方法は?なんと書いてあるでしょうか。 シールはクリアタイプ!台紙に貼ることで絵が完成! 8点すべて、シールとシールを貼る達成表が付録になっています。 シールは透明になっていて、達成表に貼っていくことで、自分だけの絵が完成! おかしのキャラクターたちといっしょに、どんな絵を作ろうか…… そんなところも楽しめます! アポロの中には、ラッキースターが…?! お菓子のアポロを買うと、たまに星形のアポロ「ラッキースター」が入っています。 なんと、おかしなドリルのアポロ、「小学1年 けいさん」も、紙面のどこかに ラッキースターが隠されているそうです! 私はまだ見つけられていません…… みなさんもぜひ探してみてください! 楽しくおいしい?勉強タイムをぜひ! 算数が苦手な子も、楽しく勉強できるドリルを作りたい!という思いから作られた「おかしなドリル」 算数と向き合う時間をきっと素敵なものにしてくれるはずです。 おかしなドリル豆知識は、この後も文理のTwitter・Instagramで随時更新しますのでお楽しみに! ▼Instagramでは、制作秘話をマンガで紹介しています! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら SNSキャンペーン開催中! 抽選で、「明治のおかし詰め合わせ」が当たるキャンペーンを開催中です! 応募締め切りは4/16! TwitterからでもInstagramからでも応募できますので、ぜひご参加ください! ▼以下バナーより、詳細をチェック! ~今回の執筆者~イニシャル:I所属:営業部門年代:20代今回のひとこと:顔がかいてあるチョコベビーを食べるのが好きでした
ちぇこ Czech チェコ?
Dobrý den ! (ドブリーデン) こんにちは! WBC(ワールドベースボールクラシック)、盛り上がっていますねえ~! (執筆時はまだ、大会途中です。)予選ラウンドは順調に確実に勝ちを積み重ね、イタリアにも勝って、決勝ラウンド進出しました! (私は前回、ワールドカップの開催している最中に、このBunri-LOGブログを書いたので、「ドイツ☆スペイン☆コスタリカ」と題して、コスタリカについて、ちょっとだけ紹介させていただきました。) 今回のWBC、予選ラウンドで戦った国は、中国、韓国、オーストラリア、チェコ。中国、韓国、オーストラリアは、そこそこイメージつきますよね。 中国は、言わずと知れた中華料理。万里の長城など。 韓国は、トッポギやサムギョプサル。韓流ドラマは好きな人、多いでしょう。 オーストラリアは、コアラ、カンガルー、オージービーフ。 でも、「チェコ」って? 「チェコ」といえば、って何を思い浮かべます? 今回のWBCの予選最終戦で、チェコと戦って、チェコを意識する出来事がいつくかありました。 佐々木朗希投手の剛速球がチェコの選手のひざに当たってしまったエピソードは、皆さんもご記憶に新しいのではないでしょうか。 一塁の山川選手が当たったチェコの選手に歩み寄り、謝罪する場面があり、球場内から拍手が送られてました。その2日後には、佐々木朗希投手がチェコの選手たちが泊っているホテルを訪れ、両手いっぱいのお菓子を渡した、というエピソードも!佐々木朗希選手、すばらしい! それをうけて、チェコの監督は日本の文化、観衆に驚き、「なんとジェントルなんだ」と感動してくれたらしいです。チェコの監督、すばらしい!! そんな出来事があって、チェコという国をもう少し知りたくなりました。 「チェコ」はどんな国? チェコは東ヨーロッパにある、山脈に囲まれた内陸国です。 チェコって聞くと、チェコスロバキア?って思い浮かぶのは、年代の差がありそうですが、激しく変化してきた歴史が激動を物語っています。 第二次世界大戦が終わった後は社会主義体制の国となり、チェコスロバキア共和国として復活した時代もあれば、自由化民主化路線が布かれるなど、紆余曲折を経て、社会主義の崩壊、そして、スロバキアと分離して、現在のチェコ共和国となっています。OECD(経済協力開発機構)やNATO(北大西洋条約機構)、EU(欧州連合)にも加盟しており、今回のWBSのメンバーが、社会人野球の選手のように多くが仕事を持っての選手だった、という興味深いエピソードもありました。選手たちの職業は、学校の先生だったり、消防士、営業マン、電力会社勤務や大学生など、だったようです。 「チェコ」の有名な食べ物って? チェコと言えば、「ビール」です。国民1人あたりのビール消費量は、なんとチェコが世界一なんですって。(知りませんでした) 主食は「クネドリーキ」というゆでパンです。小麦粉やじゃがいもを練って作ります。 日本人にとってのお米でしょうか。 内陸に位置するチェコは、伝統的に肉料理が中心。豚肉がよく食べられ、牛肉や鶏肉も食べる。 お魚は種類は少ないですが、「鯉(コイ)」を食べるようです。特にクリスマスは「鯉」だそうです。フライにしたり、スープにしたり。ビール煮なんかもあるそうです。 「チェコ」に行ってみたい♪ 日本の北海道よりも北に位置していて、歴史も文化も異なる「チェコ」。今回のWBCで対戦して、心温まるエピソードから「チェコ」をちぇこっと知りたくなりました。 日本代表が決戦のアメリカの地に降り立った際、大谷翔平選手、空港で「チェコ」の国旗が付いた帽子を被っていましたね!粋な計らいに、チェコのキャプテンも喜びのコメントを発表してました。そんな、日本とつながりが深くなった「チェコ」首都プラハには、世界遺産にもなっているお城やステンドグラスなど、世界の中でも屈指の美しい街が広がります。 世界の国々、いつか訪れるのを夢みながら・・・♪ 世界の国々といえば・・・ 文理の定番「小学教科書ワーク」の新学期限定4科目セットの付録は、今年は「世界のあいさつと国旗カード」になっています。そして、あの「地球の歩き方」とコラボしているので、国旗カードの裏には世界のあいさつとともに「ものしりまめちしき」も載っています!よかったら、書店さんに行って、見てみてください。 ※冒頭の「Dobrý den!(ドブリーデン)」はチェコ語で「こんにちは!」です(^^♪ ~今回の執筆者~イニシャル:N所属:営業部門年齢:50代今回のひとこと:世界はひとつ(^^♪
【2025年度最新】小学生向け問題集7選|子どもに適した問題集で学力アップを目指そう
「学力を向上させたい」「勉強習慣を身に付けたい」そんなときはどうすればいいのでしょうか。 小学生の学力アップには問題集選びが重要です。 ただし、小学生向けの問題集は数多く出版されており、選び方が分からないという方も少なくありません。 そこで今回は、問題集の選び方や小学生におすすめの問題集を紹介します。 問題集の必要性や使用のメリットについても併せて解説するため、問題集を買うべきか迷っている方にも必見の内容です。 目次 1. 小学生向け問題集で家庭学習を始めよう 2. 小学生|問題集で家庭学習するメリット4つ 3. 小学生の問題集を選ぶ4つのポイント 4. 基礎から応用まで!全学年におすすめの「小学教科書ワーク」 5. 毎日コツコツ!短時間でできるおすすめ問題集3選 6. 中学受験にも!ハイレベルを目指すおすすめ問題集2選 7. 「全科まとめて」で全ての教科を1冊で学習 8. まとめ POINT ・問題集の導入には、「学習習慣が身に付く」「自分のペースで進められる」「経済的な負担が少ない」など複数のメリットがある。 ・子どもの性格や学力、得手不得手に合わせて問題集を選ぶことが大切。 ・学校の授業内容の予習・復習には、教科書準拠品と呼ばれる問題集が適している。 小学生向け問題集で家庭学習を始めよう 家庭学習として授業内容の予習・復習をすることで、 「学習内容が記憶に残りやすくなる」 「苦手な分野を認識できる」 「テストに出やすい問題の傾向を掴める」 といった効果が期待できます。 さらに、中学校に進学した際、「勉強のやり方が分からず困ってしまう」「授業についていけない」といったことが起こらないようにするためにも、小学生のうちに正しい学習方法を身に付けておくことが重要です。 学習方法が分かっていれば、たとえ勉強内容の難易度が上がっても自身の力で学習を継続できます。 学校での勉強だけではなく、問題集を使用した家庭学習も導入しましょう。 小学生|問題集で家庭学習するメリット4つ 問題集を用いた家庭学習は、子どもの学力を高めるための代表的な学習方法のひとつです。 塾に通ったり通信教育を始めたりするよりも気軽に導入できるため、「問題集でも効果はあるの?」と、疑問を感じている方もいるでしょう。 ここでは、問題集による家庭学習のメリットを4つ紹介します。 メリット1 学習習慣が付く 小学生のうちに家庭学習を始めておくことで、「机に向かい決まった時間勉強をする」という習慣が身に付くのが最大のメリットです。 歯を磨くことや顔を洗うことと同じように、勉強することが日常生活の一部になれば、テスト勉強や受験勉強の際にも大きな抵抗を感じることなく勉強に取り組めるでしょう。 また、小学校で習う勉強内容は、中学校や高校で習う勉強の基盤になるため、毎日自主学習し基礎をしっかりと固めておくことが大切です。 メリット2 子どもの理解度に合わせられる 学校の授業や塾では、複数人で一緒に勉強を進めます。 しかし、学習の理解度や得意・不得意な分野は人それぞれのため、じっくりと理解を深めたい子と、どんどん先に進みたい子の間で差が出てしまう恐れがあります。 一方、家庭学習の場合は、自分のペースで学習することが可能です。子どもの理解度やモチベーション、その日の体調などを見ながら進められます。 メリット3 親子で楽しく学べる 「家庭学習は、子どもが一人でやるもの」と考えている方もいますが、家庭学習は親子で一緒に勉強することが大切です。 学習内容の確認や解説を通して自然と会話が増え、信頼関係を深められるといったメリットがあります。 また、おうちの方と一緒に勉強すると「勉強が楽しい」「今日も褒めてもらえるかな」といった前向きな気持ちが生まれるかもしれません。 会話を交えて楽しく取り組むことで、子どもの学習意欲向上の効果も期待できるでしょう。 メリット4 費用が抑えられる 塾や家庭教師といった他の学習方法と比べると、問題集による学習は費用負担が少ないです。 たとえば、通信教育を始める場合は月に3,000円~数万円程度、塾に通う際は月に1万円~数万円程度の費用がかかります。 一方、問題集による学習では、基本的に教材の購入費用しかかかりません。 金額は問題集によって異なりますが、数百円~数千円程度で購入できるものがほとんどです。 家計にかかる経済的な負担を軽減できるのもメリットのひとつでしょう。 小学生の問題集を選ぶ4つのポイント 小学生向けの問題集にはさまざまな種類があるため、子どもに合った内容のものを選ぶことが大切です。 「何となく」で選んでしまうと、せっかく家庭学習を導入しても思うように学習が進まない可能性があります。 問題集を選ぶ際の重要なポイントは全部で4つです。ポイントを押さえて、適切な教材を選びましょう。 ポイント1 続けられるかどうかが重要 最初から問題量が多く時間のかかるものを選ぶと、子どもの負担になりかねません。 勉強自体を苦痛に感じてしまう可能性があります。 子どもの集中できる時間は意外と短いものです。 最初は易しい問題や一問一答形式の問題など、達成感を得やすいものから始めましょう。 家庭学習に慣れてきたら学習時間を少しずつ伸ばしていくことで、大きな負担をかけることなく集中力を高められます。 ポイント2 教科書に対応したものは使いやすい 学校の授業内容の予習・復習をしたり、テスト範囲を学習したりする際は、教科書準拠品が使いやすいでしょう。 教科書準拠品とは、普段使っている教科書の内容に準拠して作られた問題集のことです。 教科書に書かれている用語などがそのまま使用されていたり、教科書の参照ページが記載されていたりするため、教科書の内容に関する理解を深めたいときに適しています。 また、習っていない問題が急に出てきたり問題の傾向が違ったりして、混乱してしまうという心配もありません。 教科書準拠問題集を探すなら ポイント3 子どもの好みを尊重する 小学生向けの問題集には、イラストが描かれていたり、カラーが多用されていたりするものがあります。 毎日使用するもののため、子ども自身ができるだけ楽しい気持ちで取り組める問題集を選ぶのがポイントです。 1ページ達成するごとにシールを貼れる仕様になっているものや、最後に賞状がもらえる仕組みになっているものもあります。 さまざまな問題集を比較し、やる気を高められるものを選択しましょう。 ポイント4 適切な難易度のものを選ぶ 基礎ができていない状態でハイレベルな問題集に取り組むと、難しいと感じ、挫折してしまう恐れがあります。 そのため、「基礎」から始め「標準」「応用」「発展」と、少しずつ難易度を上げていくようにしましょう。 問題集には対象年齢や難易度が記載されています。事前にしっかりとチェックし、子どもの理解度に合った教材を選びましょう。 基礎から応用まで!全学年におすすめの「小学教科書ワーク」 これから家庭教育を始める場合や苦手分野の勉強の際は、文理の「小学教科書ワーク」がおすすめです。 小学教科書ワークは、各教科書会社の許可を得て作られた教科書準拠の学習参考書となります。 ここでは、小学教科書ワークの特長について紹介します。 特長1 基礎・練習・応用を段階的に学べる 問題集の中には、「基礎だけ」「応用だけ」と難易度が絞られたものも少なくありません。 一方、小学教科書ワークは「基本のワーク」「練習のワーク」「まとめテスト」と3段階の構成になっているのが特徴です。 1冊の中で基礎から応用に向かって順番に学べるため、効率的に知識を定着させることができます。 また、達成感を得やすいのもうれしいポイントです。 簡単な問題から取り組んで成功体験を積むことで、学習に対するモチベーションを維持できます。 特長2 役立つ付録が充実 家庭学習に役立つ付録が充実しているのもポイントのひとつです。 付録があると楽しく学習を進められるため、子どものやる気につながります。以下は、小学教科書ワークの付録の一例です。 【主要5教科共通ふろく】・わくわくポスター ・実力判定テスト ・わくわくシール(※英語は除く) ・わくわく動画 ・自動採点CBT 【教科別】・国語:漢字練習ノート・算数:計算練習ノート・理科:理科カード(WEB版つき)・社会:社会カード(WEB版つき)、白地図ノート・英語:英語練習ノート、英語カード、音声配信「onhai」、文理のはつおん上達アプリ「おん達」 値段は1冊あたり1,518円(税込)で、1年間使用できます。 塾や習い事に通う際の経済的な負担が気になる方にもおすすめです。 特長3 4科目セットなら主要科目をまとめてカバー 毎年新学期には、小学教科書ワークの4科目セットが販売されます。 通常、教科書ワークを買う際には自分の使っている教科書がどの教科書会社のものか確認しておく必要がありますが、4科目セットは地区に合うものを購入すれば、自動的に自分にあったワークが揃うため選ぶのも簡単です。 学年別のセット内容は以下の通りです。 ・1~2年生:国語・算数・漢字・数と計算・3~6年生:国語・算数・理科・社会※一部地域によって異なる場合があります。 また、4科目セットにはセット限定の特別付録も入っています。 セットの価格は6,072円(税込)で、小学教科書ワーク4冊分と同じ値段です。 そこにさらに付録が付いていることから、バラバラに4冊購入するよりもセットのほうがお得に購入できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 毎日コツコツ!短時間でできるおすすめ問題集3選 学習習慣を身に付けたいときや集中力を高めたいときは、空き時間を利用して気軽に取り組める「ドリル」が最適です。 ここでは、文理のおすすめドリルを3つ紹介します。 ドリルを使用して、毎日コツコツと問題に取り組む癖を付けながら、日々の予習・復習により基礎学力向上を目指しましょう。 教科書ドリル 教科書ドリルは、教科書レベルの問題に毎日少しずつ取り組むことができるドリルです。 コンパクトなA5サイズで、1回あたり10分で問題が解ける構成になっているのも魅力です。 勉強にかかる負担が少なく、自然と集中が続きます。 特に、学習の基礎となる国語・算数については、教科書の内容に合わせて作成された教科書準拠品となっています。 学校の教科書と一緒に使用すれば、授業内容と同じ速度で学習でき、教科書の知識を早期に定着させることに役立ちます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できるがふえるドリル できるがふえるドリルは、一般的なノートと同じB5サイズのドリルです。 空きスペースを利用して大きめの挿絵やポイント解説、豆知識などが記載されており、勉強に苦手意識を持っている子や、楽しく勉強を進めたい子におすすめです。 また、ドリルのページは1枚ずつはぎ取れる仕様になっています。 やるべき範囲が一目で分かるため、「どこまで進めるのだろう」「まだこんなにやるページがある」といった気持ちが起こりにくいでしょう。 勉強に対するモチベーションの維持に役立ちます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 毎日ちょっと365日ドリル 毎日ちょっと365日ドリルは、個別指導の明光義塾と共同開発した英語の教材です。 7日間かけて10単語を繰り返し学習するという明光式メソッドが取り入れられています。 小学校で習う英単語を6冊で完了できるのもうれしいポイントです。1日1ページ進めれば、1年半で学習が完了します。 なお、読み書きだけでなく、リスニングの学習も可能です。スマートフォンやタブレットで全ての単語の音声を確認できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学受験にも!ハイレベルを目指すおすすめ問題集2選 家庭学習が定着してきた方や受験の予定がある場合は、難易度の高い問題集にも積極的に取り組みましょう。 ここでは、ハイレベルを目指す方におすすめの問題集を2つ紹介します。 トップクラス問題集 トップクラス問題集は、中学入試に備えた問題集です。 小学校1年生から4年生までの国語と算数に対応しており、全8種類あります。 中学入試問題の出し方や傾向に基づいた内容になっているのが特徴で、学力診断ができる「総しあげテスト」も付帯されています。 さらに、問題集の答えが記載されている「答えと解き方」に、各問題の考え方や指導のポイントが書かれているため、勉強の教え方が分からない場合や指導に難しさを感じている保護者にとっても役立つ1冊となるでしょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル算数ドリル ハイレベル算数ドリルは、得意を伸ばしたい子や学校の勉強では物足りないと感じている子に適した教材です。 問題は「標準レベル」「ハイレベル」「トップレベル」の3段階構成になっており、学習の理解度に合わせて学びを深められます。 ドリルの紙面はオールカラーで、子どもでも取り組みやすいデザインを採用しているのが特徴です。 問題集のページ上部には、学習のねらいやアドバイスも記載されています。 また、解答の「てびき」には答えの導き方も記載されているため、問題の解き方が分からない場合も安心です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「全科まとめて」で全ての教科を1冊で学習 「どのドリルがよいか分からない」「問題集選びに悩む」というときは、1冊で全教科の内容を学習できる「全科まとめて」がおすすめです。 1ページごと切り離せるようになっているため、取り組む範囲を一目で確認できます。 また、表面と裏面に同じ問題が載っており、2回取り組めるようになっています。 集中が続かない子や達成感を味わいたい子に適した問題集です。 なお、学年別に「ひらがな」や「九九」「都道府県」などが記載された便利なボードも付いてきます。 リビングや勉強部屋に貼り、学習を促しましょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 小学生は中学校や高校で習う勉強の基礎を学ぶ大切な時期です。 学校での授業だけでなく家庭学習も導入し、学習習慣を身に付けましょう。 毎日机に向かう時間を設けることで勉強をする癖ができれば、テスト勉強や受験勉強の際に感じる負担を軽減できます。 家庭学習の際は、市販の問題集を利用すると便利です。 小学生向けの問題集選びに悩む場合は、文理の教科書準拠の問題集がおすすめです。 問題集は各ネット書店でも購入できますので、ぜひご検討ください
いま、“大人”に伝えたい! 「小中学校の勉強やり直し」オススメ書籍3選
小中学生の保護者の皆さま、突然ですが、こんな経験はありませんか? ☑テレビのニュースを見ていたら、答えられない質問を子どもにされた。 ☑子どもの勉強の相手を小学校までしてたけど、中学校に上がって内容がわからなくなった。 ☑生活での疑問や悩みに直面して、「あの頃もっと勉強していれば……」と思わされた。 人生100年時代などと謳われているとおり、現代は子どもだけでなく、大人になっても勉強を続ける時代。 ……というのは言いすぎかもしれませんが、 「わからなかったことが、わかる。」 「自分が、昨日の自分より成長している。」 という感覚は、代えがたい喜びです。 そこで今回は、「大人の皆さんにこそ伝えたい、【学び直し】にぴったりの文理の教材」を(筆者の独断と偏見で)ご紹介したいと思います! オススメ書籍その1:『わからないをわかるにかえる 中学公民』 ※『わからないをわかるにかえる 中学公民』は2025年に改訂しました。本記事に掲載の紙面は改訂前の画像になります。最新版のご案内はこちら。 中学生向けの超基礎問題集である『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 本シリーズは、中1~中3の国語・数学・理科・社会・英語…と多種多様なラインナップがあります。 あえてその中から、「大人の学び直し」に最適な1冊を選ぶなら、「中学公民」をオススメします。 中学の「公民」の授業でどんなことを学習したか、皆さまは覚えていますか? 例えば、以下のような項目を扱います。 ・選挙や政党のしくみ ・家計と消費 ・労働者の権利 ・税金や社会保障のしくみ ……どれも、大人の私たちからすると、身近な話題ですよね? 正直なところ、筆者が中学生のときは、 「地理、歴史と比べて、公民は暗記ばかりでつまんない」(←失礼) と思っていました。 しかし、大人になり社会経験を経た今こそ、公民の学習内容は身にしみることが多いです。 △本紙34ページ。つい先日に参議院選挙がありましたが、小選挙区制と比例代表制の違いを身近な人に説明できるでしょうか? 『わからないをわかるにかえる』シリーズは、左ページで解説をし、右ページで問題を解く仕組みになっているので、その名の通り、「わかりやすさ」は折り紙つきです。 △左ページに解説、右ページに問題 右ページの問題の多くは左ページの解説を見ることで解くことができます。 問題を解くことで、一時しのぎでない、ずっと残り続ける「知識」をしっかり定着させられます。 また、同じ『わからないをわかるにかえる』シリーズから、英検®対策本も出ています。 勉強でなにか具体的な目標を持ちたい方は、英検®合格を目標に本書に取り組んでみてはいかがでしょうか? △『わからないをわかるにかえる』英検®シリーズ。詳しくは公式ページをご参照ください。 オススメ書籍その2:『中学教科書ワーク 技術・家庭(1~3年 全教科書対応)』 ※『中学教科書ワーク 技師・家庭』は2025年に改訂しました。本記事に掲載の紙面は改訂前の画像になります。最新版のご案内はこちら。 『教科書ワーク』は、小中学校の授業の進度と合わせて学習できる準拠教材で、文理の看板商品ともいえるシリーズです。 この教科書ワークに、国語・数学・理科・社会・英語のいずれでもない、実技の銘柄があるのをご存じですか? 現在は「美術」「音楽」「保健体育」「技術・家庭」の4銘柄が出ており、 いずれも学年別でなく、また特定の教科書に紐づかない「全教科書対応」の銘柄です。 中学での実技科目は、高校入試で扱われないためか、どうしても相対的に小さく扱われがちです。 私自身も中学生のときは、 「実技とか、おまけでしょ」(←失礼) と正直思っていました……。 しかし、実は大人になった今こそ、実技(「美術」「音楽」「保健体育」「技術・家庭」)はお役立ち情報の宝庫なのです! ためしに、『教科書ワーク 技術・家庭』の誌面を少しのぞいてみましょう。 あなたは、下の問題を何問正解できますか? △57ページ「情報の技術」より。※現在、通信方式は「http」ではなく「https(Hypertext Transfer Protocol Secure)」が主に使われています。 △87ページ「家族・家庭と地域の関わり」より △101ページ「食品の調理」より △137ページ「金銭の管理と購入(2)」より こたえ ★本記事で出題された問題の答えはこちら (※2ページ目のアンケートについては回答期間を終了いたしました。) ……いかがでしたか? 誌面をご覧いただくとわかる通り、大人になった私たちから見ると、「技術・家庭」には、 「かゆいところに手が届く~~!」 そんな知識が満載なのです。 今回取り扱った「技術・家庭」だけでなく、「美術」「音楽」「保健体育」など実技の他銘柄にも、大人が身につけていたい教養や、生活の知恵が詰まっています。 この機会に、ぜひ手に取ってみませんか? オススメ書籍その3:『できるがふえるドリル 小学4年 計算』 最後は、これまでと少し違う趣向の1冊をご紹介します。 たとえば仕事を退職されたり、子育てから手離れをしたりして、 「1日で使える時間にゆとりができた」 という方は、「小学校の計算」をやり直してみませんか? 「小学校の勉強なんて……」と侮るなかれ。 紙面を見てみると、意外とややこしいことを小学生がしていることに気がつくはずです。 △小学4年のわり算。しっかり解ききることができるでしょうか? 小学校の「算数」は、中学で「数学」にステップアップします。 それに伴い、必要とされる考え方が、目に見えるものを扱う具体的な思考から、現実の例に落とし込みづらい抽象的な思考へとだんだん移っていき、だんだんと算数に「ニガテ意識」を持つ子どもが増えていきます。 大人になった皆さまの中にも、 「この辺りから、算数・数学がよくわからなくなったんだよなぁ……」 という方がいるのではないでしょうか。 もし生活で自由に使える時間が増え、新しく何かをはじめようと思った方は、あの頃のニガテ意識を解消する時間をあえて作ってみるのもアリかもしれません。 最新版のご案内 今回の記事では、「大人の学び直し」に最適な文理の教材として、以下の3つの書籍を取り上げました。 ・『わからないをわかるにかえる 中学公民』(※2025年度改訂版のご案内です。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・『中学教科書ワーク 技術・家庭(1~3年 全教科書対応)』(※2025年度改訂版のご案内です。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・『できるがふえるドリル 小学4年 計算』 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 大人の立場になると、自身が持てる時間がどうしても限られてしまいます。 その一方で、「自分が気になったことを好きなだけ勉強できる」のは大人の特権! 今回取り上げた書籍が気になった方は、ぜひ書店に足を運んでみてください。 「大人の教科書ワーク」好評発売中! 2024年2月1日に、文理から初の大人の学び直しシリーズ「大人の教科書ワーク」が発売しました! ”教科書をひもとけば、日常がちょっぴり楽しくなる”をコンセプトに、 教科書を軸にして学び直すことができるシリーズとなっています。2 ▲日常の悩みやギモンを、小中学校の教科書で解決! 「学び直しって何からやればいいんだろう」 「なんとなく中学生くらいの勉強をやり直したいけど…」 といった方におすすめです。 ・『大人の教科書ワーク』 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
夏休みはドリルで復習しよう!
夏休みがはじまりますね。 たくさん遊んで、ぜひいろいろなことを経験してほしいですが、 毎日机に向かって勉強する習慣は、夏休みもキープしましょう。 どうしてドリル学習がいいの? 夏休みにはドリル学習がぴったりです。 実際書店での売れ行きを見ても、毎年この時期はドリルが上位にランクインしています。 ではどうして、夏休みにドリルが選ばれるのでしょうか? 一つの理由としては、1日〇分、〇ページとペースを決めて取り組みやすいから。 せっかく一学期(前期)に身につけた学習習慣をなくさないためにも、ドリル学習がおすすめです。 ドリルの選び方は? 一口にドリルといっても、いろいろなタイプのものがあります。 どのドリルを選んだらいいか迷ってしまう場合は、 次のポイントを参考にしてみてください。 学年・分野で選ぶ 「国語1年」「算数2年」など、教科別のもの 日々の学習におすすめです。 とくに、「教科書準拠版」のドリルは、授業で学んだことの確認にぴったりです。 「かんじ1年」「たし算・ひき算1年」など、特定の領域別のもの 漢字・計算・英単語など、反復練習で習得が必要なものだったり、 教科の中で苦手な分野がはっきりしていたりする場合は、 特定の領域別のドリルで学習しましょう。 夏休みに苦手を克服するのにぴったりです。 「夏休みドリル」「全科まとめて」など、複数教科合本のもの 夏休みなどの長期休暇に、まとめて復習するのにおすすめです。 1冊に複数教科がまとまっているので、取り組みやすいです。 レベルで選ぶ ドリルを選ぶ際は、レベルが自分に合っていることが大切です。 難しすぎれば続けられませんし、簡単すぎれば力がつきません。 書店で実物を見たり、ネットでサンプルを見たりして、 自分に合ったレベルのものを選びましょう。 学習時間で選ぶ 「朝5分」や「1回10分」のように、タイトルなどで学習時間を前面に出している商品もありますが、そうでなくても、 紙面に1回の取り組み時間の目安が書かれているドリルは多いです。 日々の学習であれば、1教科につき10分くらいが続けやすいですが、 夏休みはもう少し学習したいところ。 1回に取り組むページを増やしたり、ほかのドリルと組み合わせたりして、 1教科につき20分~30分くらい取り組むとよいでしょう。 苦手分野は30分、得意分野は10分などメリハリをつけるのもよいですね。 第一印象も大切! 学年・分野、レベル、時間などもドリル選びの大事なポイントではありますが、 「これなら楽しく勉強できそう」「飽きずに毎日取り組めそう」という第一印象はあなどれません。 好みの大きさやデザインのものだと、気分が上がりますし、 シールなどの付録が、学習のやる気につながることもあります。 実際に書店に行って、いろいろなドリルを手に取ってみて、 自分に合ったドリルを選んでみてください。 ドリルの進め方 夏休みにドリル学習に取り組む際に大切なことは、毎日続けることです。 まずは、1日どのくらいやるか、何時からやるかを決めましょう。 時間になったら、ドリルに取り組み、そのあと丸付けもしましょう。 また、学習の記録も大切。 ドリルには、学習した日付や取り組んだ時間を記入できるタイプのものもあります。 ここを記入すると、毎日続けるモチベーションを保ちやすいです。 丸付けが大事! 問題を解いたあとに、丸付けをすることはとても大切です。 とくに漢字ドリルや計算ドリルの場合は、反復により学習を定着させるため、 間違って覚えてしまわないように、解き終わったらすぐに丸付けをして、 間違っていたところを解きなおしましょう。 自分で丸付けをするのが難しい場合は、保護者の方に丸付けをしてもらいましょう。 保護者の方にとっては、毎日の丸付けをするのは大変かもしれません。 しかし、丸付けはお子さまに学習習慣を身につけさせたり、 お子さまの学習の進度や理解度を知ったりする、よい機会になります。 ドリルの中には紙面に赤刷りで解答が入っている、縮刷解答タイプのものもあります。 答えが一目でわかるので、保護者の方が採点する場合も採点しやすいです。 夏休みにおすすめのドリル4選! 最後に、文理の商品の中からおすすめのドリルを紹介します。 自分に合ったドリルを選んで、夏休みにチャレンジしましょう。 教科書ドリル 1回10分。日々の授業の確認に。国語算数は教科書準拠版。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼がふえる↑ドリル 分野別の標準版ドリル。付録充実。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 全科まとめて 全教科複合型ドリル。夏休みの学習にピッタリ。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル算数ドリル 丸付けしやすい縮刷解答。付録充実。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
ドリル選びのすすめ【後編】
こんにちは! 今日は前編に引き続き、ドリルの特長と選び方についてご紹介します! 前編を読んでいない方はぜひこちらから ドリル選びのすすめ【前編】 さっそく、文理のこの4シリーズのうち…… A4判ドリルを、2つ見ていきましょう! ※「ドリル」について 本記事では、図のような綴じ方のドリルについて扱います。 こちらの記事は2022年春時点の情報で書かれたものです。 2024年最新版はこちら▼ 全教科を薄く広く、は全科まとめて ※「全科まとめて」は2025年に改訂しました。下記は旧版の情報です。 「全科まとめて」の裏表紙ですべて説明されているので、見てみましょう。 ということで、 〇何冊も買わなくていい 〇短期間で終えられる 〇カラフルで分かりやすい 〇1枚ずつ切り取って使える 〇英語は聞く練習もできる それが「全科まとめて」です! 目次を見てみると、1冊の中に全教科の学習内容がつまっているのがわかります。 切りはなして、1回分取り組みましょう。 全科ドリルは他社からも何種類か出ていて、「問題の量」「色づかい」「イラスト」「解説の量」などに それぞれ個性があります! ぜひ比較して、目的に合ったものを選んでみてください! さらっと全体をおさらいしたいというときは、5教科それぞれでドリルを買うよりお得かもしれませんね。 特設サイトはこちら。 ★文理で表紙のキャラクターに明確に名前がついているのはこのドリルだけかも… マトちゃんメテちゃんを描いてくださったのはイラストレーターの大塚朗さんです! 算数が得意で、もっとやりたいキミに… 最後はかなり個性的! ハイレベル算数ドリルは、 算数でイチバンをめざす小学生におすすめです! 表紙は大変かわいらしいですが…… タイトルに偽りなく、かなりのハイレベル問題になっています。 学校の勉強では物足りず、もっと力をのばしたいときにはとてもよいです! 逆に、苦手の克服や復習用にはあまり向いていないのでご注意ください。 紙面はオールカラーで、ハイレベルな教材の中では、とっつきやすいデザインです。 難点は、問題をたくさん入れた結果、計算スペースが少ないところです…… 計算用の紙などを別で用意していただくと、さらに取り組みやすいです! 地味にすごいのが「学力診断テスト!」 最後に収録されている「そうしあげテスト」に取り組んで、 大設問ごとの得点を文理HPに入力すると…… 学習診断の結果を見ることができます! 大設問ごとに、正解数に応じたアドバイスを得ることができます。 (今回は全問正解と入力しましたが、それでも声かけしてくれます) 特設サイトはこちら! ドリル選びのすすめ ドリルを選ぶときは、まず目的を意識! 毎日短時間さっと取り組む習慣をつけたい! →小さいサイズのA5判ドリルがおすすめ! カラーかそうでないかなど、お子さまの好みに合わせて決めましょう! 苦手分野の克服を、負担軽めにやりたい! →B5サイズくらいのドリルがおすすめ。 多くの場合冒頭に特長がまとめてあるので、そこを見比べてみてください! キャラクターものも結構あったりします。 お子さまが興味を持てそうなものを、一緒に選ぶといいかもしれません。 手軽に前の学年の総復習がしたい! →「全科」と名のついたドリルがおすすめ! 全教科が1冊にまとまっています。 問題の量や色づかいなどを見比べて選んでみてください。 普通のドリルよりも単元の分け方がざっくりしているため、進行中の授業に合わせて使うと 習っていない内容が混ざってしまうことも。 復習に特におすすめです。 ハイレベルな問題を解きたい! →まずタイトルに「ハイ」や「トップ」が入っているものを探しましょう! ただし、少し力試し……で挑むと難しすぎるものもあるので、 実際に紙面を見る、レビューを見る、などで確認してみてください! ▲サイズも様々! ▲大きめサイズには、はぎ取り式など持ち運びやすい工夫も。 いかがでしたでしょうか。 書店でドリルを選ぶとき、ぜひ今日お話ししたような点に注目してみてください! それではまた! ー小学教科書ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーできる‼がふえる↑ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ー全科まとめてー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーハイレベル算数ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
ドリル選びのすすめ【前編】
こんにちは! 今日から新学期!という方も多いのではないでしょうか。 ご入学・ご進級おめでとうございます。 さて、新しい学校生活が始まり、 書店でドリルでも買っておこうかな、という方もいらっしゃるかと思います。 そんなとき、書店に所狭しと並ぶドリルを見て いったい何がちがうのだろうか? そう思うことはございませんか? 今日は、文理で作っているドリルについて、そのちがいをご紹介していきます! 他社のドリルを見る際にも、参考になれば幸いです。 ※「ドリル」について 本記事では、図のような綴じ方のドリルについて扱います。 こちらの記事は2022年春時点の情報で書かれたものです。 2024年最新版はこちら▼ まず、「文理のドリル」を並べてみます。すみません… さすがに全部を持ってくるのが大変だったので、各シリーズ少しずつ持ってきました。 現在刊行されているのは、以下4シリーズ。 ★教科書ドリル ★できるがふえるドリル ★全科まとめて ★ハイレベル算数ドリル それぞれ特徴があるので、紹介していきます! 教科書ドリルは1回10分! 学習習慣づけに ※「教科書ドリル」は2024年に改訂しました。こちらの記事は旧版の情報です。 教科書ドリルは、A5サイズの小さいドリル。 ▲持った感じ ▲iPhone7と並ぶと 1回あたり10分程度で終わる分量になっており、 毎日さっとドリルに取り組む習慣をつけたい、というときにおすすめです! ※小さい紙面で書く欄は少し小さめ。 苦手を感じている分野については、後述する「できるがふえるドリル」や「教科書ワーク」がよいかもしれません。 国語と算数は、教科書準拠版をご用意! より学校の授業の進度に合わせた学習がしやすくなっています。 ▲表紙の教科書会社名と教科書名を確認 「教科書ワーク」との併用もおすすめです! 名前も似てますしね。 例)ワークで勉強したことを、教科書ドリルでさらに反復。 例)算数の「教科書ワーク」と、算数分野別の「教科書ドリル」を併用。 ラインナップは特設サイトをご確認ください。 楽しい工夫たくさん! 弱点克服にはできるがふえるドリル こちらはB5サイズ。一般的なノートと同じですね。 教科書ドリルが「1回10分、問題をこなして定着させる」のに対して、 「少し勉強が苦手で、楽しく取り組める工夫が欲しい」ときにおすすめです。 ▲楽しく取り組める工夫が随所に。 取り組む時間は、自分で書きこみます。 時間を意識して取り組むことで、集中力もUP! はぎとれるのもうれしいポイントですね! ラインナップはこちらです。 後半へ続く…… 残り2つ、大判(A4判)のドリルについてと、ドリルの選び方まとめは 明日更新しますので、お楽しみに! それではまた! ー小学教科書ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーできる‼がふえる↑ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ー全科まとめてー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーハイレベル算数ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら