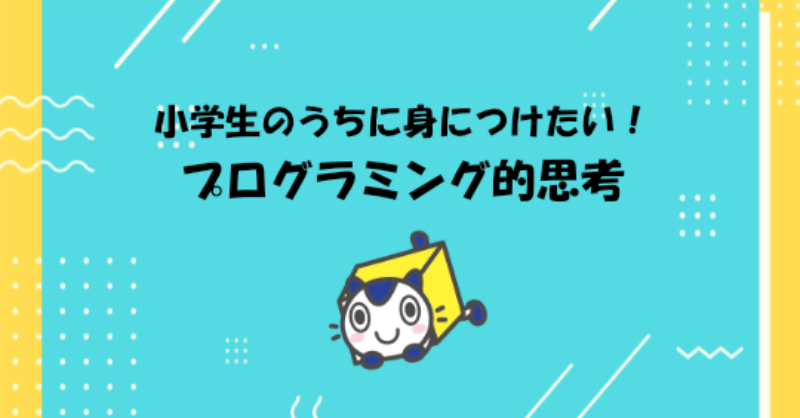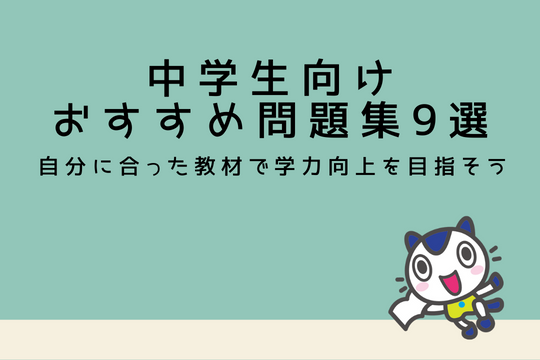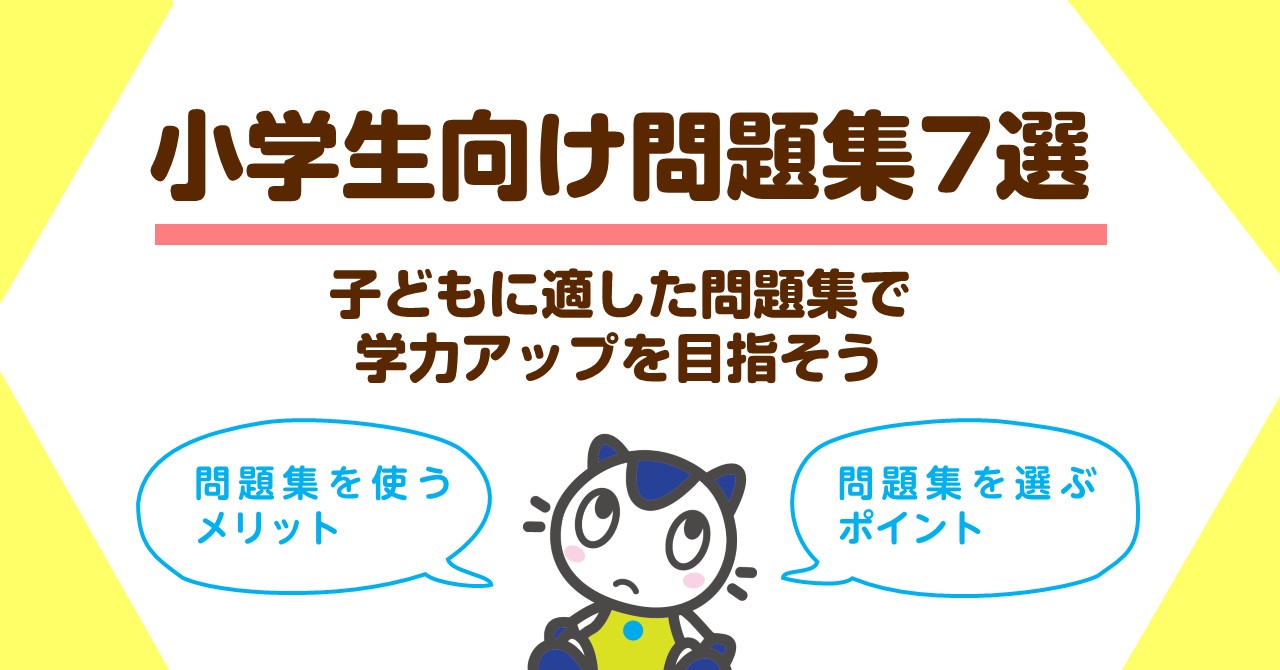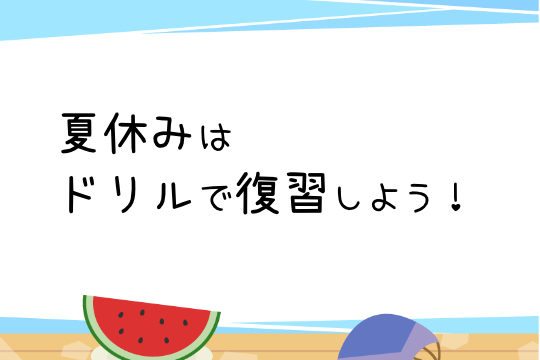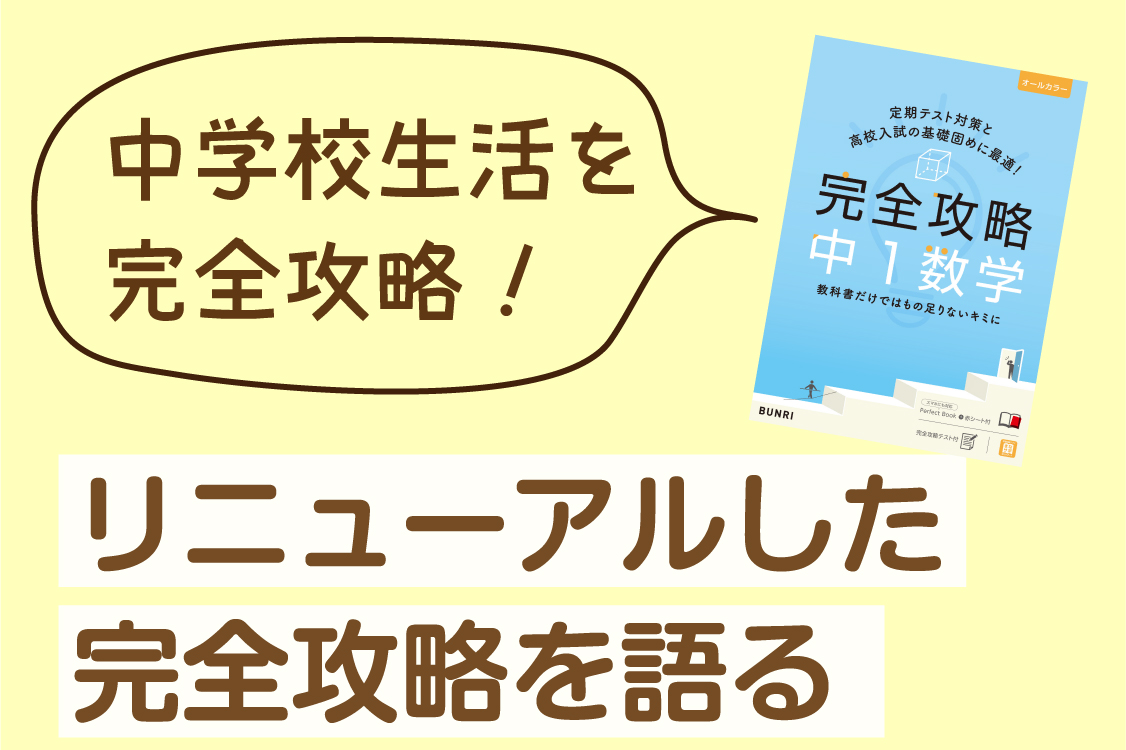なるほど!Bunri‐LOG
対象
小学生のうちに身につけたい! プログラミング的思考
お子さまの将来のために、「プログラミングを学ばせたい」とお考えの保護者の方もいらっしゃるかと思います。 実際、近年プログラミングは人気の習い事です。 プログラミングは将来どんな職業に就くにしても不可欠な知識のため、現在の教育課程では小学校から学習するようになっています。 しかし、プログラミングは保護者のみなさまが子どものころにはなかった学習事項のため、学校で何を学んでいるのかイメージしにくいかもしれません。 そこで、今回は小学校のプログラミングではどんなことを学ぶのか、また、プログラミングの習得のためにどんな力を身につければよいかについてご紹介します。 目次 1.小学校で学ぶプログラミング 2.プログラミング的思考とは 3.「小学教科書ワーク プログラミング的思考」 POINT ・2020年から小学校でプログラミング教育が必修化 ・プログラミング言語や技能ではなく「プログラミング的思考」を学ぶ ・「小学教科書ワーク プログラミング的思考」で親子でプログラミングを学ぼう! 1.小学校で学ぶプログラミング 小学校では、2020年からプログラミング教育が必修化されています。 しかし、「プログラミング」という教科があるわけではなく、専用の教科書もありません。 子どもたちはさまざまな教科・学年の中でプログラミング的な考え方を学んでいきます。 たとえば、算数はプログラミングと深い関係のある教科で、小学5年生で学ぶ「正多角形の作図」は正確な繰り返し作業を行う必要があり、さらに一部を変えることでいろいろな正多角形を同様に考えることができるため、プログラミングの「反復」や「変数」の考え方に通じます。 このように、小学校のプログラミング教育で学ぶのは、プログラミング的な考え方であって、特定のプログラミング言語や技能の習得ではありません。 2.プログラミング的思考とは プログラミング言語や技能は日々どんどん進化していきますが、基本となる考え方を身につけておけば、将来どんな言語や技能を学ぶ際にも役立ちます。 だから、小学生のうちにまず「プログラミング的思考」を習得しておくことが大切です。 では、「プログラミング的思考」とはいったい何でしょうか? 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説では、「プログラミング的思考」を「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」と定義しています。 わかりやすく言い換えると、プログラミング思考とは ・身の回りの物事のしかけやはたらきにはどのようなパターン(規則性)があるのか ・パターンにはどのような特徴があるのか ・どのようなパターンを組み合あわせて命令すれば動くのか を筋道を立てながら考えること、と言えます。 3.「小学教科書ワーク プログラミング的思考」 では、プログラミング的思考を身につけるにはどうすればよいのでしょうか? 大切なのはプログラミングのパターンと組み合わせを知り、筋道を立てて考えられるようにすることです。 それには、プログラミング的な思考の流れを、実際に自分の頭で考えながらたどってみるという経験が大切です。 そこでおすすめなのが「小学教科書ワーク プログラミング的思考」です。 文理のキャラクター「キュリオ」といっしょに各章でのミッションをクリアしながら、ゲーム感覚で「プログラミング的思考」を身につけられる楽しい構成になっています。 難しい用語や説明は出てきませんが、扱っているのは、「変数」「比較」「データ構造」「座標」「文字コード」「条件分岐」「逐次実行」といった、プログラミングの核心的な内容です。 そのため、お子さまは楽しくミッションに挑んでいるうちに、おのずとプログラミング的思考を身につけることができます。 保護者向けの解説も充実しています。 その章でプログラミングのどんなパターンを学んでいるのかについてかみ砕いて解説しているため、大人の学びなおしにもなります。 ぜひ、本書をつかって親子で「プログラミング」学習をスタートさせましょう! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
【2025年度最新】中学生向けおすすめ問題集9選|自分に合った教材で学力向上を目指そう
「思うように学力が伸びない・・・」「どの問題集を使えばよいか悩んでいる・・・」 そんな中学生のみなさん、学力を向上させるには自分に合った問題集を使うことが重要です。 しかし、中学生向けの問題集は数多く出版されており、 実際に本屋さんに行ったときにどの問題集を選べばよいか悩んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、自分に合った問題集の選び方と、目的やレベル別で中学生向けのおすすめ問題集を9つ紹介します。 あわせて、問題集の効果や活用方法についても解説します。 成績アップのために問題集を探している方、どの問題集を買うべきか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。 <目次> 1.中学生の学力向上には問題集が効果的 2.中学生向け|問題集の活用方法 3.中学生の問題集はどう選ぶ? 4.学校の予習・復習、定期テスト対策におすすめの問題集3選 5.実力アップ&得点アップにおすすめの問題集3選 6.高校入試の合格力をつけるためのおすすめ問題集3選 7.まとめ <POINT> ●問題集を活用することは学力向上に効果的。 ●科目ごとにレベルと学習目的に適した問題集を選ぶのがおすすめ。 ●問題集は内容を理解し、続けられるものを選ぶことが重要。 1.中学生の学力向上には問題集が効果的 中学生の学力向上には問題集を使って多くの問題を解くことがとても効果的です。 多くの問題を解くことで、解答のスピードが上がります。 決められた試験時間で行う定期テストや入試などでは、解答のスピードが重要になってきます。 高校受験を控える中学生は、多くの問題集を使ってより多くの問題に触れることが必要です。 さらに、多くの問題を解くことで、解答パターンが理解できるようになります。 解答パターンが理解できれば、類似した問題が出題された場合に、正しい解答を導きだすことができるようになります。 このように、問題集を活用することには多くのメリットがあるのです。 2.中学生向け|問題集の活用方法 前述のように、問題集を活用することは多くのメリットがあり、中学生の学力向上にとても効果的ということがわかりました。 しかし、問題集の使い方を間違えると膨大な時間がかかり、学力向上につながりにくくなってしまいます。 それでは、どのように問題集を活用するのが良いのでしょうか。 ここでは、効果的な問題集の活用方法を3つ紹介します。 苦手な科目は一冊の問題集を完璧に 苦手な科目ほど、まずは一冊の問題集を繰り返し解き、解けない問題を減らしていくことが効果的です。 一冊の問題集を終わらせることで「できた」という自信に繋がります。 この「できた」自信をつけることが、苦手科目の学力向上にはとても重要なのです。 一冊をやり切った成功体験が、次の勉強のモチベーションになり、苦手意識をなくしていきます。 「一冊を終わらせる」→「自信をつける」→「勉強をしたくなる」の成功サイクルをつくるイメージです。 複数の問題集を同時進行しない 問題集を使って多くの問題を解くことが学力向上に効果的だという話をしました。 多くの問題を解くうえで重要になるのが、複数の問題集を同時に使うのではなく、一冊クリアしたら次の問題集へ進むということです。 たとえば、1冊の問題集をやって60%できたとします。 40%はわからない問題で、この状態でほかの問題集を解いても、もとの問題集の40%は解けないままなので、実力は変わりません。 ですから、一冊の問題集を100%できたという状態にしてから次の問題集へと進むことで、問題を解く力を着実につけることが重要なのです。 暗記教科にはマーカーなどを使う 暗記系の科目は、問題集の本文や解説にオレンジペンや赤シート、暗記ペンなどを使い、繰り返し学習ができるようにしましょう。 オレンジペンで答えを書いたあと、赤シートで隠して繰り返し学習することで、どんどん記憶に定着します。 すでに答えを書き込んでいる場合や、解説を暗記したい場合には、暗記ペンを使いましょう。 暗記ペンで暗記したい文字の上に線をひき、赤シートをのせましょう。オレンジペンと同様に文字を隠すことができるのでくり返し解くことができます。 問題集によっては付録として赤シートやポケットタイプの学習カードが付いてくるものがありますので、付録のチェックも重要です。 3.中学生の問題集はどう選ぶ? 中学生向けの問題集は、種類がたくさんあり、いざ本屋さんに行って問題集を買おうと思っても、どれを選んだらいいか迷ってしまいますよね。 問題集を買ったけど、 「結局合わずに長く使い続けられなかった」「思うように成績が伸びなかった」 そんな経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。 それでは、どのように問題集を選べば良いのでしょうか。 ここでは、問題集の選び方のポイントを3つ紹介します。 教科書に沿った問題集がおすすめ 市販されている問題集には「教科書準拠版」と、そうでないものがあります。 教科書準拠版とは、それぞれの教科書の内容に沿った問題集です。 実は、お使いの教科書は出版社によって、それぞれ内容が異なっています。 学校の授業は教科書に沿って行われるため、家庭での予習・復習には教科書の内容に沿った「教科書準拠版」の問題集がおすすめです。 また、定期テストの問題は教科書の範囲から出題さるため、教科書準拠版で学習すれば成績アップが見込めます。 授業の予習・復習、定期テスト対策は、まずは教科書準拠の問題集で学習を始めるのがよいでしょう。 教科書準拠の問題集を探すなら 科目ごとに自分のレベル・目的に適したものを選ぶ 得意な科目はハイレベルなものを、苦手な科目は基礎を学べるものを、といった風に科目ごとに自分のレベルにあった問題集を探しましょう。 事前に自分のレベルを把握することと、問題集の難易度をチェックすることが大切です。 また、学習目的によっても適した問題集は異なります。学生向けの問題集には 「日常学習用」、「定期テスト対策用」、「入試対策用」などがあり、それぞれの問題集は、学習者の目的を効率よく達成できるようにつくられています。 そのため、自分の学習目的に適した問題集を選ぶことが、効率的・効果的に学力を伸ばす近道になるのです。 解説の量やレイアウトもチェックする 問題集は内容を理解し、続けられるものを選ぶことが重要です。 解説が充実している問題集は、内容を理解しやすいです。 せっかく問題集を頑張っていても、わからない部分の解説がないと困りますよね。 そのため、苦手な科目ほど、解説が充実したものを選びましょう。 また、中身のデザインやレイアウトが自分の好みに合っているかも大切です。 カラフルな紙面がよいのか、1色、2色刷のシンプルなデザインがよいのかは好みによります。 市販の問題集は、図やイラストを用いて視覚的にも頭に入りやすくしていたり、 ぱっと見てわかりやすいレイアウトであったりと、さまざまな工夫がされています。 実際に問題集の中身を見てみて、「見やすい・使いやすい」と感じるものを選びましょう。 4.学校の予習・復習、定期テスト対策におすすめの問題集3選 こちらでは、学校の予習・復習、定期テスト対策にぴったりの教科書準拠問題集を紹介します。 学校で習った内容を自分のものにするには自宅での学習は欠かせません。 教科書準拠の問題集ならば学校の授業と教科書の内容に沿って予習・復習ができ、テスト対策にもとても効果的です。 中学教科書ワーク 【2025年度改訂】 教科書ワークはオールカラーの整然とした見やすく親しみやすい紙面が特徴の問題集です。 わかりやすいイラストと図や鮮やかな写真で内容の理解を深めます。 ステージ1→ステージ2→ステージ3の3段階構成(主要5教科)。 基礎から応用へ段階をおって勉強でき、教科書の内容理解が深まります。 そのため勉強がしやすく、毎日の予習・復習からテスト対策まで、学校の授業に合わせて、家庭学習で確かな学力をつけることができます。 テストの出題頻度が高い問題が収録されていて、テスト対策も万全です。 また、たくさんの特別付録で学習を楽しくサポートしてくれます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学教科書ガイド 中学教科書ガイドは、教科書の内容を、もれなく・くわしく・わかりやすく解説してあるので、教科書の予習・復習に最適です。 教科書の問題について、考え方やヒント・解答が詳しくつけてあるので、教科書の内容がズバリわかり、勉強が進みます。 教科書の重要事項や定期テストに出題されやすい事項がひと目でわかるようまとめてあるので、定期テストの準備もこれで万全です。 中学教科書ガイドが1冊あれば、1年間の教科書レベルの内容が習得できるつくりになっているのも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 定期テストの攻略本 【2025年度改訂】 定期テストの攻略本は、定期テスト対策にぴったりの問題集です。 教科書に合わせて、テスト範囲を集中学習することができます。 特に大切な要点を押さえた解説と、テスト対策に絞った問題がそろっています。 重要なポイントを赤シートで隠しながら、効率的に学習できます。 毎日の学習に「教科書ガイド」や「教科書ワーク」を利用しながら、定期テスト前にはこちらの問題集で集中学習、といった使い方が効果的です。 本番を想定した「予想問題」や、テスト直前まで使える「5分間攻略ブック」の付録など、定期テストに向けて必要なサポートが充実しています。 学校の定期テストを攻略したいという方には、この一冊がおすすめです。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 5.実力アップ&得点アップにおすすめの問題集3選 こちらでは、学力のレベルごと、目指したい得点ごとにおすすめの問題集を紹介します。 簡単すぎて手応えのないものはもちろん、難しすぎる教材も身につかないため、 自分の学力レベルに合った問題集を選ぶことで実力アップ&得点アップにつながります。 わからないをわかるにかえる【学年別・領域別】【2025年度改訂】 わからないをわかるにかえるシリーズは、基礎の基礎から勉強したい人におすすめの問題集です。 やさしくわかりやすい説明、豊富なイラスト、オールカラーが特徴の一冊で、基本からつみあげることを追求しています。 基本→練習→まとめの3ステップ。 各単元で要点を確認し、練習問題で反復したら、単元のまとまりごとにテスト形式で定着度を確認します。 1回分は見開き2ページになっていて、無理なく学習を進められるようになっています。 覚えておきたい知識をチェックできる「ミニブック」や重要知識の暗記に使える「暗記カード」など、教科ごとに学習に役立つ付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略【学年別・領域別】 完全攻略シリーズは、教科書の内容はある程度理解できていて、さらに一歩進みたいという人におすすめです。 基本問題、標準問題、実戦問題と段階的にステップアップできます。 教科書とはちがう題材で豊富に演習するため、定期テスト対策から高校入試の基礎固めまでの確かな実力を身につけることができます。 国語・社会は「耳ヨリ音声解説」、英語(英文法を除く)は発音上達アプリ「おん達」など、教科別のWEB付録が充実していることも特徴です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイクラス徹底問題集 ハイクラス徹底問題集は、最高峰の問題演習で、定期テスト・実力テスト対策から、入試対策まで、あらゆる試験に強い実力をつける問題集です。 過去の入試で出題されたレベルの問題に触れられます。 定期テストによく出題される標準的なレベルの「徹底理解」から、 公立・国立・私立高校入試のやや高いレベルの「実力完成」、 主に国立・私立高校入試で出題された、かなり高いレベルの「難関攻略」と、 段階的に国立・私立難関校を目指せる高い学力を育成する構成になっています。 問題集の最後は総合実力テストになっていて、強くブレない実力をつけることができます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 6.高校入試の合格力をつけるためのおすすめ問題集3選 高校入試は、中学3年間で学習した内容の理解が求められます。 高校入試の約7割が中学1 ~2年生で学ぶ範囲から出題されるため、早めの対策と学習の定着が合格のカギです。 高校入試対策ができる問題集を活用し、着実に高校入試の合格力をつけましょう。 わからないをわかるにかえる【高校入試】 わからないをわかるにかえる高校入試シリーズは、超基礎からやさしく学んで高校合格をめざす問題集です。 高校入試対策のはじめの1冊として、苦手な単元をしっかりやり直して高校入試の合格力をつける内容となっています。 「得点力UP! 入試特集」で実際の入試に近い総合問題にチャレンジできます。 入試直前まで使える赤シートつき「合格ミニブック」など便利な付録もついています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら コーチと入試対策! 「8日間完成 中学1・2年の総まとめ」「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 コーチと入試対策は、8日間or10日間で仕上げる入試対策用の問題集です。 ウサギとヒツジのかわいいキャラクターがコーチとしてていねいに解説をしていて、受験対策が楽しくなるような紙面が特徴です。 「8日間完成中学1・2年の総まとめ」 入試までまだ時間的余裕はあるけれど、これまで勉強してきた単元に不安がある、短期間に復習をしたいという人に最適です。 8日間で中学1年、2年の復習と定着確認ができます。 使用時期は3年生に進級する直前の春休みや3年生の夏休み頃がおすすめです。 「10日間完成 中学3年間の総仕上げ」 こちらは3年間の総仕上げができる問題集です。 使用時期は3年生の夏休み∼冬休み頃がよいでしょう。 入試のリハーサルができる模擬テストの入試チャレンジテストつきです。 どちらも、机に飾って眺めるだけで勉強の役に立つ「応援日めくり」や 点数を記録して弱点を発見できる「ふりかえりシート」など、 楽しく前向きに学習できる付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 完全攻略 【高校入試】 「中1・2の総復習」「3年間の総仕上げ」 完全攻略高校入試は、効率よく勉強をして、高校入試を攻略したい人にぴったりの問題集です。 「中1・2の総復習」 入試に向けての基礎力をつけるにはこちらがおすすめです。 入試出題範囲の約7割を占める、中1・2年の学習内容を効率よく復習でき、苦手な単元の克服にもぴったりです。 「3年間の総仕上げ」 入試に向けての実戦力をつけるにはこちらがおすすめです。 入試で出題頻度の高い問題を、出題形式別や模擬テスト形式など、さまざまな角度から演習ができます。 どちらも、要点とポイントが簡潔にまとめてあり、標準問題からステップバイステップで入試レベルまで力を伸ばせます。 「中1・2の総復習」は1カ月程度、「3年間の総仕上げ」は2カ月程度で取り組めます。ボリュームがあるため計画的に進めるのがよいでしょう。 単元内容をいつでもどこでも確認できる赤シートつきミニブックの「入試直前チェック」や、 いつ、何ページやるのか計画を立てやすい「学習計画表」など、 学習をサポートする付録が充実しています。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 7.まとめ 中学生の学力向上には問題集が効果的ですが、目的を決めてレベルに合ったものを選ぶ必要があります。 教科書準拠の教材を使えば、普段の予習・復習として基礎を固めることができますし、 入試対策の教材を使えば、効率的に目標とする高校の合格に近づけるでしょう。 本記事を参考に、自分に適した問題集を見つけてみてください。 そして、ぜひ文理が発行する問題集を学力アップにお役立てください。 問題集は各ネット書店でも購入できますので、ぜひご検討ください。
【2025年度最新】小学生向け問題集7選|子どもに適した問題集で学力アップを目指そう
「学力を向上させたい」「勉強習慣を身に付けたい」そんなときはどうすればいいのでしょうか。 小学生の学力アップには問題集選びが重要です。 ただし、小学生向けの問題集は数多く出版されており、選び方が分からないという方も少なくありません。 そこで今回は、問題集の選び方や小学生におすすめの問題集を紹介します。 問題集の必要性や使用のメリットについても併せて解説するため、問題集を買うべきか迷っている方にも必見の内容です。 目次 1. 小学生向け問題集で家庭学習を始めよう 2. 小学生|問題集で家庭学習するメリット4つ 3. 小学生の問題集を選ぶ4つのポイント 4. 基礎から応用まで!全学年におすすめの「小学教科書ワーク」 5. 毎日コツコツ!短時間でできるおすすめ問題集3選 6. 中学受験にも!ハイレベルを目指すおすすめ問題集2選 7. 「全科まとめて」で全ての教科を1冊で学習 8. まとめ POINT ・問題集の導入には、「学習習慣が身に付く」「自分のペースで進められる」「経済的な負担が少ない」など複数のメリットがある。 ・子どもの性格や学力、得手不得手に合わせて問題集を選ぶことが大切。 ・学校の授業内容の予習・復習には、教科書準拠品と呼ばれる問題集が適している。 小学生向け問題集で家庭学習を始めよう 家庭学習として授業内容の予習・復習をすることで、 「学習内容が記憶に残りやすくなる」 「苦手な分野を認識できる」 「テストに出やすい問題の傾向を掴める」 といった効果が期待できます。 さらに、中学校に進学した際、「勉強のやり方が分からず困ってしまう」「授業についていけない」といったことが起こらないようにするためにも、小学生のうちに正しい学習方法を身に付けておくことが重要です。 学習方法が分かっていれば、たとえ勉強内容の難易度が上がっても自身の力で学習を継続できます。 学校での勉強だけではなく、問題集を使用した家庭学習も導入しましょう。 小学生|問題集で家庭学習するメリット4つ 問題集を用いた家庭学習は、子どもの学力を高めるための代表的な学習方法のひとつです。 塾に通ったり通信教育を始めたりするよりも気軽に導入できるため、「問題集でも効果はあるの?」と、疑問を感じている方もいるでしょう。 ここでは、問題集による家庭学習のメリットを4つ紹介します。 メリット1 学習習慣が付く 小学生のうちに家庭学習を始めておくことで、「机に向かい決まった時間勉強をする」という習慣が身に付くのが最大のメリットです。 歯を磨くことや顔を洗うことと同じように、勉強することが日常生活の一部になれば、テスト勉強や受験勉強の際にも大きな抵抗を感じることなく勉強に取り組めるでしょう。 また、小学校で習う勉強内容は、中学校や高校で習う勉強の基盤になるため、毎日自主学習し基礎をしっかりと固めておくことが大切です。 メリット2 子どもの理解度に合わせられる 学校の授業や塾では、複数人で一緒に勉強を進めます。 しかし、学習の理解度や得意・不得意な分野は人それぞれのため、じっくりと理解を深めたい子と、どんどん先に進みたい子の間で差が出てしまう恐れがあります。 一方、家庭学習の場合は、自分のペースで学習することが可能です。子どもの理解度やモチベーション、その日の体調などを見ながら進められます。 メリット3 親子で楽しく学べる 「家庭学習は、子どもが一人でやるもの」と考えている方もいますが、家庭学習は親子で一緒に勉強することが大切です。 学習内容の確認や解説を通して自然と会話が増え、信頼関係を深められるといったメリットがあります。 また、おうちの方と一緒に勉強すると「勉強が楽しい」「今日も褒めてもらえるかな」といった前向きな気持ちが生まれるかもしれません。 会話を交えて楽しく取り組むことで、子どもの学習意欲向上の効果も期待できるでしょう。 メリット4 費用が抑えられる 塾や家庭教師といった他の学習方法と比べると、問題集による学習は費用負担が少ないです。 たとえば、通信教育を始める場合は月に3,000円~数万円程度、塾に通う際は月に1万円~数万円程度の費用がかかります。 一方、問題集による学習では、基本的に教材の購入費用しかかかりません。 金額は問題集によって異なりますが、数百円~数千円程度で購入できるものがほとんどです。 家計にかかる経済的な負担を軽減できるのもメリットのひとつでしょう。 小学生の問題集を選ぶ4つのポイント 小学生向けの問題集にはさまざまな種類があるため、子どもに合った内容のものを選ぶことが大切です。 「何となく」で選んでしまうと、せっかく家庭学習を導入しても思うように学習が進まない可能性があります。 問題集を選ぶ際の重要なポイントは全部で4つです。ポイントを押さえて、適切な教材を選びましょう。 ポイント1 続けられるかどうかが重要 最初から問題量が多く時間のかかるものを選ぶと、子どもの負担になりかねません。 勉強自体を苦痛に感じてしまう可能性があります。 子どもの集中できる時間は意外と短いものです。 最初は易しい問題や一問一答形式の問題など、達成感を得やすいものから始めましょう。 家庭学習に慣れてきたら学習時間を少しずつ伸ばしていくことで、大きな負担をかけることなく集中力を高められます。 ポイント2 教科書に対応したものは使いやすい 学校の授業内容の予習・復習をしたり、テスト範囲を学習したりする際は、教科書準拠品が使いやすいでしょう。 教科書準拠品とは、普段使っている教科書の内容に準拠して作られた問題集のことです。 教科書に書かれている用語などがそのまま使用されていたり、教科書の参照ページが記載されていたりするため、教科書の内容に関する理解を深めたいときに適しています。 また、習っていない問題が急に出てきたり問題の傾向が違ったりして、混乱してしまうという心配もありません。 教科書準拠問題集を探すなら ポイント3 子どもの好みを尊重する 小学生向けの問題集には、イラストが描かれていたり、カラーが多用されていたりするものがあります。 毎日使用するもののため、子ども自身ができるだけ楽しい気持ちで取り組める問題集を選ぶのがポイントです。 1ページ達成するごとにシールを貼れる仕様になっているものや、最後に賞状がもらえる仕組みになっているものもあります。 さまざまな問題集を比較し、やる気を高められるものを選択しましょう。 ポイント4 適切な難易度のものを選ぶ 基礎ができていない状態でハイレベルな問題集に取り組むと、難しいと感じ、挫折してしまう恐れがあります。 そのため、「基礎」から始め「標準」「応用」「発展」と、少しずつ難易度を上げていくようにしましょう。 問題集には対象年齢や難易度が記載されています。事前にしっかりとチェックし、子どもの理解度に合った教材を選びましょう。 基礎から応用まで!全学年におすすめの「小学教科書ワーク」 これから家庭教育を始める場合や苦手分野の勉強の際は、文理の「小学教科書ワーク」がおすすめです。 小学教科書ワークは、各教科書会社の許可を得て作られた教科書準拠の学習参考書となります。 ここでは、小学教科書ワークの特長について紹介します。 特長1 基礎・練習・応用を段階的に学べる 問題集の中には、「基礎だけ」「応用だけ」と難易度が絞られたものも少なくありません。 一方、小学教科書ワークは「基本のワーク」「練習のワーク」「まとめテスト」と3段階の構成になっているのが特徴です。 1冊の中で基礎から応用に向かって順番に学べるため、効率的に知識を定着させることができます。 また、達成感を得やすいのもうれしいポイントです。 簡単な問題から取り組んで成功体験を積むことで、学習に対するモチベーションを維持できます。 特長2 役立つ付録が充実 家庭学習に役立つ付録が充実しているのもポイントのひとつです。 付録があると楽しく学習を進められるため、子どものやる気につながります。以下は、小学教科書ワークの付録の一例です。 【主要5教科共通ふろく】・わくわくポスター ・実力判定テスト ・わくわくシール(※英語は除く) ・わくわく動画 ・自動採点CBT 【教科別】・国語:漢字練習ノート・算数:計算練習ノート・理科:理科カード(WEB版つき)・社会:社会カード(WEB版つき)、白地図ノート・英語:英語練習ノート、英語カード、音声配信「onhai」、文理のはつおん上達アプリ「おん達」 値段は1冊あたり1,518円(税込)で、1年間使用できます。 塾や習い事に通う際の経済的な負担が気になる方にもおすすめです。 特長3 4科目セットなら主要科目をまとめてカバー 毎年新学期には、小学教科書ワークの4科目セットが販売されます。 通常、教科書ワークを買う際には自分の使っている教科書がどの教科書会社のものか確認しておく必要がありますが、4科目セットは地区に合うものを購入すれば、自動的に自分にあったワークが揃うため選ぶのも簡単です。 学年別のセット内容は以下の通りです。 ・1~2年生:国語・算数・漢字・数と計算・3~6年生:国語・算数・理科・社会※一部地域によって異なる場合があります。 また、4科目セットにはセット限定の特別付録も入っています。 セットの価格は6,072円(税込)で、小学教科書ワーク4冊分と同じ値段です。 そこにさらに付録が付いていることから、バラバラに4冊購入するよりもセットのほうがお得に購入できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 毎日コツコツ!短時間でできるおすすめ問題集3選 学習習慣を身に付けたいときや集中力を高めたいときは、空き時間を利用して気軽に取り組める「ドリル」が最適です。 ここでは、文理のおすすめドリルを3つ紹介します。 ドリルを使用して、毎日コツコツと問題に取り組む癖を付けながら、日々の予習・復習により基礎学力向上を目指しましょう。 教科書ドリル 教科書ドリルは、教科書レベルの問題に毎日少しずつ取り組むことができるドリルです。 コンパクトなA5サイズで、1回あたり10分で問題が解ける構成になっているのも魅力です。 勉強にかかる負担が少なく、自然と集中が続きます。 特に、学習の基礎となる国語・算数については、教科書の内容に合わせて作成された教科書準拠品となっています。 学校の教科書と一緒に使用すれば、授業内容と同じ速度で学習でき、教科書の知識を早期に定着させることに役立ちます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できるがふえるドリル できるがふえるドリルは、一般的なノートと同じB5サイズのドリルです。 空きスペースを利用して大きめの挿絵やポイント解説、豆知識などが記載されており、勉強に苦手意識を持っている子や、楽しく勉強を進めたい子におすすめです。 また、ドリルのページは1枚ずつはぎ取れる仕様になっています。 やるべき範囲が一目で分かるため、「どこまで進めるのだろう」「まだこんなにやるページがある」といった気持ちが起こりにくいでしょう。 勉強に対するモチベーションの維持に役立ちます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 毎日ちょっと365日ドリル 毎日ちょっと365日ドリルは、個別指導の明光義塾と共同開発した英語の教材です。 7日間かけて10単語を繰り返し学習するという明光式メソッドが取り入れられています。 小学校で習う英単語を6冊で完了できるのもうれしいポイントです。1日1ページ進めれば、1年半で学習が完了します。 なお、読み書きだけでなく、リスニングの学習も可能です。スマートフォンやタブレットで全ての単語の音声を確認できます。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 中学受験にも!ハイレベルを目指すおすすめ問題集2選 家庭学習が定着してきた方や受験の予定がある場合は、難易度の高い問題集にも積極的に取り組みましょう。 ここでは、ハイレベルを目指す方におすすめの問題集を2つ紹介します。 トップクラス問題集 トップクラス問題集は、中学入試に備えた問題集です。 小学校1年生から4年生までの国語と算数に対応しており、全8種類あります。 中学入試問題の出し方や傾向に基づいた内容になっているのが特徴で、学力診断ができる「総しあげテスト」も付帯されています。 さらに、問題集の答えが記載されている「答えと解き方」に、各問題の考え方や指導のポイントが書かれているため、勉強の教え方が分からない場合や指導に難しさを感じている保護者にとっても役立つ1冊となるでしょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル算数ドリル ハイレベル算数ドリルは、得意を伸ばしたい子や学校の勉強では物足りないと感じている子に適した教材です。 問題は「標準レベル」「ハイレベル」「トップレベル」の3段階構成になっており、学習の理解度に合わせて学びを深められます。 ドリルの紙面はオールカラーで、子どもでも取り組みやすいデザインを採用しているのが特徴です。 問題集のページ上部には、学習のねらいやアドバイスも記載されています。 また、解答の「てびき」には答えの導き方も記載されているため、問題の解き方が分からない場合も安心です。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 「全科まとめて」で全ての教科を1冊で学習 「どのドリルがよいか分からない」「問題集選びに悩む」というときは、1冊で全教科の内容を学習できる「全科まとめて」がおすすめです。 1ページごと切り離せるようになっているため、取り組む範囲を一目で確認できます。 また、表面と裏面に同じ問題が載っており、2回取り組めるようになっています。 集中が続かない子や達成感を味わいたい子に適した問題集です。 なお、学年別に「ひらがな」や「九九」「都道府県」などが記載された便利なボードも付いてきます。 リビングや勉強部屋に貼り、学習を促しましょう。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら まとめ 小学生は中学校や高校で習う勉強の基礎を学ぶ大切な時期です。 学校での授業だけでなく家庭学習も導入し、学習習慣を身に付けましょう。 毎日机に向かう時間を設けることで勉強をする癖ができれば、テスト勉強や受験勉強の際に感じる負担を軽減できます。 家庭学習の際は、市販の問題集を利用すると便利です。 小学生向けの問題集選びに悩む場合は、文理の教科書準拠の問題集がおすすめです。 問題集は各ネット書店でも購入できますので、ぜひご検討ください
「365/46」
このブログがアップする11月15日は、1年365日のうち残り46日という、なんとも安易なタイトルと思われるかも知れないが実はちゃんと落ちがあったりして、ともかく11月というのは私にとっていつも、あるノスタルジーを思い起こさせられてしまうことがある。 北海道出身者にとって本州の、いや東京の11月というのは、同じ日本でもこんなにも違うものかと感じるのは私以外にも多くいるであろう。東京の11月は基本的にいつも晴れていて気温は20度前後で過ごしやすく、毎日がお出かけ日和でなんだかこう、とてもいい月なのである。THE秋なのである。 対して北海道の11月は、それはもう暦通り初冬であって、こちらは基本的に天気がいつもぐずついており、わずかな晴れの日が本当に小春日和であって、三温四寒をすっとばして二温五寒といっても過言でなく、朝、暖かいから薄手の格好(とはいってもすでに上着は必須)で出て行ったら、帰りは北風ビュービュー、そして雪になるかならないかのような冷たい雨で、気を許すと一発で風邪をひいてしまう、そんな命がけと隣り合わせなのが、北海道の11月の学生たちだったりする。 私の中学校は山の麓にあり、3年間であらゆる登下校ルートを探ったが、どうしても徒歩45分の壁を破ることが出来ず、友人と別れた後のひとり帰り道20分間は、妄想をするくらいしかなかった。 帰り道の最大の難所は、ここを通らなければ家に帰れないほぼ1キロの直線道路であって、私が住んでいたところは、当時はまだ新興住宅街のはしりだったことから、住宅街というよりは原野にポツポツと家が建っているといった、それはもう、前後左右遮るものがなく非常に開放的な直線道路であった。 で、11月である。北海道の11月は日が沈むのも早く、16時半にはもう既に真っ暗だったりして、北風は容赦なく吹くは、みぞれ交じりの雨が降る中、その直線ほぼ1キロを歩くのはほぼ罰ゲームであり、時間にして約10分をいかに過ごすかが、1日の中で一番難儀なことであった。 何か楽しいことを考えようにも、かように過酷な状況では土台無理なことであって、それならば逆に苦痛のことを考えれば、この外的環境と中和されてイーブンになるのではと考えた。そして、当時の最大の苦痛は英単語を覚えることであった。 覚え方は至ってシンプル。北風にさらされながら、頭の中でひたすら単語を書くのである。そして比較的文字数の多い単語を選んだ。真っ暗の中、体を縮こまってブツブツと何かを言っている中学生は異様だったであろう。 一番覚えているのが「understand」であって、なぜ「下」と「立つ」を合体させたら「理解する」になるのか、それこそ全く理解できなかったのだが、無になり、念仏のように唱えていたら、頭では理解できずとも、いまだにその単語だけは自信を持ってその意味を答えることができるのは、苦行の賜物だと思っている。なおそれ以外、苦行中で唱えたであろう単語はほぼ覚えることが出来なかった。理由は暗記をするにあたり、文字として書かなければ私のスペックでは覚えることが出来なかったからだ。無念である。 そして30年後、そんなアホらしい苦行をせずとも、確立されたメソッドにて英単語を覚える本をプロデュースすることになるとは、当時の私は思いもよらなかっただろう。それが個別指導塾で超おなじみ、明光義塾さん監修の「毎日ちょっと365日ドリル英語」である。 1週間に10個の単語を確実に覚えるそのメソッドは、1日1ページ、1週間計7枚にて、その10個の単語をありとあらゆるやり方で習得する、それはそれで根性が必要になってくるが、北風や冷たい雨にさらされなくとも、あたたかいご自宅で英単語をしっかりと覚えることが出来るのだ。ぜひぜひ一度お手に取ってご覧頂きたい。なおこちらの商品は小学生で学ぶ英単語約700語を収録しております。 さて今年も残り46日である。年の瀬が近づく毎年11月になるといつもあの苦行を思い出し、懐かしくもそして故郷の寒空に思いを馳せるのである。 【今回の執筆者】 イニシャル:O 所属:営業部門 年代:40~50代 今回のひとこと:東京も冬はやっぱり寒かったりする
いま、“大人”に伝えたい! 「小中学校の勉強やり直し」オススメ書籍3選
小中学生の保護者の皆さま、突然ですが、こんな経験はありませんか? ☑テレビのニュースを見ていたら、答えられない質問を子どもにされた。 ☑子どもの勉強の相手を小学校までしてたけど、中学校に上がって内容がわからなくなった。 ☑生活での疑問や悩みに直面して、「あの頃もっと勉強していれば……」と思わされた。 人生100年時代などと謳われているとおり、現代は子どもだけでなく、大人になっても勉強を続ける時代。 ……というのは言いすぎかもしれませんが、 「わからなかったことが、わかる。」 「自分が、昨日の自分より成長している。」 という感覚は、代えがたい喜びです。 そこで今回は、「大人の皆さんにこそ伝えたい、【学び直し】にぴったりの文理の教材」を(筆者の独断と偏見で)ご紹介したいと思います! オススメ書籍その1:『わからないをわかるにかえる 中学公民』 ※『わからないをわかるにかえる 中学公民』は2025年に改訂しました。本記事に掲載の紙面は改訂前の画像になります。最新版のご案内はこちら。 中学生向けの超基礎問題集である『わからないをわかるにかえる』シリーズ。 本シリーズは、中1~中3の国語・数学・理科・社会・英語…と多種多様なラインナップがあります。 あえてその中から、「大人の学び直し」に最適な1冊を選ぶなら、「中学公民」をオススメします。 中学の「公民」の授業でどんなことを学習したか、皆さまは覚えていますか? 例えば、以下のような項目を扱います。 ・選挙や政党のしくみ ・家計と消費 ・労働者の権利 ・税金や社会保障のしくみ ……どれも、大人の私たちからすると、身近な話題ですよね? 正直なところ、筆者が中学生のときは、 「地理、歴史と比べて、公民は暗記ばかりでつまんない」(←失礼) と思っていました。 しかし、大人になり社会経験を経た今こそ、公民の学習内容は身にしみることが多いです。 △本紙34ページ。つい先日に参議院選挙がありましたが、小選挙区制と比例代表制の違いを身近な人に説明できるでしょうか? 『わからないをわかるにかえる』シリーズは、左ページで解説をし、右ページで問題を解く仕組みになっているので、その名の通り、「わかりやすさ」は折り紙つきです。 △左ページに解説、右ページに問題 右ページの問題の多くは左ページの解説を見ることで解くことができます。 問題を解くことで、一時しのぎでない、ずっと残り続ける「知識」をしっかり定着させられます。 また、同じ『わからないをわかるにかえる』シリーズから、英検®対策本も出ています。 勉強でなにか具体的な目標を持ちたい方は、英検®合格を目標に本書に取り組んでみてはいかがでしょうか? △『わからないをわかるにかえる』英検®シリーズ。詳しくは公式ページをご参照ください。 オススメ書籍その2:『中学教科書ワーク 技術・家庭(1~3年 全教科書対応)』 ※『中学教科書ワーク 技師・家庭』は2025年に改訂しました。本記事に掲載の紙面は改訂前の画像になります。最新版のご案内はこちら。 『教科書ワーク』は、小中学校の授業の進度と合わせて学習できる準拠教材で、文理の看板商品ともいえるシリーズです。 この教科書ワークに、国語・数学・理科・社会・英語のいずれでもない、実技の銘柄があるのをご存じですか? 現在は「美術」「音楽」「保健体育」「技術・家庭」の4銘柄が出ており、 いずれも学年別でなく、また特定の教科書に紐づかない「全教科書対応」の銘柄です。 中学での実技科目は、高校入試で扱われないためか、どうしても相対的に小さく扱われがちです。 私自身も中学生のときは、 「実技とか、おまけでしょ」(←失礼) と正直思っていました……。 しかし、実は大人になった今こそ、実技(「美術」「音楽」「保健体育」「技術・家庭」)はお役立ち情報の宝庫なのです! ためしに、『教科書ワーク 技術・家庭』の誌面を少しのぞいてみましょう。 あなたは、下の問題を何問正解できますか? △57ページ「情報の技術」より。※現在、通信方式は「http」ではなく「https(Hypertext Transfer Protocol Secure)」が主に使われています。 △87ページ「家族・家庭と地域の関わり」より △101ページ「食品の調理」より △137ページ「金銭の管理と購入(2)」より こたえ ★本記事で出題された問題の答えはこちら (※2ページ目のアンケートについては回答期間を終了いたしました。) ……いかがでしたか? 誌面をご覧いただくとわかる通り、大人になった私たちから見ると、「技術・家庭」には、 「かゆいところに手が届く~~!」 そんな知識が満載なのです。 今回取り扱った「技術・家庭」だけでなく、「美術」「音楽」「保健体育」など実技の他銘柄にも、大人が身につけていたい教養や、生活の知恵が詰まっています。 この機会に、ぜひ手に取ってみませんか? オススメ書籍その3:『できるがふえるドリル 小学4年 計算』 最後は、これまでと少し違う趣向の1冊をご紹介します。 たとえば仕事を退職されたり、子育てから手離れをしたりして、 「1日で使える時間にゆとりができた」 という方は、「小学校の計算」をやり直してみませんか? 「小学校の勉強なんて……」と侮るなかれ。 紙面を見てみると、意外とややこしいことを小学生がしていることに気がつくはずです。 △小学4年のわり算。しっかり解ききることができるでしょうか? 小学校の「算数」は、中学で「数学」にステップアップします。 それに伴い、必要とされる考え方が、目に見えるものを扱う具体的な思考から、現実の例に落とし込みづらい抽象的な思考へとだんだん移っていき、だんだんと算数に「ニガテ意識」を持つ子どもが増えていきます。 大人になった皆さまの中にも、 「この辺りから、算数・数学がよくわからなくなったんだよなぁ……」 という方がいるのではないでしょうか。 もし生活で自由に使える時間が増え、新しく何かをはじめようと思った方は、あの頃のニガテ意識を解消する時間をあえて作ってみるのもアリかもしれません。 最新版のご案内 今回の記事では、「大人の学び直し」に最適な文理の教材として、以下の3つの書籍を取り上げました。 ・『わからないをわかるにかえる 中学公民』(※2025年度改訂版のご案内です。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・『中学教科書ワーク 技術・家庭(1~3年 全教科書対応)』(※2025年度改訂版のご案内です。) ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ・『できるがふえるドリル 小学4年 計算』 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 大人の立場になると、自身が持てる時間がどうしても限られてしまいます。 その一方で、「自分が気になったことを好きなだけ勉強できる」のは大人の特権! 今回取り上げた書籍が気になった方は、ぜひ書店に足を運んでみてください。 「大人の教科書ワーク」好評発売中! 2024年2月1日に、文理から初の大人の学び直しシリーズ「大人の教科書ワーク」が発売しました! ”教科書をひもとけば、日常がちょっぴり楽しくなる”をコンセプトに、 教科書を軸にして学び直すことができるシリーズとなっています。2 ▲日常の悩みやギモンを、小中学校の教科書で解決! 「学び直しって何からやればいいんだろう」 「なんとなく中学生くらいの勉強をやり直したいけど…」 といった方におすすめです。 ・『大人の教科書ワーク』 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
夏休みはドリルで復習しよう!
夏休みがはじまりますね。 たくさん遊んで、ぜひいろいろなことを経験してほしいですが、 毎日机に向かって勉強する習慣は、夏休みもキープしましょう。 どうしてドリル学習がいいの? 夏休みにはドリル学習がぴったりです。 実際書店での売れ行きを見ても、毎年この時期はドリルが上位にランクインしています。 ではどうして、夏休みにドリルが選ばれるのでしょうか? 一つの理由としては、1日〇分、〇ページとペースを決めて取り組みやすいから。 せっかく一学期(前期)に身につけた学習習慣をなくさないためにも、ドリル学習がおすすめです。 ドリルの選び方は? 一口にドリルといっても、いろいろなタイプのものがあります。 どのドリルを選んだらいいか迷ってしまう場合は、 次のポイントを参考にしてみてください。 学年・分野で選ぶ 「国語1年」「算数2年」など、教科別のもの 日々の学習におすすめです。 とくに、「教科書準拠版」のドリルは、授業で学んだことの確認にぴったりです。 「かんじ1年」「たし算・ひき算1年」など、特定の領域別のもの 漢字・計算・英単語など、反復練習で習得が必要なものだったり、 教科の中で苦手な分野がはっきりしていたりする場合は、 特定の領域別のドリルで学習しましょう。 夏休みに苦手を克服するのにぴったりです。 「夏休みドリル」「全科まとめて」など、複数教科合本のもの 夏休みなどの長期休暇に、まとめて復習するのにおすすめです。 1冊に複数教科がまとまっているので、取り組みやすいです。 レベルで選ぶ ドリルを選ぶ際は、レベルが自分に合っていることが大切です。 難しすぎれば続けられませんし、簡単すぎれば力がつきません。 書店で実物を見たり、ネットでサンプルを見たりして、 自分に合ったレベルのものを選びましょう。 学習時間で選ぶ 「朝5分」や「1回10分」のように、タイトルなどで学習時間を前面に出している商品もありますが、そうでなくても、 紙面に1回の取り組み時間の目安が書かれているドリルは多いです。 日々の学習であれば、1教科につき10分くらいが続けやすいですが、 夏休みはもう少し学習したいところ。 1回に取り組むページを増やしたり、ほかのドリルと組み合わせたりして、 1教科につき20分~30分くらい取り組むとよいでしょう。 苦手分野は30分、得意分野は10分などメリハリをつけるのもよいですね。 第一印象も大切! 学年・分野、レベル、時間などもドリル選びの大事なポイントではありますが、 「これなら楽しく勉強できそう」「飽きずに毎日取り組めそう」という第一印象はあなどれません。 好みの大きさやデザインのものだと、気分が上がりますし、 シールなどの付録が、学習のやる気につながることもあります。 実際に書店に行って、いろいろなドリルを手に取ってみて、 自分に合ったドリルを選んでみてください。 ドリルの進め方 夏休みにドリル学習に取り組む際に大切なことは、毎日続けることです。 まずは、1日どのくらいやるか、何時からやるかを決めましょう。 時間になったら、ドリルに取り組み、そのあと丸付けもしましょう。 また、学習の記録も大切。 ドリルには、学習した日付や取り組んだ時間を記入できるタイプのものもあります。 ここを記入すると、毎日続けるモチベーションを保ちやすいです。 丸付けが大事! 問題を解いたあとに、丸付けをすることはとても大切です。 とくに漢字ドリルや計算ドリルの場合は、反復により学習を定着させるため、 間違って覚えてしまわないように、解き終わったらすぐに丸付けをして、 間違っていたところを解きなおしましょう。 自分で丸付けをするのが難しい場合は、保護者の方に丸付けをしてもらいましょう。 保護者の方にとっては、毎日の丸付けをするのは大変かもしれません。 しかし、丸付けはお子さまに学習習慣を身につけさせたり、 お子さまの学習の進度や理解度を知ったりする、よい機会になります。 ドリルの中には紙面に赤刷りで解答が入っている、縮刷解答タイプのものもあります。 答えが一目でわかるので、保護者の方が採点する場合も採点しやすいです。 夏休みにおすすめのドリル4選! 最後に、文理の商品の中からおすすめのドリルを紹介します。 自分に合ったドリルを選んで、夏休みにチャレンジしましょう。 教科書ドリル 1回10分。日々の授業の確認に。国語算数は教科書準拠版。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら できる‼がふえる↑ドリル 分野別の標準版ドリル。付録充実。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 全科まとめて 全教科複合型ドリル。夏休みの学習にピッタリ。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ハイレベル算数ドリル 丸付けしやすい縮刷解答。付録充実。 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
中学校生活を完全攻略! リニューアルした完全攻略を語る
この春! 文理の完全攻略シリーズが大幅リニューアルをしました! 今日は、新生・「完全攻略 学年別・領域別」について、語っていこうと思います。 ※かなりポイントを絞った話になります! 概要、また、高校入試シリーズについては特設サイトをご覧ください。 とはいえこれはおさらい! 『完全攻略』シリーズとは? 2008年の刊行以来、長く愛されるシリーズ。 「わかりやすい説明で要点をインプットする」参考書の側面と、 「様々な形式の問題を解いて学習内容をアウトプットする」問題集の側面が合体! 教科書だけではモノ足りないキミに、おすすめの学習参考書! ではさっそく語りましょう!↓↓ 表紙と紙面デザインを一新! まず、完全攻略、今までの表紙と紙面がこちらです。 そして、新しくなった表紙・紙面がこちら! ……いかがでしょうか? がらりと雰囲気が変わり、シンプルかつおしゃれな印象に生まれ変わったのではないでしょうか! 5教科並ぶと、色合いがきれいですね! 表紙の階段部分には、ピクトグラムのこびとさんが! このピクトくんたちは、教科によってさまざまな動きを見せます。 カバーを外したところにも、遊びがあるかも? ぜひ確認してみてください! こだわりの教科別付録! 今回の改訂にあたり、付録が大幅パワーUP! まず、全教科に共通でついているものは、★赤シート付小冊子(スマホにも対応!)★学習計画表(WEBダウンロード)★「定期テスト対策問題」に対応した解答用紙(WEBダウンロード) 解答用紙はこのような感じです。 「定期テスト対策問題」のページと対応した解答欄が印刷された解答用紙を、 WEBからダウンロードすることができます。 本にいきなり書き込まず、解答用紙を何枚かダウンロード・出力しておくと、何回でも解き直すことができますよ! ▼▼ここからがすごい!!▼▼ 完全攻略には、教科の力をのばすのに最適な+αの付録が用意されています。 国語・社会は 「耳ヨリ音声解説」 キャラクターの会話をラジオのように聞き流しながら、重要語句を頭に入れましょう。 真面目なだけの解説音声ではありません! 個性的な妖精たちが織りなす、一風変わった会話に思わず笑ってしまうかも……? \どういうこと?と気になったらチェック!/ 数学・理科は 「完全攻略テスト」 この2教科は、問題量をこなすことが定着への近道。 WEBからテストをダウンロードし,繰り返し演習できます。 苦手な単元も、数をこなして問題のパターンを覚えていくと、解きやすくなるはずです! \しゅばばばばばばばば……/ そして英語! 『教科書ワーク』でもおなじみ「おん達」の完全攻略バージョンが登場! 「おん達 完全攻略」 「Perfect Book」と連動して、自宅でも発音練習や会話の練習ができます。 AIが採点してくれるので、家族や友人と発音対決をしてみては! \ちょっとやってみました/ いかがでしたか? 今回紹介した見どころだけでなく、問題集としてもしっかり実力派です! ぜひ実際に使ってみてください! ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
ドリル選びのすすめ【後編】
こんにちは! 今日は前編に引き続き、ドリルの特長と選び方についてご紹介します! 前編を読んでいない方はぜひこちらから ドリル選びのすすめ【前編】 さっそく、文理のこの4シリーズのうち…… A4判ドリルを、2つ見ていきましょう! ※「ドリル」について 本記事では、図のような綴じ方のドリルについて扱います。 こちらの記事は2022年春時点の情報で書かれたものです。 2024年最新版はこちら▼ 全教科を薄く広く、は全科まとめて ※「全科まとめて」は2025年に改訂しました。下記は旧版の情報です。 「全科まとめて」の裏表紙ですべて説明されているので、見てみましょう。 ということで、 〇何冊も買わなくていい 〇短期間で終えられる 〇カラフルで分かりやすい 〇1枚ずつ切り取って使える 〇英語は聞く練習もできる それが「全科まとめて」です! 目次を見てみると、1冊の中に全教科の学習内容がつまっているのがわかります。 切りはなして、1回分取り組みましょう。 全科ドリルは他社からも何種類か出ていて、「問題の量」「色づかい」「イラスト」「解説の量」などに それぞれ個性があります! ぜひ比較して、目的に合ったものを選んでみてください! さらっと全体をおさらいしたいというときは、5教科それぞれでドリルを買うよりお得かもしれませんね。 特設サイトはこちら。 ★文理で表紙のキャラクターに明確に名前がついているのはこのドリルだけかも… マトちゃんメテちゃんを描いてくださったのはイラストレーターの大塚朗さんです! 算数が得意で、もっとやりたいキミに… 最後はかなり個性的! ハイレベル算数ドリルは、 算数でイチバンをめざす小学生におすすめです! 表紙は大変かわいらしいですが…… タイトルに偽りなく、かなりのハイレベル問題になっています。 学校の勉強では物足りず、もっと力をのばしたいときにはとてもよいです! 逆に、苦手の克服や復習用にはあまり向いていないのでご注意ください。 紙面はオールカラーで、ハイレベルな教材の中では、とっつきやすいデザインです。 難点は、問題をたくさん入れた結果、計算スペースが少ないところです…… 計算用の紙などを別で用意していただくと、さらに取り組みやすいです! 地味にすごいのが「学力診断テスト!」 最後に収録されている「そうしあげテスト」に取り組んで、 大設問ごとの得点を文理HPに入力すると…… 学習診断の結果を見ることができます! 大設問ごとに、正解数に応じたアドバイスを得ることができます。 (今回は全問正解と入力しましたが、それでも声かけしてくれます) 特設サイトはこちら! ドリル選びのすすめ ドリルを選ぶときは、まず目的を意識! 毎日短時間さっと取り組む習慣をつけたい! →小さいサイズのA5判ドリルがおすすめ! カラーかそうでないかなど、お子さまの好みに合わせて決めましょう! 苦手分野の克服を、負担軽めにやりたい! →B5サイズくらいのドリルがおすすめ。 多くの場合冒頭に特長がまとめてあるので、そこを見比べてみてください! キャラクターものも結構あったりします。 お子さまが興味を持てそうなものを、一緒に選ぶといいかもしれません。 手軽に前の学年の総復習がしたい! →「全科」と名のついたドリルがおすすめ! 全教科が1冊にまとまっています。 問題の量や色づかいなどを見比べて選んでみてください。 普通のドリルよりも単元の分け方がざっくりしているため、進行中の授業に合わせて使うと 習っていない内容が混ざってしまうことも。 復習に特におすすめです。 ハイレベルな問題を解きたい! →まずタイトルに「ハイ」や「トップ」が入っているものを探しましょう! ただし、少し力試し……で挑むと難しすぎるものもあるので、 実際に紙面を見る、レビューを見る、などで確認してみてください! ▲サイズも様々! ▲大きめサイズには、はぎ取り式など持ち運びやすい工夫も。 いかがでしたでしょうか。 書店でドリルを選ぶとき、ぜひ今日お話ししたような点に注目してみてください! それではまた! ー小学教科書ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーできる‼がふえる↑ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ー全科まとめてー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーハイレベル算数ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
ドリル選びのすすめ【前編】
こんにちは! 今日から新学期!という方も多いのではないでしょうか。 ご入学・ご進級おめでとうございます。 さて、新しい学校生活が始まり、 書店でドリルでも買っておこうかな、という方もいらっしゃるかと思います。 そんなとき、書店に所狭しと並ぶドリルを見て いったい何がちがうのだろうか? そう思うことはございませんか? 今日は、文理で作っているドリルについて、そのちがいをご紹介していきます! 他社のドリルを見る際にも、参考になれば幸いです。 ※「ドリル」について 本記事では、図のような綴じ方のドリルについて扱います。 こちらの記事は2022年春時点の情報で書かれたものです。 2024年最新版はこちら▼ まず、「文理のドリル」を並べてみます。すみません… さすがに全部を持ってくるのが大変だったので、各シリーズ少しずつ持ってきました。 現在刊行されているのは、以下4シリーズ。 ★教科書ドリル ★できるがふえるドリル ★全科まとめて ★ハイレベル算数ドリル それぞれ特徴があるので、紹介していきます! 教科書ドリルは1回10分! 学習習慣づけに ※「教科書ドリル」は2024年に改訂しました。こちらの記事は旧版の情報です。 教科書ドリルは、A5サイズの小さいドリル。 ▲持った感じ ▲iPhone7と並ぶと 1回あたり10分程度で終わる分量になっており、 毎日さっとドリルに取り組む習慣をつけたい、というときにおすすめです! ※小さい紙面で書く欄は少し小さめ。 苦手を感じている分野については、後述する「できるがふえるドリル」や「教科書ワーク」がよいかもしれません。 国語と算数は、教科書準拠版をご用意! より学校の授業の進度に合わせた学習がしやすくなっています。 ▲表紙の教科書会社名と教科書名を確認 「教科書ワーク」との併用もおすすめです! 名前も似てますしね。 例)ワークで勉強したことを、教科書ドリルでさらに反復。 例)算数の「教科書ワーク」と、算数分野別の「教科書ドリル」を併用。 ラインナップは特設サイトをご確認ください。 楽しい工夫たくさん! 弱点克服にはできるがふえるドリル こちらはB5サイズ。一般的なノートと同じですね。 教科書ドリルが「1回10分、問題をこなして定着させる」のに対して、 「少し勉強が苦手で、楽しく取り組める工夫が欲しい」ときにおすすめです。 ▲楽しく取り組める工夫が随所に。 取り組む時間は、自分で書きこみます。 時間を意識して取り組むことで、集中力もUP! はぎとれるのもうれしいポイントですね! ラインナップはこちらです。 後半へ続く…… 残り2つ、大判(A4判)のドリルについてと、ドリルの選び方まとめは 明日更新しますので、お楽しみに! それではまた! ー小学教科書ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーできる‼がふえる↑ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ー全科まとめてー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ーハイレベル算数ドリルー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら
新学期までにココだけは! 新中学3年生 押さえておきたい復習ポイント
新中学3年生のみなさん、進級おめでとうございます。 高校入試を控えた受験生にとっては、勝負の1年になりますね。 中3の勉強でよいスタートダッシュを切るには、これまでの復習が大事です。 教科ごとに中2までの学習内容のココだけは押さえておきたい!というポイントをお伝えします。 英語 ・現在、過去、未来、それぞれの形と使い方を理解できるようになりましょう ・can、 may、 mustなどそれぞれの助動詞の意味と使い方を理解できるようになりましょう ・比較に関するさまざまな表現を理解し、使えるようになりましょう ・受け身の形と意味を理解し、使えるようになりましょう 数学 ・分配法則、交換法則、結合法則について確認しておきましょう ・式の同類項のまとめ方を確認しておきましょう ・1次関数の式の形やグラフのかき方、比例との違いを確認しておきましょう ・合同の証明のしかたを確認しておきましょう ・「平行四辺形の2組の対角はそれぞれ等しい」など、図形の特徴を整理しておきましょう 国語 ・熟語の構成、類義語・対義語を理解しましょう(漢字・言語) ・敬語を理解しましょう(漢字・言語) ・活用の有無、活用形を理解しましょう(文法) ・品詞の識別ができるようになりましょう(文法) ・漢文のルールを理解し、書き下し文に直せるようになりましょう(古文・漢文) ・有名な古典の作品名や作者名をおぼえましょう(古文・漢文) 理科 ・気体の性質を確認しておきましょう(中1) ・化学変化について確認しておきましょう(中2) ・食べ物を通した生物どうしのつながりについて確認しておきましょう(小6) ・月と太陽について確認しておきましょう(小6) 社会 ・日本の地方区分ごとの自然と産業の特徴を理解しておきましょう ・武士による政治のしくみが時代ごとにどのように変化したかを確認しましょう 中1・2の復習におすすめの教材 ここでちょっと宣伝です。 高校受験を考えている新3年生には、「完全攻略 高校入試」がおすすめです。 「完全攻略 高校入試」には、 「中1・2の総復習」と「3年間の総仕上げ」の2シリーズがありますが、 今の時期には「中1・2の総復習」がぴったり。 約1か月で、中1・2の学習内容を総復習できます。 ゴールデンウィーク前までにやり切って、中3のスタートダッシュを切りましょう!