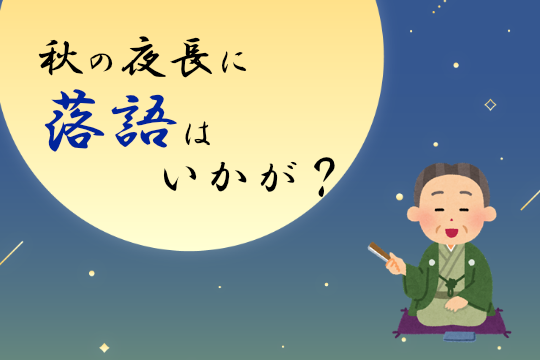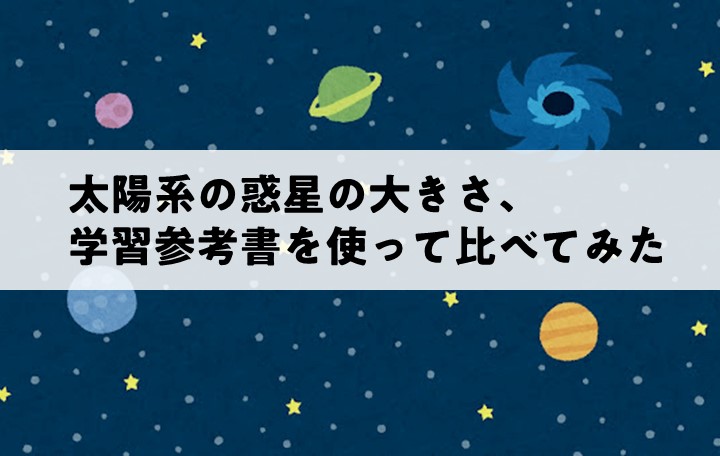なるほど!Bunri‐LOG
対象
読書週間に本を読もう!
今月は「○○の秋」についてたくさんブログを書いてきました。 スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋……、読書の秋ともいいますよね。 ということで今日は読書についてのお話です。 10月27日~11月9日は読書週間 10月27日~11月9日は公益財団法人、読書推進協議会が定める読書週間です。 「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」という理念のもとにスタートした、伝統ある秋の期間です。 読書週間とは… 終戦の2年後の1947(昭和22)年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこちに残っているとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、第1回「読書週間」が開かれました。第1回「読書週間」は11月17日から23日でした。 これはアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」が11月16日から1週間であるのにならったものです。 各地で講演会や本に関する展示会が開かれたり、読書運動を紹介する番組が作られました。 いまの10月27日から11月9日(文化の日をはさんで2週間)になったのは、第2回からです。それから70年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなかでも特に「本を読む国民」の国となりました。今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとなることを願っています。 出典:公益財団法人 読書推進協議会HPより http://www.dokusyo.or.jp/jigyo/jigyo.htm ▲読書週間マーク 読書週間にはイベントもたくさん 読書週間に合わせて、いろいろなイベントを企画している図書館もたくさんあります。 2021年には、全国で1861もの行事主催者があり、展示会や、読み聞かせ、工作などのワークショップ、ゲーム、スタンプラリーなどが企画されたそうです。 今年はどんな楽しいイベントがあるでしょう? みなさんもこの機会に図書館に行って、本を読んでみてはいかがでしょうか?
秋の夜長に落語はいかが?
こんにちは♪ すっかり日がくれるのも早くなり、夜のおうち時間も長くなっている今日このごろ…そんな時は「落語」を聴いてみませんか? 実は最近、青少年向けの落語イベントが増えてきたり、某少年漫画誌で落語をテーマにした連載が始まったりして、ちょっとしたブームになってきているのです。 今回は、そもそも落語って?というところから、おすすめの落語ネタ(演じる話のこと)まで、落語の魅力をたっぷりとお伝えいたします! 1)そもそも落語とは? 2)落語で想像力がきたえられる! 3)「じゅげむ」だけじゃない!おすすめのネタ 4)夏休み、ドキドキ寄席(よせ)体験! 1)そもそも落語とは? 戦国時代、武田信玄や織田信長などの戦国大名が、教養を高めるためにそばに仕えさせた「御伽衆(おとぎしゅう)」。 彼らが気の利いたオチのある小咄(こばなし)をしたのがそもそもの始まりとされています。 その後、安土桃山時代に安楽庵策伝(あんらくあん・さくでん)というお坊さんが登場し、説法がとても上手で聞く人の心をつかむことを心得ていたことから、現在ではこの人物が「落語の祖」と言われるようになりました。 策伝和尚は『醒睡笑(せいすいしょう)』という笑い話をまとめた本(たまに高校入試に出ます!)を出していますが、その中には「子ほめ」など、現在にも伝わる演目の元になっている話があります。 江戸時代前期には、京都に露の五郎兵衛(つゆのごろべえ)、大阪に米沢彦八(よねざわひこはち)、江戸に鹿野武左衛門(しかのぶんざえもん)という、お金を取って落語をやる「職業落語家」が同時多発的に現れました。彼らが現在の落語家の元祖と言われています。 2)落語で想像力がきたえられる! 演劇などとちがい、落語はひとりの人物がたくさんの役を演じなくてはなりません。 衣装も替えてはならず、また、使う小道具は扇子(せんす)と手ぬぐいのみ! このような演芸は世界的に見てもとても珍しいようです。 限られた道具でいろんな話を表現しなくてはならないため、落語家は仕草や声色(こわいろ)、目線の向け方などを非常に細部まで工夫して演じます。 たとえば… 上下(かみしも)を切る 話の登場人物を、顔を左右に振ることにより演じ分ける方法です。 立場が上の人(お殿さまや大家さん)が話す場合は舞台の下手(左側)、立場が下の人が話す場合は上手(右側)を向いて話します。大ベテランの落語家だと、ちょっとした動きであたかもその場に2人の人物がいるように錯覚(さっかく)してしまうことも! 扇子(せんす)と手ぬぐい 落語の小道具として欠かせないのが扇子と手ぬぐいです。 扇子は演目によってお箸(はし)になったり筆になったり手紙になったりと変幻自在です。 また、手ぬぐいも同じく手紙、お財布、はたまた丸めておイモにもなっちゃいます…! この二つが小道具として今も生きているのは、たたんだり広げたりして形を自由に変えられるのが理由のようです。 余談ですが、筆者はある落語家さんが手ぬぐいを「パンツ」に仕立てているのを見ました(笑)。 落語家の工夫が見事であればあるほど、観客も想像力がどんどん広がってその世界にひたることができるのです。 3)「じゅげむ」だけじゃない!おすすめのネタ 「じゅげむ」といえば、教科書にものっているぐらい有名な落語のネタ。 生まれた子どもの長生きを祈って、「じゅげむじゅげむ……」から始まるおめでたい名前を全て付けてみたものの、名前が長すぎていろいろとめんどうなことが起こるという、ゆかいな話です。 落語入門編としてこれさえ知っていれば!というものではありますが、それだけではモッタイナイ! 落語にはほかにもおもしろいネタがたくさんあります。いくつか紹介しましょう。 ☆時そば 江戸時代、そばの立ち食い屋台(移動式)がはやっていたころ。 夜中にそば屋を呼び止めた口のうまい男が、看板からドンブリからそばの味までさんざんほめちぎり、最後に「いくらだい?十六文か。細かいのしか持ってないんだ、一つ、二つ、三つ、…八つ、今なんどきだい?」「九つで」「とお、十一、十二、…」と、一文うまくごまかしてしまう。 それを見ていた男、自分もマネしようとするが…? ちなみに、「九つ」は昔の時間の数え方で、深夜0時のことを表します。落語家によってそばを食べる表現がまったく違うので、それも楽しめるお話です。 ☆抜け雀(すずめ) あるびんぼうな旅館に泊まった絵師が、宿代を払う代わりに衝立(ついたて。部屋と部屋をしきるもの)に描いた五羽の雀。 なんと、朝になると絵から抜けて飛び立ち、しばらくすると戻ってきて収まる不思議な雀だった! たちどころに評判になり旅館がはんじょうするように。 しかしある日、旅館を訪ねた立派な身なりの老人。「この雀は弱っておる…」と言いだして? 衝立から抜け出す絵の雀を想像するだけでわくわくする、ファンタジーあふれるお話です。 ☆お菊の皿 江戸時代から伝わる有名な怪談(かいだん)「番町(ばんちょう)皿屋敷」。 主人が大事にしていた皿を1枚盗んだというぬれぎぬを着せられて殺された女中のお菊が、夜な夜な幽霊となって現れるというお話です。 近所の廃屋敷にそのお菊が現れるとうわさを聞きつけた町内の若者たち。 怖いもの見たさで忍び込んだところ、確かに「いちま〜い、にま〜い…」と皿を数えるお菊の姿が! 10枚組の皿のうち6枚まで数えたところで逃げだした若者たちですが、繰り返し通ううちに、だんだんそのスリルが病みつきになってきて…?? シリアスなはずの怪談話が、最終的にエンターテイメントに変わっていくのがなんともいえず面白い。 昔も今も、若者たちはホラー好きですね(・_・; 4)夏休み、ドキドキ寄席(よせ)体験! 筆者の小4息子、テレビで「笑点」を見ているうちに落語に興味が出てきたようで、「寄席(よせ)に行ってみたい!」と言いだしました。 寄席とは、落語や漫才、講談などが行われる演芸場のことです。東京には主に5カ所(新宿末廣亭・上野鈴本演芸場・浅草演芸ホール・池袋演芸場・国立演芸場)あり、大阪にも天満天神繁昌亭(てんまてんじんはんじょうてい)という場所があります。 そのうちの上野鈴本演芸場昼の部に行ってきました。大人は3,000円、小学生は1,500円でおよそ10〜14組の演芸が楽しめます。 寄席はだいたい昼と夜の2回開催されていますが、比較的昼の部のほうが子連れのお客さんが多いように思います。 また、演者さんも、客席に子どもがいる時は子どもにもわかりやすいネタにしてくれるなど、うれしい気遣いがあることも。 息子と行った時は、女性の落語家さんが「客席に子どもいるね〜」というような感じでいじって(?)くれて、ちょっとうれしかったです♪ そして紙切り芸の先生からはこんなサービスも! たった1本のハサミで切り絵を作るとか、もう神業すぎる… 親子ともども、大満足の寄席体験でした! 最後に… 生の落語を見に行くのはちょっとしきいが高いかも…と思う方もいるかもしれません。 今どきはYouTubeや音楽ストリーミングサービスで落語の名演が公開されていることも多いので、興味があれば、ぜひ聴いてみてくださいね♪ おあとがよろしいようで…! 参考図書: 『マンガで教養 やさしい落語』(朝日新聞出版) 『新版 落語手帖』(講談社) 『あかね噺』(集英社) [今回の執筆者] イニシャル:F 所属:編集部 国語・日本語課 好きな落語:井戸の茶碗/あくび指南
おいしい給食、楽しい給食
秋といえば… スポーツの秋、芸術の秋、そして食欲の秋、ですね。 もうすぐお昼時。お腹がすきましたね。 「学校での一番の楽しみは給食」という人もいるかもしれません。 今日は、そんな学校給食についてのお話です。 栄養満点、安心安全な給食 日本の学校給食は「学校給食法」という法律のもと、安全で栄養バランスの取れた食事が提供されるように定められています。 給食の献立は、栄養士さんが、こどもの発達段階に応じて、必要な栄養素をバランスよく取れるように計算して考えてくれています。 また、食中毒などの事故が起こらないように徹底的に衛生管理もされているので、安心して食べることができます。 給食と食育 食について、正しい知識得て、適切な判断ができるようになり、健康的な食生活を実現できるようになることは、とても大切なことです。 そのため、学校ではいろいろな場面で食育が行われています。 給食の時間もそのひとつ。 給食は、食にまつわる知識や態度を学び、習慣化する良い機会で、 たとえば、次のようなことを学ぶことができます。 ★食事のマナーを学ぶ ★健康に良い食事のとり方を学ぶ ★安全や衛生に気を付けて、準備や後片付けをすることを学ぶ ★食品に含まれる栄養素の働きを学ぶ ★地場産物について学ぶ ★教科等の学習で得た知識を、学校給食を通して確認する 毎日何となく食べている給食かもしれませんが、じつは食についていろいろなことが学べる貴重な機会なのです。 ありがとう、給食 毎日栄養バランスが取れた、安全な食事が食べられるというのはありがたいことです。 食物に感謝し、その食事があなたの口に入るまでに携わってくれたすべての人に感謝して、今日もおいしく給食をいただきましょう。 参考文献:『日本の学校給食と食育』リーフレット
Let’s enjoy sports!
10月の第二月曜はスポーツの日! ということで、今日はスポーツにまつわるお話です。 スポーツの語源 スポーツの語源を知っていますか? 英語の「sport」は、ラテン語の「deportare」(デポルターレ)という単語に由来します。 deportareには、「運び去る、運搬する」という意味がありますが、日々の仕事から離れること、すなわち「気晴らし」の意味もあります。 遊んで、楽しみ、気晴らしすること、それがスポーツの本質なのです。 スポーツを楽しむ スポーツにはいろいろな楽しさがあります。 記録に挑戦し、達成する楽しさ スポーツ競技に参加するときは、何らかの目標をもって参加しますよね。 「県大会で優勝したい」 「中学生記録に挑戦したい」 「自己ベストを更新したい」 そんな目標が達成できたらとてもうれしいですが、 仮に達成できなくても、目標に向かって一生懸命練習してきた充実感が得られます。 自然に親しむ楽しさ スポーツの中には、自然に親しんだり、自然の厳しさに挑戦したりするものもあります。 山を歩いたり、海を泳いだり、雪の中をスキーで滑ったり…。 自然の中で行うスポーツはとくに爽快感があります。 仲間と交流する楽しさ チームメイトと一緒に練習するのは楽しいですよね。 また、よき対戦相手に恵まれるのも楽しいものです。 学生時代にともにスポーツに励んだ仲間との思い出は、一生の思い出になるでしょう。 感情を表現する楽しさ ダンスや体操、フィギュアスケートなどには、感情を表現する楽しさもあります。 これらのスポーツには、競技としての側面以外に芸術的な側面もあり、ときに人の心を打つこともあります。 体力を高め、健康を維持する楽しさ 体を動かすこと自体、楽しいですよね。 スポーツには体力を高めたり、健康を維持したりする効果があり、気晴らしにもなります。 スポーツを楽しもう スポーツへのかかわり方は、スポーツを行うことだけではありません。 スポーツを見ることも、スポーツについて調べて知ることも、スポーツの運営を支えることも、どれも大切なスポーツへのかかわり方です。 「自分は運動神経が良くない」、「運動は苦手だな」と思っている人もいるかもしれません。 でも、スポーツにはいろいろなかかわり方があり、いろいろな楽しみ方があります。 秋はスポーツにうってつけの季節です。 ぜひ、スポーツを楽しんで、日々の生活を充実させましょう。
太陽系の惑星の大きさ、学習参考書を使って比べてみた!
今日、10月4日は、宇宙開発記念日ですね! ということで、今日は少し宇宙っぽい記事です。 地球は、太陽系の惑星 JAXAの学習サイトによると、 太陽系の惑星の大きさは、地球の大きさを1とした場合 水星=0.4(地球0.4こ分) 金星=0.95(地球0.95こ分) 地球=1 火星=0.5(地球0.5こ分) 木星=11(地球11こ分) 土星=9.5(地球9.5こ分) 天王星=4(地球4こ分) 海王星=3.9(地球3.9こ分) そして、太陽の大きさは地球の109倍(!)とのことです。 惑星の大きさのちがい、もっとわかりやすく! 数字で書いても、実際の大きさのちがいってわかりづらいな…… ということで、身近なものに置きかえて、 その大きさのちがいを見てみました! ▲身近なもの=学習参考書 この本はB5サイズで、横幅が182mmあります。 ここに、 でん! と太陽を置いてみましょう。 太陽の直径がこの本の幅と同じ182mmだとしたら、 他の惑星はどのくらいの大きさなのか? この本の表紙にあるあらゆる丸から、それぞれの惑星に近い大きさを探していこうと思います! 他の惑星が何mmになるのかを出す まず、ちょっと面倒な計算をする必要がありますね。 さっき、地球を1としたときの惑星・太陽の大きさを書きました。 今度は、太陽が182mmだったとしたら…?を計算します。 計算結果は以下の通り! これをもとに、探していきましょう! 探していく さて、まずは最初に目についた「8」の丸をはかってみます。 6.7mmくらいですね!! さっきの表で言うと……天王星です。 次に、オールカラーの丸を測ってみましょう。 黄色の線の内側で、18.4mmくらい! 木星を見つけました。 小さい惑星を探せ! ここで大きめの惑星探しが行きづまったので、 おもいきり小さい惑星を探してみることにしました。 狙うは水星、0.4mm…… かなりの小ささです。 表紙右下、学習管理アプリ「まなサポ」ロゴあたりが気になります。 まなサポの「ポ」の半濁点が、0.4mmでした!! 水星発見です。 さらに、本のキャッチフレーズの中から…… 0.8mmの火星を見つけました。 地球が見つからない 困ったことに、地球(約1.7mm)がなかなか見つかりません。 ん? 待てよ…… !!! 背表紙の「8日間」の「8」の下側の丸の内側が、いい感じの大きさでした。 地球発見です。 裏表紙にある、応援日めくりの紹介画像の中からは…… 「1」の丸が金星にちょうどいいのを発見! まだ見つかっていないのは? 色々見つけてきましたが整理すると、 土星と海王星がまだ見つかってないですね…… 海王星は…… カバーをめくったところにある…… タイトルの「の」の字でどうでしょうか! 土星がみつからない 海王星が見つかり、 最後に残るは、土星です。 土星は約15.9mm…… 15.9…… 15.9…… 15.9…… ・・・・・・・ すみません! 土星はどうしても見つかりませんでした!! まとめ 太陽が黄色の丸とすると、 他の惑星はこのような大きさになります。 ほとんどの惑星は、その大きさのちがいもよくわからないくらい小さくなってしまいますね! 太陽がどれだけ大きいのかがわかります。 家にあるもので、太陽と地球を表すとしたらどうなるだろう?など実際に考えてみると 楽しいかもしれません! 宇宙開発記念日をきっかけに、宇宙に親しんでみましょう! 使用した本▼ 「コーチと入試対策! 8日間完成 中学1・2年の総まとめ 英語」 ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ~今回の執筆者~イニシャル:I 所属:営業部門 年齢:20代 今回のひとこと:書いていて不安になる記事でした!
あつ~い話は飽きたから、さむ~い話をしようか
少し秋の気配を感じるものの、日中はまだまだ暑いですね! あつ~い話は聞き飽きてきたころだと思うので、今日はさむ~い話をしてみます! いま日本は暑い夏ですが、日本をとびだして世界中を見渡すと、 同じ時期でももっと暑かったり、逆にもっともっと寒かったりする地域があります。 では昨日8月18日に、一番寒かった地域はどこなのでしょうか? ※この記事では、気象庁HPの『世界の天候データツール(ClimatView 日別値)』を利用しています。 2022/8/18に一番寒かったのは この日観測された中で、もっとも気温が低かった地域は、 ボストーク基地でした! ボストーク基地の場所は……このあたりです。 南極大陸ですね。 8月18日は、平均気温-72.3℃、最高気温-71.0℃! 日本で観測史上最も低かった気温は、 北海道の旭川で1902年に観測された-41.0℃。 それよりも、30℃も低いですね! ボストーク基地は観測史上最も低い気温、-89.2℃が観測されたことでも有名です。 南極大陸は氷でおおわれている! 南極大陸は、地球の一番南側にあります。 その寒さから、大陸には大きな大きな氷の床がかぶさっています。世界で唯一、どこの国の持ち物でもない大陸で、色々な国が研究のための基地を作り、 調査を行う人たちが暮らしています。 氷の床……聞いているだけで、ひんやりとした気持ちになってきますね。 (クーラーの効いた部屋で記事を書いているからかもしれません。) 南極で暮らす動物は、ペンギンやアザラシ、クジラなど…… では問題です。 北極には、ペンギンはいるでしょうか??? ↓スクロール↓ ↓スクロール↓ ↓スクロール↓ 正解は…… ↓スクロール↓ ↓スクロール↓ ↓スクロール↓ いません! ちょっと意外ですね! ちなみに この日、一番暑かったのはクウェートのジャハラー県。 平均気温41.3℃、最高気温は50.6℃でした。(暑い!!)場所はここです。 そう考えると、今日も涼しい気がしてきませんか?夏もあと少し!元気に乗り切りましょう!
暑さとの闘い! 夏の部活あるある10選
夏休み真っただ中、部活動で忙しく過ごしている人も多いですよね。 今日は、「夏の部活あるある」をお届けします! 共感できるものはありますか? その1 顔の汗を拭きたいけどどうしようもできない 競技の特性上、途中で顔に手をもっていけないことってありますよね。 したたり落ちる汗が、目に入ってちょっとしみたり…… ▲剣道部は面が邪魔で拭けない…… その2 練習中に扇風機を使えないため、体育館が蒸し風呂状態に… バドミントン部や卓球部は、扇風機の風が羽根やボールの動きに影響してしまうため、 休憩時間以外は扇風機をつけられないんだとか…… ▲風のない体育館は暑い!! その3 合奏中、音漏れ防止で窓を閉めるため、蒸し風呂になる また蒸し風呂です。 これは学校の環境によって変わってくるかもしれませんが…… 暑さと闘うのは運動部だけではないですね! ▲楽器を演奏するのも体力が必要! その4 ジャグに水を入れるための、水道の奪い合いが起こる 複数の部活が同じ時間帯だと、結構待ちそうですね。 ▲みんなの貴重な水分 その5 休憩時間には日陰の奪い合いも起こる 日陰は本当に偉大です。 ▲校庭は日陰が少ない! その6 部によって日焼けの仕方がちがう 袖の長さやゴーグルの有無などなど、部活によって焼ける部分は変わってきます。 夏休み明けは、日焼けで何部か当てられるかもしれません! ▲日焼け止めはこまめに塗り直しましょう。 その7 凍らせた飲み物を持っていって、解けきらないうちにどんどん飲んでしまい、最後の方は味が薄い これは悲しい…… でも、最初の方は味が濃くておいしいんですよね! ▲どう頑張ってもくだけない その8 暑すぎて、お腹が空いているのに食欲がない シャワーを浴びたり、ちょっと涼しい部屋で過ごすとお腹が空いてくるかも! 暑さにやられないために、少しずつでもなるべく食べるようにしましょう。 ▲夏は冷やし中華やそうめんに助けられます。 その9 部活の帰り道、「暑いって言ったら負け」ゲームをする 「”寒い”の反対!」とか、言いませんか? ▲家が近ければなあという話を永遠にして帰る その10 午前中に部活が終わって、お昼寝して、起きたときすごくさわやかな気持ちになる(お腹も空いてくる) その時はしんどくても、頑張ったあとの時間は格別! ついおやつにも手がのびてしまう……? ▲すがすがしい気持ちの今が、宿題を終わらせる大チャンス! いかがでしたか? 色々なあるあるネタがありますが、読んでいるだけで暑い気がしてくるほど とにかく、「暑い!!!!」が一番の敵になるこの季節! 油断すると、熱中症になってしまうことも…… 常にベストを尽くせるようにするためにも、体調管理はしっかり行いましょう。 あなたの部活には、どんなあるあるがありますか? \暑さに負けず、がんばろう!/
なるほど!Bunri-LOG OPEN
\みなさん、こんにちは/ 学習参考書の出版社、文理です。 今日からスタートする「なるほど!Bunri-LOG」! このコーナーでは、学習に関するさまざまな情報を、ブログ形式で発信していきます。 具体的には、教科のスペシャリストである編集者ならではの視点で、学習のヒントや学習に関するお役立ち情報をお伝えします。 また、マーケティング担当者より、おすすめの商品や、注目のイベント・キャンペーンについてお知らせしたりします。 ブログを読んでくださる小中高生や保護者の皆様に、なるほど!と思っていただける記事を配信できるよう、スタッフ一同がんばってまいります。 これからの「なるほど!Bunri-LOG」にぜひご期待ください!