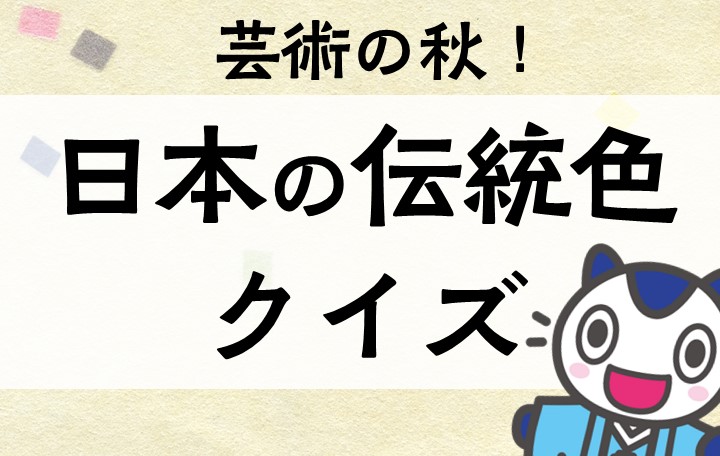Let’s enjoy sports!
10月の第二月曜はスポーツの日!
ということで、今日はスポーツにまつわるお話です。
スポーツの語源
スポーツの語源を知っていますか?
英語の「sport」は、ラテン語の「deportare」(デポルターレ)という単語に由来します。
deportareには、「運び去る、運搬する」という意味がありますが、日々の仕事から離れること、すなわち「気晴らし」の意味もあります。
遊んで、楽しみ、気晴らしすること、それがスポーツの本質なのです。

スポーツを楽しむ
スポーツにはいろいろな楽しさがあります。
記録に挑戦し、達成する楽しさ
スポーツ競技に参加するときは、何らかの目標をもって参加しますよね。
「県大会で優勝したい」
「中学生記録に挑戦したい」
「自己ベストを更新したい」
そんな目標が達成できたらとてもうれしいですが、
仮に達成できなくても、目標に向かって一生懸命練習してきた充実感が得られます。
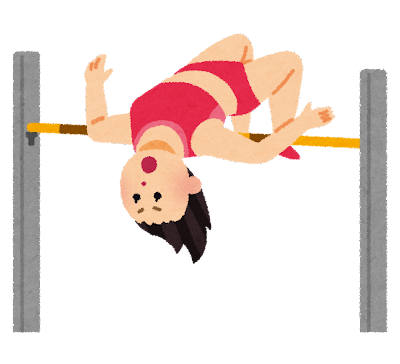
自然に親しむ楽しさ
スポーツの中には、自然に親しんだり、自然の厳しさに挑戦したりするものもあります。
山を歩いたり、海を泳いだり、雪の中をスキーで滑ったり…。
自然の中で行うスポーツはとくに爽快感があります。

仲間と交流する楽しさ
チームメイトと一緒に練習するのは楽しいですよね。
また、よき対戦相手に恵まれるのも楽しいものです。
学生時代にともにスポーツに励んだ仲間との思い出は、一生の思い出になるでしょう。

感情を表現する楽しさ
ダンスや体操、フィギュアスケートなどには、感情を表現する楽しさもあります。
これらのスポーツには、競技としての側面以外に芸術的な側面もあり、ときに人の心を打つこともあります。

体力を高め、健康を維持する楽しさ
体を動かすこと自体、楽しいですよね。
スポーツには体力を高めたり、健康を維持したりする効果があり、気晴らしにもなります。

スポーツを楽しもう
スポーツへのかかわり方は、スポーツを行うことだけではありません。
スポーツを見ることも、スポーツについて調べて知ることも、スポーツの運営を支えることも、どれも大切なスポーツへのかかわり方です。
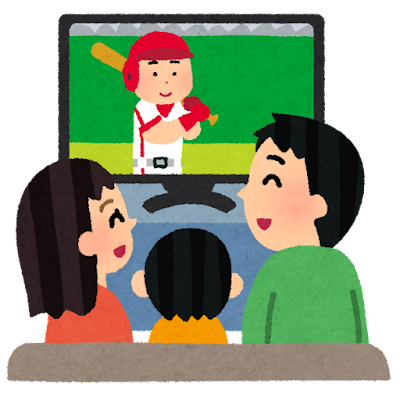
「自分は運動神経が良くない」、「運動は苦手だな」と思っている人もいるかもしれません。
でも、スポーツにはいろいろなかかわり方があり、いろいろな楽しみ方があります。
秋はスポーツにうってつけの季節です。
ぜひ、スポーツを楽しんで、日々の生活を充実させましょう。
関連記事
苦手な実技、どう向き合う?
実技が得意じゃないから、実技科目でいい成績はとれない気がする…… でも内申点のことを考えると実技を無視することもできない…… そういうときは、どうすればいいのでしょうか。 今日は、文理社員に苦手な実技を克服した体験を語ってもらいましたのでご紹介します! ーーーーーーーーーー こんにちは! 文理の社員です。 突然ですが、私はカナヅチです。 ※カナヅチ=「泳げない人」の意 今日はこの場をお借りして、 をお話ししようと思います。 授業はしっかり取り組もう 大前提として、授業はちゃんと受けましょう。 「どうせうまくできないから適当でいいや」と思うと 余計つまらない授業時間になってしまいます。 授業態度も悪く見えてしまって大損です。 私も泳ぎがからきしダメで、いくらコツを教えられても、「いや浮かないのよ…」と思っていました。 当然、水泳の時間も嫌いでした! でも、とりあえず手を抜かずに、できないなりにやる気はアピールすることを意識していました。 とはいえ 苦手な実技は気持ちが沈んでしまって、とても頑張れる気になれない…… そんな人もいると思います。 そういうときのコツは2つ! 1)「できない=だめ」ではないと認識する。 同じ人間でも、一人ひとり骨格や筋肉、ものの感じ方がちがいます。 そんな中では、苦労せずに高く跳べる人やバランスがとれる人もいれば、 それが苦手な人もいる、というのは至極当たり前の話です。 絵にしても歌にしても楽器にしても、同じです! 「ある人はできるのに自分はできない」ことも普通にありえるし、 それはだめなことではないことをまず知りましょう。(逆上がりができなくても、死にはしないので大丈夫です) 2)できないことに対して、具体的に考える。 先程述べたように、出来ないことがあるのは当然です。 ただ、「できない……しょぼん……」としているだけではいつまでも変わりませんし、 どんどん気持ちばかりが沈んでいきます。 できないときは、「なぜできないのか」「その原因をなくすにはどうするか」 を、具体化してみましょう。 たとえば、私はクロールをするときに息つぎがうまくできません。 なぜできないかというと、おそらく息つぎをするときに顔をあげすぎてしまって、 上半身を起こしたような状態になり、どんどん沈んでいってしまうんです。 「ではそれを防ぐためにどうするか?」 たとえば、息つぎの時に耳と腕の距離を近く保つように意識する、というのが考えられます。 こう考えると、「もしかしたら次はできるかも??」という気持ちになってきませんか? もちろん! 人間の体はそんなにかしこくはないので、 意識して、それができるようになるには反復が必要です。 体育の授業時間くらいでは、結局克服はし切れなかった、ということもありえます。 (私も結局息つぎは克服できていないままです……) でもそれでもいいんです。 むしろ、できないことを楽しむくらいの気持ちになれるといいですね。 筆記で盛り返せ!! 授業も頑張るとはいっても、とにかく実技テストに自信がない…… そういうときは、筆記を頑張りましょう! 私は泳ぐのがからっっっきしダメなので、 体育の筆記テストは5教科並みに勉強して高得点をもぎとりました。 実技の筆記テストはテスト範囲の教科書や、プリントの内容を頭に入れることが重要です。 教科書に緑マーカーを引いて、赤シートで確認したりしてそなえましょう。 文理からは、「中学教科書ワーク」「定期テストの攻略本」の2シリーズから、実技対策本が出ています! 問題演習もして、感じをつかんでおきたい人にはおすすめです。 「定期テストの攻略本」は、すでに赤シートで隠せるようになっている&暗記用ミニブック付き! 実技にそんなに時間かけてられない!という人にもおすすめ。 「教科書ワーク」にも暗記ブックはついているので、 カラーがいい、がっつりやりたい、という場合はこちらがいいかもしれません。 ー中学教科書ワークー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら ー定期テストの攻略本ー ▶シリーズページはこちら ▶ご購入はこちら 実技は将来役に立つ! 国語数学英語理科社会……これらももちろん、のちのちまで役に立つ教科です。 しかし、実技科目も5教科と同じくらい、もしかしたらそれ以上に、大人になってから役に立ちます。 たとえば家庭科で習う、野菜の切り方や衣服の取り扱い表示…… 今はまだ、自分で料理や洗濯をしていない人も多いと思いますが、 いつか自分でやることになったときにふんわりにでも知識があるとだいぶちがいます。 保健体育でも競技のことだけでなく、病気の種類や熱中症対策・応急手当の方法など、 生きるために必要なことを学びます。 音楽や美術は、直接生活に役立つ内容ではないかもしれませんが、 ある程度の文化的教養を身につけることは人生を豊かにすることにつながります。 歴史の文化史の勉強にもなりますよ! そう考えると、ちょっとモチベーションにつながりませんか? (私は泳ぎを習得できなかったので、川や海では遊ばないようにしています。) 実技も大事にしていきましょう! 応援しています!
芸術の秋! 日本の伝統色クイズ
冷え込む日も増え、いよいよ秋本番ですね。 先週の記事では、スポーツの秋を取り上げましたが…… 秋といえば、”芸術の秋”でもあります! ということで、今日は「日本の伝統色」クイズをお届けします! クイズスタート! ※各色のカラーコードは和色大辞典を参照しています。 第1問 山吹色(やまぶきいろ) さあ、どんな色でしょうか? 頭の中に、思い浮かべてみてください…… ▼答えをみる 答え これは色鉛筆などでも見るかもしれませんね! 山吹の花が由来になっています。 ▼次の問題へ 第2問 藤色(ふじいろ) これも、聞いたことがあるという人が多いのではないでしょうか。 有名な漫画でも、出てきましたね…… ▼答えをみる 答え このような色でした! 藤の花の色です。 よく、公園のベンチの上などに藤の花のカーテンがありますね。 ▼次の問題へ 第3問 茜色(あかねいろ) これはどうでしょうか。 空の様子を表すときに、よく使われる言葉です。 ▼答えをみる 答え きれいな赤い色でした。 夕暮れ時を、茜色の空、と言ったりしますね。 もともとは、赤根(あかね)という植物の根で布を染めたときの色から来ています。 ▼次の問題へ 第4問 鶯色(うぐいすいろ) ウグイスは鳥の名前ですね! 鳴き声は皆さんわかると思います。 さて、どんな色の鳥なのか、知っていますか? ▼答えをみる 答え このような色になります。 ウグイスの姿は次の通り。かわいいですね。 ▼次の問題へ 第5問 鳶色(とびいろ) 鳶も鳥の名前で、とんびともいいます。 タカの仲間です。 ▼答えをみる 答え 赤みがかった茶色でした。 ちなみに、鳶はこういう鳥です。 ▼次の問題へ 第6問 萌黄(もえぎ) ”黄”という字が入っていますが、果たして……? ▼答えをみる 答え 黄色…ではなく、黄緑ですね! 芽が出ることを、「萌える」といいます。 春に、木々が萌えだすような、そんな黄緑色のことです。 萌木と書くこともあります。 ▼次の問題へ 第7問 浅葱色(あさぎいろ) 葱は、「ねぎ」とも読みます。 ▼答えをみる 答え 葱(ねぎ)の葉を薄めたような色であることから、 このように呼ばれるようになりました。 ちなみに、新選組の羽織の色としても有名です。 ▼次の問題へ 第8問 鈍色(にびいろ) 鈍い、と聞くと、どんなイメージでしょうか…… ▼答えをみる 答え 鈍色の語源は、「さびて切れ味の落ちた刃物の色」です。 今でいうと、濃い灰色や、ねずみ色にあたります。 ▼次の問題へ 第9問 琥珀色(こはくいろ) 琥珀は、宝石の一種です。 ▼答えをみる 答え 琥珀は宝石の一種であり、樹脂が化石となったもの。 はちみつのような色をしています。 ▼次の問題へ 第10問 瑠璃色(るりいろ) 最終問題です! 瑠璃も、宝石のひとつ。ラピスラズリの和名です。 ▼答えをみる 答え とてもきれいな青ですね! この色は、歴史の教科書にも登場します。 奈良時代、正倉院に収蔵された品の中に、「瑠璃杯」という 青いグラスがあったことを覚えていますか? ▼おわりに おわりに 今日は10種類の色を紹介しましたが、 日本の伝統色はもっともっと、たくさんの種類があります。 植物の名前や動物の名前などの自然や、 生活で目にするものに由来した名前が多いため、 調べてみると面白いかもしれません!
おいしい給食、楽しい給食
秋といえば… スポーツの秋、芸術の秋、そして食欲の秋、ですね。 もうすぐお昼時。お腹がすきましたね。 「学校での一番の楽しみは給食」という人もいるかもしれません。 今日は、そんな学校給食についてのお話です。 栄養満点、安心安全な給食 日本の学校給食は「学校給食法」という法律のもと、安全で栄養バランスの取れた食事が提供されるように定められています。 給食の献立は、栄養士さんが、こどもの発達段階に応じて、必要な栄養素をバランスよく取れるように計算して考えてくれています。 また、食中毒などの事故が起こらないように徹底的に衛生管理もされているので、安心して食べることができます。 給食と食育 食について、正しい知識得て、適切な判断ができるようになり、健康的な食生活を実現できるようになることは、とても大切なことです。 そのため、学校ではいろいろな場面で食育が行われています。 給食の時間もそのひとつ。 給食は、食にまつわる知識や態度を学び、習慣化する良い機会で、 たとえば、次のようなことを学ぶことができます。 ★食事のマナーを学ぶ ★健康に良い食事のとり方を学ぶ ★安全や衛生に気を付けて、準備や後片付けをすることを学ぶ ★食品に含まれる栄養素の働きを学ぶ ★地場産物について学ぶ ★教科等の学習で得た知識を、学校給食を通して確認する 毎日何となく食べている給食かもしれませんが、じつは食についていろいろなことが学べる貴重な機会なのです。 ありがとう、給食 毎日栄養バランスが取れた、安全な食事が食べられるというのはありがたいことです。 食物に感謝し、その食事があなたの口に入るまでに携わってくれたすべての人に感謝して、今日もおいしく給食をいただきましょう。 参考文献:『日本の学校給食と食育』リーフレット