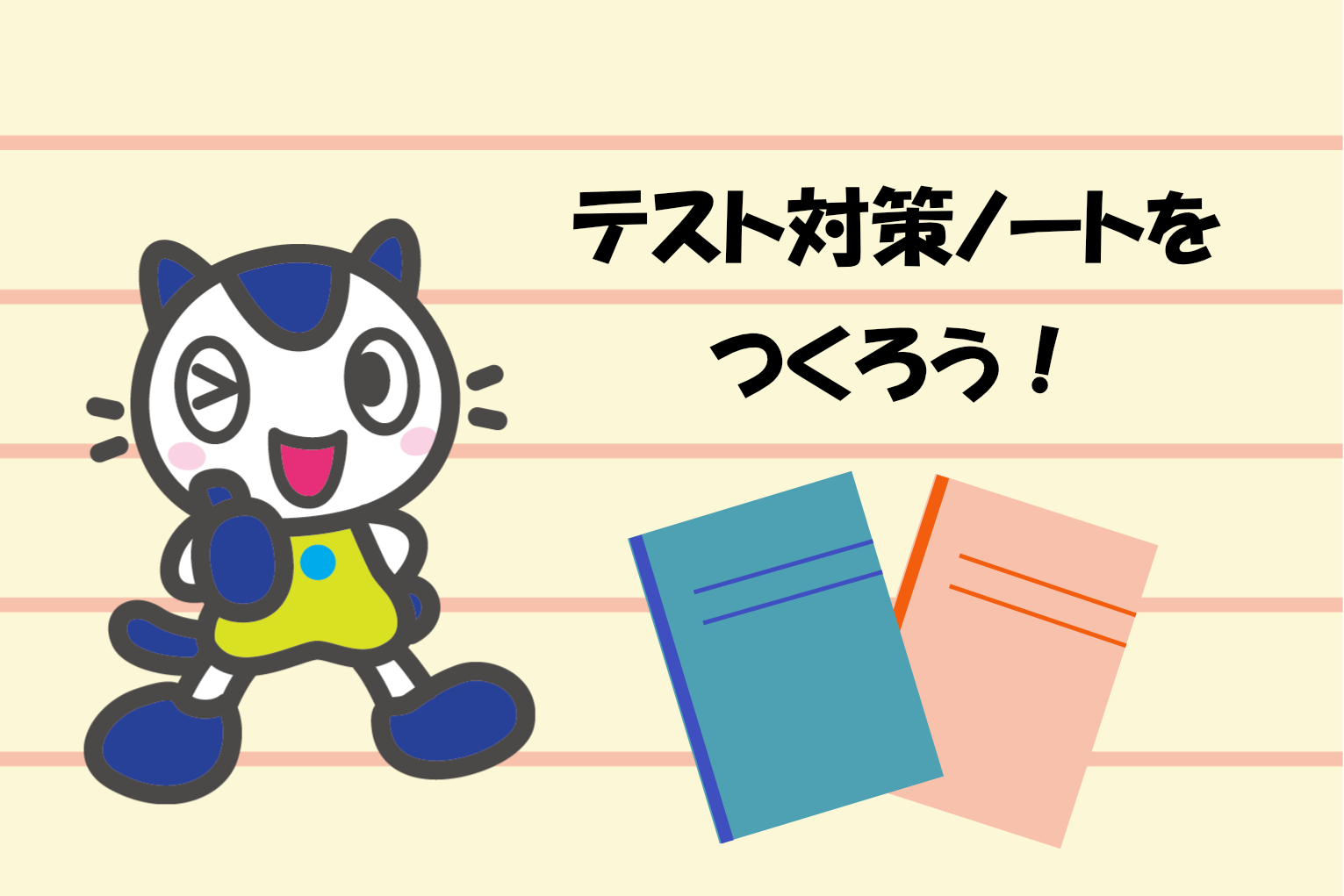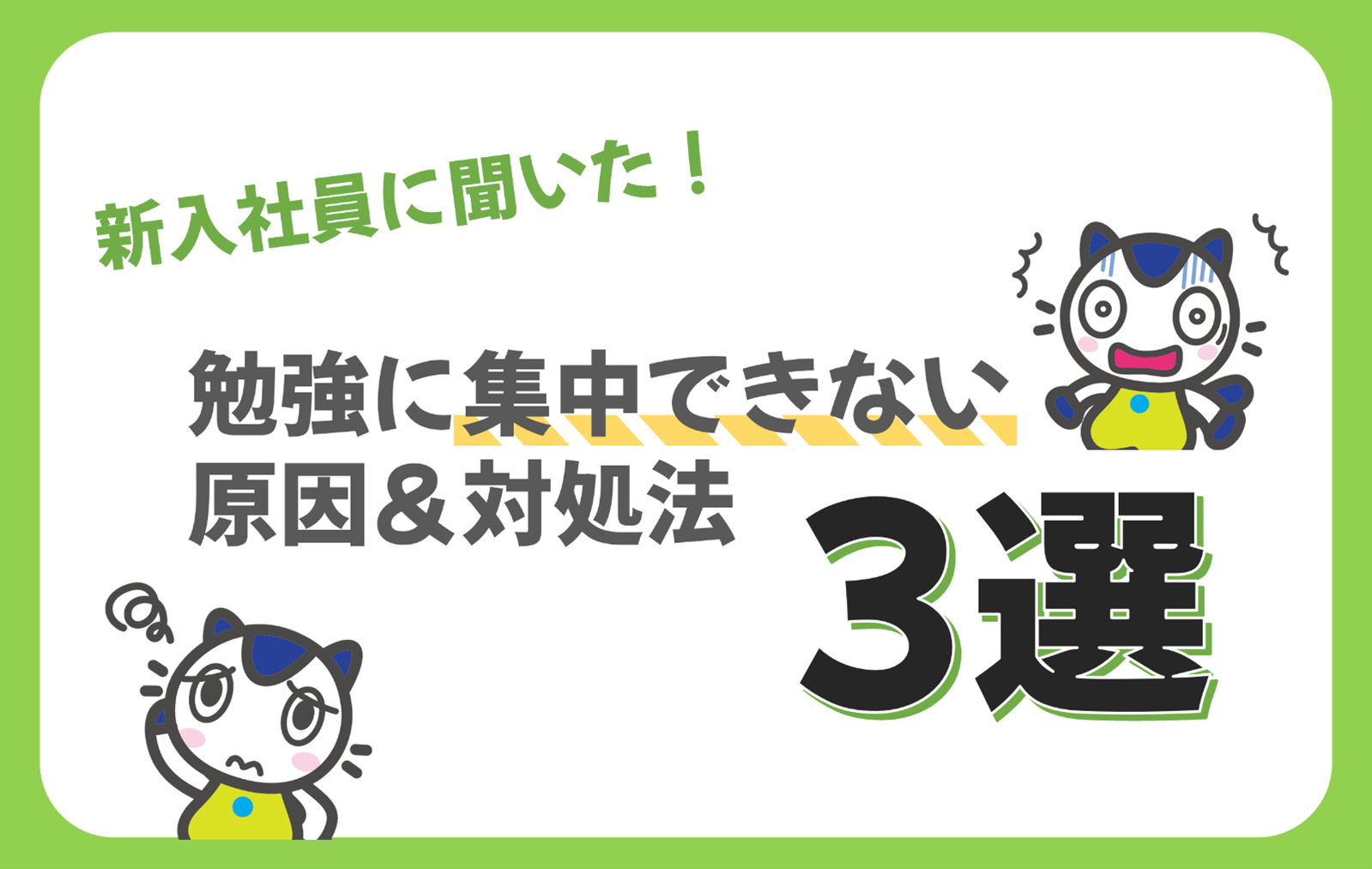定期テスト対策記事まとめました
「なるほど!Bunri-LOG」では、
定期テスト対策に関する記事もいろいろと更新してきました。
今日は、それらを一挙紹介します!
まだ読んでいない記事があったら、ぜひ読んでみてください!
ふだんからできるテスト対策
定期テスト直前の勉強はもちろん大切です。
しかし、ふだんから少しテストを意識しているだけで、
テスト対策がだいぶ楽になります。
そんな、ふだんからのテスト対策に関する記事を紹介します。
【その1】 テスト対策ノートをつくろう!
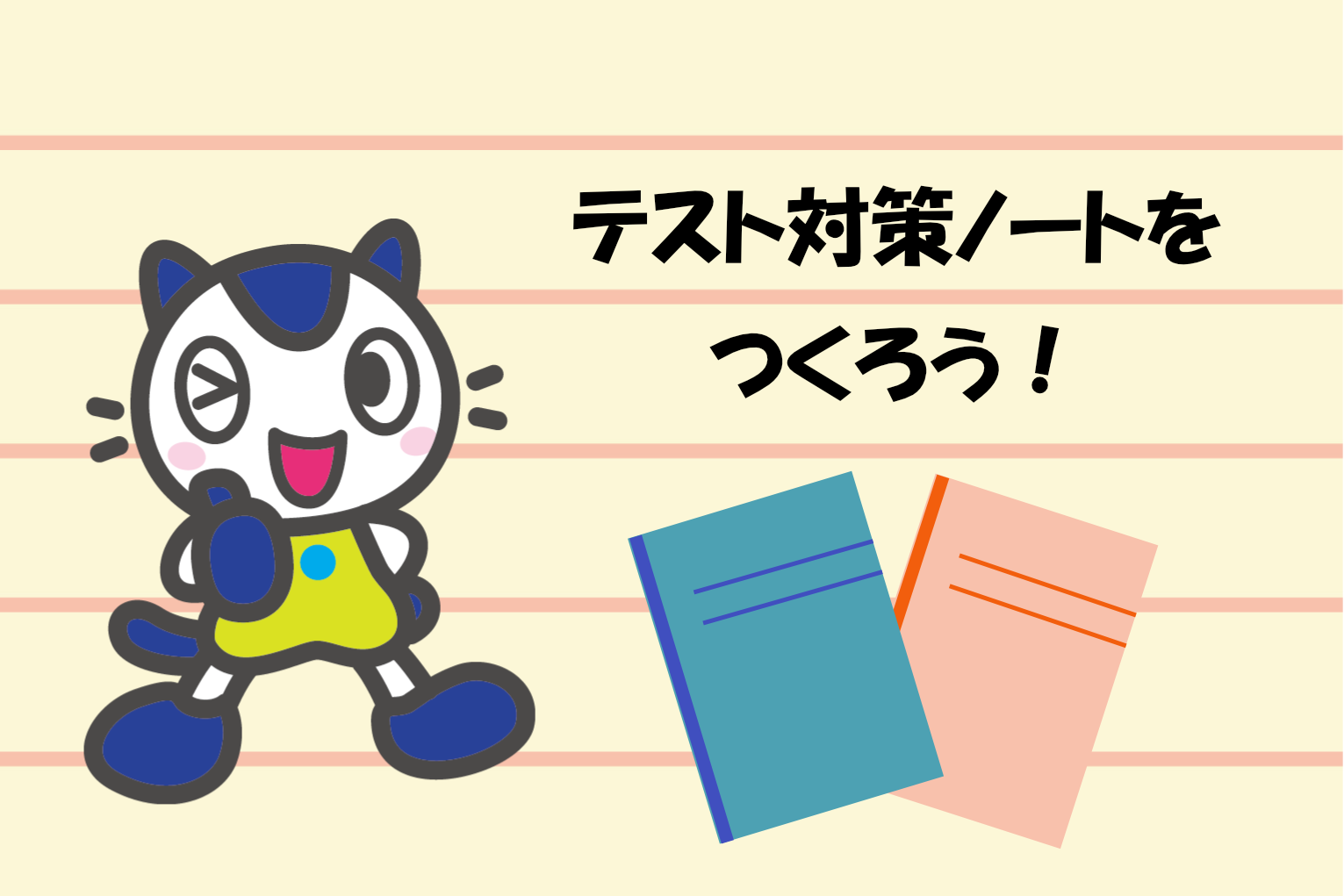
テスト前に授業ノートを使って要点を整理する方法についての記事です。
授業中に、あとから要点整理をしやすいノートをつくるコツも紹介しています!
テスト前の2週間
テスト期間、何をどうすればいいのかわからない!
そんな人におすすめな連載があります。
【連載】定期テスト対策ってどうやるの?

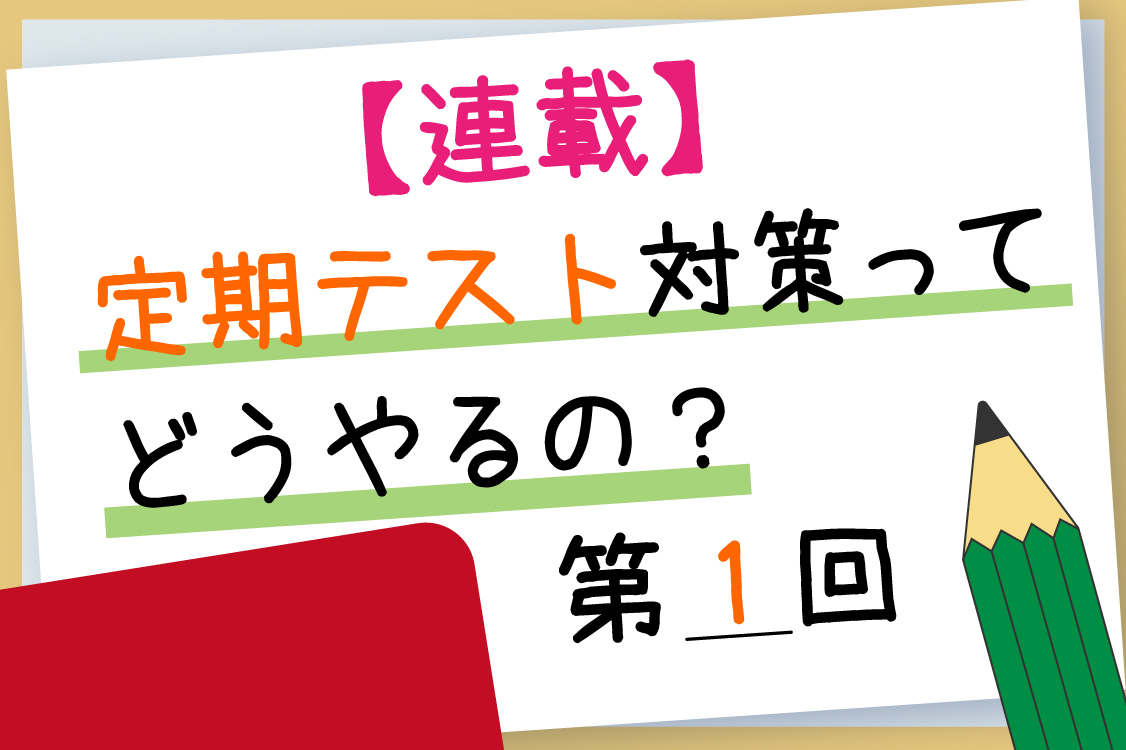
テスト範囲が配られてから、どのように対策をすればいいのか?
その一例をくわしく紹介しています!
5回にわかれているので、気になる回から読んでみてください!
↓
第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤ートで覚える!
勉強のコツいろいろ
やり方を決めて、いざテスト勉強!
勉強をするときの細かいコツについて、3記事ご紹介します!
【その1】 新入社員に聞いた! 勉強に集中できないときの原因&対処法3選

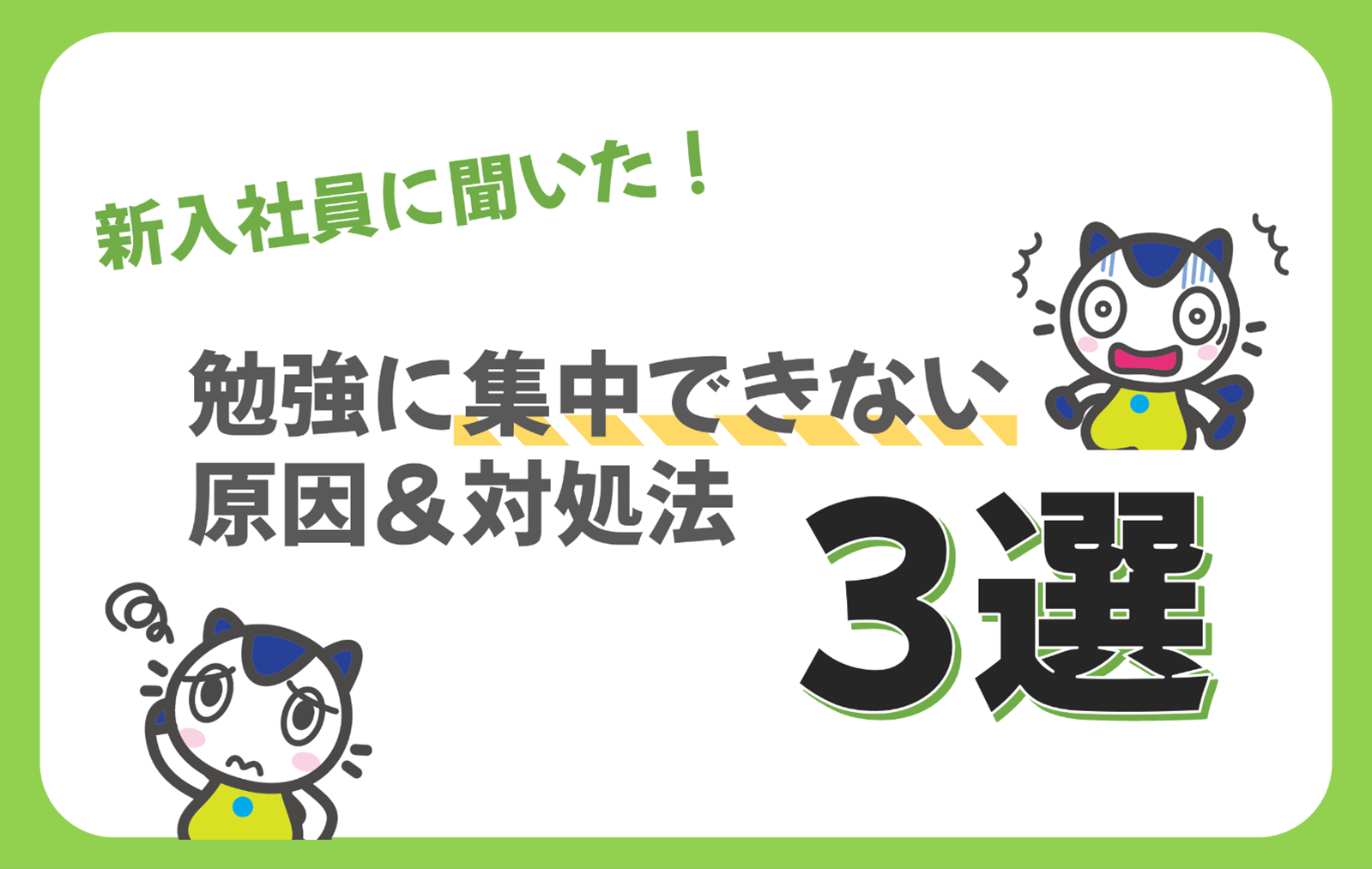
2022年春に更新した記事です。
テスト勉強の大敵は、「集中できないこと」。
文理に入社したばかりの社員に、集中切れへの対処法を教えてもらいました。
「問題が難しくてわからない」「周囲の人や騒音が気になる」「ついスマホを見てしまう」
そんなときありませんか?
【その2】 青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法

色にはいろいろな効果がある!
ノートの色や文具の色に上手に取り入れると、勉強の効率がUPするかもしれません。
【その3】楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ


テスト前は覚えないといけないこともたくさん!
赤シート・単語カード以外にも、暗記方法はいくつかあります。
自分に合う方法を探してみてください!
何を覚えるか?によって、合う方法も変わってくるかも?
テストを受けている間のコツ
【中間テスト後に読もう】定期テストの反省と活かし方 ~ケアレスミスをなくせ!編~

テストのあとに後悔するポイントといえば、ケアレスミス……
ケアレスミスを防ぐためのコツ、それはずばり、「見直し」です。
テストがんばろう!
期末テストも近づいてきていますが、
前のテストがうまくいかなかった人は、
今回の記事などを参考にしながら、何かひとつでも前とやり方を変えてみてください!
少しずつ自分なりのテスト対策を確立していきましょう!
これからも、勉強に役立つ情報をお届けしていきます!
関連記事
【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回
こんにちは! 5月に入り、そろそろ、定期テストの足音が聞こえてきた!という学校も多いのではないでしょうか。中学1年生にとっては初めての大きなテストでもありますね! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届けします。 連載予定 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第1回は、「はじめに 始める時期と最初にやること」です。 定期テスト対策を始める時期 おすすめはずばり、 \\2週間前// です! テストは教科や範囲が広く、1週間前からだとだいぶ駆け足での対策になります。特に、「普段の授業に自信がない」「高得点を狙いたい!」という方は、 早めの対策をおすすめします。 最初にやること どの時期から始めるにしても…… テスト範囲が配られたらすぐやっておくべきことがあります。 それは \\範囲の確認// です。 教科書の該当ページ・資料集の該当ページなどを確認して、 疑問があったら周りに聞いておいてください。 特に、テスト範囲でやったプリントをなくしていないかを確かめておきます。万が一ない場合はクラスの人などに内容を見せてもらいましょう。(コピーや写真をもらえるとベスト!) スケジュールをたてる 範囲を確認したら、テストまでの日数の中でいつ何をするか、を書き出してみます。 これをやっておかないと、 とりあえず目に付いたものを進めていたら、範囲が全然終わらなかった…… 今日何を始めればよいのかわからず、やる気がなくなった…… などの問題が起こります。 何より、「やるべきことをやれてる!」と確認できることは安心感につながりますね! 第2~4回までで具体的なやり方をご紹介した後、 第5回で具体的なスケジュールの立て方もお話しします。 読んでいただきありがとうございます! さて、初回は軽めにお届けしました。 具体的にどうすればいいのよ?!については、次回から紹介していきます! お楽しみに! 第2回へ▶
【中間テスト後に読もう】定期テストの反省と活かし方 ~ケアレスミスをなくせ!編~
こんにちは! 暑い日が続きますね…… 中間テストはどうでしたか? 悔いが残った人もいるかもしれませんが、 過ぎたことをいくら後悔しても仕方がありません! これが人生最後のテストではないわけなので、 次回、テストで同じことを繰り返さないための方法を考えておきましょう! 今回は後悔の中でもっとも多いのではないかと思われる、「ケアレスミスのなくし方」についてです! ケアレスミスっていやですよね…… 「単位を忘れた」「ピリオドを忘れた」 「誤っているものを選べなのに正しいものを選んだ」 これらは、答えは出せているのに少しの注意不足で点を逃してしまう、いわゆるケアレスミスです。 ケアレスミスをなくす一番の対策は、これです! 耳にタコができるくらい聞いているかもしれませんね…… 今日は見直しに関する具体的なコツ3つをお届けします。 コツ1 見直しの時間を確保せよ! 見直しの時間をあまらせるために、解ける問題から解きましょう! 少し考えてわからない問題はどんどん飛ばしてすべての問題に取り組み、 最後に、わからなかった問題に戻って考えます。 残りが10分くらいになったらいったんあきらめ、解けている問題の見直しをします。 見直しが済んだら、あとは時間ギリギリまで、わからない問題に取り組んでください。 ▼例)例えば試験時間が50分だったら…… コツ2 別人格を呼びおこせ! 見直しでありがちなのは、「まあ合っているだろう」という思い込みです。 さらさら解いた問題でも、思わぬうっかりミスをしている可能性があります。 見直しは、とことん自分にシビアな目をもたなければなりません。 そこで、問題を解いた自分とは別の人格になったつもりでやるのがおすすめです。 「自分ではない誰かが書いた解答」というつもりで、 冷静な第三者として解答用紙を見つめましょう! ▼ミスを見つけたら代わりに直しておいてあげよう! コツ3 起こりやすいミスを知るべし! 一度したミスは、二度としたくないものですよね。 どんなケアレスミスが考えられるかを、事前に想像しておきましょう。 例えば… 〇英文のピリオドつけ忘れ 〇冠詞をつけ忘れた 〇m2とm3をまちがえた 〇途中式の簡単な足し算をまちがえた 〇解答欄を1ずつずらしていた 〇字数指定を超えて書いてしまった 〇長文を答える問題で漢字をまちがえた 〇漢数字で書きなさい、なのに算用数字で書いた ・ ・ ・ こういうミスの種類を事前に把握しておくことで、そもそものミスの数を減らすことができますし、 見直しでのミス発見の確率も上がります。 また、見直しの時間が十分とれなかったときは、そのポイントに絞って見直しをして 最低限のミスをなくしましょう。 ▼問題文もよく読んで! ※それでもミスするときはする 見直しのコツを3つご紹介しましたが、もちろん人間である以上、 ここまでやっても間違えることもあります…… それは仕方ないと割り切り、次に同じミスをしないためにどうするか、をどんどん考えてください。 対策をして、それをすり抜けるミスがあり、次はそれもふまえた対策をして……としていくうちに、 自分のベストを出し切れるテストの受け方を見つけられるはずです! どんどん自分をアップデートしていきましょう!
テスト対策ノートをつくろう!
2学期制の中学校は、もうすぐ期末テストの時期ですね。 定期テスト対策には、演習問題を解いてみて、自分の理解度を確かめることも大切ですが、 授業のときにとったノートを見直して、要点を整理することも役に立ちます。 そこで今日は、要点の整理が特に重要な科目である「社会」を例に、 テスト対策ノートのつくり方のコツをお教えします。 1.授業中にとるノート 授業中は、ノートをきれいにまとめることよりも、まずは学習内容を理解して、 それを後から思い出せるように記録することを心がけましょう。 先生の板書を参考にしながら、話の流れや関係性などを意識して、 見出しを付けたり、段落を分けたり、番号を振ったりしておくと、後から思い出しやすくなります。 また、ノートの端に線を引いてスペースを取っておくと、あとからノートを整理するときに役立ちます。 ▼最初に取ったノート 2.テスト前に見直して整理しよう! テスト前には、授業中に取ったノートを見直して、大事なところに印つけたり、 授業中ではよくわからなかったことや、記憶があいまいになっていたことを調べたりしながら、ノートを整理してきましょう。 ① 自分のノートを見直して重要語句をチェックしよう! どれが重要語句かわからない場合は、教科書を見て、教科書に太字で示してあるものは、マーカーや色ペンで目立たせておきましょう。 重要語句は定期テストで出題されることが多いので、必ず書けるようにしておきましょう。 ② 調べたことをノートに補足しよう! ノートに書いてあることで意味がわからないものは、教科書や参考書で調べておきましょう。 ③ 地図を使おう! 地理では、場所や位置が重要です。ノートに書いてあることが、地球や日本のどこの地域のことなのかを確認しておきましょう。 ④ 理由や原因を考えよう! 重要語句を暗記するだけではなく、どういう理由でそうなっているのかを理解して、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。 ▼テスト対策ノート まとめ ノートを整理すると、頭の中も整理されて、記憶が定着しやすくなりますし、 また、授業中であいまいな理解だったところが、はっきりしてきます。 定期テスト前につくったノートは、のちのち受験勉強のときにも役に立つので、 ぜひ自分だけのテスト対策ノートをつくってみましょう。
新入社員に聞いた!勉強に集中できないときの原因&対処法3選
「今日はなぜか勉強に集中できない…」 「もうすぐテストなのに、机に向かってもすぐ飽きてしまう…」 そんな日は、誰にでもありますよね。 でも、あきらめるのはちょっと待った! 今回は、この春文理に入社した新入社員にインタビューを行い、 事前に用意した「勉強に集中できない原因3選」に対して、 <<自分が中学生のころに実際にやっていた対処法>>を教えてもらいました! 勉強に集中できない原因3選(対処法つき!) 原因①:問題が難しくてわからない 原因②:周囲の人や騒音が気になる 原因③:ついスマホを見てしまう 原因①:問題が難しくてわからない 苦手な教科や単元の勉強は、なかなか続きませんよね。 考えているうちに、眠気がおそってくることも…… こんなとき、新入社員のみなさんならどうしますか? 対処法①:まずは解ける問題を選んで、ひたすら手を動かす! 問題が難しすぎて集中できないときの対処法は、解ける問題だけを解くこと! 解けない問題を飛ばしたら、学力は伸びないと心配されるかもしれませんが、 もちろん他の問題にも後で取り組みます。 でも、やる気が出ないときは、思い切って簡単な問題だけを選んで手を動かしましょう! 簡単な問題をたくさん解いているうちに、だんだん勉強モードに切り替えられたり、 解き方のコツがわかったりすることもあるんです。 原因②:周囲の人や騒音が気になる 家で勉強していると、家族の話し声や物音が気になることも多いですよね。 逆に、静かすぎるとかえって集中できない! という声も聞きます。 新入社員のみなさんは、この悩みをどうやって克服しましたか? 対処法②:勉強する場所を変えてみる! 周りが気になって集中できないときは、普段とは違う場所で勉強してみましょう。 いろいろな場所を試すうちに、自分にぴったりの勉強場所が見つかるかもしれません。 おすすめ勉強場所は、例えばこんな場所です。 他にも、図書館の端っこの席を死守する! という方法も。 開館時間に合わせて行けば、お気に入りの場所が取れて早起きにもなる、一石二鳥ですよ! 原因③:ついスマホを見てしまう スマホでSNSや動画を見ていると、自分でも驚くくらい時間が過ぎていることがありますよね。 特に、通知が来たときは勉強中でもつい確認してしまいます。 新入社員のみなさんは、どうやってスマホの魔力に打ち勝ちましたか? 対処法③:時間を決めて、思い切って家族に預ける! スマホを見たくなってしまう気持ちに、意志力で対抗するのはかなり難しいです…。 そこで、思い切ってスマホを家族に預けてしまいましょう! 「1時間だけ」「問題集を3ページ終わらせるまで」など条件を決めておけば、 スマホがなくても意外と平気ですよ! 慣れてきたら、少しずつ預ける時間を伸ばしてみてもいいかもしれません。 まとめ 今回は、勉強に集中できないときの原因と対処法を3つご紹介しましたが、いかがでしたか? 勉強に集中できないことは誰にでもあるので、自分を責める必要はまったくありません。 それよりも、どうすれば少しでも集中できるのか、工夫して勉強に取り組んでみましょう! 文理では、教科書に沿った基礎的な内容から入試対策まで、幅広いラインナップの教材を通して 頑張るみなさんをサポートします。 学校の宿題のレベルが合わなくて集中できない! という方は、こちらから文理の教材も見てみてください! みなさんが楽しく順調に勉強を進められることを願っています!
青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法
今日は色についてのお話を…… 色は、人間の心に色々な影響を与えます。 色が持つ効果を知っていると、 勉強するときにも、使えるかもしれません。 さて! 文理では、教科ごとに大体のイメージカラーがあります! 国語=赤 算数・数学=青 理科=緑 社会=オレンジ 英語=紫 これらの色について、色のもつ効果を見ていきましょう! 国語 赤 赤は情熱の色! やる気を高めてくれます。 KOKUYOMAGAZINEの記事でも、「国語は赤・ピンク系」という回答が多くなっていますが、 これは5教科を並べるときに、一番初めに来ることが多いからなのでしょうか? 勉強するときには…… 【乱用に注意!】 赤は精神を興奮させ、集中を妨げる可能性もあります。 ただでさえ丸付けでも使う色。 ノートまとめでも赤を使いすぎてしまうと、集中しづらい紙面になってしまいます。 間違えやすいポイントなど、ここぞ!というときに使うのがおすすめです。 算数・数学 青 青は、冷静な気持ちになれる色。 集中力を高めてくれます! 数学にはぴったりですね。 勉強するときには…… 心を落ち着かせてくれる青を、ノートに取り入れてみましょう! 具体的には、メモや補足など、ノートの中で占める面積が大きく、 かつ大事なポイントを青にしてみるのはどうでしょうか。 理科 緑 緑は、リラックスさせる色です。 目に優しいことでも有名ですよね。 理科は、紙面にも植物や星空などの自然が登場するので、 よりリラックス効果が高そうです! 勉強するときには…… 休憩するときに、観葉植物などの緑を眺めると、 心がリラックスし、メリハリがついて集中しやすくなるかもしれません! ちなみに文理のロゴも、緑が基本になっています。 社会 オレンジ オレンジは、明るい・楽しい気分にさせてくれる色です! 食欲増進効果もあるそうです…… 地理では、食べ物もたくさん登場する社会科、思わずお腹が空いてしまうかも? 勉強するときには…… 暗記したい部分を赤シートで消して勉強したいときには、 オレンジペンで書くのが消えやすくておすすめです。 ただし、赤と同様、使いすぎると集中しづらくなってしまうので、 暗記部分に限定して使うようにしましょう。 モチベーションが上がらないときに前向きな気持ちになれるように、 文具や机の上の雑貨に取り入れておくのもいいですね! ちなみに、オレンジジュースはビタミンCが豊富で、疲労回復に効果があります! 英語 紫 紫は、ミステリアスで上品な色ですね。 聖徳太子が定めた「冠位十二階」でも、最高位は紫でした! 心身のバランスを整えたり、感性を豊かにする効果があるとか。 英語は紙面を見ても、おしゃれな感じがします! 勉強するときには…… 部屋のカーテンや、ベッドのシーツを紫にしてみると、 勉強で使れた心身のバランスがとれて、リラックスできるかもしれません。 みなさんはどの色が好きですか? 今日紹介した色以外にも、勉強にうまく使えそうな特性を持つ色があります。 たとえば黄色は注意を引きやすい・茶色も落ち着いた気持ちにしてくれる、など…… 上手に色を取り入れて、効率的に勉強しましょう!
楽しく覚えて、忘れない 暗記方法いろいろ
突然ですが、みなさん、暗記は得意ですか? テストでは、どうしても「覚えるしかない」ってことがありますよね。 でも、やみくもに覚えるのってちょっと苦痛だったりしませんか? そこで今日は楽しく暗記できるいくつかの方法をお伝えします。 まずは王道! 赤シート/暗記カード/暗記ポスター 暗記するのに、おそらく誰もが試したことがあるであろう、赤シート。 ノートに赤字で文字を書いたり、教科書に濃い緑のマーカーを引いたりして、それを透明の赤いシートで隠して覚える方法です。 つづいて、こちらも定番の暗記カード。 英単語と意味を表裏に書いて覚えたり、一問一答タイプの用語を覚えたりするのに使われます。 これもよくある、暗記ポスター。 トイレなどにポスターをはっておいて、ちょっとした時間に覚えるのに便利です。 これらの暗記アイテムは自分で作ることもできますし、学習教材の付録でついていることもありますね。 文理の教材の付録にも、いろいろついていますよ。 覚えるべきことが厳選されており、覚えやすくまとまっているので、どの付録もおすすめです。 ▲「中学教科書ワーク」付録のスピードチェック&赤シート ▲「中学教科書ワーク」付録のカード ▲「小学教科書ワーク」付録の折込ポスター 最近はアプリも便利 最近は、アプリを使って覚える人も増えてきています。 スキマ時間にどこでも学習できるのがメリットです。 高機能なアプリでは、苦手なところを何度も出題してくれたり、学習管理をしてくれるものもありますね。 ▲「中学教科書ワーク」付録の「Newどこでもワーク」アプリ あなどれない! 語呂合わせ 語呂合わせも暗記法の定番ですよね。 「え…、ダジャレじゃん…」と思うようなことが、案外記憶に残ってテストで1点、2点多く得点できたりするので、あなどれません。 誰が作ったのか知りませんが、「なんと素晴らしい平城京(=710年遷都)」「鳴くようぐいす平安京(=794年遷都)」などは、語呂が良くて、何年たっても忘れません。 ちなみに、こちらも名作だった「いい国つくろう鎌倉幕府」。 保護者のみなさんは、ほぼこの語呂合わせで、「1192年、鎌倉幕府成立」と覚えているのではないでしょうか? しかし、現在では、鎌倉幕府は段階的に成立していたと考えられており、1129年に源頼朝が征夷大将軍になったことで、幕府の組織形態が名実ともに完成したという説が優勢になっています。 覚えやすい語呂合わせも、ときにはアップデートが必要ですね。 ▲「中学教科書ワーク 社会 歴史」の付録カードより 呪文も有効! 語呂合わせと似ていますが、呪文のように唱えて覚える方法もあります。 有名なのは、中学校で習う元素記号の暗記法。 「水平リーベー ぼくのふね」ってやつですね。 ところで、「水平リーベー ぼくのふね」のあとは、どうやって覚えましたか? そのあとは、「七曲がり シップス クラークか」とか「名前がある シップス クラークか」とか、バリエーションがあるようです。 「波がある シップス クラークか」でもよさそうですね。 もうひとつ呪文のご紹介です。 高校生向けですが、古文の終止形接続の助動詞を覚える方法です。 筆者の高校ではコギャル風に(もはや死語?!)、つぎのように唱えるように習いました。 「べし らむって~ めり らしいよ~ まじ なり?!」 これだけだと意味不明な呪文ですが、なんだか強烈に記憶に残っています。 替え歌で覚えよう! メロディーに乗せて覚えるのも、覚えやすいです。 またまた高校の古文ネタですが、動揺「ももたろう」のメロディーに乗せて替え歌で、 未然形接続の助動詞と、連用形接続の助動詞が覚えられますよ。 自分に合った暗記方法を見つけよう! 今日はいくつかの暗記方法をご紹介しました。 ほかにも、書いて覚える、声に出して覚える、ストーリーで覚える、イメージで覚えるなど、いろいろな覚え方があります。 いろいろ試して、自分に合ったものを取り入れてみてください。