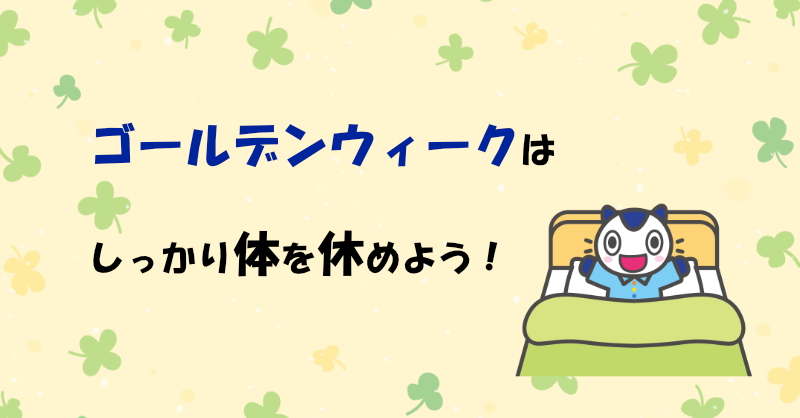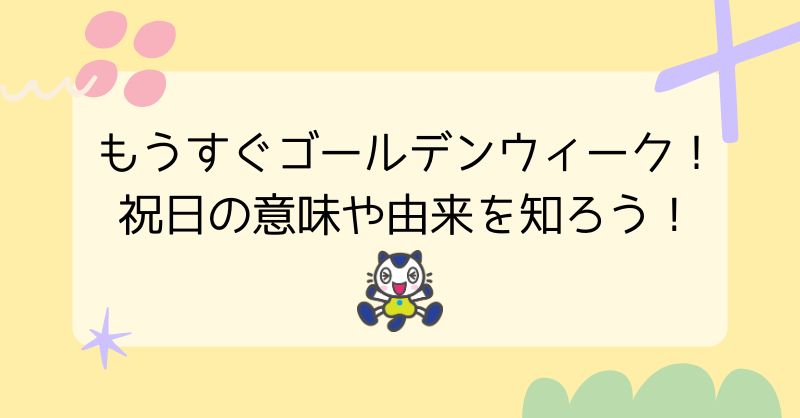GW前に、定期テストの勉強法をおさえておくのが吉!
GW、思いっきり楽しみたいですね!
色々予定が入っている人も、のんびり休むぞ!という人も、
いるでしょうか。
せっかくの連休ですから、充実した楽しいものにしたいですね。

しかしちょっと待ってください。
中学生の皆さんは、
このタイミングで定期テスト対策について知っておくのがおすすめです。
その理由は?
その理由はずばり、
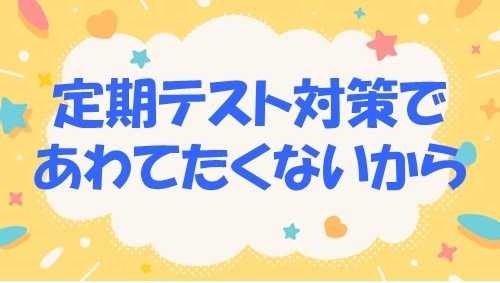
です。
中学校の中間テストは、だいたい5月中旬~6月中旬に行われます。
GW明け、なかなかスイッチが入らないうちにテスト期間に突入!となったら、
「何から始めればいいのか?」「間に合うのか?」と焦ってしまいますよね。
あんなに楽しかったゴールデンウィークを、「あの時始めておけば…」と後悔する羽目になるかもしれません。
中学1年生なら、初めての定期テストなのでなおさらです。
事前に、定期テスト対策はどのくらいの期間で、何をすればいいかが分かっていれば、
休み明けに対する心づもりをしておくことができますね。
いままで「なるほど!Bunri-LOG」では、定期テスト対策についてもたくさん紹介してきました。
GW前に一度読んでおくといい記事を、いくつかまとめます!
定期テスト対策のオススメ記事
中学生の定期テストで高得点を狙うには? 教科別勉強法やおすすめ問題集を紹介
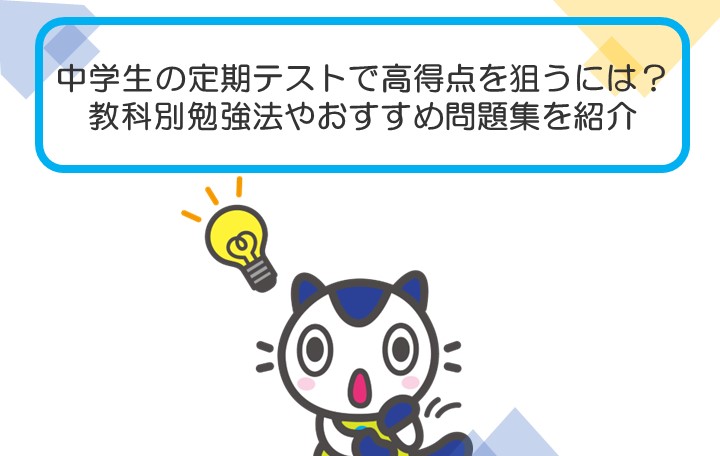
テスト勉強を始める時期や、教科別のポイント、テスト対策に
おすすめの問題集についてまとめています。
【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回
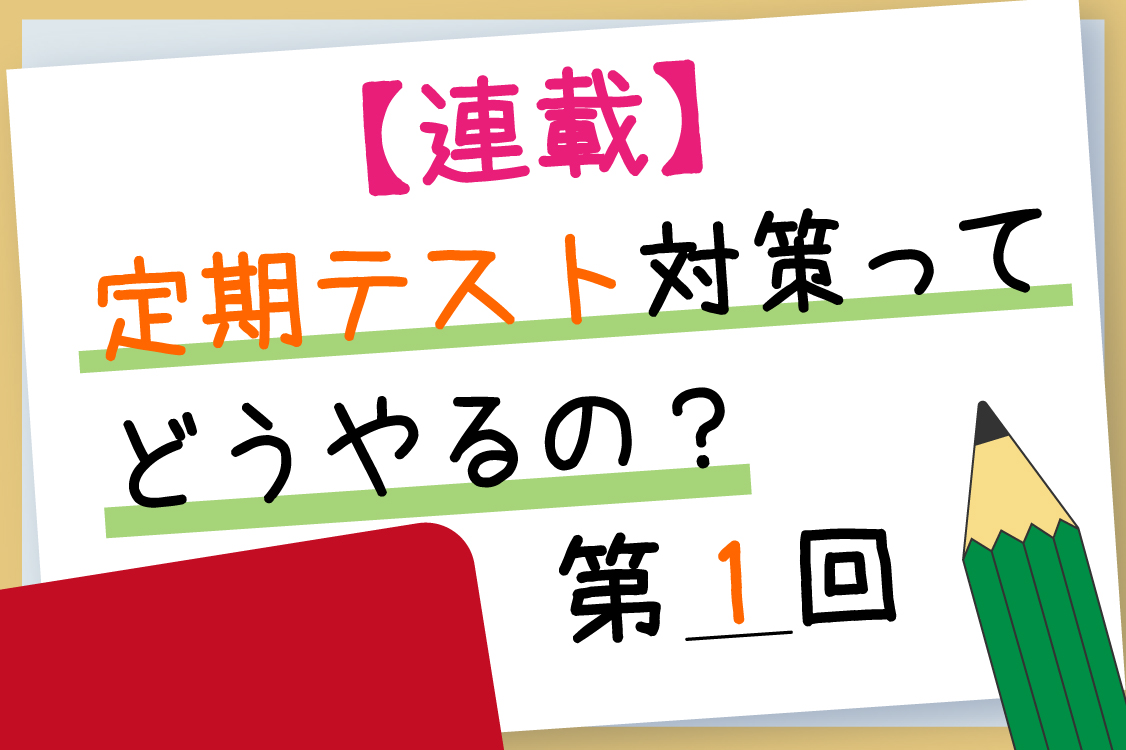
より具体的に、テスト勉強のやり方の一例を紹介!
全5回+おまけ の連載記事です。
青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法

青色、オレンジ色、緑色…
色が勉強のしやすさに与える影響があるという話を聞いたことはありませんか?
心構えを作ったうえで、GW楽しみましょう!
悔いのないGW、悔いのない定期テストになるよう、応援しています!

関連記事
【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第1回
こんにちは! 5月に入り、そろそろ、定期テストの足音が聞こえてきた!という学校も多いのではないでしょうか。中学1年生にとっては初めての大きなテストでもありますね! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届けします。 連載予定 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第1回は、「はじめに 始める時期と最初にやること」です。 定期テスト対策を始める時期 おすすめはずばり、 \\2週間前// です! テストは教科や範囲が広く、1週間前からだとだいぶ駆け足での対策になります。特に、「普段の授業に自信がない」「高得点を狙いたい!」という方は、 早めの対策をおすすめします。 最初にやること どの時期から始めるにしても…… テスト範囲が配られたらすぐやっておくべきことがあります。 それは \\範囲の確認// です。 教科書の該当ページ・資料集の該当ページなどを確認して、 疑問があったら周りに聞いておいてください。 特に、テスト範囲でやったプリントをなくしていないかを確かめておきます。万が一ない場合はクラスの人などに内容を見せてもらいましょう。(コピーや写真をもらえるとベスト!) スケジュールをたてる 範囲を確認したら、テストまでの日数の中でいつ何をするか、を書き出してみます。 これをやっておかないと、 とりあえず目に付いたものを進めていたら、範囲が全然終わらなかった…… 今日何を始めればよいのかわからず、やる気がなくなった…… などの問題が起こります。 何より、「やるべきことをやれてる!」と確認できることは安心感につながりますね! 第2~4回までで具体的なやり方をご紹介した後、 第5回で具体的なスケジュールの立て方もお話しします。 読んでいただきありがとうございます! さて、初回は軽めにお届けしました。 具体的にどうすればいいのよ?!については、次回から紹介していきます! お楽しみに! 第2回へ▶
【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第2回
こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第2回は、「その1 問題演習を繰り返し、体で覚える!」です。 数学で特におすすめ 数学はパターンを覚えてしまうのが一番近道なので、問題演習を繰り返して慣れるのが手っ取り早いです。 テスト日にノートの提出が求められる場合もありますね! その場合は一石二鳥です。 その他の教科でも、余裕があればやっておくと、より高得点が狙えるかもしれません。 用意するもの 〇問題集学校で配られているワークがあればそれを用意してください。丁度いいワークがない場合は、書店で定期テスト対策の本を探してみてください!(色合いやデザインなど、自分の気持ちが上がるものを選びましょう。)書店の棚の前に立っていると、学習意欲も高まります! ★書店で買うときのワンポイント国語や英語は、教科書ワークや中間・期末の攻略本などの 「教科書に準拠したもの」だと、教科書の文章を題材にした問題を解けます。 ※2025年春に「中間・期末の攻略本」は「定期テストの攻略本」に書名を変更して改訂しました。 「中学教科書ワーク」も2025年春に改訂しています。 〇ノート問題集に書きこまず、ノートを使って2周していきます。気分が上がるノートを選びましょう。 〇シャープペンシルまたは鉛筆 〇消しゴム 〇赤ペン(個人的に、ゲルインキだとちょっとテンションが上がります。) やり方 さあ、始めていきます。ノートを半分のページを半分に折って、戻します。 これで真ん中に線が入ったページができました。 左側を1周目で、右側を2周目で使います。 問題番号は、わかればいいです。途中式や図もなるべく書きましょう。頭で考えるのも大事ですが、手をたくさん動かすのも大事です。 どうしてもわからないときは…… 解説を見てしまいましょう! 赤ペンで解答を写しながら、なんでそうなるのかを考えます。解説を見てもわからない…というときは先生や友達、保護者の方に聞いてみてください。 1周目で解けなくても大丈夫! 解説を理解して、2周目のときには解ける!をめざします。 1周が終わったら、(飽きるので)1日置いたりして、2周目を始めます。今度は右側を使って、問題を解いていきましょう。 2周目が終われば、テスト範囲の問題にはだいぶ慣れているはずです。 1周目も2周目も間違えた問題や不安な問題があったら、 ワークにしるしをつけて、前日やテスト直前に見返しましょう。(しるしをつけたくない人は、付箋で!) 読んでいただきありがとうございます! 次回は、「その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!」をお届けします! お楽しみに。 ◀第1回へ 第3回へ▶
【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第3回
こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第3回は、「その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!」です。 国語・英語で使える勉強法! これは国語・英語で、授業で扱った文章を使って出題される場合に効果的な方法です。 文章を覚えるメリット★試験時間中に問題を読み込む時間が不要になる。★文章中から探したり、文章の穴埋めをする問題が、すぐに解ける。 時間短縮になるので、そのぶんを記述問題や、テスト独自の問題などに回すことができます。 また、音読することで… 漢字の読みや、単語のアクセント・発音などをつかんでおくこともできますよ! ※漢字の書きや英単語のスペルについては、読むだけだと度忘れするので、 10回くらい、手を動かして書いておくことをおすすめします…… 用意するもの 〇教科書 〇授業ノート 〇資料集・プリント 〇カラーのボールペン やり方 まず事前準備をします! しなくてもよいのですが、しておくと一石二鳥です。 授業中の先生の「この文章はこういう感情」「この言葉はこういう意味」などのコメント、 ノートにメモしてありますか? メモしてあるものがあったら、それをボールペン等で教科書に書きこみましょう。 小さい字でOKです! ※画像はイメージ こうしておくと、音読するついでにそのあたりのコメントも頭に入ります。 いよいよ音読します! メモした文字も視界に入れつつ、声に出して読んでいきます。 声に出していさえすれば読み方は自由です! 小声でもいいですし、留守番の日を狙って、感情豊かに読むのもいいでしょう。 声に出すことは気分転換にもなります!手を動かす作業の合間や、疲れてあまり頑張れない日などに行うといいかもしれません。 古文の場合は暗唱できるとよりGood! 大人になってから、枕草子をそらんじられるのもかっこいいですよ。 2回くらい読んで飽きたら、あとはテストまでに1回か2回、読み返しておきましょう。(このときは音読でも黙読でも) これで、テストに出る文章を頭に入れたうえで、テストに臨むことができます! 読んでいただきありがとうございます! 次回は、「その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!」をお届けします! お楽しみに。 ◀第2回へ 第4回へ▶
【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第4回
こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 第4回は、「その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!」です。 社会や実技など覚えることが多い教科に! テストまでに、「これだけ覚えればOK!」というまとまりを作ります。あとはひたすら赤シートを使って覚えるのみです。 まとめておくメリット★持ち運びが楽になる!★覚えるべきことの全体を把握でき、不安が軽減できる! 作るのに時間を使いますが、書くことで覚えられる側面も。テスト2・3日前までにはまとめ切れるといいですね。 ※テストまで1週間!という場合はちょっと間に合わないかもしれません。また、まとめるのが苦手、という人も無理をする必要はありません。 後述する時短バージョンを参照 用意するもの 〇ルーズリーフやノート今回はノートを使用。好きな方を選びます。 ルーズリーフは複数教科持ち運ぶのに便利! 〇授業ノート 〇資料集・プリント・教科書 〇オレンジのボールペン 赤シートで消えるもの 〇カラーのボールペン 〇赤シート やり方 オレンジペンを使って、授業ノートをまとめ直していきます。 ポイントは、覚えやすいように書き直すこと! そして、資料集・プリント・教科書などの中から、「ノートに書いていないけど先生が触れた部分」もノートに入れていきます。(資料集のコピーやプリントに緑マーカーを引き、それを教科書に挟んでおく対応でもOK) こうすることで、「この内容さえ覚えていれば大丈夫!!」という紙束ができます。これを赤シートで隠しながら、何度も読みましょう。 ★余裕があれば、第2回の問題演習と組み合わせるとより定着します。 時短バージョン まとめ直している時間がない時や、まとめるのが苦手な場合は……教科書や市販の学習参考書を活用します! 用意するもの 〇教科書か市販の参考書など 今回は中間・期末の攻略本を使います! ※「中間・期末の攻略本」は2025年春に「定期テストの攻略本」に書名を変更して改訂しました。 〇授業ノート 〇資料集・プリント 〇オレンジのボールペン 赤シートで消えるもの 〇緑マーカー 〇カラーのボールペン 〇赤シート やり方 教科書(学習参考書)の重要単語に、緑マーカーを引いていきましょう。 こうすると、赤シートで隠したときに消えるようになります! さらに、ノートや資料集・プリントには、教科書(学習参考書)に書いていない情報もあります。 そういうものの中で、先生が授業で触れたことはボールペンで書きこんでいきましょう!(資料集のコピーやプリントに緑マーカーを引き、それを一緒に挟んでおく対応でもOK) 中間・期末の攻略本は赤シート対応なので、 もともと消えるようになっている部分も! さらに穴埋めもオレンジペンで書いて、赤シートで消せるようにしてみました。 これをひたすら赤シートで覚えていきましょう! 読んでいただきありがとうございます! 次回は、「おわりに まとめとスケジュールの立て方」をお届けします! お楽しみに。 ◀第3回へ 第5回へ▶
【連載】定期テスト対策ってどうやるの? 第5回
こんにちは! 定期テストに向けた勉強についてのアドバイスを、5回に分けてお届け! 第1回 はじめに 始める時期と最初にやること第2回 その1 問題演習を繰り返し、体で覚える! 第3回 その2 テストで扱われる文章は音読して頭に入れる!第4回 その3 「覚えるものセット」を作り、赤シートで覚える!第5回 おわりに まとめとスケジュールの立て方 ※今回紹介する方法はあくまで一例です。 参考にしつつ、自分に合う方法を見つけていきましょう! 最終回は、「おわりに まとめとスケジュールの立て方」です。 教科ごとにまとめます 第2~4回でお伝えした勉強方法について、 結局教科ごとに何をやればいいのか?をまとめた図です。 こんなにやるの?!と焦る前に、冷静にスケジュールを立ててみましょう。 スケジュールの立て方 5教科で考えてみます! 例えば以下のように、教科ごとにやることと、かかる日数を考えます。 国語1)作者情報・資料集の知識、文法事項など、暗記したいものをまとめる→1日2)教科書に情報を書きこみ、2回くらい音読する→1日1回ずつ、2日 3)漢字を練習する→1単語10回くらいずつ。2日 ※不安なら、読みのとなりにオレンジペンで漢字を書いたものを用意し、1)に追加。 4)1)を覚える→テスト2日前から 数学1)前日までにワークの問題を2周する→13日 英語1)単語を練習して、赤シートで消えるように(単語カードでも)まとめる→1日2)教科書の文を覚えるくらい音読する→1回ずつ、2日3)ワークがあれば最低1周する→3日 理科1)ノートに取ったことをオレンジペンを使ってまとめる→3日3)1)を覚える→遅くてもテスト2日前から 社会1)ノートに取ったことをオレンジペンを使ってまとめる→3~4日2)1)を覚える→遅くてもテスト2日前から ※国語・理科・社会のワークは、最後にもし余裕があれば1周しておく! これらをそれぞれ、テストまでの日程に当てはめてみてください。 ★この日は習い事があるから、帰ってから布団で赤シートチェックをする★この日は外出するから、それまでにまとめを作っておけば行き帰りで覚えられる★この日は留守番だから、音読にあてるなど、それぞれの事情に合わせて調整します。 そうすると、今日何をこなせばやりたいことが全部消化できるのかがわかります! ※テスト前日は予備日として空けておきましょう。 今回、5回にわたり紹介してきたテスト対策は、あくまで一例です! 〇赤シートは飽きてしまう〇たくさん問題を解くのが一番おぼえる〇先生の出題傾向がかなり独自 など、今回のやり方が合わない場合もあると思います。 定期テストはその名の通り定期的にやってくるものですので、自分に合うやり方を探していってみてください! ◀第4回へ おまけ▶
青色で集中力UP! 色の効果と勉強での活用法
今日は色についてのお話を…… 色は、人間の心に色々な影響を与えます。 色が持つ効果を知っていると、 勉強するときにも、使えるかもしれません。 さて! 文理では、教科ごとに大体のイメージカラーがあります! 国語=赤 算数・数学=青 理科=緑 社会=オレンジ 英語=紫 これらの色について、色のもつ効果を見ていきましょう! 国語 赤 赤は情熱の色! やる気を高めてくれます。 KOKUYOMAGAZINEの記事でも、「国語は赤・ピンク系」という回答が多くなっていますが、 これは5教科を並べるときに、一番初めに来ることが多いからなのでしょうか? 勉強するときには…… 【乱用に注意!】 赤は精神を興奮させ、集中を妨げる可能性もあります。 ただでさえ丸付けでも使う色。 ノートまとめでも赤を使いすぎてしまうと、集中しづらい紙面になってしまいます。 間違えやすいポイントなど、ここぞ!というときに使うのがおすすめです。 算数・数学 青 青は、冷静な気持ちになれる色。 集中力を高めてくれます! 数学にはぴったりですね。 勉強するときには…… 心を落ち着かせてくれる青を、ノートに取り入れてみましょう! 具体的には、メモや補足など、ノートの中で占める面積が大きく、 かつ大事なポイントを青にしてみるのはどうでしょうか。 理科 緑 緑は、リラックスさせる色です。 目に優しいことでも有名ですよね。 理科は、紙面にも植物や星空などの自然が登場するので、 よりリラックス効果が高そうです! 勉強するときには…… 休憩するときに、観葉植物などの緑を眺めると、 心がリラックスし、メリハリがついて集中しやすくなるかもしれません! ちなみに文理のロゴも、緑が基本になっています。 社会 オレンジ オレンジは、明るい・楽しい気分にさせてくれる色です! 食欲増進効果もあるそうです…… 地理では、食べ物もたくさん登場する社会科、思わずお腹が空いてしまうかも? 勉強するときには…… 暗記したい部分を赤シートで消して勉強したいときには、 オレンジペンで書くのが消えやすくておすすめです。 ただし、赤と同様、使いすぎると集中しづらくなってしまうので、 暗記部分に限定して使うようにしましょう。 モチベーションが上がらないときに前向きな気持ちになれるように、 文具や机の上の雑貨に取り入れておくのもいいですね! ちなみに、オレンジジュースはビタミンCが豊富で、疲労回復に効果があります! 英語 紫 紫は、ミステリアスで上品な色ですね。 聖徳太子が定めた「冠位十二階」でも、最高位は紫でした! 心身のバランスを整えたり、感性を豊かにする効果があるとか。 英語は紙面を見ても、おしゃれな感じがします! 勉強するときには…… 部屋のカーテンや、ベッドのシーツを紫にしてみると、 勉強で使れた心身のバランスがとれて、リラックスできるかもしれません。 みなさんはどの色が好きですか? 今日紹介した色以外にも、勉強にうまく使えそうな特性を持つ色があります。 たとえば黄色は注意を引きやすい・茶色も落ち着いた気持ちにしてくれる、など…… 上手に色を取り入れて、効率的に勉強しましょう!
ゴールデンウイークはしっかり体を休めよう!
4月もそろそろ後半ですね。 新学期から始まった新生活には慣れましたか? 入学したての学校やクラス替えで緊張したり、部活に入部してハードな練習をしたり、学年が上がって学習内容も難しくなって来て、、、と忙しい毎日を過ごしているのではないでしょうか。 新しい生活は刺激いっぱいで楽しいですが、知らず知らずのうちに疲れやストレスも溜まってくるものです。 5月のゴールデンウイークで少し学校もお休みですから、この機会に新学期の復習に集中・・・も良いですが、ここは一旦机を離れて、ゆっくりお休みするのはいかがでしょう? ということで、ゴールデンウイークに取り入れたい休み方を考えてみましょう。 入浴 身体を休めるには入浴が効果的なようです。 もし普段は部活や習い事に追われてゆっくりお風呂に浸かっていないという人は、せっかくのお休みの日は時間をかけてお風呂に入るのはどうでしょうか? 個人的におススメなのでお風呂の電気を暗くして、温めのお湯に入浴剤を入れてゆっくり浸かることです。 リラックスできて良いですよ~。 昼寝 5月となれば暖かくなってきますからね。 早い時間にお風呂に入って、暖かい日差しをうけながらウトウトと昼寝・・・。 最高ですね。 コーヒーや紅茶などカフェインが入っている飲み物が好きな人もいるかも知れませんが、なるべくカフェインを取らない方が寝ている間に体が休まるようですよ。 なお、学校が休みだからと言って夜遅くまで起きて、朝寝坊するのは考えものです。 生活のリズムが狂ってしまいますから、学校がある日と同じように早寝早起きは基本ですね。 適度な運動 身体を休める、と言うとついつい家にこもりがちですが、適度に運動した方が睡眠の質は良くなるようです。 晴れた日は友達と外で遊んだり、ひとりで家の近くを散歩したり、家族と近所のお店に買い物に行ったり、日中は太陽の光を浴びて気持ち良く過ごしたいですね。 家のお手伝いで体を動かすと家族に感謝されて一挙両得ですよ。 ごはんを食べる 体力回復には十分な栄養補給が一番。 普段忙しくて朝食を摂っていないなど不規則な食生活をしていませんか? 連休の内に規則正しい食生活を意識しましょう。 好きなメニューのレシピを調べて、自分で作ってみるなど、新しいチャレンジをしてみても良いですね! という事で、今年のゴールデンウイークは新学期から頑張った心と体を一旦休めることを意識して過ごしてみてはいかがでしょうか。 充分休養を取って元気が出たら、また文理の問題集を開いて勉強を頑張って行きましょう! ~今回の執筆者~ イニシャル:T 所属:営業部門 年代:30代 今回のひとこと:最近は毎週末ヤリイカを買ってさばき、イカソーメンにして食べています。北海道のヤリイカは美味しいですね~。
もうすぐゴールデンウィーク!祝日の意味や由来を知ろう!
4月も後半!ということで、もうすぐ「ゴールデンウィーク」が訪れますね。 2024年のゴールデンウィークは4月27日(土)~5月6日(月)まで!29日(月)が「昭和の日」、5月3日(金)が「憲法記念日」、5月4日(土)が「みどりの日」、5月5日(日)が「こどもの日」、5月6日(月)が振替休日になります。祝日が盛りだくさんで、今から何をするかワクワクですね。 また、「国民の祝日」は年間に計16の日と定められているので、その4分の1がゴールデンウィークにあたります。 今回はそんなゴールデンウィークにあたる祝日の由来や意味をそれぞれご紹介していきます! 昭和の日の意味と由来! 昭和の日は、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代をかえりみ、国の将来におもいをいたす」日とされています。(国民の祝日に関する法律 第二条より)昭和時代は様々な変化があり、また、戦後の復興から経済成長を遂げ、日本が国際社会においても重要な位置を築いた時期であり現在の日本の土台を築き上げた時代です。 そんな、昭和時代に思いをはせる「4月29日」ですが、なんと昔は「昭和の日」と呼ばれていませんでした! もともとは、昭和天皇の誕生を祝う祝日でしたが、昭和天皇崩御後は、植物の学問に詳しかった天皇にちなみ、1989年より「みどりの日」と呼ばれていました。その後、2007年より様々なことがあった昭和の時代を忘れてはいけないという思いをこめ、「昭和の日」に変更になったようです。 また、「みどりの日」の前は「天長節」や「天皇誕生日」と呼ばれており、4度名前が変わっているようです。 憲法記念日の意味と由来! 憲法記念日は、その意味や由来がわかりやすいですよね。その名の通り、憲法記念日は、日本国憲法を祝う日です。 しかし、ここで注意が必要なので、日本国憲法が公布された日ではなく、施行された日ということです。 ※公布とは・・・広く世の中に知らせること 施行とは・・・実際に行うこと 日本国憲法は1946年11月3日に公布され、5月3日に施行されました。 この憲法施行を記念しつつ、これからの日本の成長を期待しよう!という休日です。 ちなみに日本国憲法が公布された11月3日は「文化の日」として祝日が定められています。この日は世界で初めて戦争放棄を憲法で宣言した日であることから「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」とされています。 みどりの日とは? みどりの日は「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日」です。つまりは、自然に感謝しよう!ということですね。そ の名の通り、「みどりの日」には国立公園が自然解放されたり、季節のお祭り、自然体験イベントなどが開かれていることが多いです。 「昭和の日」でもご紹介したとおり、もともとは4月29日にありましたが、「昭和の日」に変更になったことにより、5月4日が「みどりの日」として祝日に決められました。 せっかくの「みどりの日」、お弁当やお菓子などをもって、友達や家族と公園や山へピクニックに行ってもいいかもしれませんね! こどもの日とは? こどもの日は、子どもたちの健やかな成長と幸福を願う祝日です。この日は、子どもたちに愛情を注ぎ、彼らの未来を祝福する意味を持ちます。 また、家族の絆を深め、子どもたちへの教育や育成に対する意識を高める日でもあります。 もともとは、端午の節句として知られ、5月5日に行われる伝統的な行事です。元々は男の子の成長や幸せを願ってお祝いする日でしたが、「国民の祝日に関する法律」で「こどもの人格をを重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と定められたことによって、子どもたち全体の成長を願うようになったんですね。 ちなみに「端午の節句」ですが、「端午」には、「最初の午(うま)の日」といった意味があるようです。「端」ですが、訓読みで読むと「はし」であり、一番最初や始めを表します。そして「午」は、中国の古い暦である十二支から来ています。 「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」 寅(とら)が1月なので、午の月は5月ということになります。 5月5日は午の月の午の日なんですね。 そして「節句」は、「季節の節目になる日」のことを表しており、実は、端午の節句だけではなく他にも4つ節句があるそうです。 そんな、5月の季節の節目となる日「端午の節句」ですが、江戸時代のころ病気や災いを払う花として「菖蒲(しょうぶ」を飾る決まりがあったようです。 「しょうぶ」という音の聞こえが武道などを重んじる意味を持つ「尚武」と同じ読みだったため、男の子の成長を願う行事に変化していったようです。 まとめ ゴールデンウィークといえば楽しい連休!というイメージですが、祝日には様々な意味が込められていたんですね。 「昭和の日」は激動の昭和の時代を顧みて、これからの将来を考える日。 「憲法記念日」は日本国憲法のが実行されたことを祝う日 「みどりの日」は自然に感謝し、豊かな心を育む日 「こどもの日」はこどもたちの成長を願い、母に感謝する日 という日でした。皆さんは知っていましたか? 「こどもの日」などは、お家でお祝いすることもあるので、印象が強かったですが、「みどりの日」の由来や、「昭和の日」がもともと別の名前だったりなど、驚きの事実もありました。 込められた思いにも心をはせながら有意義なゴールデンウィークを送れると良いですね。