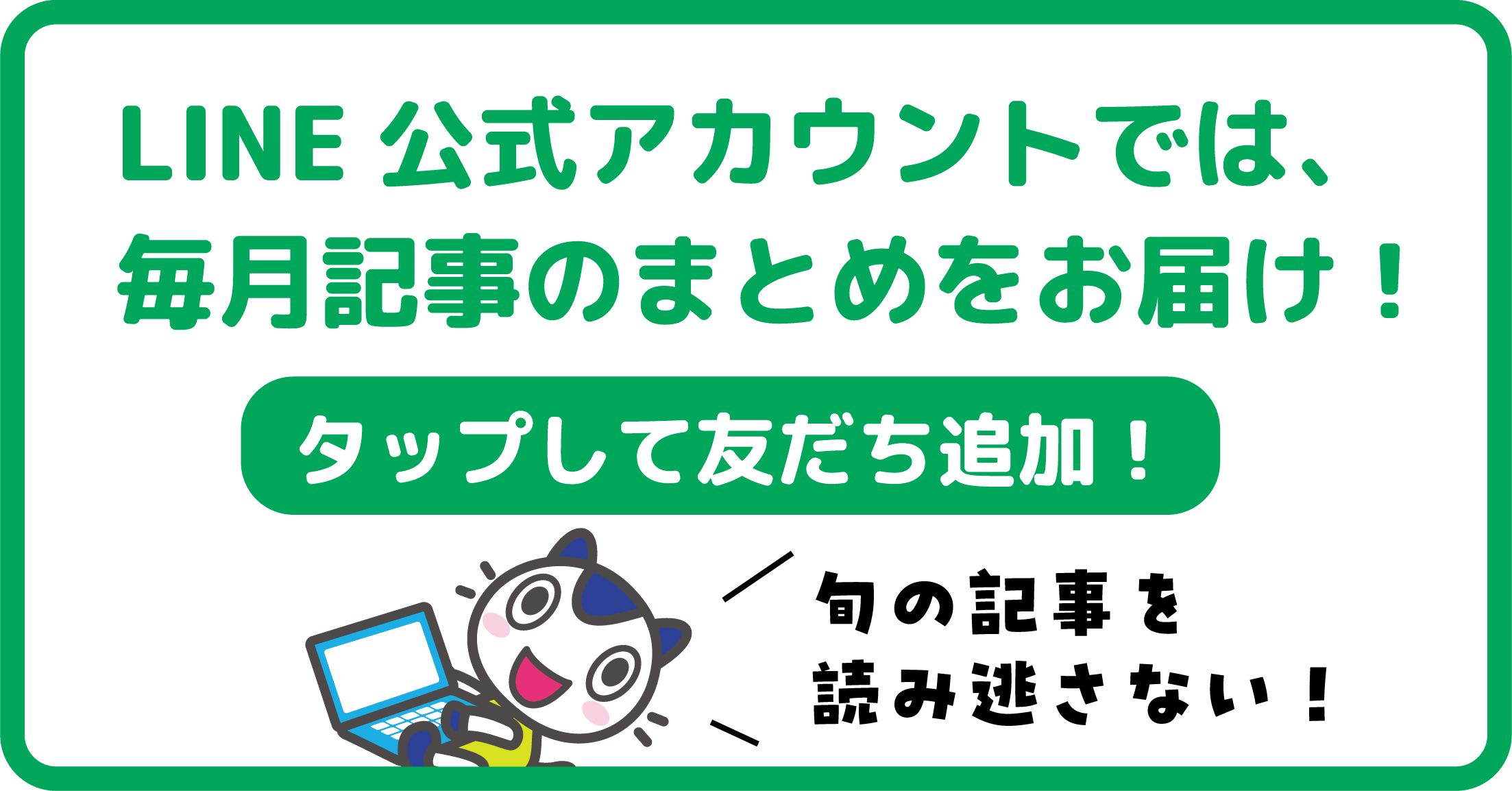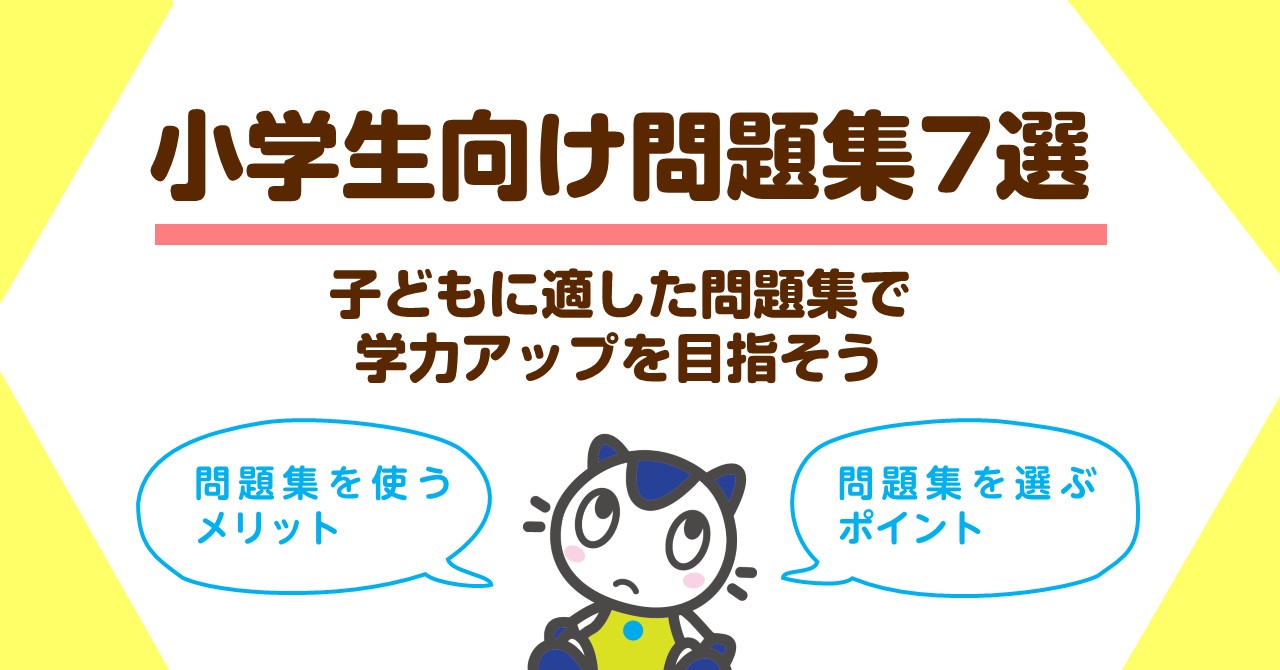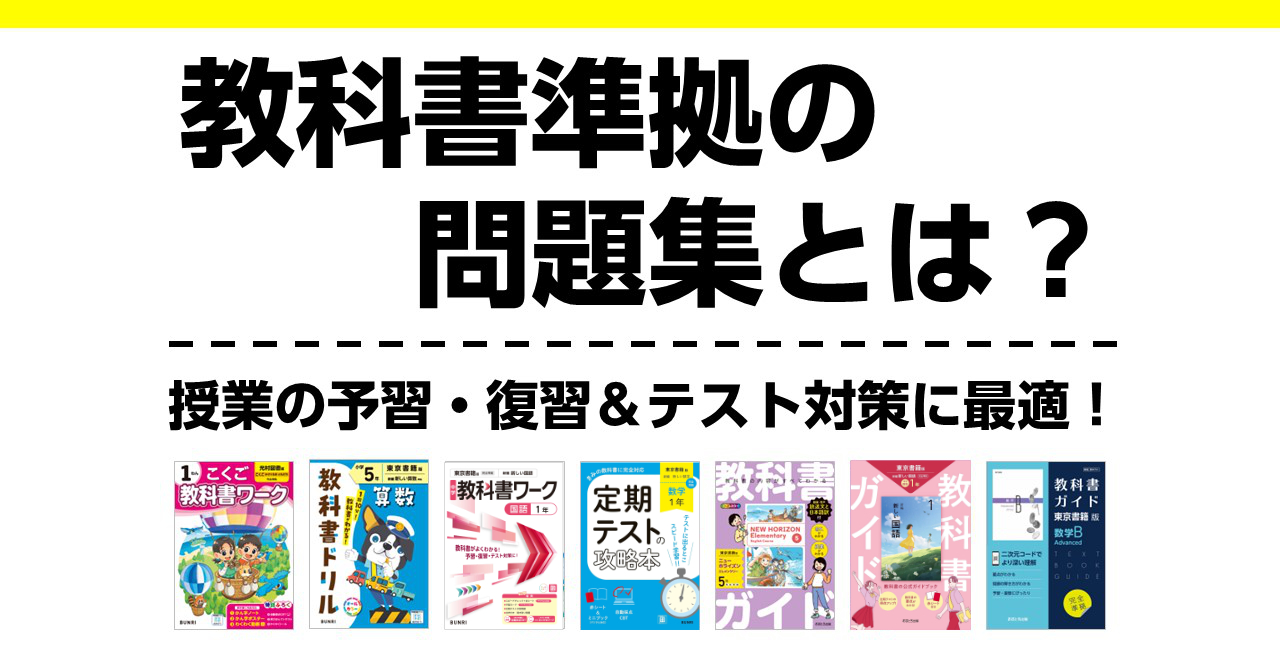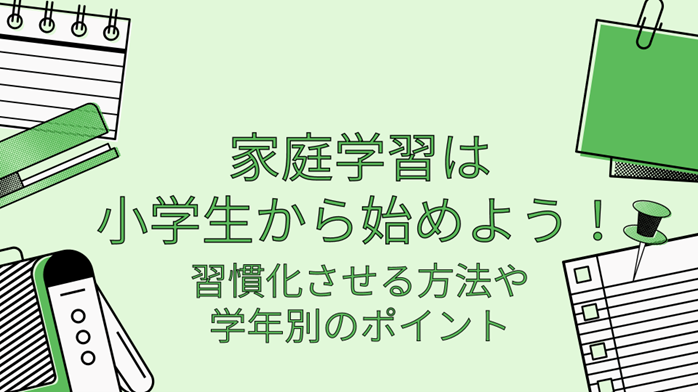【保護者必見!】宿題嫌いな子をやる気にさせるアプローチ方法とは?
子どもが宿題をなかなか進めないことは、多くの保護者が直面する共通の悩みかと思います。
この悩みに対処するためには、子どもたちに対する効果的なかかわり方を見つけ、
子どもたち自身が自発的に宿題に取り組むようになる方法を模索することが重要です。
以下に、具体的なアプローチとポイントをご紹介いたします。
子どもが宿題をしないのはなぜ?
そもそも、子どもが宿題をしないのはなぜでしょう?
まずはその原因と原因に対する策を考えてみましょう。
もしかしたら、似たような経験が私たち大人にもあったのではないでしょうか…?
遊びたいから
子どもたちの遊びたいという欲求は大切です。
遊ぶことから学ぶことも多くあります。
しかし、遊びと勉強のバランスを取ることが重要です。
定期的に遊びの時間を設け、その前後で宿題に取り組むルーティンを作りましょう。
子どもが自分でスケジュールを管理できるよう、共有のカレンダーを導入するのも良いアイディアです。

勉強がわからないから
わからないと手がついつい止まってしまいがちに…。
そんな時は保護者から積極的に声がけをしましょう。
子どもにどこの箇所がわからないのか質問を促し、一緒に取り組むことで子どもの理解を深めることができます。
また、学習参考書や学習動画などを活用して、難しい部分をサポートする方法もあります。
やらされていると思っているから
やらされていると感じているとやる気もでません。
できるだけ、子どもが宿題をやらされていると感じることは避けたいです。
保護者は宿題を共に進め、子どもの意見やアイディアを尊重することで、やる気を引き出すことができます。
宿題を楽しい学習体験に変えましょう。
机に向かい習慣ができていないから
毎日机に向かう学習習慣ができていないと、宿題を始まる前段階の机に向かうことも困難です。
習慣を身につけるために、子どもが集中しやすい学習スペースを作ることが大切です。
机や椅子の高さを調整し、散らかりがちな場所を整理することで、宿題に取り組む環境を整えましょう。
同時に、毎日同じ時間に宿題に取り組む習慣を築くことも提案します。

宿題をやる気にさせる保護者のアプローチ
先ほどの原因と対策から、さらに具体的に保護者のアプローチ方法をご紹介します。
学習環境を整える
学習には、静かで明るい環境が適しています。
子どもが宿題に取り組む場所を整え、必要な文房具や教材を揃えることで、効果的な学習環境を提供します。
また、子どもの好みを考慮して、デコレーションやカラフルな文房具を活用すると、モチベーションが向上します。

宿題に取り組む時間を習慣にする
毎日同じ時間に宿題に取り組むことで、スケジュールに慣れ、自ら進んで宿題に取り組むようになります。
スケジュールを視覚的に示すカレンダーや時計を利用し、規則正しい生活習慣を身につけるサポートを行います。
遊びと勉強のルールを決める
家庭内で遊びと勉強のルールを共有することで、子どもは両方に適切な時間を割り当てやすくなります。
例えば、宿題終了後に特別な遊び時間を設けるなど、報酬的な要素を取り入れることも考えましょう。
できたらたくさんほめる
子どもが宿題で成果を上げたら、その努力をたくさん褒めましょう。
ポジティブなフィードバックは自己肯定感を高め、学習へのモチベーションを向上させます。
ただし、褒める際には具体的な行動や努力に焦点を当てると効果的です。
ごほうびを用意する
宿題が終わったら、小さなごほうびを用意して子どもに与えましょう。
これは宿題に対するポジティブな関連付けを促進し、やる気を高める手段となります。
具体的なごほうびは子どもの好みに合わせ、週末や大きな課題を達成した際には特別なごほうびを考えると良いでしょう。

宿題をしない子どもへのNGアプローチ
感情的にしかる
怒りっぽい態度で接すると、子どもは宿題に対してネガティブな感情を抱く可能性があります。
代わりに、冷静で理解のある態度で問題を共有し、解決策を一緒に考えることが大切です。

命令してやらせる
「やらなければならない」といった命令的な言葉ではなく、「一緒にやろう」と協力的な態度を示すことが大切です。
子どもとのコミュニケーションを大切にし、協力して宿題に取り組む雰囲気を醸成しましょう。
イライラした態度で接する
イライラした態度は子どもに不安を与え、学習意欲を低下させる原因となります。
冷静で穏やかな態度で接し、子どもが自分の気持ちを安心して表現できるように心がけましょう。
きょうだいと比べる
兄弟姉妹との比較は子どもにプレッシャーをかけ、モチベーションを低下させる可能性があります。
子どもの個別性を尊重し、個々の進捗に焦点を当てることが大切です。
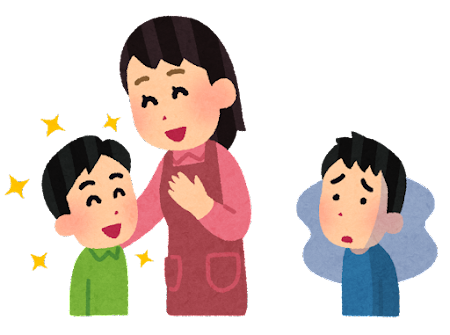
宿題への保護者のかかわり方
宿題に取り組む子どもを見守る
子どもが宿題に真剣に取り組んでいるかを見守り、必要であればサポートを提供します。
子どもが集中しているときには、邪魔をしないよう気をつけましょう。
宿題をやったかチェックする
子どもの宿題の進捗を確認するために、週に一度などの定期的なチェックを導入します。
これにより、子どもに宿題に対する責任感を育てることができます。

学校から丸付けを求められることも
学校から丸付けや進捗報告を求められる場合、保護者は子どもの取り組みをサポートする役割を果たります。
子どもと一緒に学習計画をたて、宿題の進捗を管理することで、学校との連携を強化します。
宿題でわからないことがでてきたら
子どもがつまずいているところを早めにフォロー
子どもが宿題でつまずいたら、即座にフォローすることが大切です。
子どもにどこが難しいかを尋ね、一緒に問題を解決する手助けをします。
問題集で知識の定着を確認
宿題だけでなく、関連する問題集や参考書を活用して、基礎知識の定着を確認します。
定期的なクイズや挑戦的な問題を通じて、子どもの学習の深化を促進します。

おすすめは「小学教科書ワーク」
小学教科書ワークは、教科書に沿って作られた教科書準拠の学習参考書です。
授業に合わせて、基本から応用までしっかり学習できるように作られているため、学校の予習・復習に最適です。

楽しく見やすいオールカラー
オールカラーで図や要点が見やすいのはもちろん、楽しい気持ちで勉強に取り組むことができます。
かわいいキャラクターもたくさん!
3ステップで基礎から段階的に学べる
小学教科書ワークは「基本のワーク」「練習のワーク」「まとめのテスト」と3段階の構成になっているのが特徴です。
★「基本のワーク」では、穴埋めやなぞり書きをしながら教科書の要点を学びます。
★「練習のワーク」で基礎的な問題に取り組み、知識を定着させます。
★「まとめのテスト」では、時間を図り、応用問題も含めた確認テストに取り組みます。
1冊の中で基礎から応用に向かって順番に学べるため、効率的に知識を定着させることができます。
簡単な問題から取り組んで成功体験を積むことで、学習に対するモチベーション維持にもつながります。
付録がたっぷりでお得
付録があると楽しく学習を進められるため、子どものやる気につながります。
本の中に、ポスターや模擬テスト、小冊子など、さまざまな役立つツールが入っています。
また、動画やCBT(コンピューターで受けるテスト)などなどのWEB特典もついています。
以上、宿題嫌いな子をやる気にさせるアプローチ法のご紹介でした。
毎日忙しい保護者の方も、少しでも子どもたちとの学習の時間を作って、宿題嫌いを解消していきましょう!