小学生のための漢字テスト攻略ガイド ~楽しく学んで高得点を目指そう~
小学生の保護者のみなさま、お子さまの漢字学習はいかがでしょうか?
お子さまが学校で漢字テストに取り組んでいる姿を見て、学習の進捗を気にしている方も多いと思います。漢字は日本語を理解するための重要な要素であり、後の学習のためには早いうちからしっかりと身につけておく必要があります。
今回はその「漢字テスト」についてお伝えします!
どうして小学校で漢字テストがあるの?
読み書きはすべての学習の基本となるから
正しい読み方と書き方を身につけることは、学力向上に不可欠な要素です。
国語だけでなく、算数の文章問題、理科・社会の教科書なども、漢字が読めなければ徐々に理解が難しくなってしまいます。
さらに、大学入試などで求められる文章力向上には、漢字の知識が絶対的な基礎となります。
言葉の正しい使い方を学ぶためには、漢字を正しく書ける必要があるためです。
小テストを繰り返すことで定着するから
漢字は一度覚えただけではすぐに忘れてしまうものです。
そんななか、学習した漢字を繰り返し復習できる漢字テストは、記憶を定着させるための有効な方法とされています。
定期的な小テストを通じて、自分の弱点を見つけ、重点的に復習することができます。
漢字を繰り返し書くことで、書き方だけでなく、意味や使い方も自然と身に着けられます!
特に小学校では、学年ごとに学ぶ漢字の数が増えていきます。
1年生では約80字、2年生では約160字、3年生では約200字…と、多くの漢字を学びます。
この膨大な漢字を覚えるためには、定期的にテストを行い、理解度を確認していくことが重要となるのです。
さらに、テストは達成感を得るための良い機会でもあります。点数や結果が目に見える形でわかるため、お子さまのやる気を引き出すこともできます。
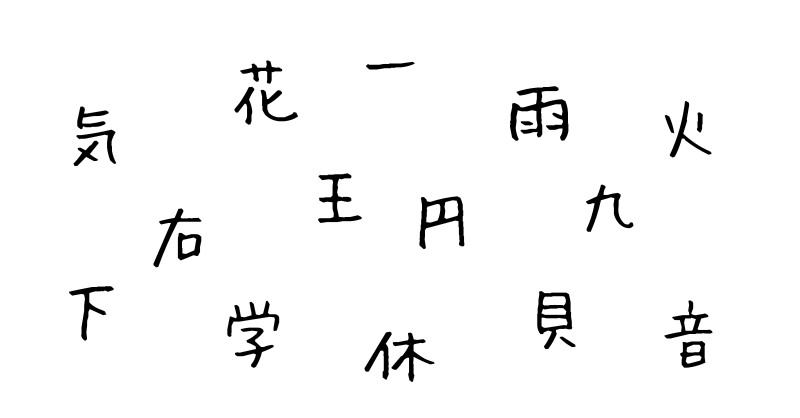
漢字学習のコツ
①読みと意味を覚える
漢字を学ぶ際には、まずその漢字の読み方と意味を理解することが大切です。
ただ形を覚えるだけでは、実際の文章で活用できません。
同じ漢字でも文脈によって違う読み方をすることがあるため、さまざまな場面でどのように使われるか、知ることが重要です。
②画数・筆順を意識しきれいに書く
漢字はただ書けるだけではなく、正しい画数と筆順で書くことも大切です。
筆順を守ることで、漢字が整って見え、テストでも点数が取りやすくなります。
筆順は「見た目の美しさ」だけでなく、「速く、正確に書く」ためにも大変役に立ちます。
③部首を知る
漢字の部首を理解することも学習の大きな助けになります。
部首は漢字の意味や読み方に深く関係しており、部首を覚えることで、似たような漢字をグループで覚えることができます。
例えば「海」や「湖」などの水に関連する漢字は「さんずい」が使われていますが、これを知っていると意味の推測がしやすくなります。
④繰り返し書く
最終的には、何度も書いて覚えることが漢字学習の基本です。
手を動かして漢字を何度も書くことで、記憶に定着しやすくなります。
ただ、闇雲に繰り返すのではなく、読みや意味を確認しながら書くことがポイントです!

漢字テストで高得点を取るには
①教科書の新出漢字が出る
漢字テストでは、主に教科書に出てくる「新出漢字」が中心に出題されます。
授業中に新しく学んだ漢字は必ず復習し、テストに備えましょう。
新出漢字は、日常生活や教科書内で頻繁に使われるため、しっかりと覚えておくことが大切です。
②今までに習った漢字も出る
漢字テストでは、新しい漢字だけでなく、これまでに学んだ漢字も出題されることがあります。
特に、低学年で習った簡単な漢字ほど、時間が経つと忘れやすくなりますので、定期的に復習することが重要です。
③トメ・ハネまできれいに書く
漢字を書く際には、トメ・ハネ・ハライといった細かい書き方まで気を配りましょう。
教師が細かい部分までチェックするため、トメやハネの丁寧さが得点に影響することもあります。見直しの際には、トメ・ハネがしっかりできているか確認する習慣をつけましょう。
④送り仮名に気をつける
漢字の書き取りでは、送り仮名にも注意が必要です。
送り仮名が正しくないと、せっかく漢字が書けても減点されてしまいます。
楽しく漢字を覚えるには
漢字検定合格などの目標を持つ
漢字検定などの目標を設定すると、やる気が一層高まります。
具体的な目標があると、計画的に学習が進められ、達成感も得やすくなります。
漢字検定は、実際のテスト形式にも慣れる良い機会ですので、定期的にチャレンジしてみるとよいでしょう。
面白い例文で覚える
例文を使って漢字を覚えるのもおすすめです。普通の例文ではなく、ちょっと面白い文や、子どもが興味を持つ内容で漢字を使うと、より覚えやすくなります。
漢字ゲームで楽しく覚える
漢字を覚えるためには、ゲーム感覚で取り組むのも効果的です。
例えば、『源氏物語』でもその名が登場し、日本に昔からあるとされる「偏つぎ」があげられます。
「偏」と「旁(つくり)」の組み合わせを考えるゲームとされており、親が「旁(つくり)」を出し、子がそれに合う「偏」を出すという楽しみ方があります。
例えば親が「月」を出した場合、子が「日」を出せば「明」、「月」をだせば「朋」となるというように、様々な漢字を作り出していくのです。
遊びながら学べる工夫を取り入れることで、楽しみながら漢字を習得できますね!
※偏つぎの遊び方には諸説あります。

小学生におすすめの漢字ドリル2選
教科書ドリル
「教科書ドリル」は、教科書に沿った内容で漢字を学べるドリルです。
学校の授業内容に合わせた問題が掲載されているため、予習や復習に最適です。
特に、テストに出やすい新出漢字を効果的に練習できるため、漢字テスト対策にも役立ちます。日々の学習に取り入れてみてください。
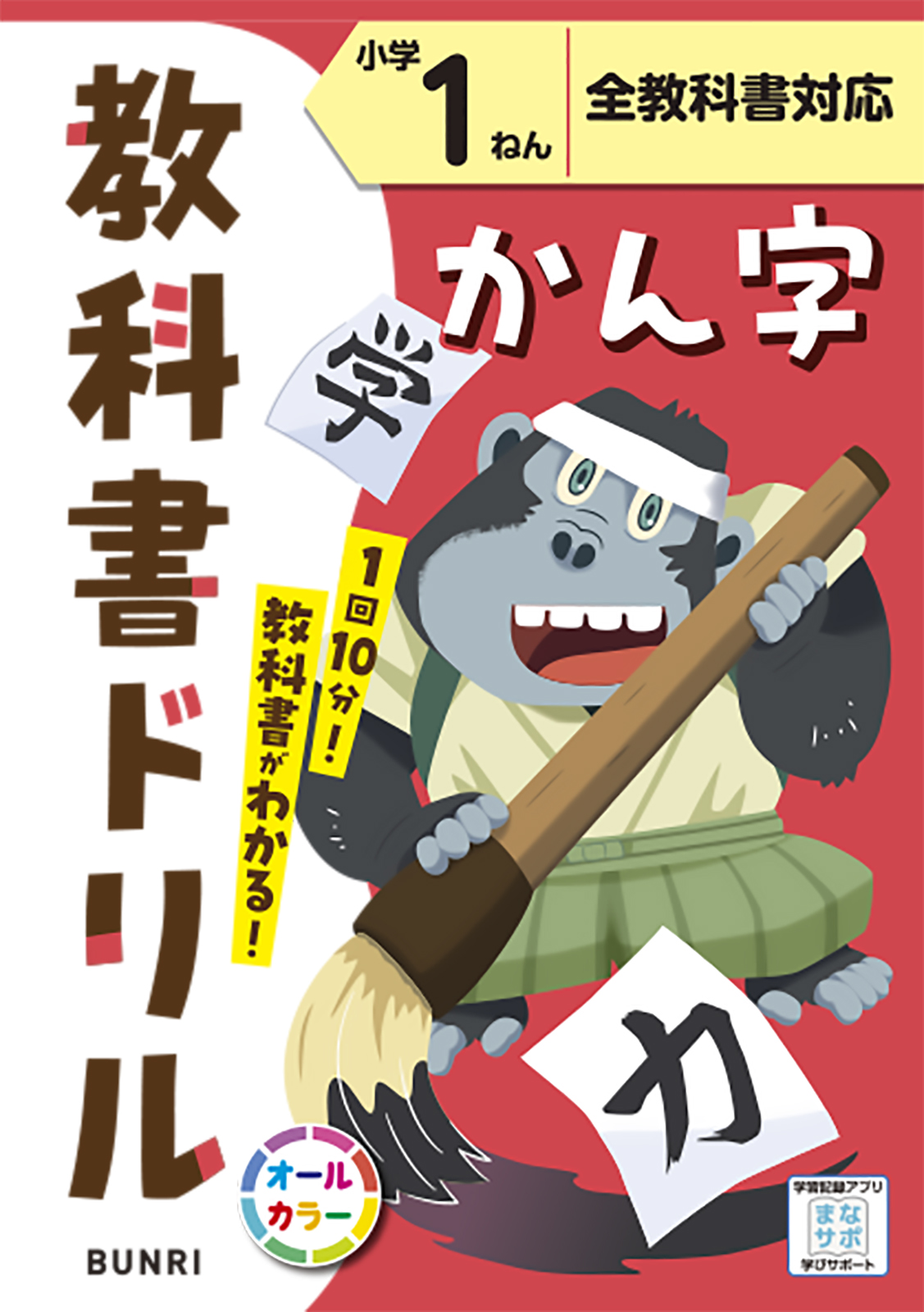
できる‼がふえる↑ドリル
「できる‼がふえる↑ドリル」は、短い時間の反復練習で、無理なくレベルアップができるドリルです。
オールカラーで、イラストも多く取り入れられており、漢字学習の苦手意識をなくしてくれます。基礎からしっかり学べるので、漢字の復習にもぴったりです。
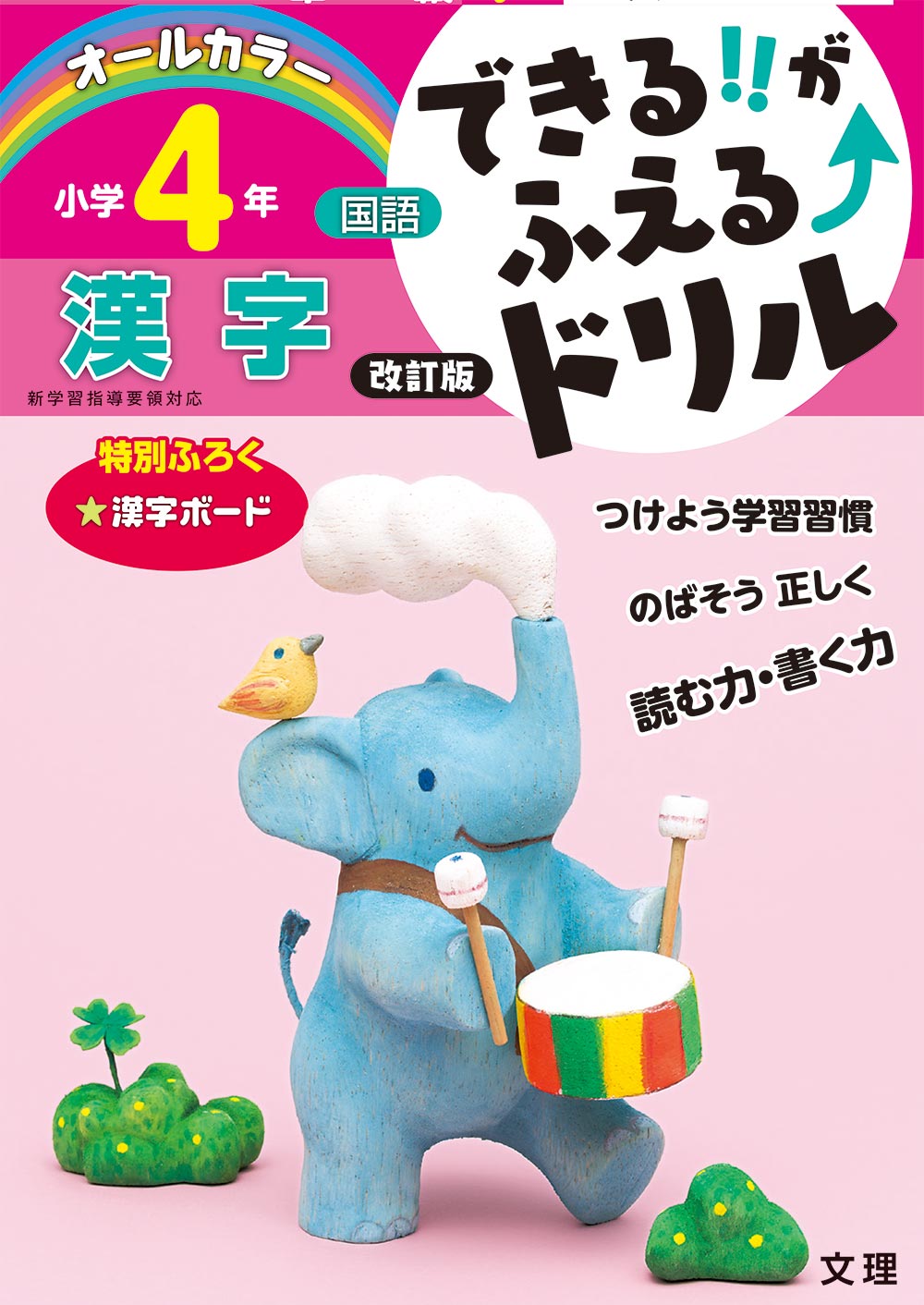
まとめ
漢字テストは、子どもたちが漢字を確実に覚えるための大切な学習手段です。コツを押さえ、楽しみながら取り組むことで、漢字学習はもっと効果的で楽しいものになります。保護者の皆さまもぜひ、お子さまの学習をサポートし、目標を持って一緒に取り組んでみてください。
【今回の執筆者】
イニシャル:M
年代:20代
~今日の一言~
自分の名前の漢字が難しく、テストの際、まず名前を書くのに大変時間がかかってました。



